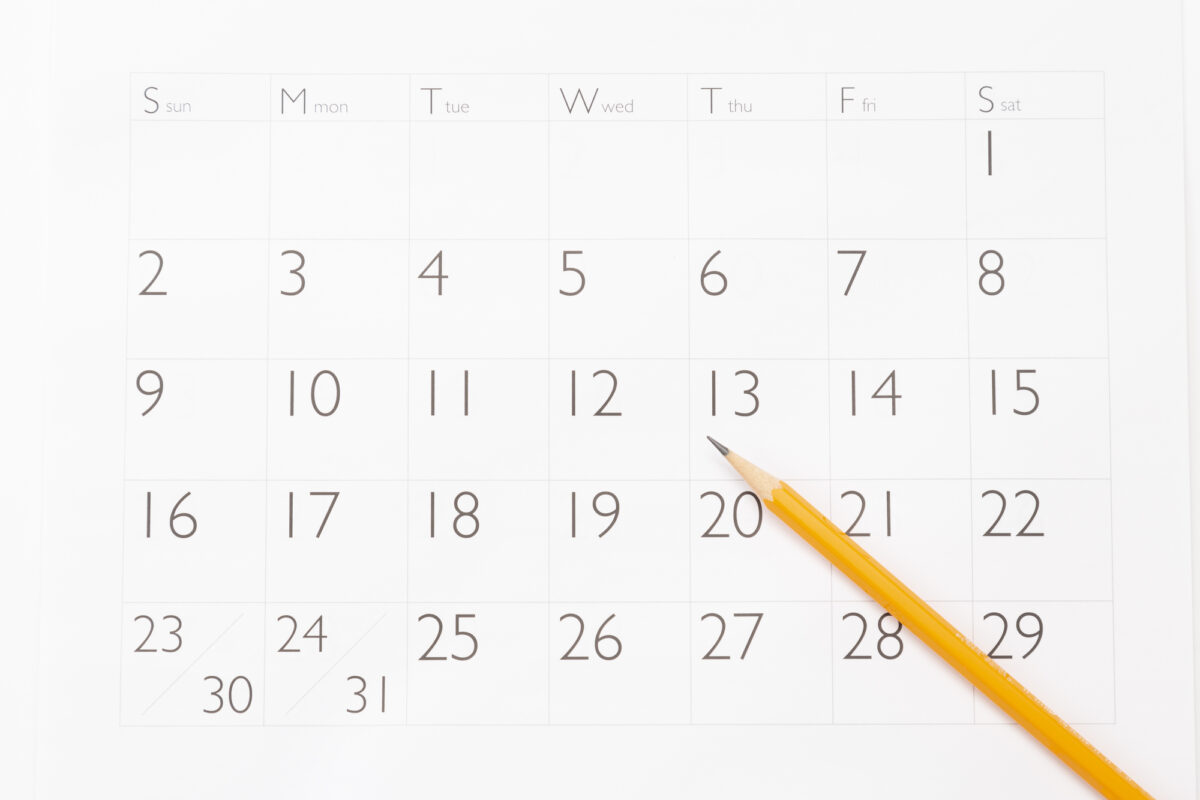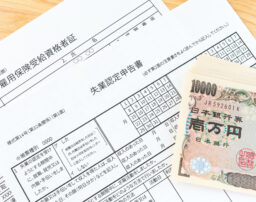「お休みである土曜日に出勤したのに休日出勤扱いになっていないのはおかしくないのかな?」
実は、一言で「休日」といっても、法律で取得が義務付けられている休日のことを「法定休日」、法定休日に加えて会社が独自に設定する休日のことを「所定休日(法定外休日)」といい、両者には違いがあります。
法律上の休日労働とは、法定休日における勤務・労働を指します。
所定休日は「法定外休日」なので、所定休日に勤務・労働をしたとしても、法律上の「休日労働」には当たりません。
ですので、例えば土・日・祝日が休みの仕事で、法定休日が日曜日の場合、土曜日出勤は法定外休日(所定休日)の勤務・労働であって、法律上の「休日労働」ではないのです。
この記事を読んでわかること
- 36協定と休日労働の定義
- 休日労働した場合の代休、割増賃金、残業
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
36協定を結ばない状態での休日出勤は、労働基準法違反
まず、前提として「休日労働」という言葉の意味について説明します。
(1)労働時間と休日に関する法律上の規定
労働基準法では、労働時間の上限(労働基準法32条)や休日(同35条)に関する規定が定められています。
それによると、労働時間は「1日8時間・1週40時間」が上限とされています。この法律上の上限を「法定労働時間」といいます。
そして、休日については、「1週間当たり1日以上又は4週間当たり4日以上」の休日を、使用者は労働者に与えなければならないと規定されています。
法律で取得が義務付けられているこの休日のことを、「法定休日」といいます。
(2)休日労働と36協定
法定労働時間を超えて働くことを「時間外労働」といい、法定休日に働くことを「休日労働」といいます。
使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせる場合は、次のことを行わなければなりません。
- 労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」(「36協定」といってご説明します)を、使用者と労働者(労働組合や労働者の過半数の代表)で締結し、労働基準監督署に届け出ること。
- 雇用契約書や就業規則等に「36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じる」旨を明記して36協定を書面で労働者に交付するなど、その内容を労働者に周知すること。
36協定の締結・届出の手続きをせずに労働者に時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法32条や同35条に違反したとして、使用者は刑事罰(労働基準法119条)を科される可能性があります。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
36協定について詳しくはこちらをご覧ください。
36協定における休日労働のポイント1|法定休日に勤務することを「休日労働」という
ここからは、休日労働に関して、自己の権利を守り、かつ適切に主張するための5つのポイントを説明していきます。
まずは、労働基準法で「休日労働」と扱われるための条件についてです。
(1)「法定休日」と「所定休日」
繰り返しになりますが、労働基準法35条では、会社は労働者に「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」を与えなければならないと定めています。
法律で取得が義務付けられているこの休日のことを「法定休日」といいます。
そして、法律上の「休日労働」とは、法定休日に行う勤務・労働のことを指します。
これに対し、法定休日に加えて会社が独自に設定する休日のことを「所定休日(法定外休日)」といいます。
所定休日は「法定外休日」なので、所定休日に勤務をしたとしても、法律上の「休日労働」にはあたりません。
法定外休日に勤務・労働した場合は、法定労働時間内での労働としてカウントされます(※法定外休日に勤務・労働をしたことにより法定労働時間を超えた場合は、時間外労働の時間としてカウントされます)。
法定休日は何曜日でも構いません。
例えば、週休2日制で、土日を休日としている会社において、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日と定めることもできます。
なお、週休2日制で土日を休日としているけれど法定休日を定めていない会社では、歴週(日~土)の後に来る日、つまり土曜日が法定休日になります(*就業規則で週の起点の規定がない場合)。
(2)変則的な労働時間制でも、法定休日の勤務は休日労働となる
労働時間の設定において弾力的な運用が認められている、次の労働時間制においても、法定休日の勤務は休日労働として扱われます。
- 変形労働時間制
- 裁量労働制
- フレックスタイム制
(3)法定休日は、事前に他の労働日に振替可能な場合がある(振替休日の指定)
就業規則等に振替休日に関する規定がある場合、会社は遅くとも前日までに労働者に連絡することによって、法定休日を他の労働日と入れ替えることができます。
このことを「振替休日の指定」といいます。
振替休日の指定によって、その日の勤務は休日労働ではなくなり、通常の労働日と同様の扱いとなります。
なお、振替休日を取得させる場合であっても、法定休日に関する規定が適用されますので、「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」を確保しなければいけません。
ですから、勤務した日から離れて振替休日を入れた結果、「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」の要件が満たされない場合には、原則として違法になります。
また、振替休日を同一週内に指定せず、その週の勤務時間が週40時間を超えてしまう場合には、超えた時間の勤務・労働については原則として割増賃金を支払われなければいけません。
36協定における休日労働のポイント2|休日労働で代休を取得できるかどうかは、会社次第
「振替休日」と似たものとして、「代休」があります。
「代休」は、休日労働をした労働者に対して、会社が事後的に与える休日のことをいいます。
代休の付与は労働基準法等の法律で義務付けられたものではないので、代休の制度があるかどうかは会社次第(就業規則等に定めがあるかどうか)ということになります。
そして、代休の付与があったとしても、すでに休日労働は行われているため、会社は労働者に対してすでに行われた休日労働について休日出勤手当(下記の所定の割増賃金率を加算した賃金)を支給しなければなりません。
この点で、振替休日とは扱いが異なります。
振替休日と代休との違いなどについて詳しくはこちらをご覧ください。
36協定における休日労働のポイント3|休日労働の割増賃金率は35%以上
休日労働をすると、会社は労働者に、所定の割増賃金率を加算した賃金(休日出勤手当)を支払わなければなりません。
休日出勤手当は、「1時間あたりの賃金×休日労働の時間数×割増賃金率」という計算式によって算出されます。
割増賃金率は会社ごとに36協定で定めることになりますが、休日労働の割増賃金率は35%以上(22~5時の深夜労働時間帯にあたる部分は深夜手当の25%が加算されて60%以上)でなければならないとされています(労働基準法第37条第1項、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
なお、これまでご説明したとおり、次のケースは休日労働に該当しないため、休日出勤手当の対象外です(時間外労働にあたる場合は、時間外労働としての割増賃金が支払われます)。
- 所定休日の勤務
- 振替休日が指定されていた場合
また、「代休を付与したから休日出勤手当は支払わない」という扱いは、休日労働に対して規定の割増賃金を支払っていないことになるため、労働基準法違反となります(未払い賃金が発生していることになります)。
36協定における休日労働のポイント4|休日労働には「時間外労働」が発生しない
36協定により労働者に休日労働をさせるには、予め労働させる法定休日の上限日数や就業時間(始業・終業時刻)を定めておかなければいけません。
36協定で定めた上限日数や就業時間を超えて休日労働をさせることは違法です。
ところで、休日労働には、「1日8時間以内」といった労働時間の上限の定めがありません(*)。
したがって、休日労働には「時間外労働」が発生しないことになります(深夜労働は別です)。
すなわち、休日労働をした場合に、労働時間が法定労働時間を超えたとしても、超えた部分は時間外労働とはならないため、休日労働と重複しての割増率が適用されることにはなりません。
つまり、休日労働をした場合の割増賃金率は、労働時間の長短に関係なく、一律の35%以上ということになっています(なお、法定休日に深夜労働をした場合、割増率は60%以上になります)。
(*)ただし、次にご説明するとおり、36協定の特別条項による休日労働に関する時間制限があります。
36協定における休日労働のポイント5|特別条項では、休日労働の時間数も「時間外労働の上限規制」にカウントされる
働き方改革関連法が2019年4月に施行されたことに伴い、労働基準法等の法律が改正され、長時間労働の是正に向けたルールとして「時間外労働の上限規制」が設けられました。
36協定によっても、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年間360時間」とされていますが、「臨時的な特別の事情」があって労使が合意する場合には、特別条項付き36協定を締結・届け出ることで、時間外労働の上限の引き上げが一定程度可能になります。
この上限の引き上げは、かつては制限がありませんでしたが、この法改正によって、特別条項付き36協定を結んだ場合にも超えることができない時間外労働の上限規制が導入されたのです。
この上限規制の中には、休日労働の時間数が関係するものも含まれています。
具体的には、次のような規定となります。
- 時間外労働と休日労働の合計が月間100時間未満(労働基準法36条6項2号)
- 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内(「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」の全てについて1月当たり80時間以内であること)
なお、その他「時間外労働」に関する上限規制には、次のようなものがあります。
- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)
- 原則である、時間外労働時間が1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(労働基準法36条5項かっこ書き)
これらの上限規制に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(労働基準法119条)。
【まとめ】法定休日における労働が「休日労働」。土曜出勤は休日労働とは限らない
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労働者を法定休日に労働させるには、36協定における休日労働の定めが必要となります。
- 法定休日における労働のことを休日労働といい、所定休日(法定外休日)における労働とは区別されます。
- 休日出勤をした後に代休を取得した場合には、当該休日出勤は休日労働と扱われますが、代休の制度があるかどうかは会社によって異なります。
- 休日労働をした場合には、通常の賃金に35%以上の割増率を上乗せした額の割増賃金が支払われなければなりません。ただし、休日労働には法定労働時間の定めがないため、時間外労働が発生しません。
- 休日労働は、時間外労働との合計時間数によっては、法律上の上限規制に抵触する場合があります。
適切な割増賃金が支払われていない等、休日労働の制度が不当に運用されている場合には、労働トラブルに精通した弁護士にご相談ください。
また、休日労働をしているにも関わらずその分の給与の支払いがなくお困りの方は、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年2月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。