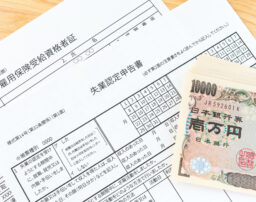「年間休日っていったい何日なんだろう」
実は、年間休日には法律上、ルールが定められています。
1日8時間労働の場合は、基本的には105日以上の年間休日が必要です。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 年間休日とは何か
- 年間休日の実態
- 年間休日が少ない場合の対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
年間休日とは
「年間休日」とは、1年間の休日の合計です。
この年間休日は、労働基準法で定められている休日(法定休日)と法定休日に上乗せされた、会社独自の休日(法定外休日)を合わせたものです。

(1)法定休日
労働基準法第35条で定められた休日を、法定休日といいます。
法定休日においては、次のようにする必要があります(労働基準法35条)。
- 「週に1回休日を設ける」
- 「4週間を通じ4日以上の休日を設ける」(変形週休制)
法定休日は、何曜日に取らなければならない、という決まりはありません。
このため、土日祝日に法定休日が設定されていなくとも違法とはなりません。
法定休日に労働した場合、一定の要件を満たせば、代わりの別の日に休日を振り替えることができます。
(2)法定外休日
法定外休日とは、労働基準法上の法定休日に上乗せされた、会社独自の休日のことをいいます。
例えば週休2日制の会社の場合は、内1日は法定休日であり、残り1日は法定外休日を設けていることになります。
年間休日の実態について
さて、厚生労働省の調べによれば、2020年の年間休日の平均は、労働者1人あたり116.1日となっております。
そして、年間休日はほとんどの業種で105日と120日に大別されます。
では、なぜ105日と120日に大別されるのでしょうか。
(1)年間休日が105日である理由
1日8時間労働の企業において、年間休日が105日とすると、労働基準法の定める基本ルールをすれすれにクリアした場合の日数となります。
というのも、労働基準法では、休日と労働時間については次のように定められています。
- 法定休日は原則として週1回、
- 労働時間は原則として、1日8時間、週40時間まで
これらの法律のルールから計算すると、次のことが導かれます。
1.法定休日を週1回とるためには、年間休日は、53日以上必要です。
365日÷7日=53日(小数点未満切り上げ)
2.労働時間を1日8時間、週40時間とすると、年間休日は、105日以上必要です。
年間の労働時間:
(365日÷7日)×40時間=2085時間(小数点未満切り捨て)
↓
年間の労働日数(年間の労働時間2085時間を1日8時間ずつ働いた場合):
2085時間÷8時間=260日(小数点未満切り捨て)
↓
最低限必要な年間休日
365日-260日=105日
3.上記1、2のいずれの条件も満たす必要があるので、労働基準法の定める基本ルールをすれすれにクリアした場合、年間休日は105日となります。
なお、1日の所定労働時間(定時)が8時間より短い場合は、最低限必要な年間休日数は、105日より少なくなります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の場合、労働基準法の定める基本ルールをクリアしようとすると、次の計算により最低必要な年間休日は、68日となります。
年間の労働日数:{(365日÷7日)×40時間}÷7時間=297日(小数点未満切り捨て)
最低限必要な年間休日:365日-297日=68日
このように所定労働時間が何時間であるかによって、最低限必要な年間休日の日数は異なってきます。
(2)年間休日が120日である理由
2022年は土日祝日合わせると120日なので(土日が計105日、土日に重ならない祝日が計15日)、年間休日120日はカレンダーどおりの休日がとれることになります。
このように、完全週休2日制+祝日休みとするためには、年間休日を120日と設定する必要があるのです。
(3)年間休日105日と年間休日120日、どっちが働きやすい?
年間休日がどのくらいが働きやすいかというのは個々人によって異なってきます。
毎週2日休んで、祝日も休むというライフスタイルを希望する場合は、年間休日120日以上の企業で働くのが望ましいということになります。
逆に、年間休日105日の企業の場合は、年間休日120日の場合と比べて1年当たり15日休みが短いため、休日が少なく、疲れが溜まりやすいと感じるかもしれません。
1年間は52~53週ありますので、年間休日105日の場合は、ほぼ週2日休めることになるものの、長期の連休を取るのは難しくなります。
仮に、休みを固めて連休を取ったとしても、その分週1日しか休めなくなる週が増えてしまうことになるのです。
もっとも働いた日数分に応じて給料がもらえるという働き方の場合は、年間休日が少ない方が、給料は増えることにはなります。
なお、厚生労働省の調べでは、2021年に、完全週休2日制を採っている企業は60.7%です(なお、完全週休2日制=祝日も休みというわけではありません)。
(4)年間休日の多い業種
厚生労働省の調べでは、2018年に、1企業あたりで年間休日の多い業種は次の通りです。
- 情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業(118.8日)
- 金融業、保険業(118.4日)
このような業種はBtoBビジネス(法人向けのビジネス)の場合が多く、会社間でのやりとりが少なくなる土日祝日は休みにするという理由があります。
参考:結果の概要|厚生労働省
(5)年間休日の少ない業種
厚生労働省の調べでは、2018年に、1企業あたりで年間休日の少ない業種は次の通りです。
- 宿泊業、飲食サービス業(97.1日)
- 運輸業、郵便業(100.3日)
このような業種はBtoCビジネス(個人向けビジネス)の場合が多く、休日や連休などに収益を上げるため休みが取りにくいという理由があります。
参考:結果の概要|厚生労働省
年間休日の決まりには例外がある
一部の業種や管理監督者の場合には、労働時間や休日の法規制が及びませんので、年間休日の最低限の基準がないことになります。
例えば、次のような業種等の場合には、年間休日の最低限の基準がありません。
- 管理監督者
一般的には、部長など、労務管理について経営者と一体的な立場にある職種の人がこれにあたります(ただし、肩書ではなく、実体に即して判断されます)。 - 農業、畜産、水産業
- 監視・断続的労働従事者
一般的には小中学校の用務員、団地管理人などがこれにあたります。
年間休日が少ない場合の対処法
所定労働時間が1日8時間労働であるにもかかわらず、年間休日が100日未満の会社であれば、労働環境改善のために何か行動を起こす必要があります。
対処法としては、次のものがあります。
- 会社の人事担当・労働組合に相談
- 労働基準監督署に相談
- 弁護士に相談
これらについてご説明します。
(1)会社の人事担当、労働組合に相談
会社の労働環境を改善するには、まずは、社内で解決を試みることが望ましいです。
1日の所定労働時間が8時間であるのに、年間休日が100日未満の場合、時間外労働や休日労働など、割増賃金(残業代)の支払の対象となる労働をしている可能性があります(管理監督者などを除きます)。
時間外労働や時間外労働をしているにもかかわらず、割増賃金などの残業代が払われていない場合は、人事担当に相談し、割増賃金の支払いを求めましょう。
また、年間休日が105日以上取れる体制にするよう交渉することも可能です。
労働組合がある企業であれば、労働組合にも相談することで解決を図れる場合もあります。
(2)労働基準監督署に相談
社内で解決に至らない場合は、雇用契約書の内容や実態をまとめ、労働基準監督署に相談してみましょう。
労働基準監督署では、無料で、労働関係の法律に詳しい職員が親身になって話を聞いてくれます。
また、相談の結果、会社が労働基準法に違反している可能性があると判断された場合には、会社に対して立ち入り調査をしたり行政指導を行ってくれることがあります。
ただし、労働基準監督署は、相談をされたからといって、必ずしも調査や行政指導を行う義務があるわけではありません。そのため、相談のみで終わってしまうこともあります。
(3)弁護士に相談
労働基準監督署は必ず動いてくれるわけではなく、また労働基準監督署の行政指導には強制力はないので、弁護士への相談も検討してみましょう。
弁護士に依頼すれば、未払いの割増賃金などを取り返すべく、企業に交渉したり、裁判をしたりしてくれます。
労働基準監督署ではなく弁護士に相談するメリットには、次のようなものがあります。
- 労働基準監督署は会社に法律のルールを守らせるのが仕事であり、労働者個々人の代わりとなって活動してくれるわけではないのに対して、弁護士は労働者個々人の代わりに権利実現のために動いてくれる。
- 労働基準監督署は労働者の代理人となることはできないが、弁護士は労働者の代理人となることができ、労働者のために交渉などを代わりに行ってくれる。
- 弁護士に依頼すれば、労働者の代わりに会社と交渉などを行ってくれるので、直接会社と交渉などを行うストレスが軽減される。
【まとめ】法律上、最低限必要な年間休日を取れているかチェックしましょう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「年間休日」とは、1年間の休日の合計のこと。
年間休日は、労働基準法で定められている休日(法定休日)と会社独自の休日(法定外休日)を合わせたもの。 - 年間休日は、ほとんどの業種で、105日と120日に大別される。
これは、1日8時間労働の企業で労働基準法の定めるルールをぎりぎりクリアした場合の日数が105日となることと、土日祝日を休みにした場合約120日となることが理由。 - 年間休日が少ない場合の対処法として、労働基準監督署に相談する、弁護士に相談するなどの方法がある。
しっかりと働くためにはしっかりと休むことが大切です。
そのためにも、労働基準法の基本ルールである年間休日105日(1日8時間労働の場合)は少なくとも休みたいものですよね。
もしも法律が求める年間休日を下回る日数でしか休日を取れていない場合には、しっかりと休みを取らせてもらえるように会社と交渉してみましょう。
また、そのような場合には、残業代が発生していることもあります。
働いた分のお金はしっかりともらいたいもの。
働いた分の残業代が払われているのか、一度確認してみましょう。
残業代の計算は複雑なので、弁護士に相談・依頼するのもおすすめです。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年12月時点
土日休みと説明されていたのに土曜日は出勤を強いられていたものの残業代請求をしたことで約300万円の残業代を獲得したケースについて、詳しくはこちらをご覧ください。
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。