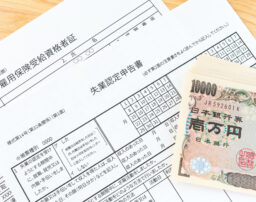「家族が毎日のように長時間残業していて過労死してしまいそう……」
過労死とは、過労を原因とする死亡のことです。
過労死は、決して遠い存在ではありません。
何よりも、家族を過労死させないことが大切なのは言うまでもありません。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 過労死とは何か
- 家族を過労死させないための予防策
- 家族に過労死が疑われる場合に検討すべきこと
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
過労死とは?
過労死とは、次のような過労を原因とする死亡のことです。
- 過労を原因とする脳血管疾患・心臓疾患による死亡
- 過労による精神障害を原因とする自殺による死亡
また、死亡にまでは至らないものの、過労を原因として脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を患ってしまうこともあります。
家族を過労死等させないためにすべき予防策
身内が過労死等(過労による死亡や疾病)になってしまう前に、家族として過労実態の事実に気づくことが大切です。
本人は「忙しくて病院に行けない」と言うかもしれませんが、おかしいと思ったら、産業医など医師による面談を受けるように勧めてみましょう。
休職や、場合によっては退職などを勧めることも大切です。
過労状態について、労働基準監督署や弁護士等の専門家に相談することも検討してみましょう。
家族に過労死が疑われる場合に検討すべきこと
残念ながら過労死が疑われる状況で家族が亡くなった場合、次の2つを検討します。
- 労災保険制度による給付を請求する
- 会社に対して損害賠償請求をする
労災保険給付は、労働者の疾病・障害・死亡等に対して迅速・公平な保護をするための制度です。
しかし、過労死によって被った損害全てを補償してくれるわけではありません。
そのため、会社に対する損害賠償請求も検討する必要もあるのです。
いずれの請求をするにも、まずは過労死を証明できるものがないか探してみましょう。過労死等が疑われる場合には、弁護士に相談・依頼して、会社に証拠を開示してくれるように求めましょう。
次のような証拠が過労死等の証拠として有効です。
- タイムカードや業務日報、施錠記録簿など労働時間を記録したもの
- 会社のパソコンのログイン記録・ログオフ記録
- 業務上の事故を報告する事故報告書
- 会社から自宅までのタクシーの領収書、ICカードの記録
- 「これから帰宅する」などのことを内容とする本人のメール
- 過重労働について記した本人の日記
- 健康診断の面談記録や病院のカルテ
- 職場の同僚からの証言
これら以外にも証拠として活用できる場合があるので、専門家に相談するとよいでしょう。
(1)労災保険制度による給付を請求する
過労死が疑われる場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に労災申請を行いましょう。
労災保険制度では、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等について、一定の要件を満たすと保険給付が行われます。
(1-1)過労死等に認定される基準
厚生労働省によると、2021年度には過労死等について3099件労災申請がされ、801件で支給決定がされました(この支給決定件数には、2021年度以前に請求があったものも含まれます)。
参考:令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省
過労死等の認定基準は、脳・心臓疾患と、精神障害の場合に分けられています。
脳・心臓疾患の労災認定基準
過労死等の認定の対象となる疾病は次の通りです。
- 脳出血(脳内出血)
- クモ膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む)
- 解離性大動脈瘤
業務上の病気かどうかは、次の3つの基準から判断されることになります(平成13年12月12日基発1063号)。
- 発症直前から前日までの間に、発症状態を時間的・場所的に明確にできる「異常な出来事」(※)に遭遇したといえるか
- 発症に近接した時期(発症前概ね1週間)に特に過重な業務(短期間の過重労働)に就労したといえるか
- 発症前の長期間(発症前概ね6ヶ月以内)に著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重労働)に就労したといえるか
(※)次のようなケースであれば、異常な出来事があったと判断されやすくなります。
- 業務に関連した重大な人身事故に直接関与し、著しい精神的なショックを受けたケース
- 事故に伴って救助活動などの処理をし、著しく身体に大きな負担がかかったケース
- 温度差のある場所に頻繁に出入りしたケース
精神障害の労災認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」によると、次の3つの条件をすべて満たして自殺した場合に、過労自殺と認定されます。
- 統合失調症、うつ病など対象となる精神障害を発症していること
- 対象となる精神障害の発病前概ね6ヶ月以内に業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
参考:脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-|厚生労働省
参考:精神障害の労災認定|厚生労働省
(1-2)労災保険制度によって受けられる給付
労災保険によって受け取れるお金には様々な種類があります。
これらのうち、家族を過労死を理由として失った場合に受け取れる遺族(補償)給付、葬祭料・葬祭給付について詳しくお伝えします。
なお、大切な家族を失った精神的苦痛を補う慰謝料は制度化されておらず、慰謝料を求める場合には会社に対して請求していくことになります。
(これからのご説明は、受給権者が1人である場合の受給額についての説明です。)
遺族(補償)給付について、詳しくはこちらをご覧ください。
遺族(補償)給付
業務災害または通勤災害により死亡したときには、一定の要件を満たす遺族に次の給付がなされます。
- 遺族(補償)年金
- 遺族特別年金
- 遺族特別支給金
遺族(補償)年金の支給金額は遺族の人数等に応じて、給付基礎日額153〜245日分が支払われます(1回のみ年金の前払いを受けることができます)。
また、遺族特別支給金として一律300万円の一時金が支払われます。
さらに、遺族特別年金として、遺族の人数等に応じ、算定基礎日額の153~245日分の年金が支払われます。
また、遺族(補償)年金を貰える人がいない場合など一定の要件を満たすと、亡くなった労働者の遺族のうち、最も優先される順位の方に、次の給付がされます。
- 遺族(補償)一時金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別一時金
遺族(補償)給付を受ける権利は労災にあった労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効にかかります。
また、遺族(補償)年金を一時金として前払いを受ける権利の時効は、労災にあった労働者が亡くなった日の翌日~2年です。
葬祭料(葬祭給付)
労災で死亡した方の葬祭を行う場合、一定の要件を満たすと葬祭の費用を負担した方に対して支給されるお金です。
支給金額は以下の通りです。
葬祭料(葬祭給付)=31万5000円+(給付基礎日額×30日分)
なお、上記金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には給付基礎日額の60日分が支給されます。
労働者が死亡した日の翌日~2年を過ぎると、時効によって請求できなくなります。
参考:労災保険給付の概要|厚生労働省
参考:遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
(1-3)労災保険の請求が認められなかった場合
労災保険の請求をしたにもかかわらず希望通り認められなかった場合には、労働者災害補償保険審査官に対して「その判断はおかしいのでもう一度検討して欲しい」と審査請求を行います。
審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
審査請求でも認められなかった場合には、労働保険審査会に対して決定から2ヶ月以内(※)に再審査請求をします。
※2016年3月31日以前に通知を受け取った場合は、60日以内
この再審査請求の結果(裁決)に不服がある場合、裁決から6ヶ月以内に裁判所に行政訴訟を提訴することになります(一定の場合には、再審査請求をせずに裁判所に提訴することも認められています)。
労災認定されなかった場合の審査請求などについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(2)会社へ民事上の損害賠償請求をする
会社は、従業員が死亡した場合の補償制度を設けていることがあります。過労死等によって世帯主が亡くなった場合には、そうした補償交渉を行うのが良いでしょう。
補償制度を設けていない会社に対しても、労働条件に十分に配慮していなかったと疑われる場合には、安全配慮義務違反を理由に慰謝料や将来にわたる収入の填補(逸失損益)などの民事上の損害賠償を請求できます。
次のようなケースでは、会社に対する損害賠償を検討しましょう。
- 過重労働を原因とする遺書のあるケース
- 長時間の休日出勤や深夜労働について会社として何ら是正措置を採っていないケース
手元に十分な証拠がなくても、個人情報開示手続きによって労災認定にあたって労働基準監督署が手に入れた資料を入手できることがあります。
なお、過労死に対して労災保険給付が行われた場合は、その支払われた金額分、同じ過労死に対する民事上の損害賠償額は減額されます。
【まとめ】過労死で労災請求できることがある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 過労死とは、過労を原因とする脳血管疾患・心臓疾患による死亡や、過労による精神障害を原因とする自殺による死亡のこと。
- 家族が過労により死亡したり疾病にかかってしまう前に、おかしいと思ったら病院を受診させたり休職などを勧めることが大切。
- 残念ながら家族が過労死により死亡してしまった場合には、労災保険制度による給付を請求したり、会社に対して損害賠償請求をするなどの方法がある。
- 過労死の場合、労災保険によって、遺族(補償)給付などを受け取ることができる。
- 労災保険の請求が認められなかった場合には、審査請求などを行うことができる。
過労死は、とてもつらいものです。
ぜひ家族が過労死してしまう前に、休んだり病院を受診するように勧めてあげて、過労死を防ぎましょう。
また、不幸にも過労死によって家族が死亡してしまった場合には、悲しいだけでなく、経済的にも苦しくなってしまいます。
労災保険により受けることのできる給付をしっかりと受け取るようにしましょう。
過労死に直面すると、ご自身で全て対処するのは難しいかもしれません。
そのような場合には、労働問題を扱う弁護士に対応を相談するようにしましょう。