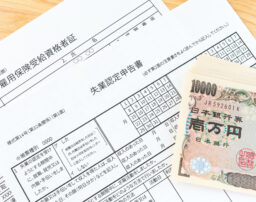「派遣期間の終わりが近づいてきた。次はどうなるのだろう……」
2018年、労働契約法と労働者派遣法の改正が施行されました。
派遣社員は、同一事業所では、原則として3年以上働けなくなる一方で、有期雇用の派遣社員にも、無期転換権(有期雇用の従業員が、その契約期間が更新されて通算5年(例外あり)を超えると、無期雇用契約に転換する旨を申し込むことができる権利)が生じている場合があります。
「自分には、無期転換できないのだろうか」とか、「無期転換したらどうなるのか」など、気になる方はいらっしゃいませんか。
無期転換ルールによって、無期転換した場合、同じ派遣先で3年以上働けるようになります。一方で、雇用条件が変わることがあるため従来よりも自由な働き方ができなくなる場合もあります。
この記事を読んでわかること
- 派遣社員の同一の派遣先事業所で働ける期間
- 無期転換ルール
- 無期雇用派遣のメリット、デメリット
- 無期転換ルールの利用前に不当に雇い止めに遭ったときの対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
2018年の法改正で、派遣社員の雇用ルールはどう変わった?
2018年、派遣に関するルールを定める法律が改正されました。
まず、労働契約法改正によって、2018年4月1日からいわゆる「無期転換ルール」が開始されました。
また、労働者派遣法改正によって、2018年10月1日からいわゆる「派遣3年ルール」が開始されました。
派遣3年ルール、無期転換ルールについて、それぞれ説明します。
(1)「派遣3年ルール」によって、同一の派遣先で働けるのは原則3年までに
「派遣3年ルール」とは、派遣社員が同一の派遣先の事業所で働けるのは、原則として3年までというルールのことです。
派遣の働き方や利用は、臨時的・一時的なものであるという考えを原則とし、派遣の常用代替を防止、派遣労働者の雇用安定やキャリアアップを図るために「抵触日」が設けられているのです。
派遣3年ルールに抵触する日、すなわち、「抵触日」とは、派遣期間が切れた翌日のことを意味します。
ただし、例外として、次の場合は、3年を超えて同一の派遣先の事業所で働くことができます。
- 派遣元で無期雇用されている場合
- 派遣社員が60歳以上の場合
- 終了時期が明確なプロジェクトに派遣されている場合
- 1ヶ月の勤務日数が所定の基準を下回っている場合
- 産休や育休、介護休暇等の取得者の代わりに派遣されている場合
(2)「無期転換ルール」によって無期雇用契約に転換できることも
「無期転換ルール」とは、雇用期間が通算5年を超えた有期雇用契約の派遣社員は、申請によって無期雇用契約に転換できるというルールです。
派遣社員の場合、無期転換の申請先は派遣元企業です。
すなわち、派遣元企業と締結している労働契約の通算契約期間が5年を超えると、派遣元企業に無期転換の申込みをすることができます。
ただし、同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(労働契約の存在しない期間。これを「無契約期間」といいます)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。これを「クーリング」と呼びます。
しばらく派遣会社で派遣社員として働いた後、自己都合によりいったん退職し、その後、一定期間をおいて再び同じ派遣会社で働きだしたような場合です。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、次のとおりです。
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年以上で、無契約期間が6ヶ月以上の場合
⇒無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。クーリングされます。
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年以上で、無契約期間が6ヶ月未満の場合
⇒無契約期間より前の有期労働契約も通算契約期間に含まれます。クーリングされません。
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
⇒無契約期間の前の通算契約期間に応じて、決まります。
無契約期間がそれぞれ下の表に記載する期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
| 無契約期間の前の通算契約期間 | 契約がない期間 (無契約期間) |
|---|---|
| 2ヶ月以下 | 1ヶ月以上 |
| 2ヶ月超~4ヶ月以下 | 2ヶ月以上 |
| 4ヶ月超~6ヶ月以下 | 3ヶ月以上 |
| 6ヶ月超~8ヶ月以下 | 4ヶ月以上 |
| 8ヶ月超~ 10ヶ月以下 | 5ヶ月以上 |
| 10ヶ月超~ | 6ヶ月以上 |
無期転換ルールにより、有期雇用契約の雇用期間が通算5年を超えれば、契約期間中であればいつでも無期労働契約への転換申請できることになりました。
なお、「登録型派遣」(派遣労働を希望する場合に、あらかじめ派遣会社に登録しておき、派遣をされる時に、その派遣会社と期間の定めのある労働契約を締結し、派遣先に派遣されること)で働く方の場合は、派遣されるたびに、有期労働契約を締結することとなり、この場合も派遣会社との間で無期転換ルールが適用されます。
したがって、同一の派遣会社との間で通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生し、その契約期間の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。
ただし、「登録型派遣」の場合、単に派遣会社に登録している状態では、一般に、労働契約は結ばれていませんので、その期間は、通算契約期間にカウントされません。
この無期転換ルールを利用すると、派遣社員の派遣3年ルールの適用外となり、同一の派遣先の事業所で3年を超えて働けるようになります。転換後は、無期労働契約となります。
無期雇用派遣のメリット・デメリット
では、有期雇用で勤務している派遣社員の方が、無期転換ルールによって無期雇用の派遣社員になった場合、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
ここからは、無期転換ルールによって、有期雇用から無期雇用に切り替えた場合のメリットとデメリットを説明します。
(1)無期雇用契約を結ぶメリット
無期雇用契約を締結する代表的なメリットとしては、次の3点があります。
- 長期間の雇用が保証される
- 収入が安定しやすい
- 同じ派遣先で3年以上働けるようになる
(1-1)長期間の雇用が保証される
1つ目は、期間の定めがなくなるため、長期間の雇用が保証される点です。
これまでは、有期雇用契約であったことから、契約期間の終了のたびに更新するかどうかの問題がありましたが、無期契約になると、更新がなくなります。このため、雇用が安定するというメリットがあります。
(1-2)収入が安定しやすい
2つ目は、収入が安定しやすい点です。
これは、期間の定めがなくなり、長期間でのキャリア形成が可能になるため、長期的に見て収入が安定するということです。
(1-3)同じ派遣先で3年以上働けるようになる
3つ目は、同じ派遣先で3年以上働けるようになる点です。
派遣3年ルールにより、有期雇用の場合は、派遣社員が同一の派遣先の事業所で働けるのは原則として3年までとされていました。
しかし、無期雇用になると、同じ派遣先で3年以上働くことが可能になります。
(2)無期雇用契約を結ぶデメリット
一方で、無期雇用契約を結ぶにはデメリットもあります。
1つ目は、これまで通り、派遣会社に業務命令された派遣先で働くことになるため、自分で職場を選べないという点です。
派遣社員は派遣元派遣会社との間で無期雇用契約を締結することになり、派遣元の派遣会社からの指示で派遣先に派遣されます。したがって、無期転換をしたからといって、自分で職場を選ぶことはできません。
2つ目は、派遣会社との労働条件は、無期転換により、有期が無期になるだけで、その余の条件が有期雇用のときと同一とされることも多く、その場合には、これまでの労働条件より有利になるという訳ではありません。就業規則等で、例えば、無期転換により、職種や勤務地の限定がなくなる旨の定めがあるときは、これまで経験したことのない職種の業務を命じられ、有期雇用のときより大変になったと感じることも起こり得ます。
無期転換ルールを利用する前に雇い止めに遭ってしまった!対処法はある?
無期転換ルールを避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは望ましいものではないと厚生労働省は明言しています。会社が無期転換ルールを避けることを目的として雇い止めをした場合、一定の場合には雇い止めが無効となります。
雇い止めが無効であると主張するためには、次の方法が考えられます。
- 会社に直接雇止めの無効を申し入れる
- 公的機関の窓口に相談する
- 弁護士に相談・依頼して雇止めの効力を争う
まずは、会社に直接雇止めの無効を申し入れることです。
社内で同じように雇い止めにあった同僚や、労働組合に加入して団体交渉をするのも一つの方法です。
会社に申し入れても期待する結果を得られなければ、公的相談窓口、具体的には近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(無期転換ルール特別相談窓口)に相談することが考えられます。
この相談窓口は、無期転換ルールに特化した窓口です。
このほか、派遣社員の労働問題を取り扱っている弁護士に相談・依頼して雇い止めの効力を争うという方法もあります。雇止めの効力を争うには、労働審判、訴訟などの法的手続きを取ることも考えられます。
参考:無期転換ルールのよくある質問(Q&A)|厚生労働省
参考:無期転換ルール特別相談窓口|厚生労働省
【まとめ】雇用期間が通算5年を超えると無期雇用契約に転換できる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 2018年の法改正で、雇用期間が通算5年を超えた有期雇用の派遣社員は、申請によって無期雇用契約に転換できることになった(無期転換ルール)
- 無期雇用契約への転換によって雇用や収入は安定する一方、派遣会社の業務命令によっては、従来よりも自由な働き方ができなくなる可能性がある
- 無期転換ルールの利用前に雇い止めに遭ったときは、公的相談窓口などに相談したり雇止めの無効を主張するとよい
派遣契約の無期転換ルールに関してお困りの方は、「無期転換ルール特別相談窓口」などにご相談ください。