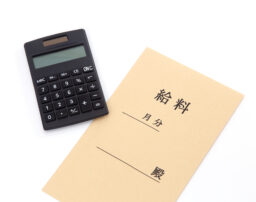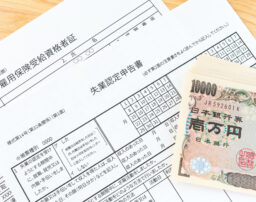「所定労働時間という言葉を聞いたことがあるけれど、どういう意味?」
所定労働時間とは、いわゆる「定時」のことで、労働契約や就業規則で会社が独自に定めた労働時間のことです。
所定労働時間を超えて労働すると残業になりますが、残業した時間数や、残業の時間帯などによって、法律上の割増賃金が発生する場合と、そうでない場合に分かれます。
この記事では、所定労働時間や割増賃金について、弁護士が解説いたします。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
所定労働時間とは?
「所定労働時間」とは、労働契約や就業規則の中で会社が定めた就労時間のことです。
所定労働時間は、労働基準法で定められた範囲内で設定されます。
勤務時間(始業時間から終業時間までの間の時間)から休憩時間を引いた時間が、所定労働時間となります。
所定労働時間と実際の労働時間は異なります。
「所定労働時間に労働した時間+これを超えて労働した時間」が、実際の労働時間となります。
(1)始業開始前の朝礼なども労働時間
所定労働時間の定めにかかわらず、会社の指揮命令下(会社の指示)で労働した、と判断される場合は、そのような時間は労働時間に含まれる可能性があります。
会社により、義務づけられているのであれば、例えば次の行為も労働時間にあたる可能性があります。
- 始業開始前の交替引継ぎ
- 始業開始前の朝礼
- 始業開始前の体操
これらの行為を行うように会社から指示されて実際に行った結果、所定労働時間を超えて労働をしたということになれば、その超えた分について残業代を請求することができます。
(2)所定労働時間と法定労働時間の違い
労働基準法第32条では、原則として、1週間で40時間、1日8時間以内の労働が法律上の上限とされています。
このように、法律上設けられた1週・1日の労働時間の上限のことを、「法定労働時間」といいます。
所定労働時間:会社が独自に定める労働時間
法定労働時間:労働基準法で定められる労働時間の上限
所定労働時間は法定労働時間の範囲内で定めることになります。
たとえば、所定労働時間を1日8時間とすることは、法定労働時間(1日8時間)を超えないため、許されます。
これに対して、所定労働時間を1日9時間と定めることは、法定労働時間を超えてしまうことになるため、原則として許されません。
労働基準法第34条では休憩時間についてもルールが、決められています。
| 1日の労働時間 | 休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 0分以上 |
| 6時間超え~8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間超え~ | 1時間以上 |
割増賃金になるケースと計算方法
労働時間が所定労働時間を超えるか、さらに法定労働時間を超えるかなどによって、残業代の計算方法が異なります。
次のケースの場合、割増賃金が発生します。
- 法定労働時間を超える残業
- 法定休日での残業
- 深夜労働
しかし、
- 所定労働時間は超えるが、1~3には当たらない残業(法内残業)
の場合には、法律上は割増賃金を払う必要がありません。
会社の就業規則などで、4の場合も割増賃金を払うとのルールがない限り、所定労働時間と同じ賃金を基に、残業代が払われます。
以下1~4について、詳しく説明いたします。
※なお、管理監督者など、一部の方は、原則として、割増賃金(深夜労働手当を除く)が支払われません。
管理監督者とは、経営者と一体の地位にあるものとして、労働基準法上残業代の支払などがなされないでもよいとされる立場の人のことです。
管理監督者にあたれば、基本的には残業代は支払われません。
もっとも、管理監督者にあたる人は、多くはありません。
管理監督者の判断基準について、詳しくはこちらをご覧ください。
(1)法定労働時間を超える残業
法定労働時間を超える残業(後述の休日労働を含みません)を、「時間外労働」といいます。
時間外労働は、法律上、割増賃金の対象となります。
【時間外労働の割増賃金の計算式】
割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×法定時間外労働の時間数×割増率1.25以上(※)
※時間外労働が月60時間を超えた部分は、割増率1.5以上となります。
ただし、次に該当する企業(中小企業、以下同じ)は、2023年3月末までは、最低の割増率は1.25以上となります。
- 小売業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が50人以下
- サービス業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者が100人以下
- その他:資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下
所定労働時間が7時間で2時間の残業の場合、最初の1時間は法定労働時間内(法内残業)のため、割増賃金を支払う義務はありません。
他方で、あとの1時間は時間外労働にあたりますので、法律上、割増賃金を払う義務があります。
(2)法定休日での労働
休日についても労働基準法上で定められた週1日の「法定休日」と、会社が独自に定める「法定外休日」があります。
法定休日に労働すると、休日労働となり割増賃金の対象となります。
【休日労働の割増賃金の計算式】
割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×休日労働の時間数×割増率1.35以上
法定外休日の労働は、法律上、休日労働の割増賃金の対象とはなりません(就業規則などに別段の定めがある場合は除く)。
もっとも、法定外休日に労働することにより、1週間40時間の法定労働時間を超える場合は、法定外休日での労働も、原則として、時間外労働の割増賃金の対象となります(休日労働の割増率は適用されません)。
例えば、就業規則で週休2日、労働時間が1日当たり7時間であれば、
「7時間×5日=35時間」
となるため、休日の1日だけ出勤して5時間働いても週40時間を超えないため、法律上、会社は割増賃金を払う義務はありません(独自に割増賃金を支払うルールを定めている会社を除く)。
他方で、労働時間が1日8時間の場合は、「8時間×5日=40時間」となるため、法定外休日の労働をすると、原則として、時間外労働となり、割増賃金が発生します。
(3)深夜労働
22~5時までは深夜労働となり、割増賃金の対象になります。
残業代=1時間あたりの基礎となる賃金×深夜労働の残業時間数×割増率1.25倍以上
(※割増率につき、詳しくは次の表をご覧ください)
【割増率表】
| 他の法定外残業との重複の有無 | 割増率 |
|---|---|
| 重複なし | 1.25倍以上 |
| 時間外労働が0時間を超えて月60時間までの部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.5倍以上 |
| 時間外労働が月60時間を超えた部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.75倍以上 (中小企業では2023年3月末までは、1.5倍以上) |
| 法定休日に深夜労働した部分 | 1.6倍以上 |
例えば、労働契約で17~24時までの勤務の場合、17~21時59分は通常の賃金、22~24時は深夜労働となるため、2時間分が深夜労働の割増賃金となります。
割増賃金率について、詳しくはこちらをご覧ください。
(4)所定労働時間は超えるが、1~3には当たらない残業(法内残業)
この場合、法律上は、会社は割増賃金を支払う義務はなく、割増のない、所定労働時間の賃金を基に残業代を支払えば足ります。
ただし、会社が独自に4の法内残業の場合も、割増賃金を払うと、就業規則などで定めている場合には、この独自のルールに従って割増賃金が貰えます。
【まとめ】所定労働時間とは会社が独自に定めた労働時間のこと
この記事のまとめは次のとおりです。
- 所定労働時間とは、会社が独自に定めた労働時間のこと。
- 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のこと。
- 法定労働時間を超える残業などについては、割増賃金が支払われる。
この記事でもご説明したとおり、法定労働時間を超える残業などについては割増賃金(残業代)が支払われます。
しかし、場合によっては適切に残業代が支払われていないことも少なくありません。
そのような場合には、会社に残業代を請求するというのもひとつの方法です。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。