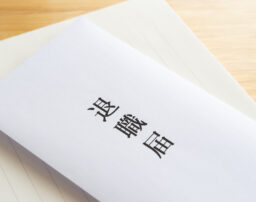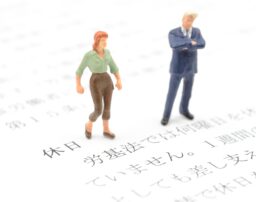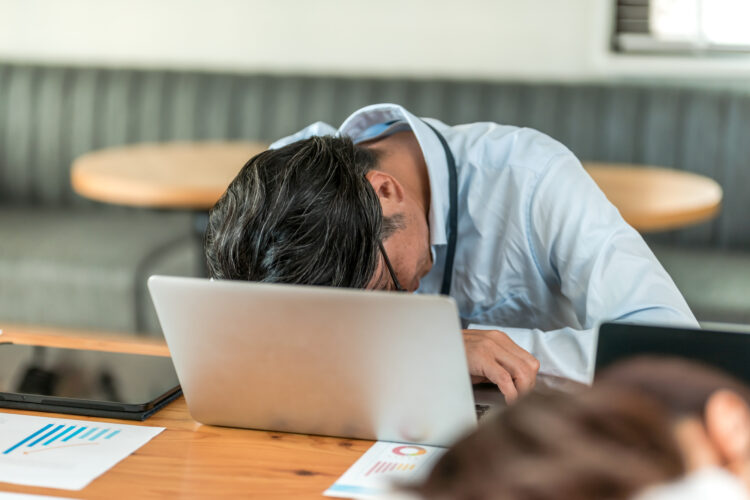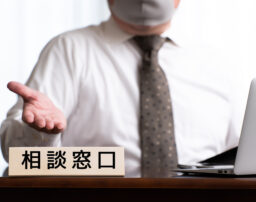「業績不振を理由に給料が全額支払われなかったり、給料日より遅れて支払われたりする…」
このような場合、労働基準法第24条違反である可能性があります。
労働基準法第24条は、労働者の賃金を守るための重要な条文ですが、その具体的な内容を詳しく理解している方は少ないかもしれません。
そこで、本記事では、賃金支払いの5原則をはじめ、その例外や違反時の罰則などについて解説します。
これを機に、労働者としてのあなたの権利をしっかりと把握し、実生活に役立ててください。
この記事を読んでわかること
- 賃金支払いの5原則
- 労働基準法第24条違反の実態と罰則
- 労働者が知っておくべきこと
ここを押さえればOK!
これらは「賃金支払いの5原則」として知られており、具体的には次のとおりです。
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月1回以上の原則
・一定期日払いの原則
同条違反が発生すると、労働者の生活に重大な影響を及ぼし、企業には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反の原因としては、企業の経営不振や管理体制の不備、労働者の権利に対する無理解が挙げられます。
労働者は自分の権利を理解し、賃金が適切に支払われているか確認することが重要です。
問題があれば、労働基準監督署に相談し、必要に応じて法的措置を検討することが求められます。
労働者は、自分の賃金に関する権利を理解し、給与明細を定期的に確認することが重要です。不明な点があれば使用者に問い合わせたり、弁護士などの専門家に相談したりしましょう。問題解決のサポートが期待できます。
労働基準法第24条とは
労働基準法第24条は、労働者の賃金支払いに関する基本的なルールを定めた条文です。
この条文は、労働者が適切に賃金を受け取るための基盤を提供し、労働者の生活を守ることを目的としています。
具体的には、賃金の支払方法や頻度、賃金を全額支払うことなどが定められています。
これにより、労働者は安定した収入を得ることができ、生活の不安を軽減することができます。
労働基準法第24条の内容は、次のとおりです。
1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条は、労働者の権利を守るための重要な法律であり、労働者にはその内容を理解することが求められているといえるでしょう。
労働者はこの法律を理解し、自分の権利をしっかりと把握することで、賃金の支払いに関するトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
賃金支払いの5原則
労働基準法第24条では、賃金の支払い方法について定めています。
労働基準法第24条で決められたルールを「賃金支払いの5原則」といい、次の5つです。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上の原則
- 一定期日払いの原則
では、それぞれについて解説します。
(1)通貨払いの原則
賃金は原則として、通貨で支払う必要があります。
つまり、現物支給や小切手、商品券などで支払うことは原則として禁止です。
ただし、労働者の同意があれば、労働者の銀行口座に振り込むことなどは、例外として認められています(労働基準法施行規則第7条の2)。
また、労働基準法施行規則の改正により、現在では電子マネーによる賃金の支払いも一部可能となっています(その場合も、労働者の同意は必要です)。
(2)直接払いの原則
中間に誰かが入って賃金を搾取することを防ぐため、賃金は直接労働者本人に支払われる必要があります。
そのため、たとえ労働者の希望であったとしても、労働者本人以外に賃金を支払うことはできません。
たとえば、労働者が未成年者の場合で、親などの法定代理人に対する支払いであっても、この原則に違反することになります。
ただし、「使者」に対する支払いは可能とされています。
(3)全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わねばなりません。そのため、賃金の分割払いは認められません。
また、使用者の労働者に対する債権と労働者の賃金債権を一方的に相殺することも、原則として認められないとされています。
ただし、例外として源泉徴収や社会保険料の控除など、一定の控除は認められています。
(4)毎月1回以上の原則
賃金は、毎月必ず1回以上支払わねばなりません。労働者の生活の安定を図るためです。
年俸制を採用している場合であっても、分割して少なくとも月に1回以上支払う必要があります。
ただし、臨時に支払われる賃金や賞与(ボーナス)には、この原則は適用されません。
(5)一定期日払いの原則
賃金は、あらかじめ決めた一定の期日に支払う必要があります。
たとえば、「毎月25日」や「毎月末日」などです。
一方、「毎月第2月曜日」のように毎月の変動が大きい期日や「毎月15日から25日の間」のように幅を持たせた期日を設定することは、この原則に反し許されません。
ただし、臨時に支払われる賃金や賞与(ボーナス)には、この原則は適用されません。
労働基準法第24条違反の実態
労働基準法第24条の違反は、労働者の賃金に直接影響を及ぼす重大な問題です。
よくある違反事例としては、賃金の未払い、支払いの遅れなどが挙げられます。 これらの違反は、労働者の生活を不安定にし、経済的な困難を引き起こす可能性があります。
違反が発生する原因としては、企業の経営不振や管理体制の不備、労働者の権利に対する無理解などが考えられます。
また、労働者自身が自分の権利を十分に理解していないことも、違反を見過ごす要因となりかねません。
違反が発覚したら、労働基準監督署への相談や、場合によっては法的措置を取ることも検討してください。
労働者には、自分の賃金が適切に支払われているかを常に確認し、問題があれば早期に対応することが求められています。 特に違反を未然に防ぐことが、労働者の権利を守る第一歩です。
違反した場合の罰則
労働基準法第24条に違反した場合、企業や使用者には罰則が科されることがあります。
賃金の未払いといった同条の違反行為の法定刑は、30万円以下の罰金です。 罰則は、労働者の権利を守るために、企業に対して法令遵守を促す役割を果たしています。
まず、労働者は、自分の賃金が適切に支払われていないと感じた場合、労働基準監督署に相談することを検討してみましょう。 その場合、労働基準監督署が会社に賃金支払いを促してくれることがあります。
それでも賃金の支払いがない場合は、労働基準監督署による立入調査や行政指導が行なわれることもあります。
それでも企業が賃金を支払わない場合、前述の刑事罰を科されることもあるでしょう。
労働者が知っておくべきこと
労働基準法第24条に関して、労働者が知っておくべきことは、自分の賃金に関する権利についてです。
基本的に、賃金は通貨で直接、全額、毎月1回以上、一定の期日に支払われるべきであることを理解しましょう。これらの原則が守られていない場合、労働者は不利益を被る可能性があるからです。
さらに、賃金に関する問題が発生した場合には、労働基準監督署に相談することができます。労働者は、自分の給与明細を定期的に確認し、不明な点があればすぐに使用者に問い合わせましょう。
また、労働組合や、弁護士など専門家への相談窓口を活用することで、問題解決のサポートを受けることができる場合があります。
知識を持つことで、労働者は自分の権利を守り、安心して働ける環境を築くことができるでしょう。
【まとめ】労働基準法第24条では、「賃金支払いの5原則」が定められている
労働基準法第24条は、労働者の賃金に関する基本的な権利を守るための重要な条文です。 この条文では、「賃金支払いの5原則」が定められています。
賃金支払いの5原則は次のとおりです。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上の原則
- 一定期日払いの原則
これらの原則をしっかりと理解し、それぞれの例外や違反となりやすいケースについても知識を深めることが大切です。
そして、問題が発生した際には、労働基準監督署に相談するなど、適切な対応を取ることが求められます。
自分の権利を守るために積極的に行動し、安心して働ける環境を整えることが、より良い労働生活を実現する鍵となるでしょう。