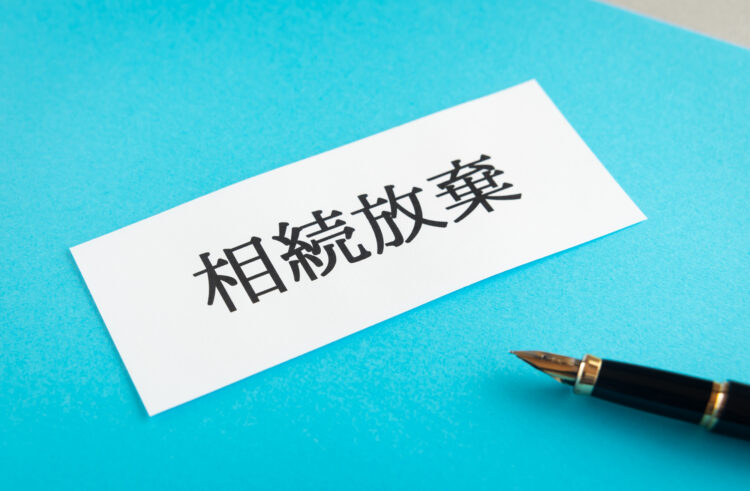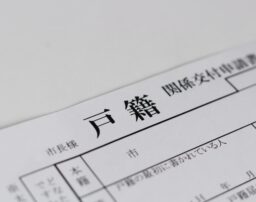相続の場面では「相続開始日」と「相続開始を知った日」という2つの日付が存在し、それぞれ違う意味を持ちます。これらの日付を正しく理解しないと、手続きの期限を守れずにペナルティを受けるリスクがあるため、非常に注意が必要です。
例えば、相続放棄の期限や相続税の申告期限は、これらの日付を基準に設定されており、期限を過ぎると重大な問題に発展する可能性があります。
本コラムでは、相続開始日や相続開始を知った日の違いや特別なケースにおける相続開始日についてくわしく解説します。
これを読んでいただくことで、相続手続きの期限を把握することができるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 相続開始日と相続開始を知った日の違い
- 相続手続き(相続放棄や税金など)の期限
- 失踪宣告をした場合の相続開始日
ここを押さえればOK!
相続開始日は被相続人が死亡した日であり、医師の診断書に記載された日が該当します。一方、相続開始を知った日は、相続人が被相続人の死亡を知り、自分が相続人であることを認識した日です。この日付は相続人ごとに異なる場合があります。
相続手続には期限があり、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内、遺留分侵害額請求は1年以内に行う必要があります。
失踪宣告を受けた場合には、7年経過後や危難が去った後1年経過した時点で死亡とみなされ、相続開始日が設定されます。
相続手続には、手続によって守らなければならない期限がありますので、書類の収集や作成も早め早めに進めることをお勧めします。相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続開始日とは
相続開始日とは、相続される人(被相続人)が死亡した日を指します。
例えば、病気や老衰で亡くなった場合、医師の診断書に記載された死亡日が相続開始日となります。
相続開始日と相続開始を知った日の違いとは
相続開始日と相続開始を知った日の違いは、次の通りです。
- 相続開始日:相続される人(被相続人)が亡くなった日
- 相続開始を知った日:相続する人(相続人)が相続される人(被相続人)の死亡を知り、かつ、自分が相続人であることを知った日
相続開始を知った日は、相続人ごとに違ってくる場合があります。
例えば、相続人の一人が疎遠で、被相続人の死亡を知るのが遅かった場合には、その人だけ相続開始を知った日が遅くなります。
相続に関する手続きの期限とは
相続手続きの期限を過ぎると、ペナルティを受ける場合もあります。
相続手続きの期限を守るために、各手続きの期限について知っておきましょう。
(1)相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。相続放棄を行うことで、相続人は遺産や負債を一切受け取らずに済みます。
期限の延長の手続をしないままこの期限を過ぎてしまうと、原則相続放棄することができなくなります。
(2)限定承認の期限
限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
限定承認を行うことで、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことができます。
(3)相続税の申告の期限
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告期限を過ぎると、追加の税金やペナルティが発生する可能性があります。
この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。
(4)準確定申告の期限
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
準確定申告とは死亡した人の1月1日から死亡した日までの所得税の申告をすることです。
(5)遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する贈与(遺贈)を知った日から1年以内に行う必要があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その不足分を請求する手続きです。
例えば、法定相続人であるのに、遺言で相続人から外されて何の財産も相続できなかった場合に使います。法定相続人は、法律上一定の財産の取り分が保証されていて、遺言で「相続しない」とされていても「遺留分」を自己の取り分として請求することができます。
相続開始日はいつになる?失踪宣告とは
失踪宣告とは、生死がわからない状態が続いている場合に死亡したとみなす制度のことです。例えば、次のような場合に、家庭裁判所は利害関係人(家族など)の請求を受けて失踪宣告をすることができます。
- 生死がわからないまま7年経過したとき
- 船舶事故や戦争などの危難が去った後1年間生死がわからないとき
そして、失踪宣告を受けると、生きていることの証明がない限り、死亡したものとみなされます。
- 生死がわからないまま7年経過したとき :7年の期間が満了したときが「死亡日(相続開始日)」
- 船舶事故や戦争などの危難が去った後1年間生死がわからないとき:危難が去ったときが「死亡日(相続開始日)」
【まとめ】相続開始日とは死亡した日|相続開始を知った日とは違う
この記事のまとめは、次の通りです。
- 「相続開始日」と「相続開始を知った日の違い」
- 相続開始日:被相続人が死亡した日
- 相続開始を知った日:相続人が被相続人の死亡を知り、自分が相続人であることを認識した日
- 相続手続きの期限
- 相続放棄の期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
- 限定承認の期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
- 相続税の申告の期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 準確定申告の期限::相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 遺留分侵害額請求の期限:相続開始と遺留分を侵害する贈与(遺贈)を知った日から1年以内
- 失踪宣告(生死がわからない状態が続く場合に死亡とみなす制度)
- 生死がわからないまま7年経過した場合:7年満了の日が相続開始日
- 船舶事故や戦争などの危難が去った後1年間生死がわからない場合:危難が去った時が相続開始日
相続手続きを適切に進めるためには、期限を守ることが不可欠です。手続きが複雑で不安な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
アディーレ法律事務所は、相続税・相続放棄など相続手続について積極的にご相談・ご依頼を承っております。
「もしうまくいかなかったら弁護士費用無駄になってしまうんじゃない?」
ご安心ください、アディーレには「損はさせない保証」というものがあります。
すなわち、アディーレ法律事務所では、弁護士にご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません。
なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。
※以上につき2025年5月時点
相続税・相続放棄など相続手続についてお困りの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談ください。