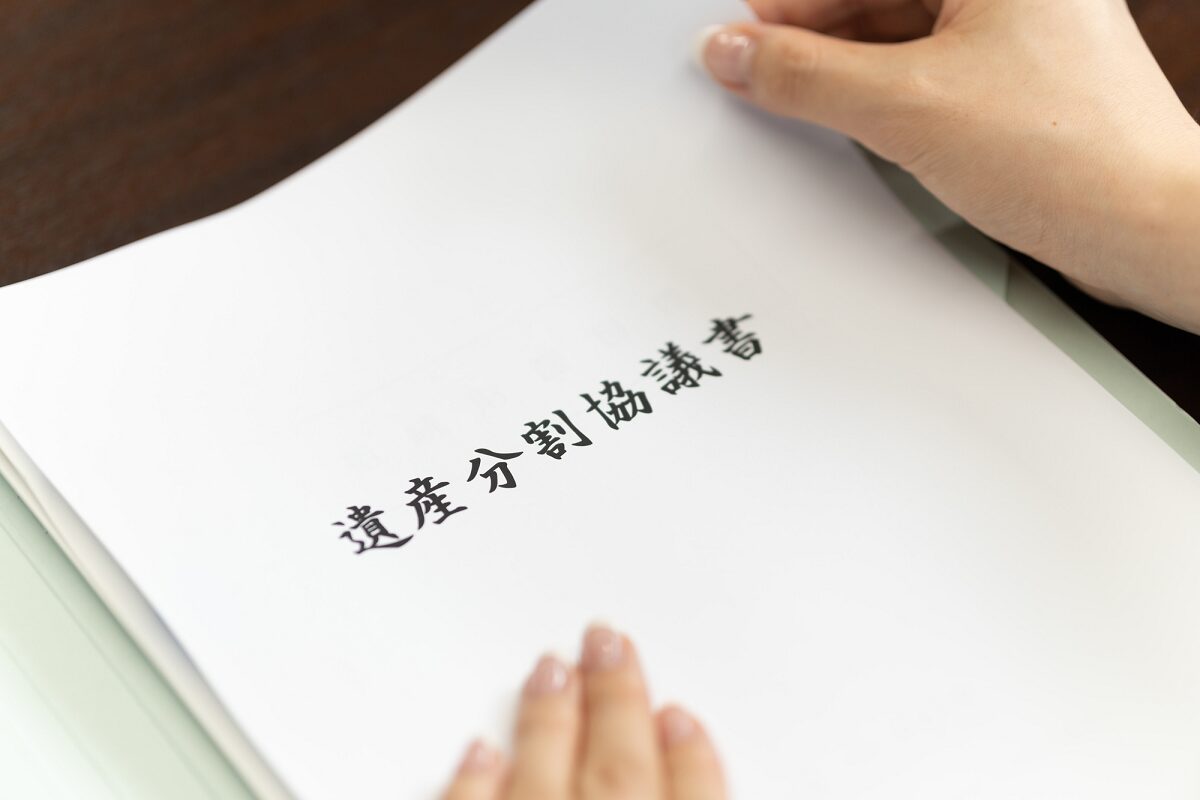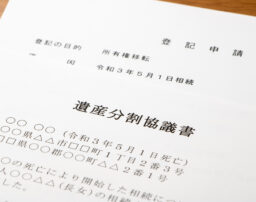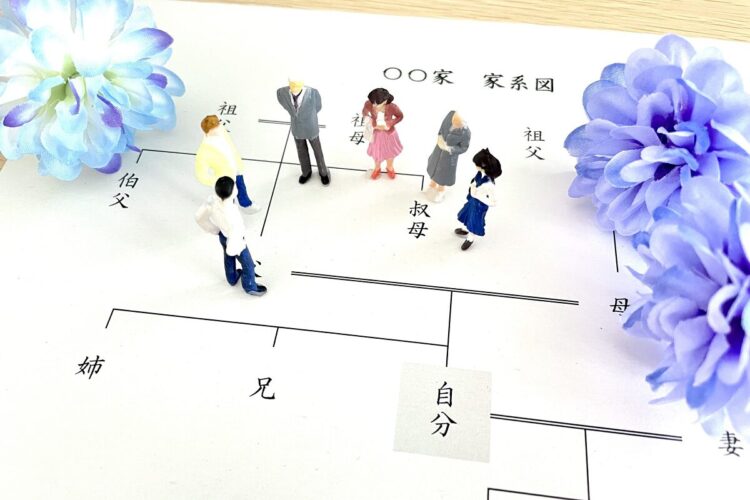「亡くなった親の遺産を、兄弟姉妹でどう分けるか話し合うことに。遺産分割ってどんな風にやればいいの?」
相続人の間で遺産を分ける手続である「遺産分割」では、相続人同士の意見の違いからトラブルに発展するケースも珍しくありません。
お金が絡む話であるだけに、当事者同士ではなかなか話がまとまらないこともあるでしょう。
なるべくスムーズに遺産分割などの相続手続を終えるためには、第三者である弁護士に対応を任せることをおすすめします。
この記事を読んでわかること
- 遺産分割の種類や手続の流れ
- 遺産分割で揉めるケース
- 遺産分割でよくある疑問の答え
ここを押さえればOK!
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
相続手続の流れとしては、まず遺言書の有無を確認し、遺産の調査と相続人の確定を行い、相続人全員で遺産分割協議を行って協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、さらに調停が不成立の場合は審判手続に移行します。
遺産分割で揉めるケースとしては、連絡が取れない相続人や寄与分・特別受益を主張する相続人がいる場合、不動産の分割方法で意見が合わない場合などがあります。
遺産分割に関わりたくなく、遺産にも興味がない場合には、相続放棄を検討してみましょう。また、遺言書に1人がすべての財産を相続すると記載されていて、遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求が可能です。
相続手続きでお悩みの方は、1人で悩まず、アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺産分割とは?
遺産分割とは、基本的に被相続人が遺した財産を相続人の間で具体的に分ける手続のことです。
遺産分割協議において、各相続人が受け取る財産の内容と割合を話し合います。
ただし、遺産分割協議がまとまるまで遺産は相続人全員の共有状態となるため、基本的には相続人が単独で遺産を処分することはできません。
(「仮払い制度」により、一定の範囲内であればほかの相続人の同意なく預貯金を引き出すことは可能。)
遺産分割協議において、各相続人が受け取る財産の具体的な内容と割合を決定します。
なお、後述のとおり、遺言書が存在する場合には、原則としてその内容に基づいた遺産分割が行われます。遺言書がない場合や相続人間での合意が難しい場合には、調停や審判といった手続が必要となることもあります。
遺産分割の方法は4種類ある
遺産といっても、預貯金のように分割しやすいものだけとは限りません。
遺産分割には4種類あるため、それぞれについてご説明します。
(1)現物分割
現物分割とは、遺産を売却して現金化などせず、現物をそのまま相続人ごとに分ける方法です。
たとえば、「この不動産は○○さん」「この銀行口座の預金は△△さん」「この証券口座の株式は××さん」といった具合でように分けます。
現物分割には、各相続人の相続分が公平になるように分けることが難しいといった問題点があります。
(2)代償分割
代償分割とは、不動産などを一部の相続人が相続した結果、相続分以上の財産を取得することになった場合に、その代償としてほかの相続人に金銭等を支払う方法です。
土地や建物など、物理的に分割することが不可能あるいは難しい遺産を、売却処分せずに相続したい場合には、代償分割が選択されやすいでしょう。
(3)換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えたうえで、各相続人に分割する方法です。
この方法には、公平に遺産を分けられるというメリットがありますが、遺産そのものは手放す必要が生じてしまいます。
また、売却処分に手間や費用がかかるだけでなく、場合によっては譲渡所得税がかかるため、その点には注意が必要です。
参照:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
(4)共有分割
共有分割とは、遺産を各相続人の共有状態のままにしておく方法です。
基本的に何もしなくていいので楽ではありますが、不動産などの場合で、のちに売却・賃貸したいとなった際にトラブルに発展しかねません。
また、共有者の一人が亡くなった場合、その共有者の相続人が共有者として新たに加わり、権利関係が複雑になりがちです。
結局は問題の先送りになってしまうと考えられるため、おすすめしやすい分割方法とはいえないでしょう。
遺産分割手続の流れ
次に、遺産分割手続の大まかな流れについてご説明します。
まずは「遺言書があるかどうか」が注目すべきポイントになるでしょう。
(1)遺言書の内容確認
亡くなった人(被相続人)の遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割を行う(遺言執行)のが原則です。
もっとも、遺言書が法律で決められた方法に従って作成されていない場合や、遺言書の内容によっては、遺言書が無効となる可能性があります。
そのため、まずは遺言書の内容をきちんと確認しましょう。
遺言書がかかれた当時、認知症などで被相続人には遺言能力がなかったと判断される場合にも、遺言書が無効となる可能性があります。
遺言書がある場合の手続について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)遺産の調査および相続人の確定
どんな遺産がどれだけあるのか調査し、相続人は誰なのか確定しましょう。
遺産の調査は、プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても洗い出すことを忘れないようにしてください。
また、不動産に関しては、価格も調査しておきましょう。
なお、遺産分割には、相続人全員の同意が必要です。
一人でも欠けた状態でまとまった遺産分割協議は、無効になる可能性があります。
誰も知らなかった相続人が見つかるケースも考えられるため、場合によっては被相続人の出生から死亡までの戸籍の調査が必要になります。
(3)遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
のちのちトラブルになることを回避するためにも、協議がまとまったら書面にその内容を記載するようにしましょう。
また、不動産の相続登記や金融機関の名義変更などの相続手続の際にも、遺産分割協議書が必要になることがあります。
(4)協議がまとまらなければ遺産分割調停
相続人同士の話合いである遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所を介した手続を利用することになるでしょう。
具体的には、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
申立費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で、主な必要書類は次のとおりです。
- 申立書(および相手方の人数分の写し)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書(例:不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し) など
参照:遺産分割調停|裁判所
調停は、あくまで調停委員を介した話合いの手続です。
相続人同士で納得できない部分があれば、調停が長引いてしまうケースもあります。
(5)調停もまとまらなければ遺産分割審判
遺産分割調停がまとまらず、不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行し、家庭裁判所が結論を出します。
その場合、各相続人が取得する遺産の額は、基本的には法定相続分を基準に決められることとなるでしょう。
遺産分割で揉めるケースとは?
それでは、遺産分割協議においてよくある、揉めてしまいがちなケースをご紹介します。
(1)連絡が取れない・参加を拒否する相続人がいる
遺産分割協議への参加を拒否したり、そもそも連絡の取れない相続人がいたりすると、協議がいつまで経っても進められません。
参加を拒否する相続人がいる場合、最終的には家庭裁判所における手続を利用するしかないため、遺産分割調停を申し立てることになるでしょう。
また、どうしても連絡が取れない相続人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることが必要です。
選任された不在者財産管理人が、さらに家庭裁判所の許可を得たうえで、連絡の取れない相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
相続手続などを弁護士に依頼していれば、その調査により、連絡の取れなかった相続人の住所などが判明する場合もあります。
家庭裁判所での手続を利用する前に、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。
(2)寄与分や特別受益などを主張する相続人がいる
一部の相続人が被相続人を無償で介護することなどによって、その財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その相続人が本来の法定相続分よりも多くの遺産を相続できるようにする制度があります。
これが「寄与分」の制度です。
たとえば、介護施設やサービスを利用せずに介護を行った場合、その分の料金を節約できるため、被相続人の財産を減らさずに済んだといえるでしょう。
したがって、被相続人の生前に介護などの身の回りの世話をしていた相続人がいる場合には、自分の取り分を多くすべきだと主張することがあります。
一方、被相続人の生前、被相続人から贈与を受けていた相続人がいる場合、その相続人の相続分は本来の法定相続分よりも少なくなります。
これが「特別受益者の相続分」です。
たとえば、相続人である子どもたちのなかで、長男だけが結婚の際に多大な経済的援助を受けていたような場合などです。
被相続人の介護や、被相続人からの経済的援助などの事情があると、相続人間における不公平感が生じやすいため、揉める原因になりやすいでしょう。
(3)すべての遺産が開示されない
被相続人と長らく同居していた相続人が、ほかの相続人に対して遺産を開示しないとせず、「隠している財産があるのでは?」といったトラブルが生じることがあります。
すでに調停など裁判所の手続を利用している場合には、裁判所の調査嘱託などの制度を利用できる場合があります。
また、調停委員や裁判官などの説得により、当該相続人が遺産に関する情報や資料の開示に応じることもあるでしょう。
なお、遺産の使い込みが発覚した場合には、使い込みをした相続人以外の相続人全員の同意により、使い込まれた遺産がまだ存在するとみなして、遺産分割を行うことができます。
(4)不動産の分割方法で意見が合わない
特に土地や建物といった不動産については、その分割方法について相続人間で意見が合わないことも多くあります。
また、思い出のある家を売却して手放したくない一方、その家が非常に高額である場合、代償分割したくても代償金を支払うことができないという問題に直面することもあるようです。
遺産分割でよくある質問(Q&A)
(1)遺産分割に関わりたくない場合はどうするべき?
遺産分割に関わりたくない場合には、相続放棄をすれば協議に関わらずに済みます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。裏を返せば、相続人でなければ参加しなくてもよいのです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄は、被相続人にプラスの財産を上回る負債がある場合だけでなく、相続争いに関わりたくない相続人がいる場合にも利用されることがあります。
なお、相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申述することが必要です。
参照:相続の放棄の申述|裁判所
事情によっては、書類を郵送するだけで、実際に家庭裁判所に出向くことなく相続放棄ができるケースも多いです!
相続放棄の手続を弁護士に依頼することを検討中の方は次の相続放棄についてのページをご覧ください。
(2)遺産分割はいつ行うべき?
法律上、遺産分割を行うべき明確な期限はありません。
しかし、あまり長い間放置していると、誰かに遺産を使い込まれるリスクが高まるだけでなく、せっかくの遺産を有効に活用できなくなってしまいます。
そのため、遺産分割はなるべく早く行うようにしましょう。
なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内とされています。
参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
相続税の申告が必要なケースは多くありませんが、遺産分割を完了すべき目安として意識するといいでしょう。
(3)遺言書に1人がすべての財産を相続すると記載されていた場合、遺産を受け取れないは?
相続人全員(受遺者(※1)を含む)相続人全員の同意があれば、必ずしも遺言の内容に従う必要はないと考えられています。
※1:被相続人から財産を遺贈された人
もっとも、全員の同意が得られそうにないなら、「遺留分侵害額請求」という手段があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(例:配偶者や子ども)に認められている、最低限保証される相続分のことです。
遺留分を下回る遺産しか相続できなかった相続人は、多めに遺産を相続した人(受遺者を含む)に対し、不足している分を金銭で支払うよう請求することができます(民法第1046条1項)。
したがって、「1人がすべての財産を相続する」といった遺留分を侵害する内容の遺言があった場合は、遺留分侵害額請求によって、最低限の取り分を確保することができます。
遺留分侵害額請求には期限(※2)があり、遺留分の計算方法は複雑で難しいことも多いため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
※2:遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」、あるいは「相続開始の時から10年を経過したとき」には、時効又は除斥期間の経過によって消滅します。
【まとめ】遺産分割とは、相続人の間で遺産を分ける手続|揉める前に弁護士に相談を
連絡が取れない相続人や、被相続人の介護をしていた相続人、被相続人から特別に援助を受けていた相続人がいる場合などでは、遺産分割協議が進まないこともあります。そのような場合には、一度弁護士への相談をお勧めします。
事情によっては、弁護士の介入によって協議段階でまとまるケースもありますし、調停を行うことになっても、申立てなどの手続をサポートしてもらえるためです。
相続問題でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。