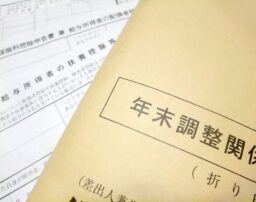「給与」「手当」「賞与」など、様々な名称で支払われる金銭。
これらの意味や違いを正確に理解しているでしょうか。
本コラムでは、報酬や、給与、手当、賞与などのそれぞれの違いについて、弁護士が分かりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 報酬とは
- 給与、手当、賞与とは
- 報酬に関する法律
ここを押さえればOK!
賃金の種類には、基本給である「給料」、特定の目的や条件に応じて支給される「手当」、業績や功績に応じて支給される「賞与」があります。
賃金に関する法律として、労働基準法と最低賃金法があります。労働基準法では賃金支払いの5原則(通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払い)を定めています。最低賃金法では、地域別最低賃金と特定最低賃金を規定しています。
また、パートタイム・有期雇用労働法により、同一労働同一賃金の原則が定められ、正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されています。
自分の賃金について疑問や不安がある場合は、そのままにせず、まずは会社の担当者に相談してみるとよいでしょう。
賃金とは?
法律上、労働法の分野では「賃金」と呼ばれ、社会保険の分野では「報酬」と呼ばれています。その中には、給料、手当、賞与その他の名称で支払われるものも含まれます。
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
労働基準法第11条
「この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
健康保険法3条5項
賃金の種類:あなたが受け取っているのはどれ?
賃金には様々な種類があり、労務管理上区別されています。
ここでは、給料、手当、賞与について説明します。
自分がどんな報酬をもらっているかは、給与明細や労働契約書などで確認することができるでしょう。
(1)基本給
基本給は、労働の基本的な対価として定期的に支払われる固定給です。
手当や賞与は含みません。
基本給の特徴:
- 定期的に一定額が支払われる
- 昇給の対象となることが多い
(2)手当
諸手当は、基本給に加えて特定の目的や条件に応じて支給される追加的な給付です。法律で支払いが義務付けられているものと、会社の裁量で決められるものがあります。
<法律で支払いが義務付けられている手当の例>
- 時間外労働手当:原則1日8時間週40時間を超える労働に対して支払われる(25%以上の割増率、月60時間を超えたら50%以上の割増率)
- 深夜労働手当:午後10時から朝5時までの労働に対して支払われる(25%以上の割増率)
- 休日出勤手当:法定休日の労働に対して支払われる(35%以上の割増率)
<会社の裁量で決められる手当の例>
- 通勤手当:通勤にかかる費用の補填
- 住宅手当:住居費用の補助
- 家族手当:扶養家族がいる従業員への支援
- 役職手当:管理職などの責任に対する対価
- 資格手当:特定の資格保有者への追加給付
- 慶弔手当:結婚祝いなど
手当の内容がよくわからない場合には、労働契約や就業規則で諸手当の支給条件などを確認したり、給与を扱っている担当部署に問い合わせたりするとよいでしょう。
(3)賞与
賞与は、一般的には、企業の業績や従業員の功績等に応じて支給される一時金です。
通常、年に1〜2回支給されることが多く、従業員のモチベーション向上や業績向上への貢献を目的としています。
労働基準法上では、賞与とは、支払期日が定められておらず、臨時に支払われる労働の対価のことを言います(労働基準法24条2項但書)。
厚生年金保険法、健康保険法上では、賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。(厚生年金保険法3条1項4号、健康保険法3条6項)。
このように、社会保険上、年4回以上支払われるものは報酬とみなされ、賞与としては扱われません。
賃金に関する法律:労働者の権利を守る基本ルール
賃金に関する労働者の権利は、主に労働基準法と最低賃金法によって保護されています。
これらの法律は、労働者が適正な賃金を確実に受け取れるよう、使用者に対して様々な義務を課しています。
主な法律と保護内容:
- 労働基準法:賃金支払いの5原則を定める
- 最低賃金法:最低賃金額を規定する
- パートタイム・有期雇用労働法:同一労働同一賃金の原則
以下、説明します。
(1)賃金支払いの5原則:使用者が守るべきルール
労働基準法第24条では、賃金支払いに関する5つの原則を定めています。これらの原則は、労働者が確実に報酬を受け取れるよう、使用者に義務付けられたものです。
<賃金支払いの5原則>
- 通貨払いの原則
:賃金は原則として現物支給などではなく「円」のお金で支払わなければならないというルール - 直接払いの原則
:賃金は原則として代理人などの第三者ではなく労働者に直接支払わなければならないというルール - 全額払いの原則
:原則としてその支払日に支払われるべき賃金の全額が支払われなければならないというルール - 毎月1回以上払いの原則
:賃金は原則として毎月1回以上支払わなければならないというルール - 一定期日払いの原則
:賃金は原則として一定の期日に支払われなければならないというルール
残業代も賃金に含まれますので、支払日に支払われなければ、全額払いの原則に違反することになります。
(2)最低賃金:あなたの賃金は適正?
「最低賃金」とは、法令で定められた最低限支払わなくてはならない1時間あたりの賃金です。
正社員はもちろん、パート・アルバイトの方であっても、正社員と同じ水準の最低賃金が適用されます。
最低賃金を下回る賃金で雇用契約を結んでも、その契約のうち賃金の部分は無効とされます。
この場合、労働者は最低賃金を基準とする賃金を請求することができます。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
(2-1)地域別最低賃金:都道府県ごとに定められる
地域別最低賃金は、例年10月に改訂されます。
2024年10月以降、最低賃金が最も高いのは東京都(1時間1163円)、最も低いのは秋田県(1時間951円)です。
地域別の一覧については、下記サイトを参考にしてください。
(2-2)特定最低賃金:特定の産業に適用される
特定最低賃金とは、鉄鋼業、各種商品小売業、自動車小売業、非鉄金属製造業など特定の職業に定められている地域別最低賃金よりも高い最低賃金です。
2024年3月時点で、全国で224件の最低賃金が定められています。
自分の給料が最低賃金より少ない場合には、労働基準監督署や労働トラブルを扱う弁護士に相談するとよいでしょう。
(3)同一労働同一賃金の原則:正社員と非正規の不合理な待遇差の禁止
同じ会社で、正社員と非正規雇用の労働者(バイト、パートなど)について、基本給や賞与などあらゆる待遇については、不合理な差を設けることは禁止されています(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)。
例えば、正社員とパートで賃金が違う場合、「将来の役割の期待が異なるため、賃金の決定基準が異なる」といった主観的・抽象的理由では不十分です。
賃金の決定基準は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはいけません。
まとめ
労働における賃金は、基本給だけでなく、手当や賞与も含む労働の対価全体を指します。法律により定義が違うことがあるので注意が必要です。
自分が受け取っている賃金について、給与明細などを確認してしっかり理解するようにしましょう。
もし最低賃金を下回る賃金だったり、法律上支払うことが義務付けられている一定の残業手当を支払っていなかったりする場合には、あなたの労働力が不当に搾取されている可能性があります。
疑問や不安がある場合は、そのままにせず、就業規則や労働規則を調べる、会社の担当者に質問する、労働基準監督署に相談するなど、適切に対処するとよいでしょう。