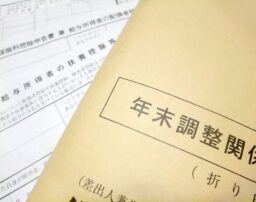仕事中の事故でケガ、病気、最悪のケースでは死に至ることも。
そんな不測の事態に遭遇したときには、労災保険による給付を受けることができます。
しかし、「労災申請には期限があるの?」「申請の手続きはどうすればいいの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、労災申請の期限や手続きについて、わかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 労災給付金の種類
- 労災給付金別の申請期限
- 労災申請の手続き
ここを押さえればOK!
期限を過ぎると給付を受けられなくなるため注意が必要です。
労災申請の基本的な流れは、1.労働災害の発生と報告、2.医療機関での受診、3.申請書類の準備、4.労働基準監督署への申請、5.調査、6.支給・不支給の決定となります。
健康保険使用後の労災申請も可能ですが、手続きが必要です。会社が労災申請に非協力的でも、労働者自身で申請できます。また、労災申請と別に会社への損害賠償請求も可能ですが、労災問題を扱っている弁護士に相談する事をお勧めします。
労災申請について不明点は、早めに労働基準監督署に相談するようにしましょう。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
労災保険制度とは
労災保険制度は、労働者の業務に起因して、又は通勤による事故・病気等に対して、必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その費用は、原則として、事業主が負担している保険料によって賄われています。
労災保険は、原則として、一人でも労働者を使用していれば、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
アルバイトやパートタイマー等の雇用形態とは関係なく、すべての労働者が保険給付の対象となります。
参考:労災補償|厚生労働省
労災保険給付金の種類
労災保険の給付金には、主に下記のように様々な種類があります。
- 療養(補償)給付:業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき
- 休業(補償)等給付:業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養することができず、そのために賃金を受けていないとき
- 障害(補償)給付:業務又は通勤が原因となった傷病が治った(症状固定した)が、障害等級に該当する身体障害が残ったとき
- 傷病(補償)給付:業務又は通勤が原因となった傷病の療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、障害の程度が傷病等級に該当するとき
- 遺族(補償)年金:労働者が死亡したときの給付
- 遺族(補償)一時金:労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合の給付
- 葬祭料(葬祭給付)など
まずは、ご自身が受け取れる可能性のある給付金はどれなのか、押さえておきましょう。
労災保険の給付金別の申請期限
労災保険の給付金を受けとるためには、必要書類等を労働基準監督署に提出して申請する必要がありますが、種類により、申請期限が異なります。
労災保険の給付請求権には時効があるため、起算日より一定の期間を経過すると、給付を受けられる権利が消滅してしまうのです。
申請期限を過ぎてしまった場合には、労災保険による給付は受けられません。
給付金ごとの期限を知り、期限内に申請を行うことは、労働者にとって非常に重要です。
主な労災保険給付の種類と申請期限は次の通りです(労働者災害補償保険法42条1項)。
| 給付金 | 時効 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 遺族(補償)年金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)一時金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
| 傷病(補償)年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。 |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
労災申請の基本的な流れ
労災申請の基本的な流れを理解することは、労働者が迅速かつ適切に補償を受けるために不可欠です。
申請プロセスは主に6つのステップに分かれます。
以下に、労働災害発生から申請、そして給付決定までの流れを説明します。
- 労働災害の発生と報告:
- 災害発生後、直ちに使用者に報告する
- 使用者は労働者死傷病報告を作成し、労働基準監督署に提出する(休業4日以上の場合)
- 医療機関での受診:
- 可能であれば労災指定医療機関で受診する
- 受診の際に労災保険を使用する旨を伝える
- 申請書類の準備:
- 必要な申請書類を入手し、記入する
- 医師の診断書や使用者の証明を取得する
- 必要書類は請求する給付金の種類によって異なる
- 労働基準監督署への申請:
- 準備した書類を労働基準監督署に提出する
- 原則として、労働者本人が申請するが、使用者が代行することも可能
- 労働基準監督署による調査:
- 提出された書類の審査
- 必要に応じて追加の調査や資料提出を求められる場合がある
- 支給・不支給の決定:
- 調査結果に基づき、労働基準監督署長が決定
- 本人に対し、決定を通知
労働基準監督署に提出す書類は給付金の種類によって異なります。厚生労働省のサイトを確認しながら、漏れのないように準備しましょう。
労働者からよくある労災申請の疑問と回答
業務上ケガや病気を負った労働者は、様々な不安があります。
労災申請に関しても、慣れない手続きで疑問がある人も少なくありません。よくある疑問と回答を紹介します。
(1)健康保険使用後の労災申請は可能か
健康保険使用後でも労災申請は可能です。
労災であることが後から判明した場合や、当初は業務外の傷病と思っていた場合は、健康保険で治療をした後になりますが、だからといって労災申請ができなくなるわけではありません。
受診した病院に、健康保険から労災保険に切り替えができないか相談します。切り替えができない場合には、いったん医療費全額を払ったうえで、労災保険に請求します。
切り替えができる場合には、切り替え手続きを行うことで、一部負担した医療費が返還されます。
ただし、すでに労災認定を受けていて、経済的事情で医療費全額の返納ができない場合には、一時的に自己負担することなく労災保険に請求する方法もあります。
詳しくは、労働基準監督署の窓口で問い合わせるようにしましょう。
(2)会社が労災申請に協力的でない場合はどうすべきか
会社の協力がなくても、労働者自身で労災申請を行うことができます。
会社が「労災に当たらない」といったとしても、労働者が必要だと思うのであれば、あきらめないようにしましょう。
労災申請は個人で行うことができますので、労働基準監督署へ出向き、会社が協力してくれない状況について説明して申請方法の指導を受けるとよいでしょう。
(3)会社の責任も問いたいが、会社に損害賠償請求は可能か
労災申請と民事上の損害賠償請求は別個の手続きです。
労災保険の給付金は、法律で決められた範囲のみであり、労働者が受けた損害すべてが保障されるわけではありません。
事業者の安全配慮義務違反によって、労働者の身体・生命に損害が生じた場合、労働者は事業者に対して、債務不履行(不法行為)に基づく損害賠償をすることができます。
両者の主な違いは次の通りです。
主な違い:
- 制度の根拠:
- 労災申請:労働者災害補償保険法
- 損害賠償請求:民法(不法行為責任や債務不履行責任)
- 請求の相手:
- 労災申請:国(労働基準監督署)
- 損害賠償請求:使用者(会社)
- 過失の要否:
- 労災申請:無過失責任(使用者の過失は問わない)
- 損害賠償請求:原則として使用者の過失が必要
- 補償・賠償の範囲:
- 労災申請:法定の保険給付(医療費、休業補償等)
- 損害賠償請求:実際の損害全額(慰謝料含む)
- 時効期間:
- 労災申請:原則2年または5年(給付金の種類によって異なる)
- 損害賠償請求:身体・生命に損害が生じた場合、権利を行使できることを知ったときから5年又は権利を行使することができるときから20年
例えば、工場で機械の不具合により負傷した場合、労災申請では使用者の過失を問わず補償を受けられますが、より広範な賠償を求める場合は、会社の民事上の責任を問う必要があります。
労災と損害賠償請求の両方の請求を行うことも可能ですが、2重取りできるわけではなく、労災保険給付分は損害賠償額から控除されます。
会社に対して損害賠償請求する場合には、労災問題を扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
【まとめ】労災申請には給付金の種類ごとに期限あり|早めに対応を
労災申請には給付金の種類ごとに定められた期限があり、期限内に申請しないと給付金を受け取ることができません。
労災事故が発生した場合には、速やかな事故報告、医療機関での適切な対応、労働基準監督署への申請などを速やかに行う必要があります。会社の協力が得られない場合でも、労災だと思う場合には、労働者が労災申請することができます。
不安な点は早めに労働基準監督署に相談するようにしましょう。
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2024年12月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。