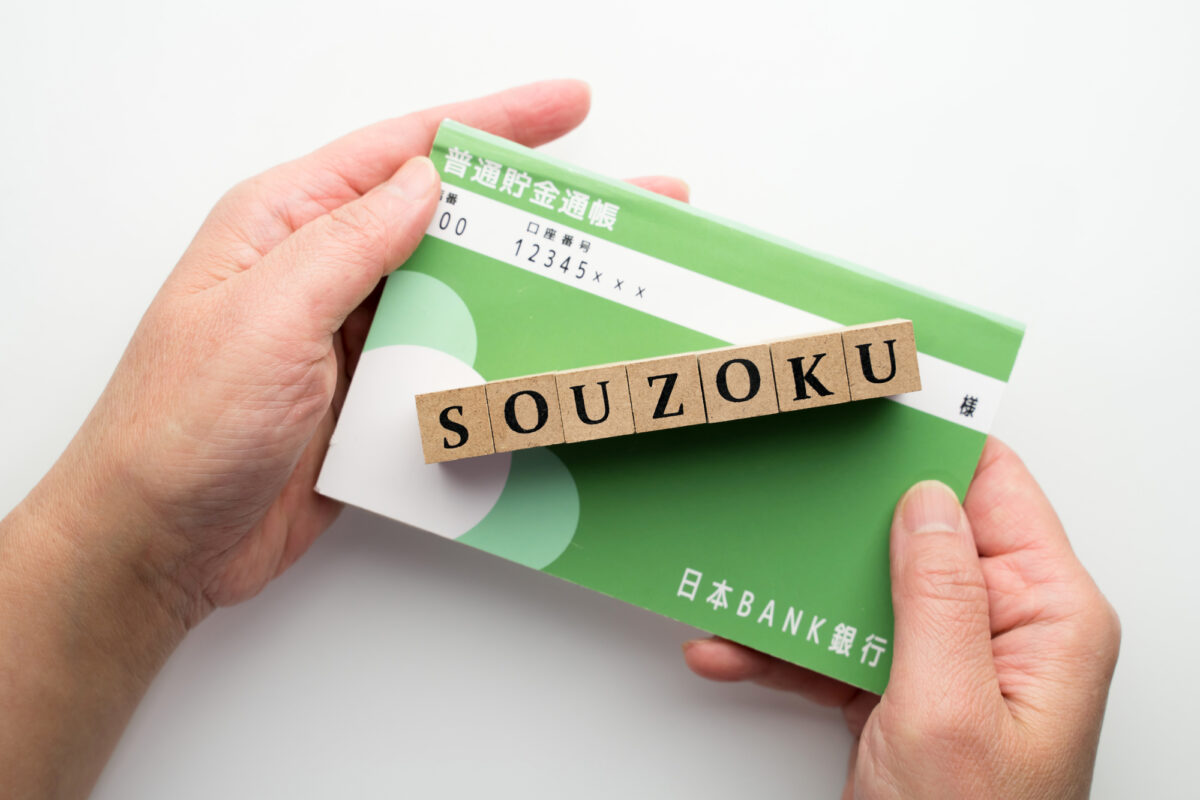大切な家族が亡くなった後、悲しむ間もなく様々な支払いに追われ、亡くなった方の預金を引き出す必要に迫られることがあります。
しかし、亡くなったことを銀行が把握すると、口座が凍結されるので、どのような手続きを踏めば良いか戸惑うことも多いでしょう。法的手続や必要な書類、注意点について知識がないと、手続がスムーズに進まない可能性があります。
この記事では、弁護士が故人の預金を引き出すための具体的な手続と注意点を詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
相続手続は遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって異なります。
遺言書がある場合はその内容に従い、遺産分割協議書がある場合は相続人全員の合意に基づいて進めます。
どちらもない場合は遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議が成立していない場合でも、預金払い戻し制度を利用して一部の預金を引き出すことが可能ですが、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続手続は複雑で労力がかかるため、相続人が多い場合や財産が不明確な場合、相続税が発生する可能性がある場合は、弁護士や税理士に相談することが重要です。相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続手続のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
故人の銀行口座が凍結されるタイミングと理由
銀行が預金の名義人の死亡を把握すると、その名義の銀行口座は凍結されます。相続人であっても、原則としてお金を引き出すことはできません。
これは、主に相続人間のトラブルを防ぐためと、不正引き出しを防止するための措置です。
相続人が被相続人の凍結された口座からお金を引き出すためには、面倒かもしれませんが必要な書類をそろえたうえで手続をする必要があります。
面倒な相続手続では、弁護士が強い味方になりますので、一度ご相談ください。
凍結前に預金を引き出すことはできる?
銀行が預金の名義人が死亡したことを把握するのは、通常相続人などからの連絡がきっかけとなります。
そこで、死亡したことを銀行に伝えなければ、口座は凍結されず、キャッシュカードや暗証番号が分かれば事実上預金を下ろすことができるでしょう。
しかし、被相続人の預金は相続財産ですので、亡くなった後に「黙って引き出した」ということになれば、後々相続人間でトラブルになる可能性があります。
銀行など金融機関には、速やかに死亡したことを伝えたうえで、適切な手続を経て、お金を引き出すようにしましょう。
故人の生前に、本人の了解を得て、本人に係る医療費や介護費などを本人の口座から引き出すことは問題がありません。ただし、相続トラブルを避けるために、使途や金額をメモし、領収証を保管しておくとよいでしょう。
【ケース別】個人の預金を引き出す手続
故人の預金は、相続財産です。
相続財産は、相続人が相続分に従って相続することになりますが、実際にどれだけ相続するかは、遺言があるかどうか、相続人同士でどのように合意するかによって異なります。
ここでは、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合の預金の引き出し手続について、ケース別に説明します。
(1)遺言書がある場合の手続
被相続人に遺言書がある場合、基本的に、遺言書に書かれた内容に従って相続財産が分割されます。
遺言書で「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇 の預貯金の元金及び利息について、〇〇(特定の相続人)に相続させる」という記載がある場合には、基本的にはその特定の相続人が、預金を引き出すことができます。
この場合、預金引き出しには次のような手順が必要です。
- 相続人の調査、確定
- 家庭裁判所に遺言書の検認の請求(自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合)
- 金融機関へ必要書類を提出(金融機関所定の届出書、遺言書、検認済証明書、故人の死亡が確認できる戸籍謄本(※)、当人の実印と印鑑登録証明書、故人の通帳・キャッシュカードなど) ※法務局で取得した法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできる
各金融機関によって、必要とされる書類が異なることがあります。事前に何が必要が問い合わせたうえで、書類を集めるとよいでしょう。
また、原本を提出した場合でも必要であれば原本は返却してくれるので、書類を提出するときに返却希望であることを伝えます。
遺言で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が預貯金を解約・引き出すことになります。
その場合でも、基本的に必要となる書類は同じですが、家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合にはそのことが分かる書類(遺言執行者選任審判書謄本)も必要です。遺言執行者が引き出す場合にも、事前に金融機関に対して必要な書類を確認するようにしましょう。
遺言がある場合の相続手続について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)遺産分割協議書がある場合の手続
遺産分割協議書がある場合、相続人全員の合意が成立しているため、その協議書に基づいて手続を進めます。具体的な手順は以下の通りです。
- 相続人と遺産の調査、確定
- 遺産分割協議書の作成・署名
- 金融機関へ必要書類の提出(金融機関所定の届出書、遺産分割協議書、亡くなった方の戸籍謄本(※)、すべての相続人の戸籍抄本(謄本)、すべての相続人の印鑑登録証明書、代表して預金を引き出す者の実印、故人の通帳・キャッシュカードなど) ※法務局で取得した法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできる
各金融機関によって、必要とされる書類が異なることがあります。事前に何が必要が問い合わせたうえで、書類を集めるとよいでしょう。
また、原本を提出した場合でも必要であれば原本は返却してくれるので、書類を提出するときに返却希望であることを伝えます。
(3)遺言書も遺産分割協議書もない場合の手続
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。その後、協議書に基づいて手続きを進めます。
しかし、遺産分割協議が成立するには何ヶ月もかかるケースもあり、その間被相続人の預金から支払いができないとなると、相続人が生活に困るなどの様々な問題があります。
(3-1)預金払い戻し制度とは
そのような場合には、預金払い戻し制度を利用しましょう。仮払い制度と言われたりもします。
この制度の利用により、遺産分割協議が成立していなくても、被相続人の預貯金を一部引き出すことが可能です。
この場合、本人確認書類に合わせて以下の書類を提出すれば、預金を払い戻すにあたって他の相続人の同意を得る必要はありません。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
※出生から死亡までの連続したもの - 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
- 金融機関所定の依頼書
ただし、金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、あらかじめ払戻しを受けたい金融機関に問い合わせておくのが確実でしょう。
(3-2)預金払い戻しの限度額
単独で払戻しができる額には次の限度があります。
「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」
被相続人の預金額が300万円で、相続人の法定相続分が2分の1のケースだと、 300万円×3分の1×2分の1=50万円を払い戻せます。
ただし、同一の金融機関から1人の相続人が払い戻せるのは上限150万円までです。
もし被相続人の預金額が1200万円であったとしても、150万円までしか払い戻せません。
払い戻したお金の使い道に限定はないので、何に使っても構いません。
当面の生活費に苦労しているのであれば、払戻し制度の利用は1つの方法です。
もっとも、この制度を利用すると相続放棄できなくなる可能性があることに注意が必要です。
弁護士や税理士に相談すべきケース
相続手続は、亡くなった後すぐに行わなければならないものから、数年かかっても大丈夫なものまで様々です。喪失感を抱えながら日々の生活を送らなければならない中で、相続手続を漏れなく行うことは大変な労力がかかります。
特に、相続人が多いケースや財産がよくわからないケース、相続税が発生するかもしれないケースでは、弁護士や税理士などへ相談する事が大切です。
通常、弁護士は相続に関する法律上の問題、税理士は相続に関する税金上の問題を取り扱いますが、税金の扱いについても依頼できる法律事務所もあります。
相談料無料で、電話で相談できる法律事務所も多いので、一度早い段階で相談してみるとよいでしょう。
【まとめ】遺産分割協議が成立していなくても、亡くなった人の預金引き出しは一部可能
被相続人の預金を引き出したい場合、遺産分割協議が成立していなくても、相続人が1人で一定額まで払い戻しできる制度がありますので、その利用を検討しましょう。
相続手続は、通常、相続人の確定、相続財産の把握、相続税の概算、他の相続人との合意形成が必要になりますが、相続人同士が疎遠だったりすると話し合いもうまくできないことがあります。
早い段階で、弁護士に相談・依頼することが、相続手続をスムーズに進めるポイントと言えるでしょう。
アディーレ法律事務所には、相続放棄、相続税、遺言書作成など、複雑な遺産相続の手続をまとめて依頼できます。相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。