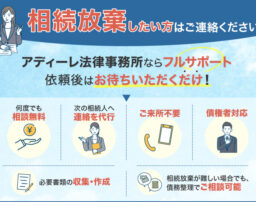亡くなった人の預金が少額であっても、相続手続は避けられません。
しかし、具体的な手続方法や必要な書類、注意点については多くの方が不安を抱えています。
特に、手続の手間や時間を最小限に抑えたい、精神的な負担を軽減したいという方にとって、正確な情報は欠かせません。
本記事では、少額の預金に関する相続手続の具体的な方法や注意点を詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると口座は凍結されますが、相続人は残高証明発行依頼書を提出して預金残高を確認できます。
預金を引き出すには相続手続が必要で、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を準備しなければならず、費用と手間がかかります。
相続手続は、預金を含めた財産調査、相続人調査、遺産分割協議を経て行われ、必要書類を準備して預金を引き出します。
少額しかない預金口座は生前に解約することも検討しましょう。
借金が多い場合は相続放棄を検討し、相続財産には触れないようにします。
相続手続でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続手続のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
亡くなった人の預金が少額の場合は放置していい?
亡くなった人=被相続人の預金額が少額であっても、基本的には、相続人が相続手続をすることになります。
しかし、預金額が数百円、数千円など極めて少額の場合、実際に相続手続を行って預金を引き出すかどうかは、それにかかる手間や費用を考慮する必要があるでしょう。
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、その人の口座を凍結します。
凍結後であっても、相続人は預金残高を確認することができます。相続用の「残高証明発行依頼書」を提出して、預金残高を正確に把握しましょう。
相続人が凍結された口座から預金を引き出すためには、遺言かあるかどうかで必要書類が異なります。
一般的に、被相続人の死亡が分かる戸籍謄本、相続人の戸籍抄本又は謄本、相続人が複数いる場合には遺産分割協議書など、様々な書類が必要です。書類を集めるのにも費用と手間がかかります。
このような費用と手間を考えると、放置することが経済的には合理的な判断となることもあるでしょう。
放置された口座はずっとそのままにされるわけではありません。10年取引のない「休眠預金」は法律に基づき民間公益活動のために利用されます。
亡くなった預金をどうにかしたいが、自分では不安という方は、相続手続を弁護士に任せることができます。
亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続が必要な場合
亡くなった人の預金が少額の場合でも、相続人が複数いる場合や相続税の申告が必要な場合には、相続手続を行った方がよいでしょう。
「相続人とは疎遠で話し合いが難しい」「相続財産の調査方法がわからない」など相続手続でのお悩みは、なるべく早い段階で、相続を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
(1)相続人が2人以上の場合
預金額が少額で遺産が少なくても、相続人が2人以上いる場合には、遺産分割協議を行って遺産をどうわけるか合意をする必要があります。
相続分については法律で決まっていますが、どの相続人が、どの財産をどのように相続するかまでは法律で決まっていません。また、相続分も相続人同士の話し合いで変更することが可能です。
この話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印で押印することで、正式に遺産分割協議が成立します。
預金引き出しの際には、遺産分割協議書も必要書類となります。
(2)相続税の申告が必要な場合
亡くなった人の預金が少額でも、不動産などの価値が高い場合などでは、相続税が発生することがあります。
相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に、相続税の申告をし、かつ納付しなければなりません。
預金額が少ない場合でも、相続税の対象となる相続財産ですので、そのまま放置することはできず、相続手続きが必要となります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」が相続税の基礎控除額です。
相続税の計算は複雑でわかりにくいので、相続を扱っている弁護士や税理士に相談するとよいでしょう。
預金が少額の場合は生前に解約を
預金が少額の場合は、相続人にかかる負担を考慮して、生前に終活の一種として、解約を検討することも一つの方法です。生前に少額の預金口座を解約し、遺産を整理しておくと、相続手続の手間を省くことができるでしょう。
借金の方が多いときは相続放棄を検討する
少額の預金はあるが、それ以上に借金が多い場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄を家庭裁判所に申述して認められると、初めから相続人でなかったことになりますので、少額の預金も借金も、遺産は相続しません。
ただし、相続財産である預金を解約・払い戻ししてしまうと、相続放棄できなくなるおそれがありますので、相続放棄を検討しているときには預金の払い戻しを含め、遺産には一切触れないようにしましょう。また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから原則3ケ月以内にする必要があります。
相続放棄は、借金の方が多い場合の他、被相続人とは疎遠で相続に関わりあいたくない、というようなケースでも利用されます。
相続放棄を検討している人は、相続財産には触らず、相続開始後なるべく早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。
亡くなった人の預金が少額の場合の相続手続
相続手続は、基本的に相続財産が少なくても通常と同じ流れです。遺言がある場合には遺言に従って相続手続を行います。遺言書がない場合には、一般的に次のような流れで相続手続を行います。
(1)被相続人の財産調査
まず、亡くなった人の全財産を把握します。これには預金だけでなく、不動産や株式、車なども含まれます。また、借金やローンも調査します。
この過程で、銀行へ名義人が死亡したことを伝えることになるでしょう。銀行から相続の案内があるはずですので、それに従って必要書類の準備も進めます。
(2)相続人の調査
被相続人の財産の調査と並行して、相続人の調査を行います。
特に被相続人に離婚歴がある場合、前の婚姻生活で子どもをもうけている場合にはその子も相続人になりますので、注意が必要です。
また、相続人が相続放棄すると、次順位の法定相続人が相続人となります。
(3)遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、誰がどのように遺産を受け取るのか、話し合いで合意します。
合意した内容について遺産分割協議書を作成し、すべての相続人が署名・実印で押印します。
遺産分割協議を行わず、相続人が一定額について預金を払い戻しできる相続預金仮払い制度もあります。ただし、預金額が少額の場合はこの制度を利用しても引き出せる金額が少ないため、あまりメリットはないかもしれません。
相続預金仮払い制度について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(4)預金の払い戻し
預金引き出しに必要な書類を準備して、代表者が預金を払い戻します。通常、次のような書類が必要となりますが、金融機関によって必要書類は異なりますので、事前に連絡して確認するようにします。
- 金融機関所定の届出書
- 遺産分割協議書
- 亡くなった方の戸籍謄本(※)
- すべての相続人の戸籍抄本(謄本)
- すべての相続人の印鑑登録証明書
- 代表して預金を引き出す者の実印
- 故人の通帳・キャッシュカードなど
※法務局で取得した法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできる
預金が少額だから口座凍結前に引き出してもよいのでは?
金融機関が被相続人の死亡を把握しなければ、口座は凍結されません。
したがって、被相続人が死亡した後も、被相続人のクレジットカードや暗証番号があれば、事実上預金を引き出すことができるでしょう。
数百円や数千円レベルの預金であれば、仮にすべて引き出したとしても事後の遺産分割協議でそれを踏まえて話し合うことができますので、相続トラブルになることはあまりないかもしれません。
しかし、引き出した後、借金の方が多いことがわかって相続放棄したいとなった場合、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
預金が少額とはいえ、やはり原則通り、遺産の調査などを行ってから、正式な手続きを経て預金を引き出す方がよいでしょう。
「相続手続って何をすればいいの?」と不安になる必要はありません。遺産調査などの相続手続は弁護士に任せることができます。
【まとめ】預金の相続には労力と一定の費用がかかる
亡くなった人の預金が少額であっても、通常通り相続手続きは必要です。 ただそれにかかる労力や費用を考慮したうえで、放置する手段もあります。
しかし、「借金が多く相続したくない」という場合には、放置するだけでは不十分で、決められた期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続手続きは複雑で、遺産分割協議の成立には時間がかかることもありますので、お困りの際には弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所には、相続放棄、相続税、遺産分割協議など、複雑な遺産相続の手続をまとめて依頼できます。 相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。