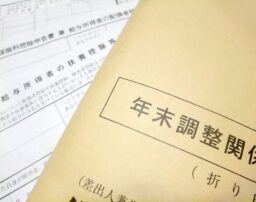過労による労災は、現代社会における深刻な問題の一つです。
長時間労働やストレスの多い職場環境により、労働者が健康を害し、最悪の場合、命を落とすこともあります。
しかし、過労に関する労災の認定基準や申請方法について正しく理解している人は少ないのが現状です。
本記事では、過労による労災の認定基準、申請方法、さらには給付内容まで解説します。あなたや大切な人の健康と権利を守るために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 過労による労災とは
- 過労死ラインとは
- 労災の認定基準
- 労災が認められないケース
- 労災保険給付金の申請方法
ここを押さえればOK!
厚生労働省は、発症前1ヶ月間に約100時間の時間外労働や発症前2~6か月間に月平均で約80時間を超える時間外労働を「過労死ライン」としており、これを超える長時間労働は過労死のリスクが高いとされています。
労災認定基準は脳・心臓疾患と精神障害で異なり、労働時間や業務内容、職場環境などの要因が総合的に評価されます。
労災申請には、必要書類の準備、申請書の記入、労働基準監督署への提出が必要です。申請書には個人情報や業務内容、発症状況を詳細に記載し、必要書類を添付します。労働基準監督署へ申請後、調査・審査が行われ、結果が通知されます。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
過労による労災とは?
過労による労災は、過度の労働が原因で発生した健康被害が労災として認定されるケースを指します。主に脳・心臓疾患と精神障害が対象となります。これらの疾患は、長時間労働や過度のストレスによって引き起こされる可能性が高く、労働者を長時間労働やストレスから守ることが重要になっています。
過労による労災の認定を受けるためには、業務と疾病との因果関係を証明する必要があります。具体的には、労働時間や業務内容、職場環境などが考慮されます。
(1)過労死等の法的定義
労災認定される健康被害、死亡などは「過労死等」として過労死等防止対策推進法2条に定義されています。
第2条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
この定義は以下の3つの要素を含んでいます。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患による死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
- 死亡に至らない、これらの脳血管疾患・心臓疾患や精神障害
(2)過労死ラインの基準
過労による病気が労災認定されるためには、それが業務に起因している必要があります。
しかし、実際に健康被害が起こっても、それが業務に起因するかどうかはっきりとは分からない場合も少なくありません。
そこで、厚生労働省は、労災認定の目安となる労働時間の基準を明らかにしており、その基準は俗に「過労死ライン」と呼ばれています。
厚生労働省は、次の場合に、業務と発症との関連性が強いと評価しています。
- 発症前1か月間に約100時間の時間外労働
- 発症前2~6ヶ月間に月平均で約80時間を超える時間外労働
これらの基準を超える長時間労働は、過労死のリスクが高いとされています。ただし、この基準はあくまで目安であり、個々の事例に応じて総合的に判断されることには注意が必要です。
例えば、労働時間が基準を下回っていても、業務の質や労働環境などの要因により過労死と
認定されるケースもあります。逆に、基準を超えていても、他の要因により認定されないこともあります。
過労による労災の認定基準
過労による労災の認定基準は、脳・心臓疾患と精神障害で異なります。
認定にあたっては、労働時間や業務内容、職場環境などの要因が総合的に評価されます。重要なのは、単に長時間労働だけでなく、業務の質や責任の重さ、労働環境なども考慮される点です。労災認定を受けるためには、これらの基準を理解し、適切な証拠を提示することが重要です。
(1)脳・心臓疾患の労災認定基準
下記のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けて発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として労災が認められます。
1. 発症前の長期間の過重業務:次の場合業務と発症との関連性が強いと評価できる
- 発症前1か月間に約100時間の時間外労働
- 発症前2~6ヶ月間に月平均で約80時間を超える時間外労働
2. 発症前の短期間(概ね1週間)の過重業務:次のような場合に業務と発症との関連性が高いと評価できる。
- 発症直前から前日までに特に過度の長時間労働
- 発症前約1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働
3. 異常な出来事:発症直前から前日に、強度の精神的負荷、急激で著しい身体的負荷、急激で著しい作業環境の変化
これらの要素を総合的に評価し、業務と発症との因果関係が認められれば労災と認定されます。
(2)精神障害の労災認定基準
精神障害が労災認定されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 対象となる精神障害を発症していること
- ICD-10第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であること
2. 対象疾病の発病前概ね6ケ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 心理的負荷の総合評価は強・中・弱に分けられる
- 「特別な出来事」(生死にかかわる、極度の苦痛を伴う又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガ。発症直前の発病直前の1か月に概ね160時間を超える時間外労働を行った場合等)の心理的負荷の総合評価は強
- 「特別な出来事」以外の出来事については、出来事それ自体と、当該出来事の継続性や事後対応の状況、職場環境の変化など様々な事情を総合的に考慮して、心理的負荷の程度を判断する。
3. 業務以外の心理的負荷や労働者個人の要因により対象疾病を発病したとは認められないこと
(3)過労自殺の労災認定基準
故意に死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合には、労災認定はされません。
しかし、過労自殺がすべて労災認定されないというのは妥当ではありません。
そこで、業務による心理的負荷により精神障害を発病した人が自殺した場合には、その精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、自殺に至ったこと(故意の欠如)と推定され、原則としてその死亡は労災認定されます。
過労による労災が認められないケース
過労による労災の申請をしても、必ずしも認定されるとは限りません。
例えば、業務起因性や業務遂行性が認められない場合は、労災と認定されません。また、労災給付金には様々な種類があり、それぞれに必要な要件を満たさなければ給付金は受けられません。
主に以下のような場合が該当します。
- 業務との因果関係が薄い場合
- 私生活での要因が大きい場合
- 個人の既往症や体質が主な原因と判断される場合
これらのケースでは、個別の状況を慎重に検討する必要があります。労災認定の可能性が低いと思われても、疑問がある場合は労働基準監督署や労災申請をを扱っている弁護士などに相談することをおすすめします。
過労による労災の申請方法
労災保険給付金の申請は、正確な手順を把握し、適切な書類の準備を準備すること重要です。申請のプロセスは以下の3つの主要なステップに分けられます。
- 必要書類の準備
- 申請書の記入
- 労働基準監督署への提出
これらのステップを正確に進めることで、スムーズな申請と適切な審査につながります。労災保険法に基づく申請は、被災労働者またはその遺族が行うことができます。申請から認定までの期間は案件により異なります。迅速な対応のためにも、できるだけ早く申請することをおすすめします。
以下、各ステップを説明します。
(1)必要書類の準備
労災の給付金には、様々な種類があります。申請に必要な書類は、給付金によって異なりますので、まずはどの給付金を申請するのか理解したうえで、必要な書類を集めるようにしましょう。
下記は、療養(補償)等給付金を申請するときの基本的な必要書類です。
1.療養の給付を請求する場合
療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付 及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)または「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を提出
2.療養の費用を請求する場合
所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)または「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を提出
その他、ケースによっては領収書や診断書などの資料の提出が必要なことがあります。
労災の各種給付金請求に必要な書類については、厚生労働省のホームページで最新の情報を確認するようにしましょう。
(2)申請書の記入方法
申請書の記入は、以下の手順で行います。
1. 労災保険給付請求書を入手
- 厚生労働省のウェブサイトから入手可能
2. 必要事項を漏れなく記入
- 個人情報(氏名、生年月日、住所など)
- 事業場の情報(名称、所在地など)
- 災害の原因及び発生状況
- 指定病院等の情報
- 傷病の部位及び状態 など
3. 業務内容や発症状況を詳細に記載
- 具体的な業務内容、労働時間、ストレス要因などを時系列で記載
4. 添付書類の確認
- 準備した書類が全て揃っているか再確認
記入にあたっては、事実に基づいて正確に記載することが重要です。
不明な点がある場合は、労働基準監督署の窓口で確認したり、労災申請を扱っている弁護士に相談・依頼したりするとよいでしょう。
参考:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(3)労働基準監督署への申請手順
労働基準監督署への労災申請は、以下の手順で行います。
1. 管轄の労働基準監督署を確認
- 原則として、労働者が所属していた事業場を管轄する労働基準監督署
2. 必要書類一式を提出
- 郵送または窓口持参
- 郵送の場合は、配達記録が残る方法(簡易書留など)を推奨
3. 受付
- 提出書類の確認が行われ、不備がなければ受付完了
- 不備がある場合は、追加書類の提出を求められることがある
4. 調査・審査
- 労働基準監督署による調査
- 必要に応じて、申請者や事業主、同僚などへの聞き取り調査が行われることもある
5. 結果通知を受け取る
- 支給決定の場合は、給付を待つ
- 労災保険の不支給決定に納得できない場合は、審査請求の手続きを検討する
提出後も、もし労働基準監督署からの問い合わせがあれば、速やかに対応するようにしましょう。
よくある質問:過労による労災に関するQ&A
過労による労災に関しては、多くの労働者が疑問や不安を抱えています。ここでは、主な質問とその回答を紹介します。
(1)労災申請の期限はあるの?
労災保険給付金の請求権は、原則として2年から5年で時効となり、請求できなくなります。時効にかかる期間は給付金の種類によって異なりますので、期限に注意したうえで、なるべく早く手続きを行うことが重要です。
主な労災保険給付の種類と申請期限は次の通りです(労働者災害補償保険法42条1項)。
| 給付金 | 時効 |
| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 遺族(補償)年金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)一時金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
| 傷病(補償)年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。 |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
(2)会社が労災申請に協力してくれない…あきらめるしかない?
労災申請の書類には、事業主証明欄がありますので、会社が申請に協力してもらった方が、申請自体はスムーズに進むでしょう。
もっとも、会社が協力してくれない場合には、その事情を報告書等にして添付することで申請は可能です。
中には、「労災を申請するなら解雇する」「労災を申請するなら降格する」などと労災申請を妨害しようとする会社もあるかもしれません。
もし、会社からの妨害や不利益取扱いがあった場合は、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。
会社との良好な関係を維持しつつ申請を進めることが、スムーズな認定と職場復帰につながる可能性が高いことは確かですが、不当な待遇に甘んじる必要もありません。
自分のために適切な判断をするようにしましょう。
参考:1-5 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。|厚生労働省
(3)労災が認められなかった場合の再申請は可能?
労災申請が認められなかった場合でも、以下の方法で再度チャレンジすることが可能です。
1. 審査請求
- 労災保険給付の決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う
- 決定を行った労働基準監督署を管轄する労働者災害補償保険審査官に対して行う
2. 再審査請求
- 審査請求の決定に不服がある場合、その決定の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に行う
- 労働保険審査会に対して行う
3. 訴訟
- 労災保険給付に関する決定の取消訴訟は、審査請求に対する労災保険審査官の決定を経なければ裁判所へ訴訟を提起することはできない
- 審査請求をした日から3ヶ月経過しても決定がない場合には訴訟提起可能
- 会社が、従業員の労災認定の取消訴訟を起こすことはできません(2024年7月4日最高裁判決)
審査請求をする際には、認定の可能性を高めるためにも、労災申請を扱っているの弁護士に相談するのも効果的です。
手続で不明な点は、管轄の労働基準監督署に確認しましょう。
参考:労災保険給付に関する決定(不支給決定や障害等級の決定など)に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。|厚生労働省
【まとめ】過労による労災への理解を深め、健康を守るため適切な対応を
過労による労災は決して他人事ではありません。
認定基準を理解し、自分の病気が労災の給付対象になる可能性があることについて、早期に気づくことが重要です。
労災申請の時効は原則2年~5年です。疑わしい症状がある場合は、速やかに医療機関を受診し、症状が現れる以前の労働時間や業務内容の記録を確保しましょう。
あなたの健康と権利を守るため、必要に応じて労働基準監督署や労災問題を扱う弁護士などに相談することをおすすめします。
一人で抱え込まず、適切な支援を受けることが、問題解決の第一歩となります。
また、今回は労災保険給付申請手続についてご説明しましたが、過労による病気について労災認定されるようなケースは、別途、使用者(雇い主)に対して安全配慮義務違反などに基づく損害賠償請求をすることが可能な場合もあります。
損害賠償請求ができるかどうかについても、労働問題を扱っている弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2025年1月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。