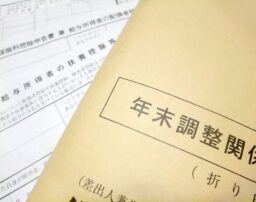現代社会において、長時間労働や過度なストレス、職場での人間関係のトラブルが原因で、心身に大きな影響を及ぼすことがあります。
なかには、仕事が原因でうつ病になってしまう方もいるようです。
そのような場合でも、うつ病が労災認定されることで、経済的な補償を受けることができます。
しかし、労災認定を受けるためには、認定のための条件を満たすだけでなく、必要資料を集めることや、複雑な申請手続きが必要です。
この記事が、労働者が適切なサポートを受け、安心して治療に専念できる一助となれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- うつ病が労災認定されるための条件
- 労災申請の手続きと流れ
- 労災申請をした場合のメリット・デメリット
ここを押さえればOK!
具体的には、職場での過度なプレッシャーやパワーハラスメント、長時間労働などがうつ病の発症に寄与していることを示す証拠が必要になるでしょう。
労災認定の条件は次の3つです。
・認定基準の対象となる精神障害を発病していること
・認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
・業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
労災申請の手続きは労働基準監督署に申請書を提出することから始まり、調査を経て認定の可否が決定されます。
認定されれば治療費や休業補償などの給付を受けられますが、手続きが煩雑で証拠集めに時間と労力がかかると考えられます。
労災申請は労働者の権利であり、弁護士などのサポートを受けることでスムーズに進めることが期待できます。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
うつ病による労災認定の基本知識
「労災」(労働災害)とは、労働者が仕事に従事したことによって起きたケガや病気のことです。一般的には、肉体的なケガや病気が対象とされることが多いですが、近年では精神疾患も労災認定の対象となるケースが増えています。
とはいえ後述するように、うつ病などの精神疾患の場合、業務上の事故によるケガなどと比べて、業務が原因であることを証明しづらいことが多いと考えられるでしょう。
うつ病が労災として認定されるためには、業務上のストレスや過重労働が直接的な原因であることを証明する必要があります。
具体的には、職場での過度なプレッシャーやパワーハラスメント、長時間労働などがうつ病の発症に寄与していることを示す証拠が必要です。
労災認定を受けることで、治療費や休業補償などを受けられるようになるため、労働者の生活を支える大きな助けとなるでしょう。
うつ病が労災認定されるための条件
精神障害が労災認定されるには、次の3つの条件を満たす必要があります。
(1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること
(2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヵ月の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
(3)業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
うつ病は、(1)の認定基準の対象となる精神障害に含まれます。
(2)の具体例としては、たとえば発病直前の1ヵ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った、といった極度の長時間労働があったことなどが挙げられます。
もっとも、強い心理的負荷といえるかどうかは、その他の事情が加わることで変化し得ます。
そのため、月の時間外労働が160時間に達していなかったとしても、たとえば転勤で新たな業務に従事し、その直後の1ヵ月におおむね100時間の時間外労働を行ったような場合には、強い心理的負荷があったと認められるようです。
そして、発病の原因が業務によるものであることが必要です。
たとえば、発病以前に離婚していたり、配偶者や子ども、親との死別があったりした場合には、(3)についてより慎重に判断されると考えられます(業務以外の心理的負荷)。
また、精神障害の既往歴やアルコール依存状況などがある場合についても、やはり(3)についてより慎重な判断がされると考えられます(個体側要因)。
労災認定のために必要な証拠
うつ病が労災認定されるためには、業務上のストレスや過重労働が直接的な原因であることを証明することが必要です。
例えば、長時間労働の記録や、過度な業務量を示す資料、職場でパワハラ受けていたことを示す証拠です。
具体的には、タイムカードや業務日誌、メールのやり取り、録音データなどが考えられるでしょう。
また、同僚や上司の証言も有力な証拠となる場合もあります。
職場での状況や業務内容、ストレスの原因について、第三者の視点から証言を得ることで、より客観的な証拠として認められる可能性が高まるでしょう。
証言は、陳述書として労働基準監督署に提出することが一般的です。
こういった証拠を複数揃えることで、うつ病が業務上の原因で発症したことを効果的に証明できるようになると考えられます。
さらに、基本的には医師作成の診断書が必要です。
労災申請の手続きと流れ
労災申請の手続きは、まず労働者が労働基準監督署に対して申請書を提出することから始まります。
申請書と必要な添付資料を揃えたら、労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署は提出された証拠を基に調査を行い、必要に応じて労働者や関係者への聞き取りを実施します。調査が終わると、労災認定の可否が決定され、結果が通知されます。
労災が認定されれば、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。
労災申請の手続きは複雑ですが、適切な準備とサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。
労災申請をする場合のメリット・デメリット
労災申請をすることで労働者に生じ得る、メリット・デメリットの両面をご紹介します。
(1)メリット
労災申請をする最大のメリットは、労災認定された場合に経済的なサポートを受けられることです。
具体的には、治療費が支給されるほか、休業中の賃金補償として休業補償給付が支給されます。これにより、治療に専念できる環境が整い、経済的な不安を軽減することができるでしょう。
(2)デメリット
一方で、労災申請をすることにはデメリットも存在します。まず、労災申請の手続きが煩雑であり、必要な証拠を揃えるために多くの時間と労力を要することがあります。
特に、精神疾患の場合は、業務上のストレスや過重労働が原因であることを証明するのが難しい場合が多く、精神的な負担が大きい場合も多いと考えられます。
また、労災申請をしたことが職場での評価に影響を与える可能性もあります。労災申請を行ったことで、会社との関係が悪化するリスクがあり、職場復帰後に働きにくさを感じることがあるかもしれません。
しかし、労災の申請は労働者の権利ですから、申請を遠慮する必要はありません。
労災認定を受けるためのポイントと注意点
まず、必要な証拠を揃え、申請書類の記載内容に誤りがないように注意し、時効までに申請することが必要です。
そして、労災申請の手続きは複雑で時間がかかることも多いため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
弁護士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができると考えられます。
【まとめ】うつ病による労災認定には3つの条件がある|申請は弁護士に依頼できることも
うつ病による労災認定は、労働者が適切なサポートを受けるために重要な手続きです。
まず、うつ病と労災認定の基本知識を理解し、労災認定を受けるための具体的な条件や必要な証拠を把握することが大切です。
労災申請の手続きは複雑な場合も多いですが、弁護士などのサポートを受けることでスムーズに進めることが期待できます。
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2025年1月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。