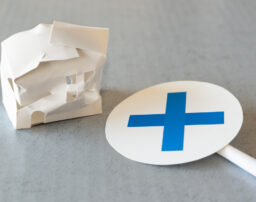親が亡くなり、兄弟姉妹で相続放棄を検討している方は、全員が放棄した場合に誰が相続人になるのか、事前に確認することが必要です。
被相続人(亡くなった人)の子ども全員が放棄すると、被相続人の父母や兄弟姉妹、または甥姪が相続人になる可能性があります。
相続放棄を検討しているなら、手続きの流れや必要書類、注意点などを理解し、兄弟姉妹間でよく話し合い、必要に応じて弁護士に相談するようにしましょう。
ここを押さえればOK!
被相続人の子ども全員が放棄した場合、相続順位は次に移り、被相続人の父母や兄弟姉妹、または甥姪が相続人となる可能性があります。
父が亡くなり、母を単独相続人にしたい場合、子ども全員の相続放棄では目的を達成できないケースがあり、注意が必要です。
相続放棄の期限は相続人になったことを知ってから原則3ヵ月以内です。被相続人最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。
相続放棄の手続きは自身でも可能ですが、なかには複雑なケースもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄は基本的に撤回できないため、慎重な判断が必要です。
相続手続きについてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続放棄のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
兄弟姉妹で相続放棄を検討する際に知っておくべきこと
まず、相続放棄の概要や影響についてご説明します。
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄する手続のことです。
相続人になると、自動的に被相続人のプラスの財産と借金などマイナスの財産の両方を相続することになります。
そのため、マイナスの財産の方が多い場合や、相続に関わりたくないなどの理由で相続したくない場合は、相続放棄を選択します。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
一度相続放棄すると、プラスの財産も受け取ることができなくなるため、慎重に判断するようにしましょう。
(2)兄弟姉妹の全員が相続放棄するとどうなる?
被相続人の子である兄弟姉妹全員が相続放棄した場合、相続人は誰になるかは法律で定められた相続順位によって決まります。
まず、被相続人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子が相続人となりますが、子が全員相続放棄すると、配偶者と被相続人の父母が相続人になります。
被相続人の父母が既に亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(ケースとしてはあまり想定しがたいですが、被相続人の祖父母がまだ健在である場合は、配偶者と被相続人の祖父母が相続人になります。)。
つまり、被相続人の子が全員相続放棄しても、被相続人の配偶者が健在であれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人になる可能性が高いということです。
被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、さらにその子(被相続人から見ると甥姪)が相続人になる可能性もあります。
子である自分たちが相続放棄することで、意図せず疎遠な親族が相続人になるケースもあるため、注意が必要です。
(3)母を単独相続人にしたい場合の注意点
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をしたいと考える際によくあるのが、父が亡くなり、母だけを相続人にしたいという理由で、被相続人の子どもが全員で相続放棄をしようというケースです。
もともと住んでいた家が母(被相続人から見れば妻)の単独名義にできるなど、相続関係をシンプルにできると考えてのことだと思います。
しかし、母を単独相続人にしたい場合、単純に子が全員相続放棄をするだけでは達成できない可能性があります。
前述のように、被相続人の子が全員相続放棄すると、被相続人の父母や兄弟姉妹も相続人になる可能性があるからです。
そのため、誰が相続人になるかを慎重に確認し、どのように相続手続きを進めるかを決めておくことが重要です。
場合によっては、専門家(弁護士や税理士など)に相談するとよいでしょう。
相続放棄の手続きの流れ
次に、相続放棄の具体的な手続方法や流れについてご説明します。
(1)相続放棄の期限
相続放棄には期限があり、自分が相続人になったことを知ってから原則3ヵ月以内に行うことが必要です。
被相続人が自分の親である場合、通常は親が亡くなった時から3ヵ月となるでしょう。
また、相続放棄の期限は延長できる場合もありますが、必ず認められるとは限りません。
期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなってしまうため、相続放棄を検討している場合は、早めに手続きを進めることが大切です。
(2)相続放棄に必要な書類
相続放棄をする人と被相続人との関係によって異なりますが、被相続人の子が相続放棄をする場合の必要書類はおおむね次のとおりとなります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の子が全員(兄弟姉妹まとめて)手続きをする場合、戸籍などの添付書類については、同一のものを複数用意する必要はありません。(申述書は相続放棄をする人数分必要です。)
参考:相続の放棄の申述|裁判所
(3)具体的な手続方法
基本的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を郵送で提出すれば足ります。
ただし、場合によっては、追加で照会書に対する回答書の提出を求められることなどがあります。
兄弟姉妹で相続放棄を行う際の注意点
被相続人の子である兄弟姉妹が、全員まとめて相続放棄をする際の注意点についてご説明します。
(1)全員が同じ意思であることを確認する
相続放棄自体は個人の権利であり、自分の意思だけで行うことができます。
ただし、兄弟姉妹が全員で、親の相続放棄をしようとしているなら、全員が同じ意思であることを確認することが大切です。
相続放棄をする前に、兄弟姉妹間で十分に話し合い、全員が納得したうえで手続きを進めるようにしましょう。
また、一部の兄弟姉妹だけが相続し、ほかの兄弟姉妹が相続放棄した場合、不公平感が生じてしまう場合もあります。
事前にしっかりとコミュニケーションをとっておくことが、後々のトラブル防止につながるでしょう。
(2)弁護士への相談も検討する
相続放棄の手続き自体は、自分自身で行うことも可能ですが、法律的な知識が必要となる場面もあります。
特に、相続放棄をする人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合などは、手続きが複雑になると考えられます。
そのような場合は、弁護士への相談・依頼を検討してください。弁護士は、法律の専門家として適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。
また、家庭裁判所への書類作成や提出も代行してくれるため、手続きの負担を軽減することができます。
弁護士費用はかかりますが、スムーズかつ確実な相続放棄を行うためには、弁護士への依頼は有効な手段といえるでしょう。
相続放棄後の注意点
相続放棄の手続きをする前に知っておきたい、相続放棄の注意点についてご紹介します。
(1)相続財産には一切関与できない
相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
したがって、被相続人の不動産や預貯金などプラスの財産を受け取れなくなる一方、被相続人の借金といったマイナスの財産についても、返済義務を負うこともなくなります。
ただし、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有していた場合には、相続人などに引き渡すまでの間、当該財産を保存する義務を負うためご注意ください(同第940条1項)。
(2)相続放棄は撤回できない
相続放棄は、一度手続きが完了すると、原則として撤回することはできません(同第919条1項)。
そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
相続放棄後に、価値のある財産の存在が判明したなど、事情の変化があったとしても、相続放棄を撤回して相続することはできないためご注意ください。
よくある質問
(1)兄弟姉妹の一部だけが相続放棄することはできますか?
相続放棄は自分の意思だけで行うことができ、ほかの相続人など他人の許可は必要ありません。
ただし、ほかの相続人に対して相続放棄の意思を伝えるだけでは十分でなく、家庭裁判所を介した手続をすることが必要です。
また、被相続人の子が全員相続放棄するわけではないなら、被相続人の父母や兄弟姉妹が自動的に相続人になることはありません。
(2)相続放棄の手続きは自分自身で行うことはできますか?
できます。
ただし、相続人の数が多い場合や、自分(たち)が相続放棄すれば本来相続人になるはずではなかった人が相続人になる場合など、相続関係が複雑な場合には、弁護士に依頼したほうが後々のトラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。
【まとめ】
兄弟姉妹でまとめて親の相続放棄を検討する際は、それぞれのメリット・デメリット、そして全員が放棄した場合の相続の流れを理解しておくことが重要です。
手続き自体は個人で行えますが、思わぬ落とし穴もあるため、事前に兄弟姉妹間でよく話し合い、情報や思いを共有するようにしましょう。
特に、父が亡くなったため、母を単独相続人にしたい、など具体的な希望がある場合は、安易に相続放棄をするのではなく、ほかの方法も検討する必要があります。
手続きの期限や必要書類なども確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
相続に関する疑問や不安があれば、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。