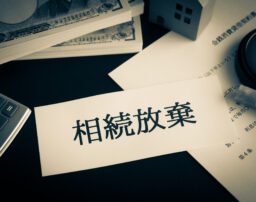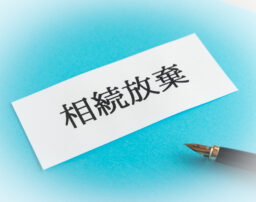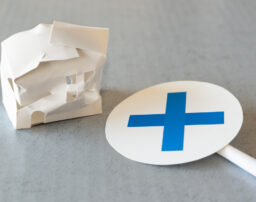相続放棄の期間を知らず、期間内に手続きできなかったとしても、まだ希望はあります。
被相続人が亡くなってから3ヵ月が経過していても、特定の状況下では相続放棄が認められる可能性があるのです。
相続放棄の機会を逃すと、予期せぬ債務を抱えることになるかもしれません。
被相続人が借金を抱えていたのではないか、などの不安や疑問がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することが賢明です。
適切なアドバイスを受けることで、あなたの権利を守り、自分にとって最善の選択を目指すことができるでしょう。
ここを押さえればOK!
相続放棄によって、プラスもマイナスも含めたすべての権利義務を承継しないことになります。主に借金相続の回避や相続争いの回避のために利用されます。
相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。一度行うと撤回できないため、慎重な検討が必要です。
熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長が認められる可能性があります。
また、被相続人の死を知らなかった場合や、先順位者の相続放棄により相続人となった場合、相続財産の存在を知らなかった場合など、被相続人の死から3ヵ月経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。
相続放棄できなかった場合、自動的に権利義務を承継することになり、債務返済義務や遺産分割の問題に直面する可能性があります。早めの弁護士相談が推奨されます。
相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続放棄のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
相続放棄の概要
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の相続財産の一切を放棄する法的手続きです。
これにより、相続人は被相続人の権利義務を一切承継しないことになります。
つまり、相続放棄をすれば、プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続しません。
そのため、被相続人の借金相続を回避する手段として利用されることが多いですが、単に相続人同士の争いに巻き込まれたくないという理由で相続放棄が選ばれることもあります。
相続放棄は、相続開始を知った時から原則3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
これは「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための期間です。
相続放棄は一度行うと基本的に撤回できません。慎重に検討するようにしましょう。
また、相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄の期間とは
相続放棄は、いつまででもできるわけではありません。
相続放棄は基本的に、3ヵ月の熟慮期間内にすべきとされています。
相続放棄の期限は原則3ヵ月
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」にしなければならないのが原則です(民法第915条1項本文)。
「相続は、死亡によって開始する(同法第882条)」ため、たとえば親の相続放棄をしたいのであれば、相続放棄の期限は親が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内となります。
もっとも、場合によってはこの熟慮期間を伸長できることがあります。
3ヵ月の熟慮期間は伸長の申立てが可能
相続放棄の熟慮期間である3ヵ月は、場合によっては伸長することができます。
伸長するには、熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続放棄するかどうかを決定できないといえる事情が必要です。
そのため、ただ熟慮期間の伸長を申し立てさえすれば、伸長が無条件に認められるわけではない点に注意しましょう。
裁判所は申立ての内容を審査し、正当な理由があると判断すれば熟慮期間の伸長を認めます。
なお、熟慮期間伸長の申立てにも期限があり、熟慮期間内(つまり相続開始を知ってから3ヵ月以内)に行わなければならない点にもご注意ください。
3ヵ月経過後の相続放棄が認められるケース
被相続人の死亡から3ヵ月以上経過していても、相続放棄が認められる主なケースをご紹介します。
状況によっては、「知らなかった!」と諦める必要はないかもしれません。
(1)熟慮期間を伸ばす申立てが認められた
すでにご説明しましたが、熟慮期間の伸長の申立てが認められるのが、もっとも一般的なケースです。
相続放棄を検討しているのであれば、熟慮期間の伸長の申立ても含めて弁護士に依頼するとスムーズに手続きを進められるでしょう。
(2)被相続人の死を知らなかった
相続放棄の期限は被相続人の死を知ってから3ヵ月ですので、被相続人が亡くなってから3ヵ月以上経過したあとでも相続放棄ができるケースがあります。
たとえば被相続人と長年音信不通だった場合や、海外に長期滞在していて連絡が取れなかった場合であれば、被相続人が亡くなったことをすぐに知ることは難しいでしょう。
ただし、単に死亡の事実を知らなかったと主張するだけでは不十分で、知らなかったことに相当の理由が必要になる可能性はあります。
相続放棄の申述の際には、被相続人の死亡を知った経緯や生前あまり交流がなかったことなどを説明できるようにしておくと良いでしょう。
たとえば、被相続人の債務を請求する書面が届いたことにより、はじめて被相続人の死亡の事実を知った場合には、その書面を保管しておくことをおすすめします。
(3)先順位者の相続放棄により相続人となった
相続順位が後の人が、先順位者の相続放棄によってはじめて相続人となった場合、被相続人の死亡から3ヵ月経過していても相続放棄は認められると考えられます。
この場合、後順位者が、先順位者が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知った時点から3ヵ月の熟慮期間が始まるからです。
たとえば、被相続人の配偶者と子ども全員が相続放棄した場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合が典型的なケースです(被相続人の父母はすでに死亡していることが多いため)。
もっとも、先順位者の相続放棄を知ってから3ヵ月間という期間は変わらないため、すみやかに相続放棄をするかどうかについて検討する必要があります(もしくは、3ヵ月以内に熟慮期間の伸長の申立てをする)。
兄弟姉妹間での相続放棄についてはこちらの記事をご覧ください。
(4)相続財産について知らなかった
相続人が相続財産の存在を知らなかった場合、3ヵ月の熟慮期間を過ぎていても例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)によると、相続人が相続財産が全く存在しないと信じたことに「相当な理由」がある場合、相続財産の全部もしくは一部を知った時点、あるいは知ることができた時点から熟慮期間が始まるとされています。
たとえば、被相続人にはプラスもマイナスも含めてめぼしい財産は何もないと思っていたが、相続人が知り得なかった債務の存在が後になって判明した場合などが該当するでしょう。
相続放棄できなかったらどうなる?
熟慮期間内になにも手続きをしなければ、相続人は自動的に被相続人の権利義務をすべて承継する(つまり相続する)こととなります。
したがって、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続人は被相続人の債務を返済する義務を負うことになります。
また、ほかに相続人がいる場合には、遺産分割の協議や調停、審判、訴訟などに巻き込まれる可能性もあります。
相続放棄ができなかった場合の影響は大きいため、熟慮期間内に慎重に判断することが重要です。
相続放棄をするか判断するための財産調査から依頼できることもあるため、自分が相続人となる相続が生じた場合には、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
相続放棄の注意点について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】
相続放棄の期間を知らなかったからといって、諦める必要はありません。
状況によっては被相続人の死亡から3ヵ月以上経っても相続放棄できる可能性があります。
しかし、相続に関する法律は複雑で、専門家でない人が適切に判断するのは困難なケースもあります。
もし相続放棄の期間や手続きについて不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談するとよいでしょう。
相続の問題は人生に大きな影響を与えます。一人で悩まず、専門家のサポートを受けることで、より良い未来への道を開くことができるかもしれません。
遺産放棄を検討している方は、早めにアディーレ法律事務所にご相談ください。