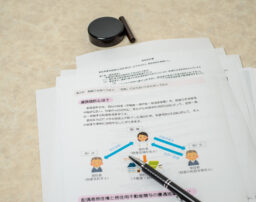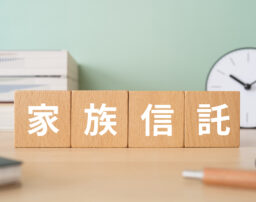家族信託は魅力的な財産管理・相続対策の手段ですが、導入には慎重な検討が必要です。
この記事では、家族信託の主なデメリットを詳しく解説し、その導入を検討する際の注意点を説明しています。
家族信託が必ずしも万能の解決策ではないことを理解し、専門家のアドバイスを受けながら、自身の状況に最適な選択をすることが重要です。
ここを押さえればOK!
主なデメリットは以下の通りです:
1. 手間と費用がかかる:専門家への依頼費用、登記費用、継続的な管理コストが発生します。
2. 受託者の負担が大きい:管理・運用責任、報告義務などが重荷となります。
3. 契約内容の変更が難しい:当事者の合意が必要で、柔軟な対応が困難です。
4. 家族間でトラブルになりやすい:不公平感や不信感が生じる可能性があります。
5. 節税効果はあまり期待できない:相続税の直接的な節税効果はありません。
6. 遺留分侵害額請求のリスクがある:ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
家族信託を検討する際は、相続人の理解を得ること、専門家に相談すること、受託者の選定に慎重になること、柔軟性のある契約内容にすることが重要です。
家族信託について検討中の方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
家族信託とは?基本的な仕組みと特徴
家族信託は、財産管理や相続対策の新しい手法として注目されています。
具体的には、財産所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理権限を託し、認知症による資産凍結などを防ぐ仕組みです。
家族信託の主な特徴は、認知症や相続に備えて財産を保護し、円滑な財産承継を図れることです。通常の相続と異なり、生前に財産の管理方法を決められる点が大きな利点とされています。
ただし、デメリットもあるため、利用するなら慎重に検討することをおすすめします。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとしては、主に次のような点が挙げられます。
(1)手間と費用がかかる
家族信託の設定には、予想以上の手間と費用がかかります。
まず、家族信託には専門家のサポートが必要なことも多く、通常は弁護士や税理士への費用が発生します。
専門家に依頼せず自分で手続きするにしても、信託財産の移転手続きは複雑で、不動産の場合は登記費用もかかります。
また、信託設定後も、定期的な管理報告書の作成や税務申告など、継続的な事務作業が必要です。これらの手続きや管理にかかる時間的・金銭的コストは無視できません。
特に小規模な財産の場合、そのコストが信託のメリットを上回ってしまう可能性もあるため、導入前に十分な検討が必要です。
(2)受託者の負担が大きい
家族信託において、受託者の役割は非常に重要ですが、同時に大きな負担を伴います。
受託者は信託財産の管理・運用責任を負い、定期的な報告義務や適切な意思決定が求められます。これには高度な判断力が必要で、それなりに時間的制約も生じます。
また、法的責任も重大で、善管注意義務違反が課され、場合によっては損害賠償を求められる可能性もあります。さらに、他の家族からの批判や不信感にさらされるリスクもあります。
そのため、家族信託は受託者の日常生活や精神的健康に影響を与える可能性があり、適任者を見つけることが難しいことも多いようです。
(3)契約内容の変更が難しい
家族信託の大きなデメリットの一つは、一度設定した契約内容の変更が難しいことです。
信託契約は、当事者(委託者と受託者)の利害関係を慎重に調整して作成されるため、その後の変更には多くの障壁があります。
たとえば、家族関係や経済状況の変化に応じて柔軟に対応したくても、当事者の合意が必要なため、迅速な変更が困難です。
特に委託者が認知症になった場合、その意思確認ができず、変更ができなくなる可能性があります。
変更するにしても再度の専門家への相談や法的手続きが必要となり、追加の費用と時間がかかるでしょう。
この柔軟性の欠如は、長期的な視点で家族信託を検討する際のハードルとなります。
(4)家族間でトラブルになりやすい
家族信託は、意図せずして家族間の対立やトラブルの種になる可能性があります。
たとえば、受託者の選定において家族間で不公平感が生じることも少なくありません。
また、受託者の財産管理や運用方法に対して、ほかの家族から「何も聞かされていない」「受託者が財産を使い込んでいるのでは?」といった不信や批判が向けられることもあるでしょう。
また、信託設定時には予想できなかった家族状況の変化(離婚、再婚、経済状況の変化など)により、不満や軋轢が生じることもあります。
このような家族関係への悪影響は、財産管理以上に深刻な問題となる可能性があるため、事前によく説明し、話し合っておくことが重要です。
(5)節税効果はあまり期待できない
一部では、家族信託の利用により相続税の節税ができるといった誤解があるようですが、家族信託に、相続税の直接的な節税効果はありません。
家族信託を利用すると、財産の名義は受託者に移りますが、受託者は財産を管理するだけで、実質的な利益は受益者が受け取ります。そのため、委託者と受益者が同一人物の場合には、財産の管理方法が変わっただけということになり、相続対策にはならないからです。
したがって、節税を目的として家族信託を選択することは適切ではありません。
(6)遺留分侵害額請求される可能性
家族信託を設定する際、遺留分侵害額請求のリスクを考慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。
信託契約によってほかの相続人の遺留分が侵害されたと判断された場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
これは、家族信託の目的を損ない、家族間の紛争を引き起こす原因となりかねません。
特に、財産の大部分を家族信託の対象とする場合は要注意です。
専門家に依頼し、遺留分に配慮した信託契約を締結することで、相続トラブルは未然に回避しやすくなります。
また、相続人になる予定の親族とは、事前に話し合っておくとよいでしょう。
遺留分侵害額請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
家族信託を検討する際の注意点とアドバイス
家族信託の導入を検討する際は、以下の点に注意が必要です。
まず、相続人となる予定の親族の理解を得ることが重要です。信託の目的、仕組みなどについて十分に話し合いましょう。
次に、信頼できる専門家(弁護士、税理士など)に相談し、状況に適した信託契約を締結することが求められます。
また、受託者の選定には慎重を期し、その負担と責任を十分に考慮してください。
さらに、将来の状況変化に備え、可能な範囲で柔軟性を持たせた契約内容にすることを心がけましょう。
慎重に検討し、適切に設計された家族信託は、家族の未来を守る有効なツールとなり得ます。
家族信託でよくある質問と回答
(1)家族信託をする際に、まず準備することは?
まず、預貯金や不動産、有価証券などの財産状況を整理しておいてください。家族構成についても整理しておくと、その後の手続きがすみやかに行えるでしょう。
また、誰を受託者にして、どの財産を家族信託の対象とするかについて、家族信託をしようとする目的から検討しておくことをおすすめします。
(2)家族信託の内容を途中で変更したり、やめたりすることはできる?
信託契約の内容によりますが、基本的には契約において定められた方法で変更・終了することができます。
そのため、はじめから契約自体を柔軟性のある内容にしておくとよいでしょう。
【まとめ】家族信託にはデメリットもあるため、導入には慎重な検討が必要
家族信託は財産管理や相続対策の有効な手段ですが、導入には慎重な検討が必要です。
手間と費用・受託者の負担・契約変更の難しさ・遺留分侵害の可能性などがデメリットとなることもあるでしょう。
これらを十分に理解し、家族全員で話し合い、専門家のアドバイスを得ておくことが重要です。
家族信託が本当に最適な選択肢かどうか、弁護士に相談して慎重に判断することをおすすめします。
適切に設計された家族信託は、家族の未来を守る強力なツールとなり得るでしょう。
家族信託をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。