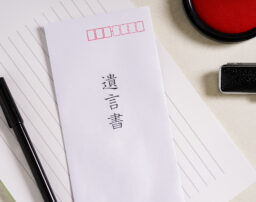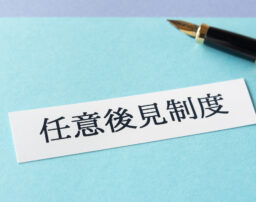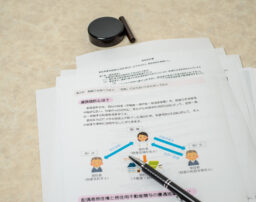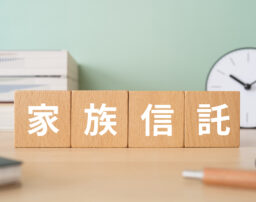家族信託は、認知症による財産凍結を防ぐための有効な手段の一つです。
高齢化が進む中、家族信託を利用して財産の凍結を防ぎ、家族のサポートを受けることは、ご本人のQOLを維持し、家族の争いを避けるためには効果的な方法です。
しかし、すべての方に適しているわけではありません。財産の状況や家族構成によっては、費用や手続きの負担が大きいだけのケースもあります。
この記事では、家族信託の利用が適さないケース、代わりに使える「遺言書」や「後見制度」といった他の選択肢についても弁護士が詳しくご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な対策を考えるヒントにしてください。
ここを押さえればOK!
信託を引き受ける家族がいない場合や、遺言書で目的が達成できる場合、すでに後見制度を利用している場合は、家族信託の必要性は低いでしょう。
一方で、認知症リスクに備えて生前に財産管理の準備を備えたい場合や、収益用の不動産など複数の不動産を所有している場合、障がいのある子の生活を長期的に支えたい場合、二次相続まで見据えた対策をしたい場合は、家族信託が適しています。
遺言書と家族信託は役割が異なり、家族信託は生前の財産管理を受託者に任せることが可能で、二次相続まで関与できるというメリットがあります。
大切なのは、メリット・デメリットを総合的に比較し、ご自身の状況に合った最適な方法を選ぶことです。
生前対策や相続に関してお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
家族信託のキホン
家族信託とは、財産(預貯金・不動産・有価証券等)を保有する方が、生前に、あらかじめ定めた信託目的にしたがって、自身の財産の管理権限を信頼できる家族などに託す仕組みです。
一方、信託銀行や信託会社に託す場合には商事信託とよばれます。
認知症や病気、加齢などで自身での財産管理が難しくなった場合、家族が本人の財産を処分してお世話をしたくても、本人の意思確認ができないので財産を処分することはできません。つまり、本人の資産は有効活用できずに凍結された状態となってしまいます。
こうなると、成年後見制度を使うほかありませんが、家族信託で事前に準備しておく方が、スムーズで柔軟な財産管理の移行が可能です。
事前に備えて家族信託契約を締結しておけば、自身の判断能力の喪失による資産の凍結を防いで財産を管理してもらい、医療費や生活費、介護施設費用などに活用することができるためです。
家族信託の仕組みには、主に以下3つの役割があります。
- 委託者:親など、自分の財産の管理を任せる人
- 受託者:子どもなど、任された財産の管理や運用をする人
- 受益者:財産の管理運用で得られた利益を受け取る人
親が子に財産の管理を任せる場合などでは、委託者と受益者が同一人物となることが多いでしょう。
家族信託の利用が適さないケースを解説!弁護士が教える判断基準
家族信託を検討している方の中には、「本当に自分に必要なのだろうか?」と疑問に思う方も少なくありません。
家族信託は、状況によっては適さない、他の手段の方が適しているケースも存在します。
ここでは、家族信託の利用が適さないと考えられる具体的なケースを3つご紹介します。
(1)家族信託で財産管理を任せたい「家族」がいない場合
家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せるという性質上、信託を引き受けてくれる家族・知人がいない場合は利用できません。
たとえば、一人暮らしで頼れる親族がいない、あるいは親族間の関係がうまくいっておらず、財産管理を任せられる相手がいないといったケースがこれに該当します。
この場合は、家族信託ではなく、商事信託、弁護士や司法書士が後見人となる任意後見制度や成年後見制度の利用を検討すべきでしょう。
(2)遺言書で十分な目的が達成できる場合
遺言書は、亡くなった後に誰にどの財産を相続させるか意思表示して指定できる制度であり、生前の財産管理を依頼することはできません。
生前の財産管理の対策ではなく、「亡くなった後で相続人がもめないよう、財産の承継先を明確にしたい」というような目的だけであれば、遺言書を作成するだけで十分な場合も多いです。
ご自身の希望を叶えるために、家族信託の仕組みを利用した方がいいのか、遺言書で十分なのか(又は家族信託に加えて遺言書を準備するのか)は、自分だけで判断するのは難しいかもしれません。どのようなスキームで目的を達成したらいいのか、一度弁護士などに相談することをお勧めします。
遺言書の種類や書き方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)すでに任意後見制度を利用している場合
任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来判断力や理解力(法的には、事理弁識能力と言いますが、ここでは単純に判断能力とします)が低下した場合に備えて任意後見契約を結び、後見人を選任しておく制度です。本人の意思に基づいて後見人を選べるため、信頼できる家族や専門家を後見人に指定できます。
任意後見人は、認知症発症などで本人の判断能力に問題が生じたときに、所定の手続きを取ったうえで、委任された財産管理と身上監護(医療行為への同意など)について、本人の意思を反映した柔軟なサポートを行います。
具体的には、任意後見人は、財産管理などができなくなった本人の代わりに、不動産の管理処分などの財産管理を行い、日々の生活のための買い物や取引行為などの身上監護を行います。
そのため、任意後見制度を準備している場合には、一般的には家族信託の必要性は低いと考えられます(※)。
任意後見制度の概要や、成年後見人との違いなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
※家族信託の受託者は、信託財産の広い管理権限を有しますが、本人である委託者の法律行為を一般的に代理することはできません。したがって、本人が認知症で判断能力を失ったような場合で法律行為が必要な際には、成年後見人の選任が必要となるケースもあります。
このようなケースで家族以外の者が成年後見人となるのを避けるために、家族信託と同時に任意後見契約を締結して家族を任意後見人とする、という方法もあります(ただし、法定後見開始等の申立ての審判により、「本人の利益のため特に必要がある」と裁判所が認めた時には、任意後見から法定後見(弁護士などが選任されることもある)に移行する可能性はあります(任意後見契約に関する法律10条1項))。
一方、本人がすでに認知症などで判断能力に問題があったり、喪失した状況では、成年後見制度を利用することができます。親族などが申し立てて家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の代わりに法律で認められた範囲の契約行為や財産管理を行います。
家庭裁判所の管理下で本人の財産を守ることが主な目的であるため、裁判所の許可なく不動産の売却をすることはできません。積極的な資産運用には不向きと考えられます。
成年後見制度の概要や、誰が成年後見人に慣れるのかなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
こんな場合は家族信託の利用を検討すべき
ここまで家族信託の利用が適さないケースを見てきましたが、逆に「家族信託を利用した方がよい」と言えるのはどのような場合でしょうか。
ここからは、家族信託の利用が適している具体的なケースについて解説します。
(1)認知症による資産凍結のリスクに備えたい
ご自身が認知症などで判断能力を失った場合、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまいます。家族が代わりにしようとしても、本人の意思を確認できませんから、代わりに行うことはできません。これを資産凍結リスクと呼びます。
こうなると、成年後見制度を利用して、後見人を定めたうえで、裁判所の許可を得て本人の財産を処分するほかありません。
家族信託では、本人が元気なうちに家族に財産を信託して管理権限を移すことで、意思能力を失った後でも受託者となった家族が本人の財産を、信託の目的にしたがって管理・運用できます。
これにより、本人の介護費用や入院費用に充てるために本人の不動産を売却するといった柔軟な対応が可能になります。
(2)複数の不動産を所有している
複数の収益不動産やアパートを所有している場合、本人が高齢で認知症を患い、意思能力が低下・喪失してしまうと、賃貸借契約の更新や修繕の手配といった管理業務が困難になってしまいます。
家族信託を利用して、不動産の管理処分権限を託しておけば、本人が元気なうちに、ノウハウを受託者に教えることが可能です。また、本人の意思能力が低下・喪失しても、受託者がこれらの不動産の管理を継続することが可能となり、安定した家賃収入の確保に繋がります。
さらに、不動産を売却して得たお金で別の不動産を購入するなど、より積極的な資産運用も可能です。
(3)障がいのある子の生活を長期的に支えたい
障がいのあるお子さんがいらっしゃる場合、親が亡くなった後の生活を心配される方も多いでしょう。
家族信託は、親が亡くなった後も、信託した財産から子どもの生活費を定期的に支給するといった契約を結ぶことができます。これにより、親が亡き後も子どもが経済的に安定して暮らせるように、事前に準備することができます。
(4)「二次相続」まで見据えた柔軟な対策をしたい
遺言書では、自分が亡くなった後の相続人にどの財産を残すかしか指定できません(一次相続)が、家族信託ではその相続人が亡くなったあとの承継先(二次相続)まで指定することが可能です。
たとえば、「自分が亡くなったら妻に全財産を相続させ、妻が亡くなったら残った財産は長男に渡す」といったように、財産の行方を複数世代にわたってコントロールできます。
これにより、特定の財産を特定の家族に承継させたいという希望を叶えられるでしょう。
「家族信託は必要ない」と判断する前に確認すべきこと
家族信託の利用が適さないケースに当てはまると思われた方も、安易に判断するのは危険です。
ご自身の状況をより深く見つめ直すために、以下の点を改めて確認してみてください。
(1)家族信託は「相続」だけでなく「財産管理」にも役立つ
遺言書は、亡くなった後の財産の承継方法を定める制度であり、本人が存命中の財産管理には対応できません。
これに対し、家族信託は本人の意思能力が低下した後に、受託者となった家族が柔軟に財産管理を行える点が大きな特徴です。
たとえば、不動産の売却やリフォーム、収益用不動産であるアパートの管理など、積極的な財産運用を希望する場合は、家族信託が非常に有効な手段となります。
(2)本当に遺言書だけで財産管理の目的を達成できるか
遺言書を作成して死後の財産の分け方を指定したとしても、生きている間に、認知症などで本人の判断能力が低下すると、本人の意思で財産を動かすことができなくなります。
そうなると、たとえば適切な時点で不動産を売却して介護施設の費用に充てる、収益用の不動産を適切に管理運営し収益を上げる、といったことが難しくなるでしょう。
遺言書はあくまで「相続」の対策であり、「生前の財産管理」を目的とする場合は家族信託が適しています。
ご自身の目的を明確にし、遺言書と家族信託のどちらがより適切かを判断することが重要です。
(3)家族信託には費用がかかる|費用対効果を検討
家族信託の契約は、信託法などの法律に沿った内容にする必要があります。法律の知識が必要となりますので、弁護士などに作成を依頼することが一般的です。
本人の財産も受託者名義に変更することになりますので、不動産などの登記も必要になります。
法律上は家族信託の契約を公正証書にする必要まではありません。しかし、家族信託は高額の不動産や財産の管理運営を任せる非常に重要な契約になりますので、公正証書で作成することをお勧めします。
家族信託は、契約書作成を依頼した弁護士などの専門家への報酬や、公正証書作成費用、登記費用など、ある程度の初期費用がかかるため、費用面を心配される方も多いでしょう。
しかし、認知症などで判断能力が低下したり、喪失したりした場合には、不動産を適切な時期に売却できなかったり、十分な管理修繕ができなくなったり、家賃収入のある不動産の契約や契約更新などができなくなったりして、結果的に多額の機会損失を被る可能性も考慮に入れる必要があります。
将来的なリスクを回避し、円滑な財産管理を実現できるという効果を考えれば、家族信託の費用は決して高いものではない場合も多いです。
費用対効果を総合的に判断することが重要です。
家族信託を検討する上での注意点
家族信託は、将来を見据えた本人の柔軟な財産管理が可能な一方で、受託者となる家族に大きな負担をかける可能性があります。
受託者は、本人の財産を処分・管理する広範な権限が認められる一方で、善管注意義務(信託法29条)、忠実義務(同法30条)、分別管理義務(同法34条)、自己執行義務(同法28条)など様々な義務が課されます。
また、受託者は、信託財産の帳簿その他の書類を作成し、受益者に報告し、信託に関する書類を10年間保存する必要もあります(同法37条)。
受託者は、委託者の家族や仲のいい親族など、近しく金銭問題を抱えていない、信頼できる人を選びましょう。
受託者となる家族と十分に話し合い、協力を得られるかを確認することが非常に重要です。
【まとめ】
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、長期的な財産管理を可能にする制度です。
しかし、財産の種類や額、家族関係によっては、遺言書や後見制度といった他の方法の方が適している場合もあります。
大切なのは、ご自身の状況を正確に把握し、「家族信託の利用が適さないケース」に当てはまるか、それとも「利用した方がいいケース」なのかを見極めることです。
安易に判断せず、メリットとデメリット、他の選択肢とを総合的に比較検討することが、将来の不安を解消する鍵となります。
家族信託や相続対策は、ご家庭の状況やご本人のご希望によって適切な方法が異なります。アディーレ法律事務所では、ご相談者様の状況に合わせて、家族信託を含む多様な対策をご提案しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。