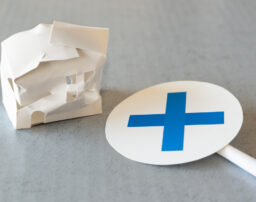相続放棄の期限は原則3ヵ月とされており、この期間内に手続を終えなければ多額の借金もすべて背負うことになってしまいます。しかし、期限の正確な起算点がいつなのか、もし期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいのかなど、多くの疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。このコラムでは、相続放棄の期限である「熟慮期間」の基本から、期限を過ぎた場合の対処法、そして相続放棄を無効にしないための注意点まで、弁護士が網羅的に解説します。この記事が、相続の負の側面からご自身を守るための手助けとなれば幸いです。
相続放棄の期限はいつまで?「3ヵ月」熟慮期間の基本
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内です。この3ヵ月という期間は、相続財産や借金などの全体像を把握し、相続するかどうかをじっくりと検討するための期間として「熟慮期間」と呼ばれています。この期間内に家庭裁判所に申立てを行わないと、特別な事情がない限り、被相続人の財産も借金もすべて引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまうため、極めて厳格な期限として扱われます。特に、多額の借金が発覚した場合、この期限を守れるかどうかが人生を左右する重要な分かれ目となるため、迅速な対応が不可欠です。
期限の起算点は「知ったとき」:相続人ごとの正確なスタート日
熟慮期間のスタート地点は、被相続人が亡くなった日とは限りません。民法第915条に定められているとおり、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」が起算点となります。これは、多くのケースで被相続人の死亡日を知り、自身が相続人であることを認識した日と一致します。しかし、この起算点は状況によって変動します。たとえば、先順位の相続人(子どもなど)が相続放棄をした結果、初めて次の順位の相続人(被相続人の父母や兄弟姉妹)に相続権が回ってきた場合、起算日は「先順位の相続人全員が放棄したことを知ったとき」となります。自身に相続権が回ってきた事実を正確に把握することが、期限超過を防ぐ鍵となります。また、未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人が相続の開始を知ったときから3ヵ月がスタートします。
3ヵ月は「申述書提出」の期限であり手続完了期限ではない
相続放棄の3ヵ月という期限に関して、誤解してはいけない重要なポイントは、3ヵ月の期間は「手続を完了させる期限」ではなく、「家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する期限」であることです。申述書が3ヵ月以内に裁判所に提出されていれば、その後の裁判所の審査や、照会書への回答、そして裁判所から受理の通知が届くまでの期間が3ヵ月を過ぎてしまっても、法的な問題はありません。書類の準備に時間がかかり、手続の完了を焦る必要はないため、まずは期限内に申述書を家庭裁判所に提出することを最優先しましょう。
3ヵ月の期限を過ぎた・間に合わない場合の対処法
原則として熟慮期間内に手続を完了させるのが一番ですが、客観的に見て財産調査が間に合わない場合や、期限が迫っていて書類が揃わないといった状況は往々にして発生します。そのような場合の対処法を見ていきましょう。
調査不足で判断が難しい場合の「熟慮期間の延長」申立て
遺産の内容が複雑であったり、相続財産や借金の調査に客観的に時間がかかったりする場合など、3ヵ月の期間だけでは判断が困難な状況も起こりえます。そのような場合、相続人は家庭裁判所に対し「熟慮期間の延長(伸長)の申立て」をすることができます。延長が認められるためには、客観的に延長が必要であることを示す合理的な理由(例:海外資産の調査、多数の金融機関への照会、複雑な親族関係による相続人確定の遅延など)を提示する必要があります。この申立ては、原則として3ヵ月の期限が到来する前に行わなければならないため、早めの行動が重要です。
期限超過を防ぐため、書類が揃っていなくても申述書提出を優先する
相続放棄を決断したにもかかわらず、戸籍謄本などの必要書類の収集が期限に間に合いそうにないといった状況は珍しくありません。このような場合は、まず相続放棄申述書のみを期限内に家庭裁判所に提出することが重要です。その際、戸籍謄本などの付属書類がまだ準備できていない旨を裁判所に伝え、後日提出する旨を申し出れば問題ありません。期限のあとに申立てを行う手続は、裁判所の厳格な審査と裁量に大きく依存し、認められるハードルが極めて高いため、書類の不備を恐れるよりも、申述書の「提出日」を3ヵ月以内に収めることが、相続放棄を成功させるうえでの最優先事項となります。
【例外】期限後でも相続放棄が認められるための条件
原則として、3ヵ月の熟慮期間を過ぎると単純承認が確定しますが、実際には期限を過ぎたあとにでも、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。しかし、これは裁判所が相続人の事情を深く考慮したうえでの判断であり、極めて厳格な要件が課されます。
期限経過後の放棄が認められるために必要な3つの要件
期限を過ぎてから相続放棄が認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たし、それを家庭裁判所に合理的に説明する必要があります。これらの要件は、申立ての際に提出する「上申書」を通じて裁判官に理解してもらうための根拠となります。
- 相続放棄の動機となる財産や借金の存在を客観的に知らなかった
- 知らなかったことについて通常期待される注意義務を尽くしても知ることができなかった合理的な事情がある
- 財産や借金の存在を知った時点から、改めて3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをした
「財産や借金の存在を知らなかった」と認められる合理的な理由
期限後申述が成功するかどうかを分けるもっとも重要な要素は、「相当な理由」があるか否かです。裁判所が相続放棄を認めるためには、相続人が被相続人に財産や借金が存在しないものと信じていたことについて、合理的な根拠が必要です。たとえば、被相続人と長期間音信不通で、生前の財産状況についてまったく知る由がなかった場合や、被相続人が遺言書などで「借金は一切ない」と示唆しており、それを信じた場合などが挙げられます。単なる主張では足りず、客観的な証拠(住民票上の別居期間など)を用いて立証する必要があり、この立証活動は専門的な知識を要する領域です。
「期限を知らなかった」という理由は原則認められない
期限のあとの相続放棄を検討する際によくある誤解として、「相続放棄の期限が3ヵ月であることを知らなかった」と主張すれば認められるのではないか、というものがあります。しかし、この「期限を知らなかった」という理由は、原則として家庭裁判所には認められません。日本の法律では、一般市民に対し、自身の権利義務にかかる調査や法的手続を一定の期間内に行うことを求めているため、単に法律や期間の存在を知らなかったことは、法的な救済の理由とはならないのです。したがって、主張の焦点を「期限を知らなかった」点ではなく、「財産や借金が存在することを知らなかった」点に置く必要があります。
期限後申述を成功させる「上申書」作成の重要ポイント
期限のあとの相続放棄は、原則として認められないため、その例外的な事情を裁判所に丁寧に説明する必要があります。この説明に用いられるのが「上申書」です。
上申書が裁判官に事情を説明する唯一の重要な役割
熟慮期間を経過したあとに相続放棄の申立てを行う際、形式的な申述書に加えて家庭裁判所に提出するもっとも重要な書類が「上申書」(経緯報告書)です。上申書は、相続放棄を認められたい相続人の意図や、期限経過に至った経緯、そして前述した例外的な承認要件(財産や借金を知らなかったこと、相当な理由があること)を満たすことを、裁判官に対し詳細かつ説得的に説明するための書面です。これは、申述書だけでは伝えきれない複雑な事情や、申述人が財産や借金を本当に知らなかったこと等を立証するための、事実上の弁護書面としての役割を果たします。
上申書で財産や負債の認知経緯を詳細かつ論理的に説明する方法
上申書を作成する際には、財産や負債の存在を知ることができなかった合理的な事情を、証拠に基づき、具体的な時系列と因果関係を明確にして記述しなければなりません。含めるべき要素として、被相続人との関係性(疎遠であったなど)、財産や借金を知らなかった理由、そして財産や借金の存在を具体的に知った正確な日付、誰から、どのような形で知らされたのかといった経緯です。これらを裁判官が事実関係を容易に把握できるように、簡潔かつ論理的に構成する必要があります。自己作成では客観的な証拠や法的論理の組み立てが不十分になりがちで、不受理のリスクが高いため、弁護士への相談が強く推奨されます。
相続放棄を無効にする「単純承認」とみなされる危険な行為
相続放棄の手続を検討している期間中、特定の行為を行うと、その時点で「法定単純承認」が成立し、相続放棄をする権利が失われてしまいます。
預貯金や不動産などの相続財産を処分・消費してはいけない
熟慮期間内において、相続人が相続財産の一部でも勝手に処分したり消費したりする行為は、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄は不可能となります。これは、相続人が財産を自己の所有物として扱ったと法的に判断されるためです。具体的には、被相続人の預貯金から私的な費用を出金すること、不動産を売却・賃貸すること、あるいは「形見分け」の範囲を超えて高価な遺品を持ち出したり売却したりすることがこれにあたります。また、被相続人の借金を自己の判断で弁済する行為も「処分行為」とみなされる可能性があるため、絶対に自己判断で支払いを開始してはいけません。
相続放棄をしても受け取れる死亡保険金と注意点
死亡保険金の取り扱いについても誤解が生じやすいポイントです。原則として、生命保険金は、受取人として指定された人物固有の財産とみなされ、民法上の相続財産には含まれません。したがって、相続放棄を行ったとしても、保険金受取人に指定されていた相続人は、保険金を受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人自身に指定されていた場合、その保険金は被相続人の財産となり相続財産に含まれることになります。また、生命保険金は、民法上は相続財産でなくても、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄が受理されたあとも残る最低限の財産管理義務
相続放棄が受理されたからといって、すべての責任からただちに解放されるわけではありません。民法第940条第1項は、相続放棄をした者は、相続放棄時点で占有していた財産について、他の相続人や相続財産清算人に相続財産を引き継ぐまで、自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理(保存)を継続しなければならない、と定めています。たとえば、被相続人と相続人が一緒に住んでいた実家が相続財産に含まれていた場合、相続放棄をしたとしても、他の相続人等が管理を引き継ぐまでの間、建物の倒壊防止などの最低限の管理義務が残ります。この義務を怠り、第三者に損害を与えた場合、その損害賠償責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄手続の流れと家庭裁判所への申立て
相続放棄の手続は、家庭裁判所へ申述書を提出することから始まります。正しい手順を踏むことが、手続を確実に成功させるために重要です。
申述書の提出から照会書、受理通知書までのフロー
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することから始まります。提出後、裁判所は、申述人の意思が真意に基づくものであるかなどを確認するため、質問書(照会書)を送付します。この照会書に回答し、返送すると、裁判所が申立てを適法と判断した場合、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、手続が完了となります。期限経過後の申立ての場合、この照会書への回答内容は上申書に記載された事実と厳密に整合していなければ、受理されない可能性があります。
債権者対応に必要な「相続放棄申述受理証明書」の取得
家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められた事実を示すものですが、これは内部的な通知書です。対外的に相続放棄の事実を証明するためには、別途、家庭裁判所に申請して「相続放棄申述受理証明書」を取得することが推奨されます。この証明書は、被相続人の債権者から借金の返済を請求された際、自身が相続放棄を行ったことを証明する場合に不可欠となります。債権者への対応において、この証明書は相続放棄の事実を客観的に示す唯一の公式文書となるため、大切に保管することが推奨されます。
相続放棄と「住んでいた家」に関する質問
相続放棄を検討する際、被相続人が住んでいた家をどうすべきか、という問題は多くの人が直面する疑問です。
相続放棄をしたあとも被相続人の家に住み続けられるか
相続放棄をした場合、その不動産を含む被相続人の財産を一切受け取ることはできません。したがって、相続放棄をしたあとは、被相続人の家に住み続けることは原則としてできません。もし住み続けた場合、その行為が相続財産の「処分」と見なされ、相続放棄が無効となるおそれがあります。ただし、被相続人の家が賃貸物件で、相続放棄をした方がその家の借主として賃貸借契約を結び直すことができれば、引き続き住むことは可能です。しかし、これは相続放棄とは別の話であり、不動産の所有権を相続しないという原則は変わりません。
まとめ
相続放棄は原則「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内という厳格な期限があります。期限を過ぎても放棄が認められるケースはありますが、そのためには「財産や借金の存在を知らなかった」という合理的な理由を上申書で説得的に説明する必要があります。これらの手続を確実に進めるためには、専門的な知識が必要です。もし期限が迫っている、またはすでに過ぎてしまったなど、少しでも不安を感じられた場合は、お一人で悩まずに弁護士にご相談ください。無料相談をご利用いただくことで、今後の最適な選択肢を速やかに見つけ出すお手伝いが可能です。