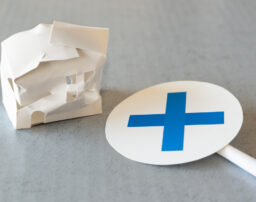被相続人の多額の負債が発覚し、「相続放棄はもうできないのではないか」と強い不安を抱える方は少なくありません。特に、すでに財産に手を付けてしまった行為(法定単純承認)や、3ヵ月の期限(熟慮期間)が過ぎたことが原因で、家庭裁判所への申立てを諦めかけているケースが多く見られます。しかし、葬儀費用支払いのような単純承認と判断されないと解釈可能な行為である場合や、期限の起算点を負債を知った日にずらす特例など、諦めるべきではない例外的な解決策が存在します。
本コラムでは、相続放棄ができないとされる具体的な3つの要件と、万が一却下された場合の即時抗告といった最終手段までを徹底解説します。ご自身の状況が「グレーゾーン」にあると感じる方は、この記事で解決への道筋を見つけ出してください。
相続放棄ができないとされる3つの要件
相続放棄の申述が家庭裁判所に却下される主な原因は、主に3つに分類されます。読者が抱える不安の根源を特定し、ご自身の状況がこれらの要件にあてはまらないかを確認することが、解決に向けた第一歩となります。
相続財産の処分や消費(法定単純承認)
相続放棄ができないとされるもっとも重要な要件の一つが、法定単純承認の成立です。これは、相続人が相続財産の処分など、一定の行為を行うことにより、法律上当然に相続を承認したとみなされる制度です(民法第921条)。この「承認とみなされる」行為が行われた場合、あとから相続放棄を申し立てても認められません。
典型的な行為としては、被相続人の預貯金や不動産を売却、譲渡、または消費する行為が挙げられます。これらの行為は、相続財産を自己の判断で利用または処分したと解釈され、負債もふくめた一切の権利義務を承継する単純承認が確定してしまうのです。
3ヵ月の期限(熟慮期間)を過ぎた場合
相続放棄の申述には、民法により「自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内」に行う必要があるという期限が定められています。この期間を熟慮期間と呼びます。この3ヵ月の期間は厳守されるべきであり、これを過ぎてから申述を行っても、原則として家庭裁判所はそれを受理しません。期間徒過は、相続放棄が却下されるもっとも頻繁な理由の一つです。
ただし、この起算点となる「自己のために相続があったことを知った時」については、特に負債の存在を知らなかった場合に専門的な解釈の余地が生じ、期限切れでも諦めるべきではない例外的な解決策が存在します。
家庭裁判所への手続に不備がある場合
相続放棄の手続は家庭裁判所に対する申述であるため、裁判所の指示や要求を適切に行うことが不可欠です。申述のあと、家庭裁判所から追加書類の提出や、相続の経緯を確認するための照会書(質問書)に対する回答が求められます。これらの家庭裁判所からの指示や照会書への回答を故意に怠ったり、必要書類の提出を無視し続けたりした場合、手続の不備として申述が却下される可能性があります。
申述書類に間違いや不備があった場合も却下事由となり得るため、手続上の義務を怠ったと判断されないよう、迅速かつ正確な対応が必要です。
単純承認と判断される行為・されない行為の境界線
相続放棄を検討する際、読者がもっとも不安を感じるのは、すでに実行してしまった行為が法定単純承認にあてはまるかどうかという「グレーゾーン」の判断です。ここでは、形式的には財産の処分に見えても、法的な解釈により単純承認とみなされない行為の境界線を明確にします。
単純承認となる行為
法定単純承認が成立する典型的な行為は、相続財産を自己の判断で利用・処分したとみなされるものです。具体的には、以下のような行為が該当します。
- 被相続人の預貯金を解約し、その金銭を私的な用途で引き出す
- 相続財産から被相続人の債務を支払う
- 不動産を売却する
- 遺産分割協議書に署名捺印して特定の財産を取得する
これらの行為は、相続人として財産を承継する意思があったと判断され、単純承認となります。
単純承認とならない行為
法定単純承認の成立要件は、財産を「処分」する行為と、財産の価値を維持するための「保存」行為の区別が鍵となります。被相続人の葬儀費用を、一般常識に照らして華美でない範囲内で相続財産から支払う行為は、亡くなった方への敬意に基づく行為であり、遺産の処分行為とはみなされず、単純承認事由にはあたるとされていません。
また、被相続人が孤独死した場合の特殊清掃費用や、賃貸借契約の解約手続、家賃滞納を防ぐための最低限の支払いは、財産の価値を毀損しないための保存行為と解釈されるため、原則として相続放棄は可能です。
土地など一部の財産だけを選ぶ「部分放棄」は不可
相続放棄は、被相続人の財産、権利、義務のすべてを一括して放棄する手続であり、一部の財産(たとえば、借金だけ、土地だけ)を選んで放棄する「部分放棄」は法律上認められていません。
特定の財産を特定の相続人に集中させたい場合は、相続放棄ではなく、遺産分割協議で話し合う必要があります。相続放棄を検討する際は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて手放すという原則を理解しておくことが重要です。
熟慮期間(3ヵ月)が過ぎた場合の解決策
相続放棄の申述期限である3ヵ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合、原則として放棄は不可能です。しかし、期限が過ぎたあとに負債の存在を知った方にとって、特定の法的要件を満たせば例外的に認められる可能性があります。
期限の起算日を「負債を知った日」にずらす特例
熟慮期間の起算点となる「自己のために相続があったことを知った時」とは、単に被相続人の死亡の事実を知った時点を指すわけではありません。単に死亡の事実を知ったにとどまらず、自分が相続人になったという事実をも知った時点を意味するとされます。、判例の考え方によればさらに、相続すべき財産(特に負債)の存在を知ることができ、かつ、相続の承認または放棄を選択できる状況になった時点まで、起算点をずらすことができる場合があります。
例えば、被相続人が遠方に住んでいて交流がなく、負債の存在をまったく知らなかったケースや、隠蔽されていた負債があとから判明したケースでは、「特別な事情」があるとして、熟慮期間の起算日が負債の存在を知った日に繰り下げて考えられる可能性があります。
期間内に調査が終わらない場合の期限延長手続
3ヵ月の熟慮期間内に相続財産(特に負債)の調査が間に合わないことが判明している場合は、期限が到来する前に家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てを行うことができます。この申立ては、相続人が期限内に財産調査を完了させる意思を示し、家庭裁判所に対して合理的な延長の理由を説明するための重要な手続です。
家庭裁判所が伸長を認めるためには、相続財産の調査状況、債権者との交渉状況、そして伸長が必要な具体的な理由を詳細に記述した書類を提出する必要があります。期限が迫っている場合は、迅速に行う必要があるため、弁護士への依頼が推奨されます。
相続放棄の申述が「却下」された場合の最終手段
相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったにもかかわらず、「却下」の審判が出てしまった場合、これは相続人にとって極めて重大な局面です。しかし、この段階でも、まだ最終的な対抗手段が残されています。
却下決定への不服申立て(即時抗告)と期限
家庭裁判所の却下決定に不服がある場合、その決定通知書を受け取った日から2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」を行うことができます。この2週間という期限は法律上の絶対的な期限であり、これを過ぎてしまうと却下審判が確定し、相続放棄は完全に不可能となります。
したがって、却下審判を受け取った瞬間から、迅速かつ正確な対応が求められます。この猶予のなさこそが、ただちに法律の専門家である弁護士に相談すべきもっとも緊急性の高い理由となります。
即時抗告によって却下審判が取り消されるケース
即時抗告が認められるのは、家庭裁判所の却下決定が法的な誤解に基づく場合や、事実認定に間違いがあることを立証できる場合に限られます。過去の判例のなかには、家庭裁判所が単純承認が成立していると判断した場合でも、申述に至るまでの経緯や、債務の存在に気づかなかったことについてやむを得ない事情があることを再立証することで、即時抗告が認められ、却下審判が取り消された事例が存在します。
却下された原因を詳細に分析し、法的な論点を再構築するためには、高度な専門知識が必要となります。
相続放棄が認められなかった場合の次善策
相続放棄が最終的に認められなかった場合、相続人は被相続人の負債をふくむ一切の権利義務を承継することになります。この最悪のシナリオに備え、負債から逃れるための代替手段と出口戦略を把握しておくことが重要です。
多額の借金を相続したあとの債務整理(自己破産など)
相続放棄が認められず、結果として多額の負債を承継してしまった場合、その負債は相続人自身の債務となります。この場合、相続人自身の財産状況と負債状況を総合的に判断し、「債務整理」(自己破産、個人再生など)を検討することになります。
相続放棄と自己破産はまったく別の法的手続であり、相続放棄の手続とは独立して、相続人自身の状況に基づいて自己破産を申し立てることは可能です。相続した負債が原因で生活再建が困難となる場合は、弁護士に相談し、適切な方針の下、債務整理を行うことが最終的な解決策となります。
亡くなった方の連帯保証人になっている場合の法的対応
相続放棄は、被相続人の残した相続債務から解放される手続です。被相続人の連帯保証人である場合、連帯保証債務は、被相続人の死亡とは別に、相続人自身が負っている債務として残ります。したがって、相続放棄をすること自体は可能ですが、連帯保証人としての責任は別途継続することになります。
この場合、相続放棄によって被相続人の相続債務からは解放されますが、連帯保証債務の履行は求められることになります。連帯保証債務についても対応が必要な場合は、連帯保証人としての負債と相続した負債を合わせて、債務整理を検討するなど、複合的な法的対応が必要となります。
まとめ
相続放棄ができないとされる主な原因は、相続財産の処分による法定単純承認と、熟慮期間の徒過です。しかし、葬儀費用の支払いなどは単純承認とされず、また期限切れでも負債の存在を知らなかったことがやむを得ないといえる「特別な事情」が認められれば、家庭裁判所への申述が可能なケースがあります。万が一、却下審判が出ても、2週間以内の即時抗告という最終手段が残されています。
相続放棄の成功は、事案の事実関係と判例に基づく法的な解釈によって大きく左右されます。ご自身の状況が「諦めるべきではない例外」にあてはまるかどうかは、時間的な猶予がないため、速やかに相続問題を扱う弁護士に相談することを強くお勧めします。まずは弁護士の無料相談をご利用いただき、解決への具体的な一歩を踏み出しましょう。