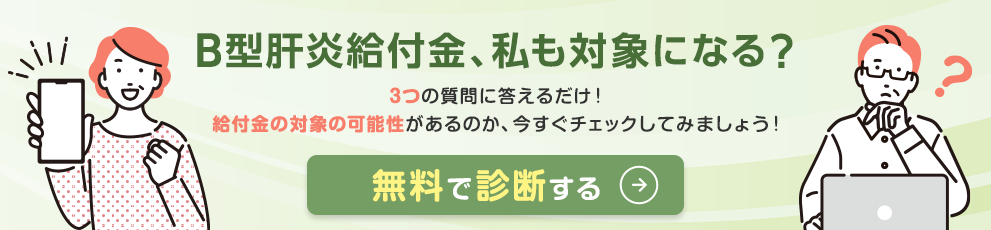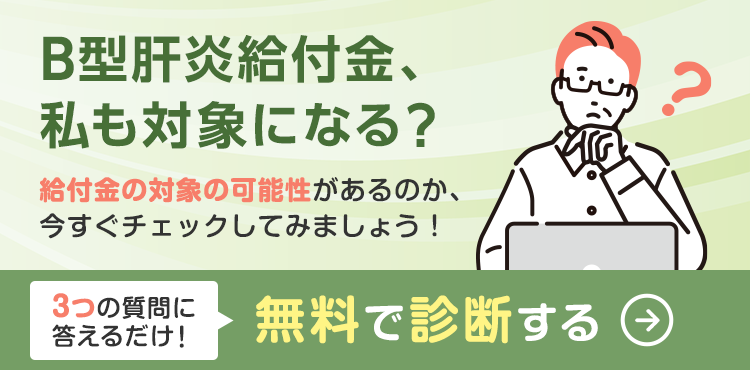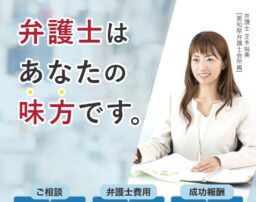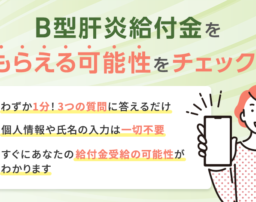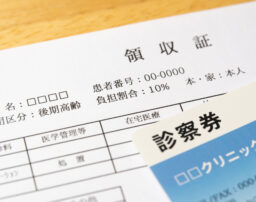B型肝炎給付金の対象者は国内に40万人以上と推計されていますが、実際に給付金を受け取るための国との和解が成立したのは、そのうちの約3割弱に過ぎません。つまり、対象者の約7割強が「もらえるはずの給付金」をまだ請求していないのが現状です。
「自分は無関係だ」と思っていませんか?集団予防接種を受けた本人だけでなく、母子・父子感染したご家族も対象になる可能性があります。
この記事では、あなたが給付対象者かどうかの判断要件や、最新の和解状況について詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
2025年1月31日時点で、B型肝炎訴訟の提訴者数の累計は13万3873人、同日時点における和解が成立した原告数の累計は11万2783人です。国は、受給対象者は約40万人に上ると推計しているので、まだまだ請求できるのに気づいていない方がいると考えられます。
受給対象者は、集団予防接種等が直接原因で感染した一次感染者だけでなく、母子感染や父子感染による二次感染者、さらには三次感染者も含まれます。
受給対象者かどうかの判断は難しいこともあるため、自己判断せず、B型肝炎訴訟を扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
アディーレ法律事務所は、B型肝炎訴訟の資料収集から給付金申請までトータルサポートを行っていますので、一度ぜひご相談ください。
B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料!
B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金とは、集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国から支払われる給付金です。
B型肝炎給付金は、B型肝炎訴訟を提起して、国との間で裁判上の和解を締結した上で、診療報酬支払基金に請求することによって支払われることになります。
参考:B型肝炎訴訟|法務省
参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省
提訴者のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
法務省により、B型肝炎訴訟の提訴者数と、和解が成立した原告数の累計が公表されています。ここからB型肝炎訴訟の提訴者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を割り出すことができます。
法務省によれば、2025年1月31日時点におけるB型肝炎訴訟の提訴者数の累計は13万3873人、同日時点における和解が成立した原告数の累計は11万2783人です。和解が成立すれば、通常は、給付金の支払いまで進みますので、和解が成立した方と給付金をもらった方はほぼ同数※と考えられます。
そして、「和解が成立した原告数の累計11万2783人」を「提訴者数の累計13万3873人」で割れば、提訴者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を算出でき、その割合は、約84.2%ということになります。
※給付金を請求する前に相続人なくして他界してしまった等の理由により、和解はしたものの給付金をもらっていないという場合もあるので、完全な同数にはなりません。
国の推計による受給対象者全体のうちB型肝炎給付金をもらった人(国と和解を成立させた人)の割合
日本国内のB型肝炎ウイルス持続感染者は110万人以上いるとされており、国の推計では、そのうち40万人以上が幼少期に受けた集団予防接種等が原因であると考えられています。つまり、国は、B型肝炎給付金の受給対象者は約40万人にのぼると推計しています。
そして、「和解が成立した原告数の累計11万2783人」を「国の推計する受給対象者数約40万人」で割れば、B型肝炎給付金の受給対象者に占める給付金をもらった人のおおよその割合を割り出すことができ、その割合は、約28.2%になります。
2025年1月31日時点におけるB型肝炎訴訟の提訴者数の累計である13万3873人、同時点におけるB型肝炎訴訟の和解者数11万2783人のいずれも、国が推計している受給対象者数の40万人に全く届いていません。
これは、B型肝炎給付金の受給対象者であるにもかかわらず、自身が受給対象者である、または、その可能性があるということに気が付いていないという方が相当数存在することも一因になっているものと考えられます。
B型肝炎訴訟の和解要件
B型肝炎ウイルスに感染している方は、ご自身がB型肝炎給付金の受給対象者かどうか、その可能性があるかについて、確認しておきましょう。
B型肝炎給付金の受給対象者となるためには、B型肝炎訴訟の和解要件を充足することが必要になります。
(1)B型肝炎給付金の受給対象者
B型肝炎給付金の受給対象者は、集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してまった方(一次感染者)だけではなく、その方からの母子感染や父子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(二次感染者)も対象になります。
また、集団予防接種等を直接の原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方からの母子感染によって感染した方から、さらに母子感染によって感染してしまった方など(三次感染者)も対象になります。
(1-1)一次感染者の要件
一次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等※を受けていること
- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
- 母子感染でないこと
- その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
※「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します
(1-2)二次感染者の要件
二次感染者の場合、母子感染と父子感染により要件が異なります。B型肝炎給付金を受給するためには、それぞれについて次のすべての要件を満たす必要があります。
【母子感染の場合】
- 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること
- 母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
- 出生から半年以内に作成された資料から、その時点で二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを確認できること
- 父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと
【父子感染の場合】
- 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること
(2)受給対象者かどうかは弁護士に相談を
B型肝炎給付金の受給対象者かどうかは、和解要件をおさえておくことによって個人でもある程度判断することが可能です。
もっとも、受給対象者かどうかは、専門知識がなければ正確に判断することはできません。一見すると受給対象者でないようにみえても、実は受給対象者であったというケースも少なくありません。
そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、一度、弁護士に相談されることをおススメいたします。
B型肝炎給付金の相談については、相談料を無料としているところもあるので、相談料無料の事務所を選べば、費用をかけることなく、B型肝炎給付金の受給対象者かどうかを相談することができます。
【まとめ】B型肝炎給付金をもらえるのに、もらっていない人がたくさんいる可能性あり
国の推計によるB型肝炎給付金の受給対象者の内、給付金を貰った人の割合は、わずか21.4%にとどまります。
受給対象者かどうかは、専門知識がなければ判断することが難しい場合があるので、受給対象者かどうかを知りたい方は、弁護士に相談する事をお勧めします。
B型肝炎給付金の請求を考えている方は、1人で悩まず一度アディーレ法律事務所にご相談ください。