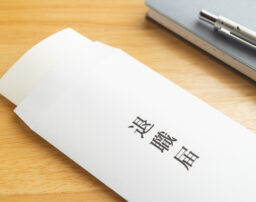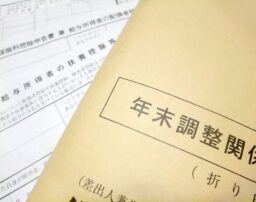「就職が決まったらお祝い金1万円贈呈!」などという人材紹介サービス事業者のインターネット上の広告を目にしたことがある方も多いかもしれません。
就職が決まって、給料が支払われる前に人材紹介サービス事業者からお祝い金ももらえるのであれば、求職者としてもうれしいですよね。
しかし、2025年4月1日から、職業安定法に基づく省令・指針の改正により、人材サービス事業者が「就職お祝い金」として就職が決まった人に金銭を支払うことは、原則として禁止されます。
これは、労働市場に大きな影響を与える重要な法改正ですが、なぜ禁止されたのでしょうか。
本記事では、法改正のポイントやその背景、企業と求職者への影響などについて弁護士が説明します。
この記事を読んでわかること
- 就職お祝い金とは
- 就職お祝い金が原則禁止された背景
- 就職お祝い金が禁止された法改正のポイント
- 企業と求職者への影響
ここを押さえればOK!
しかし2025年4月1日から、職業安定法に基づく省令・指針の改正により、募集情報等提供事業者(人材紹介サービスサイト運営者など)が「就職お祝い金」を支払うことが原則禁止されます。
社会通念上相当と認められる金銭等の提供は例外的に認められる場合がありますが、具体的な判断は慎重に行われる必要があります。
この改正により、求職者は金銭的インセンティブに惑わされることなく、質の高い人材紹介サービスを選ぶことが期待されます。また、就職お祝い金目的の短期離職・再就職が減少し、長期的なキャリア形成が促進されることで、労働市場の安定化が図られるでしょう。企業にとっても、適切な人材を確保しやすくなるメリットがあります。
これにより、求職者と企業の双方にとって健全な労働市場が形成されることが期待されます。
就職お祝い金とは?その目的と効果
求職者は、一般的に、ハローワークや職業紹介事業者(転職エージェントなど)、人材紹介サービスの事業者が運営するネットやアプリ上から、企業の情報を得て、就職活動・転職活動を行います。
就職お祝い金とは、民間の職業紹介事業者や人材紹介サービスが、求職者が転職を決めた時に支給する、金銭的なインセンティブです。
人材紹介サービスは、求職者から企業を紹介した対価として報酬をもらうことはありませんが、求職者が就職を決めたら、その企業から手数料を貰うことで営業しています。
この就職お祝い金の主な目的は、求職者の就職を決断する後押しをして、就職が決まった企業から手数料を取得することにあります。
求職者としては、就職お祝い金により、給料をもらうまでの間の生活費にしたり、就職の準備費用としたりできる、という効果もありました。
就職お祝い金が原則禁止となった理由と背景
就職お祝い金は、職業紹介事業者についてはすでに禁止されていました。
今回の改正により、新たに「募集情報等提供事業者」(人材紹介サービスサイト運営者など)についても、就職お祝い金の提供が原則禁止されます。
就職お祝い金が原則禁止となった理由と背景について説明します。
参考:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります|厚生労働省
(1)人材紹介サービスの質を見極めるため
「お金を貰える」というのは、明快でわかりやすく、強力なインセンティブです。
そのため、求職者は、そのお金がもらいたいばかりに、高額な就職お祝い金を支給する求人紹介サービスに集まってしまうおそれがあります。
しかし、そのような求人紹介サービスが、本当に求職者のことを考えて企業を紹介している=質の良いサービスを提供しているとは限りません。
お金ではなく、サービスの良し悪し=自分の経歴やキャリアプランに合った企業を紹介してもらえるか、という観点から人材紹介サービスを選ぶのが本来の姿です。
(2)短期間で離職と就職を繰り返す例があったため
就職お祝い金は、就職が決まるなどの条件を満たせばもらうことができます。
そのため、就職お祝い金目当てに、短期間で離職と再就職を繰り返す人もいたようです。
このような早期離職は、本人の中長期的なキャリア形成という観点からも、労働市場をゆがめるという観点からも好ましくありません。
もちろん、就職前に提示された条件と異なる、残業代がもらえない、不当に解雇されたなどの理由で早期離職するケースもあります。
そのような場合には、未払いの残業代を請求できたり、不当解雇を争って未払い給料の支払いを求められるケースもありますので、一人で悩まず労働問題を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
未払いの残業代について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
不当解雇について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
また、退職を言い出しにくい場合には、退職代行サービスを利用して退職する方法もあります。
退職代行サービスについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)人材紹介サービスが手数料欲しさに退職勧奨をする例があったため
人材紹介サービスのサイトの運営者は、登録した求職者が、紹介した企業に就職を決める数が多いほど、手数料収入が増えることになります。
そこで、一度就職が決まった人に対して、「こちらの企業へ転職しませんか。就職お祝い金を支給します。」などと退職・転職勧奨をすることがあったようです。
企業は基本的に長期的に働いてほしいと思っていますので、このような退職・転職勧奨は労働市場の安定性を損ないますし、企業側の手数料負担が増えるという問題がありました。
(4)人材紹介サービスと企業と金銭トラブル
就職お祝い金をもらいたい求職者が、複数の人材紹介サービスに登録して「採用が決まった」と報告する例がありました。
これにより、人材を募集する企業は、複数の人材紹介サービスから成功報酬を請求されたり、高額な違約金を請求されたりするなどのトラブルがあったそうです。
このように、企業側が安心して人材紹介サービスを利用できない状況は、企業にとっても求職者にとっても大きな問題です。また、人材紹介サービスが企業として健全に発展していくことを阻害します。
就職お祝い金禁止に関する法改正のポイント
以上のような背景から、2025年4月から、職業安定法に基づく省令・指針が改正されたのです。募集情報等提供事業者も、求職者に対して金銭等の就職お祝い金を提供することは、原則禁止されることになりました。
参考:職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)|厚生労働省
(1)募集情報等提供事業者とは
募集情報等提供事業者とは、次のような、求職者に対して求人情報を提供したり、企業に対して求職者情報を提供したりするウェブサイトや求人誌などを運営する事業者を指します。
【具体例】
- 求人サイト
- 求人情報誌
- 求人情報を投稿するSNS
- ハローワーク情報の転載サイト
- 人材データベース
(2)社会通念上相当な金銭等の提供の例外
ただし、社会通念上相当と認められる金銭等の提供であれば、例外的に認められます。
「どの程度であれば社会通念上相当といえるのか」は難しい問題です。
具体的には、個別具体的場合において、金銭等の趣旨、額や経済価値、提供手法、離転職誘引効果、複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすいまたは生じてきた形態かどうかなど、労働市場への影響をみて、総合的に判断する必要があるとされています。
厚生労働省は、「社会通念上相当と認められる程度であっても金銭等の提供は好ましくない」という前提に立っていますので、慎重に判断する必要があるでしょう。
参考:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります|厚生労働省
(3)禁止される提供行為に当たらない行為もある
厚生労働省によれば、次の2つの行為は、就職お祝い金の提供行為の禁止の対象外です。
- サービスの質の向上を図るため、アンケートの回答者に対して、抽選で少数者に500円程度の電子ギフト券等を提供する
- 来場者を確保するため、転職フェアへの来場・ブースへの訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券を提供する(求人サイトへの登録の対価は除く)
就職お祝い金禁止の企業・労働者への影響
就職お祝い金が禁止されるように、企業や労働者、ひいては労働市場にどのような影響があるのでしょうか。
(1)雇用の定着が進む
就職お祝い金の禁止により、求職者はお祝い金目当ての短期離職や再就職はできなくなります。
これにより、短期的な利益を追求するのではなく、長期的なキャリア形成を重視する傾向が強まるでしょう。結果として雇用の定着が進み、労働者にとっても雇い主にとってもよい影響が生まれ、労働市場が安定することが期待されます。
(2)人材紹介サービスの質の向上
求職者は、目先の金銭的給付に惑わされることなく、人材紹介サービスの質の高さを吟味して、就職先を決める目が養われるでしょう。
つまり、人材紹介サービスにおいては、わかりやすいインセンティブではなく、目の前の求職者に向き合いその人にあう企業を紹介していくことで、自らの企業価値を高めていくことになります。
このように、人材紹介サービスの質が向上することは、サービスを利用する求職者にもメリットがありますし、適所適材の人材を探している企業にとってもメリットがあります。
【まとめ】
2025年4月施行の就職お祝い金の禁止に関する法改正は、労働市場の健全化を目指した重要な措置です。
求職者は短期的な利益を追求するのではなく、長期的なキャリア形成を重視する必要があります。企業は適切な人材確保のために、複数の人材紹介サービスを活用して質の高い企業を見極め、労働者が長期的に働ける環境を提供することが求められます。
両者をつなぐ人材紹介サービスは、金銭的報酬により就職を後押しするのではなく、求職者の希望する地域・職種につけるよう邁進することで企業価値を高めていくことになります。
この法改正により、労働市場の安定性が向上し、企業と求職者の双方にとってより良い環境が整うことが期待されます。