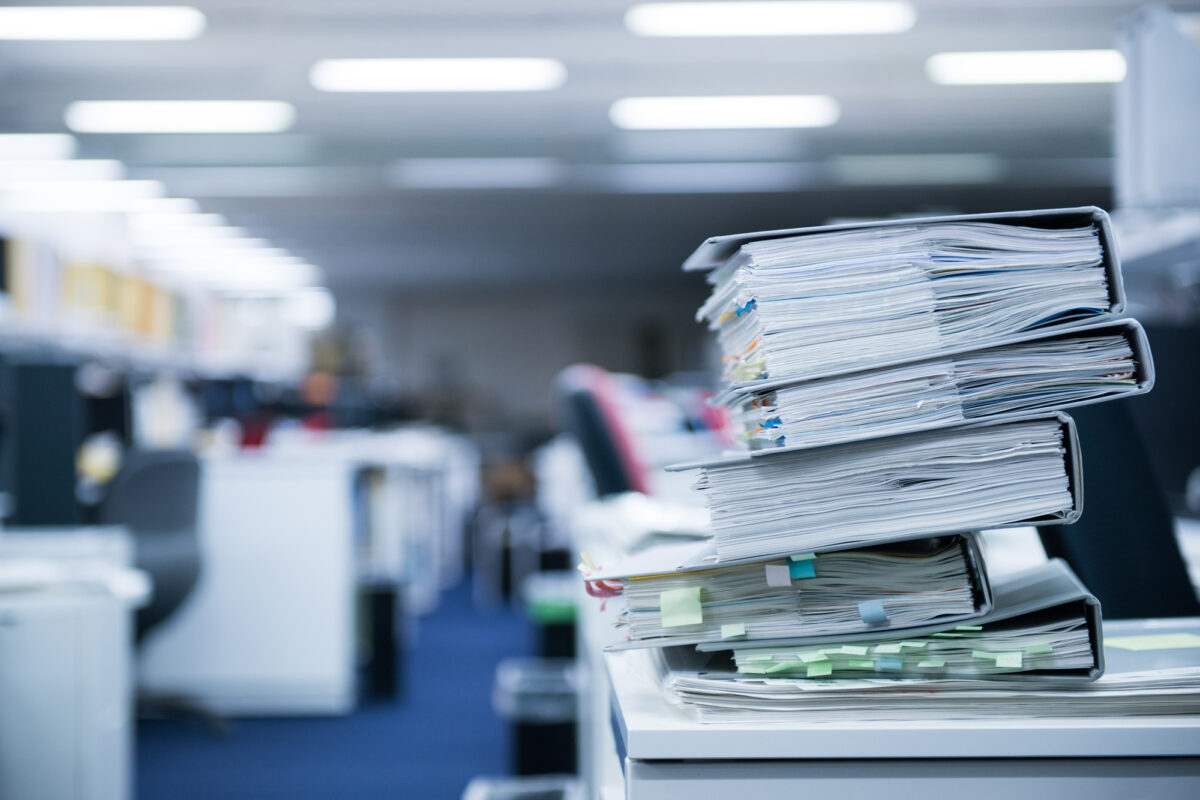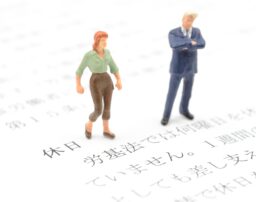仕事に追われ、休む暇もないと感じたことはありませんか?
「働きすぎ」という状況は、私たちの心身に様々な悪影響を及ぼします。
健康を守るために、そしてより良い生活を手に入れるために、働き方を見直すことが必要です。
このコラムでは、働きすぎがもたらす影響や、その原因を探り、具体的な防止策をご紹介します。仕事と生活のバランスを取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。
この記事を読んでわかること
- 働きすぎとは
- 働きすぎが招く影響
- 働きすぎの原因と働きすぎる人の特徴
- 働きすぎを防ぐ方法
ここを押さえればOK!
働きすぎの影響として、慢性疲労や不眠、うつ病、心疾患、生産性の低下が挙げられます。働きすぎの原因には、時間外労働の多さ、低賃金、長時間労働文化、無駄な業務があります。働きすぎしてしまう人の特徴として、ワーカホリックや完璧主義者、責任感が強い人が挙げられ、働きすぎの対策としては労働時間管理、業務の断り方、早退の勇気、定期的な休暇、相談先の利用があります。
アディーレ法律事務所では、退職代行や残業代請求の相談を無料で受け付けており、働きすぎにより残業代請求や退職を検討している方のご相談にのることが可能です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
働きすぎとは
働きすぎとは、過剰な労働時間が健康や生活に悪影響を及ぼす状態を指します。
ただ、働きすぎと感じる基準は個人によって違います。1日8時間労働で「働きすぎ」と感じる人もいれば、1日10時間以上働いても「まだ余裕がある」と感じる人もいます。
厚生労働省の資料によると、時間外労働・休日労働時間の合計月100時間を超えるまたは、2~6ヶ月で平均月80時間を超えると、過労死・過労自殺との関連性が強まるといわれています(過労死ライン)。
また、時間外労働時間・休日労働時間の合計が月45時間を超えると健康障害リスク(脳疾患・心臓疾患のリスク)が高まるとされています。
働きすぎが及ぼす影響とは
働きすぎは、心身の健康や業務に深刻な影響を及ぼします。
例えば、過剰な労働は体調不良やうつ病、心疾患などの健康問題を引き起こすリスクがあるほか、生産性の低下など業務にも悪影響を及ぼします。
(1)慢性的な疲労や不眠によって頻繫に体調不良になる
働きすぎは慢性的な疲労や不眠を招き、結果的に免疫力の低下や頻繁な体調不良を引き起こします。
例えば、連日の残業で疲れが全く回復しない状況が続けば、すぐに風邪や感染症などにかかりやすくなります。女性の場合は、働きすぎによるストレスで肌トラブルや月経不順などが生じる可能性もあるかもしれません。
(2)うつ病や心疾患・脳疾患などになる
長時間労働は精神的負担を増大させ、うつ病や心疾患、脳疾患のリスクを高めます。
健康診断やストレスチェックを活用し、早期発見・対策を心がけましょう。
(3)イライラや集中力の低下によって生産性が低下する
疲労の蓄積はイライラや集中力の低下を招き、仕事への集中力やパフォーマンスも低下します。例えば、本来なら絶対しないはずのミスをしてしまったり、従来の仕事量をこなせなくなったりする可能性も出てきます。
(4)仕事に対する意欲が低下する
働きすぎると仕事への興味を失い、意欲が低下します。働きすぎで心身ともに余裕がなくなると、仕事へのポジティブなイメージが損なわれ、「嫌な仕事をやらされている」と感じることがあります。
働きすぎと感じる原因とは
働きすぎと感じる原因には複数あります。
ここでは、働きすぎと感じてしまう原因について挙げていきます。
(1)時間外労働・休日労働が多い
時間外労働や休日労働が多い場合、これらの残業時間から見て「明らかに働きすぎだ」と感じることが多くなります。これは自分の過去の残業時間だけでなく、定時退社しているほかのチームの同僚や、友人、家族との比較でも実感できるものです。
また、時間外労働・休日労働時間の合計月100時間を超えるまたは、2~6ヶ月で平均月80時間を超えると、過労死ラインを超えているので、「明らかに働きすぎだ」と感じることもあるでしょう。
(2)労働時間や仕事内容に対して賃金が低い
不慣れな仕事を苦労しながら頑張っているのに、自分が思うほどの給料が支払われていない場合に、「働きすぎ」と感じやすくなります。
賃金の確保は、労働者のモチベーションと健康を支える基盤です。例えば、賃金が高いと働きすぎていても「働きすぎ」だと感じることは少ないですが、賃金が安いと働きすぎだと感じやすくなります。
(3)長時間労働が当たり前とする文化がある
会社や業界によっては、毎日残業をすることが当たり前になっている場合があります。
こうした会社に入った若手は、自分の仕事が終わったことを先輩や上司に言い出せず、付き合いで残業をしてしまうことがあります。
また、そういう会社は長期間労働を評価する傾向にあり、長期間残って仕事せざるを得ない状況になっていることもあります。
(4)無駄な業務が多い
業務の効率化が進まないと、無駄な労働が増えます。
例えば、無駄な打ち合わせや朝礼、事務作業など無駄な作業だと感じてしまう業務が多い会社だと「働きすぎだ」と感じてしまうことがあります。
働きすぎる人の特徴とは
働きすぎる人には共通する特徴があり、それがストレスや健康問題の原因となります。
主な特徴としては、次のものが挙げられます。
(1)ワーカホリックな人
仕事に没頭しすぎることで、休息を忘れがちです。
気づかないうちにストレスが蓄積しやすく、気づいた時には重大な健康問題を引き起こすリスクがあります。定期的な休暇取得を心がけましょう。
(2)完璧主義な人
高い成果を求めるあまり、過労になりがちです。ミスを許さない姿勢がプレッシャーとなり、心身に負担をかけます。適度に手を抜くことも必要です。
(3)プライドが高い人
プライドが高いために、同僚や部下など周囲を比べてできない自分を許せず自分の許容を超えた業務を抱え込んでしまう傾向にあります。
(4)責任感が強く、周囲に頼れない人
全てを自分で抱え込む傾向があり、長時間労働に陥ります。責任感は大切ですが、適度に周囲に頼ることも重要です。
働きすぎを防ぐ方法とは
働きすぎを防ぐためには、効果的な対策を講じることが重要です。次の対策を講じることで、ストレスや健康問題を軽減し、ワークライフバランスを整えることができます。
(1)労働時間を管理する
労働時間の記録をつけ、自分を客観視することで、働きすぎないように歯止めをかけることができます。また、労働時間を記録し、管理することで自己の限界を知ることもできるでしょう。
(2)できない仕事は断る
業務量が多い場合は、無理せず断ることも大切です。自己の限界を知り、無理な作業を避けることで働きすぎを防ぐことができます。
(3)早く帰る勇気を持つ
定時退社を心がけ、長時間労働を避けます。勇気を持って早く帰ることで、生活の質を向上させます。
(4)意識的に休む
仕事に没頭しすぎることで、休息を忘れがちの人は、意識的に休むようにしましょう。
定期的な休暇やリフレッシュ時間を確保し、心身のリフレッシュを図ります。
(5)会社や上司に相談する
働きすぎでキャパオーバーになっていたり、心身に不調が生じたりしている場合は、それを会社や上司に相談をすることも大切です。
過労で生産性が低下し、ミスが頻発している場合、作業要員やスケジュールの調整をしてもらったほうがプロジェクトもトラブルなく確実にまわる可能性があるためです。
(6)専門機関に相談する
会社や上司に相談できない場合には、専門機関に相談するようにしましょう。
(6-1)労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、労働基準法に基づいた労働条件の違反を取り締まる機関です。
働きすぎの相談についても行うことができます。
(6-2)弁護士に相談する
法的な対応が必要な場合、弁護士に相談することが最も効果的です。
特に、働きすぎているのに賃金や残業代の不払いがある場合や退職したいのにできない場合に適切な法的措置を取ることができます。
【まとめ】働きすぎは体調や業務に悪影響を及ぼすおそれ|会社や専門機関に相談を!
働きすぎは健康や業務に多大な悪影響を及ぼします。慢性的な疲労や不眠、うつ病、心疾患のリスクが高まるため、早期対策が必要です。
特徴的な行動パターンを見直し、労働時間を管理することが重要です。会社や専門機関への相談を通じ、ワークライフバランスを整えましょう。これにより、生活の質を向上させ、持続可能なキャリアを築けます。まずは、労働時間の管理から始め、必要に応じて専門機関に相談する行動を起こしましょう。
仕事が辛くても辞められないという方、未払いの残業代を受け取りたいという方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。アディーレ法律事務所では退職代行や残業代請求に関する相談料は何度でも無料です(2024年12月時点)。
退職代行や残業代請求でお悩みの方は、退職代行や残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。