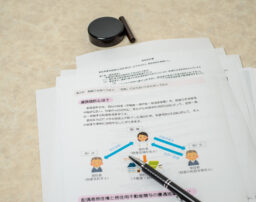「家族信託をやって後悔しない?」「家族信託って本当に必要なの?」と悩んでいませんか?
家族信託は、将来の資産管理を円滑に行うための非常に有効な手段になります。しかし、知識がないまま進めてしまうと、家族の仲が悪くなったり、思わぬ出費が発生したりとトラブルに巻き込まれたり、後悔したりする危険があるのも事実です。
この記事では、家族信託を検討しているあなたが安心して前に進めるよう、家族信託が「危険」「必要ない」と言われる理由やよくある失敗事例、その対策方法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
ここを押さえればOK!
これらのリスクを回避するためには、親が健康なうちに家族間で十分に話し合い、専門家へ依頼して適切な契約を結ぶことが重要です。家族信託でお悩みの方は、アディーレへご相談ください。
遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
家族信託は危険?必要ない?「危険」「必要ない」と言われるワケ
家族信託とは、財産の管理権限を信頼できる家族や親族に託して、認知症による資産凍結などを防ぐ仕組みのことです。たとえば、息子が父親に代わって託された財産の管理や運用を行い、それで得た利益を医療費や介護費として父親に渡すといったイメージとなります。
家族信託の最大のメリットは、親が認知症となった場合でも資産凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用を行い続けることができることです。これだけ聞くとメリットしかないように思えますが、一方で、家族信託は「危険」「必要ない」との声も聞かれます。
ここでは、家族信託が「危険」「必要ない」と言われるワケについて紹介しましょう。
(1)家族信託が「危険」と言われるワケ
「家族信託が危険」と言われるワケは、家族信託契約の内容や運用を間違ってしまうと、思わぬトラブルや税金上の不利益が生じる危険(リスク)があるからです。
たとえば、財産の管理を任された受託者による不適切な財産管理や、家族間での話し合い不足が原因でトラブルが生じたり、運用方法次第では思わぬ高額な出費が発生したりするおそれがあります。
(2)家族信託が「必要ない」と言われるワケ
一方で、「家族信託は必要ない」と言われるのは、財産の規模や家族構成によっては、他の方法でも目的を達成できることがあるためです。たとえば、次のようなケースでは家族信託よりも他の制度を利用する方が適している可能性があります。
- 預貯金や不動産といった信託できる財産がほとんどない場合
- 生前贈与などで、すでに財産の名義変更を済ませている場合
- ご本人がまだ若く、将来の認知症リスクが低い状況である場合
- 財産管理を託せる家族がいない場合
これらのケースに当てはまる場合、無理に家族信託を検討するのではなく、成年後見制度や遺言書といった他の対策を検討する方が良いでしょう。
家族信託は危険?家族信託で失敗・後悔したケース9選
次に、家族信託を検討中の方に向けて、家族信託で失敗・後悔したケースを紹介します。
ここでは、失敗・後悔ケースを踏まえて、家族信託のリスク(危険)を回避する方法についても解説しましょう。
(1)親の認知症が進んで家族信託ができなくなった
家族信託の契約は、財産の管理を委ねる委託者(親など)が家族信託の契約が適切かどうか判断できる能力があるうちにしかできません。
実際に家族信託の手続きを進めていたものの、親の認知症が急速に進行してしまい、契約を結ぶ前に家族信託の契約が適切かどうか判断できるだけの能力が失われてしまった結果、信託契約が無効になってしまったというケースは少なくありません。
家族信託を検討しているのであれば、親の心身が健康なうちに手続きを開始するようにしましょう。親に判断できる能力があるか不安がある場合には、医師から診断書を取得しておくのもおすすめです。
(2)家族・兄弟間の仲が悪くなった
家族信託は、財産の管理を委ねる「委託者」と委託者に代わって財産の管理を行う「受託者」の二者間で契約できますが、当事者以外の家族と話し合いが十分に行われていないと、不満や不安を抱かれるおそれがあります。
たとえば、受託者である長男が親の財産を管理することに対し、他の兄弟や親族から「勝手に財産を使っているのではないか」「自分は親から信頼されていないのか」と疑念を持たれるケースです。
このような家族間のトラブルを避けるためには、家族信託の契約を結ぶ前に、「どのような形で財産管理を行っていくのか」「誰に財産管理を任せるのが適切なのか」など家族間で十分な話し合いをしておくことが大切になります。
(3)受託者の負担が大きかった
財産の管理を任された受託者は、信託財産の管理や運用、収益の分配といった多岐にわたる役割を担います。これらの作業が想像以上に重荷となり、受託者が負担を感じてしまうケースがあります。
たとえば、信託財産に賃貸不動産が含まれる場合、家賃の管理や修繕の手配、不動産所得にかかる税務申告まで様々な作業をしなければなりません。
受託者の負担を軽減するためには、管理業務の範囲を明確に定めたり、他にも財産の管理や運用を任せる共同受託者(複数人で協力して財産を管理する)を定めて、作業を分担したりする方法などを検討しておくとよいでしょう。
(4)想定より高額な税金・費用がかかった
家族信託では、専門家への報酬、登記費用、登録免許税などの初期費用に加え、信託運用方法を間違うと思わぬ税が発生するなど想定外の出費が発生することがあります。
これらのリスクを回避するためには、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談し、どれぐらいの費用がかかる見込みなのか費用の見積もりをとったり、また想定外の税金が発生しないための方策などを話し合っておいたりする必要があるでしょう。
(5)信託口口座が開設できなかった
家族信託を行いたかったけど、信託口口座が開設できなかったというケースです。信託口口座が開設できないと、信託財産と受託者個人の財産が混ざってしまい、適切な管理ができなくなります。
各金融機関によってどのような信託契約書であれば信託口口座を作れるかの取り扱いが異なります。家族信託のために信託口口座を作りたいという場合には、事前に各金融機関にどういう信託契約書であれば信託口口座をつくれるのかを問い合わせておきましょう。
(6)信託できない財産を信託してしまった
家族信託では、金銭や不動産など様々な財産を信託することができますが、すべての財産を信託できるわけではありません。
たとえば、現況が農地である土地は、農地法の規定によりそのまま信託することはできません。信託契約書に記載しても、その部分は無効になってしまいます。
農地を家族信託したい場合には、事前に農業委員会への届出・許可をもらっておく必要があります。
(7)信託無効を主張された
他の親族から信託無効を主張される可能性もあります。
たとえば、「家族信託の契約を結んだときに、父親(委託者)は家族信託が適切なものなのか判断する能力がなかった」というものです。
このリスクを回避するためには、家族信託の契約を結ぶ際に、委託者が「家族信託が適切なものか判断する能力がある」とする医師の診断書を取得しておいたり、家族信託の契約を公正証書で作成したりしておくとよいでしょう。
(8)家族信託終了時に遺留分でトラブルになった
家族信託では、家族信託終了時に遺留分でトラブルになる可能性があります。
遺留分とは、簡単に言うと、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産の取得分のことです。
たとえば、家族信託終了後に信託財産を委託していた長男にそのまま承継させるように設定された場合を考えてみましょう。この場合、長男以外の相続人から「長男だけがたくさんの遺産を受け取るのはおかしい!遺留分(最低限の遺産の取得分)が侵害されている」と裁判を起こされる可能性があります。
信託契約を結ぶ前に、遺留分を侵害しないように資産の承継について家族で話し合っておくようにしましょう。
(9)専門家に依頼せずにトラブルになってしまった
家族信託を専門家に依頼せずにトラブルになったというケースもあります。
専門家の助言を得ずに、インターネットの情報だけで手続きを進めた結果、契約書に不備があったり、信託の目的が達成できなかったりするケースが少なくありません。
専門家に依頼することで、トラブルをできる限り回避しつつ、信託契約書の作成から、税務上のアドバイス、信託口口座の開設支援など、手続き全体を円滑に進めることができます。
家族信託の「費用」はいくら? |自分で行う場合と専門家に依頼する場合の違い
家族信託にかかる費用は、決して安くはありません。実際、自分で手続きする場合は数万~20万円程度、専門家に依頼する場合は50~100万円程度が相場になります。
専門家に依頼する費用が高いと感じるかもしれませんが、専門家に依頼する方が将来のトラブルを回避できる可能性が高く、この費用は将来のリスクやトラブルを回避するための投資と考えるべきといえるでしょう。
家族信託に関するよくある質問(Q&A)
最後に、家族信託に関するよくある質問をまとめています。ぜひ参考にしてください。
(1)家族信託は一人っ子にも必要ですか?
一人っ子の場合、兄弟間の相続争いは起きませんが、親が認知症になった際の財産管理という観点から、家族信託は非常に有効な手段となります。
親が認知症になり財産管理できなくなった場合、親に代わって子供が財産を自由に動かせなくなり、口座が凍結されるリスクが付きまといます。それは一人っ子であっても他の家庭と同じです。
(2)家族信託の「30年ルール」「1年ルール」とは何ですか?
家族信託には、信託期間を制限する「30年ルール」と「1年ルール」が存在します。似た言葉のように思えますが、制度としては全然違うものです。
(2-1)30年ルールとは
30年ルールとは、信託から30年を経過した後は受益権の新たな承継は1度しか認められないという制度です。
たとえば、父親が息子に財産管理を委ね、その財産から得られる利益を受け取っていた父親が死んだ場合を考えてみましょう。
父親の死後はその妻である母親が財産から得られる利益を受け取る権利(受益権)を引き継ぐことができますが、信託から30年経過した後であれば、その引継ぎは1度しか認められないという制度になります。
もし子孫などさらに受益権を引き継ぎたい場合には、いったん家族信託を終了し、新たに家族信託の契約を結びなおす必要があります。
(2-2)1年ルールとは
1年ルールとは、財産の管理を任された受託者が財産から利益を受ける唯一の受益者となり、その状態が1年間続くと信託契約が強制的に終了してしまうという制度になります。
他にも、財産の管理を任された受託者が死亡するなどいなくなって1年間経っても、新しい受託者が現れなかった場合には、信託は終了してしまいます。
これらのルールを理解しておかないと、1年ルールによって家族信託が突然終了してしまうなど、信託の目的が達成できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
(3)家族信託は途中でやめられますか?
家族信託は、途中で終了させることが可能です。信託法では、財産の管理を任せた委託者と財産から得られる利益を受け取る受益者の合意があればいつでも終了できると定められています。
しかし、実際には信託契約書に「(財産の管理を行う)受託者及び(利益を受け取る)受益者の合意が必要」と明記されていることが多く、その場合は契約書の内容に従わなければなりません。
ただし、財産の管理を委ねた委託者・受益者(親など)が認知症などで意思表示が困難になった場合、合意による終了ができなくなる点に注意が必要です。この場合には、成年後見人を選任し、親に代わって成年後見人に家族信託の終了に合意してもらう必要があります。
【まとめ】家族信託は正しい活用を行えば危険ではない!弁護士へ相談を
家族信託は、専門知識がないまま進めると家族間のトラブルや税金の問題を引き起こすリスクがあります。しかし、家族間の話し合いを十分に行い、専門家のサポートを得ることで、これらのリスクを最小限に抑え、親が元気なうちに安心して財産管理の準備を進めることができます。
家族信託についてお悩みの方は、ご家族の将来のためにも、まずはアディーレへご相談ください。