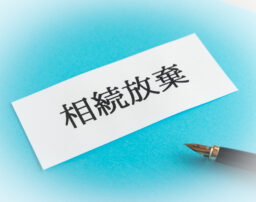故人の銀行口座をそのまま使うことは、相続人である遺族にとって一見便利に思えるかもしれません。
しかし、刑事上民事上の法的なリスクが伴います。
この記事では、故人の銀行口座を相続人が使用し続けることの法的問題点や、適切な対応方法、相続放棄を検討している場合の銀行口座の取り扱いについて詳しく解説します。
故人の財産を適切に管理、相続するための具体的な手順を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
ここを押さえればOK!
預貯金は相続人の共有財産となり、遺産分割協議を経ずに引き出すことは原則としてできません。無断で引き出すと、刑事責任が問われるリスクは低いものの、民事責任として他の相続人から不当利得として返還を求められるリスクがあります。
故人の口座から預金を引き出すには、相続手続を行いましょう。
遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議が成立していない場合でも、相続預金仮払い制度を利用して一部の預金を引き出すことが可能です。家庭裁判所の審判を通じて仮払いを求める方法もあります。
相続放棄を検討している場合、故人の預金口座を解約・引き出すと相続放棄が認められない可能性があるため注意が必要です。
預金の引き出しなど相続手続でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
相続手続のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
故人の銀行口座をそのまま使うことの法的問題点
預貯金債権はその名義人が亡くなった時点で、相続人の共有状態となり、遺産分割の対象となります。
原則として、相続人が遺産分割協議をして預金口座の扱いを取り決めない限り、勝手に故人=被相続人の預金口座から引き出すことはできません。例外的に遺産分割協議を経ずに引き落とす方法については、後でご説明します。
ここでは、相続人の一人が、名義人である被相続人が死亡したことを銀行に告げずに、当該預金口座から勝手に預金を引き出すことの法的問題点を説明します。
(1)刑事責任を負うリスク
遺産分割協議など、正当な手続を経ずに亡くなった人の口座から預貯金を引き出しても、刑事上、「他の相続人のお金を盗んだ」などとして、罪に問われることはあまりありません。
配偶者、直系血族又は同居の親族の間で、窃盗や横領、詐欺を行っても、法律上刑が免除される規定があるため(刑法244条:親族相盗例)です。
家族間の一定の犯罪については、「家族間での問題解決が望ましく法は立ち入らない」という立法政策によるものです。
ただし、相続人が複数人いて、直系血族でもなく同居の親族でもない場合には、法律上は親族相盗例に当たりませんので、注意が必要です。
(2)民事責任を負うリスク
故人の銀行口座は、相続人の共有になります。そこで、一部の相続人がそのまま引き出したりすると、「勝手に遺産を使い込まれた」として、相続人間でのトラブルが発生する可能性があります。
そのような場合でも、預金を引き出した相続人以外の全員の相続人の同意があれば、死後に引き出された預金を遺産に組み戻して、遺産分割調停で話し合って解決を目指すことができます。
遺産分割調停で話し合って解決することが困難というケースでは、権利を侵害された他の共同相続人は、引き出した相続人に対し、不当利得として返還を求めていくことになるでしょう。
故人の凍結された口座から預金を引き出す方法①:相続手続
被相続人の預金口座からお金を引き出すには、基本的に相続手続が必要です。 銀行に対しては、故人の死亡を速やかに報告し、必要な手続きや必要な書類を確認するようにしましょう。
相続手続は、遺言書がある場合とない場合で異なりますので、ケース別に説明します。
相続手続で疑問や不安を感じたら、一度弁護士に相談する事をお勧めします。
(1)遺言書がある場合
被相続人に遺言書がある場合、基本的に、遺言書に書かれた内容に従って相続財産が分割されます。
遺言書で「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇 の預貯金の元金及び利息について、〇〇(特定の相続人)に相続させる」という記載がある場合には、基本的にはその特定の相続人が、預金を引き出すことができます。
この場合、預金引き出しには次のような手順が必要です。
- 相続人の調査、確定
- 家庭裁判所に遺言書の検認の請求(自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合)
- 金融機関へ必要書類を提出(金融機関所定の届出書、遺言書、検認済証明書、故人の死亡が確認できる戸籍謄本(※)、当人の実印と印鑑登録証明書、故人の通帳・キャッシュカードなど) ※法務局で取得した法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできる
各金融機関によって、必要とされる書類が異なることがあります。事前に何が必要が問い合わせたうえで、書類を集めるとよいでしょう。
また、原本を提出した場合でも必要であれば原本は返却してくれるので、書類を提出するときに返却希望であることを伝えます。
遺言で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が預貯金を解約・引き出すことになります。
その場合でも、基本的に必要となる書類は同じですが、家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合にはそのことが分かる書類(遺言執行者選任審判書謄本)も必要です。遺言執行者が引き出す場合にも、事前に金融機関に対して必要な書類を確認するようにしましょう。
遺言がある場合の相続手続について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。 具体的な手順は次の通りです。
- 相続人と遺産の調査、確定
- 遺産分割協議書の作成・署名
- 金融機関へ必要書類の提出(金融機関所定の届出書、遺産分割協議書、亡くなった方の戸籍謄本(※)、すべての相続人の戸籍抄本(謄本)、すべての相続人の印鑑登録証明書、代表して預金を引き出す者の実印、故人の通帳・キャッシュカードなど) ※法務局で取得した法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできる
各金融機関によって、必要とされる書類が異なることがあります。事前に何が必要が問い合わせたうえで、書類を集めるとよいでしょう。
遺産分割協議が成立するには長くて1年以上かかるケースもあり、その間被相続人の預金から支払いができないとなると、相続人が生活に困るなどの様々な問題があります。
そのような場合には、次の相続手続以外の預金を引き出す方法を検討するとよいでしょう。
故人の凍結された口座から預金を引き出す方法②:相続預金仮払い制度
遺産分割前に、相続人が一定額について被相続人の預金口座からお金を引き出すことができます。この制度を、相続預金の払い戻し制度とか、仮払い制度、と言ったりします。
この制度の利用により、他の相続人の同意がなくても、被相続人の預貯金を一部を引き出すことが可能です。
この場合、本人確認書類に合わせて以下の書類を提出すれば、預金を払い戻すにあたって他の相続人の同意を得る必要はありません。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
※出生から死亡までの連続したもの - 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
- 金融機関所定の依頼書
ただし、金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、あらかじめ払戻しを受けたい金融機関に問い合わせておくのが確実でしょう。
払い戻しには限度額があります。相続開始時の預金額の3分の1の金額に、払戻しを行う相続人の法定相続分を乗じた額が、上限額です。
ただし、1つの金融機関から払い戻しできるのは150万円が上限です。
故人の凍結された口座から預金を引き出す方法③:家庭裁判所の審判
遺産分割は話し合いでも行えますが、裁判所の調停や審判手続きを利用することも少なくありません。
このような調停・審判が申し立てられている場合、相続人は、家庭裁判所に対して相続預金の全部又は一部を仮に払い戻しすることを求めて、審判を申し立てることができます。
裁判所は、仮払いの必要性があり、他の相続人の利益を害しないと認めた場合に、仮払いを認めます(仮分割の仮処分)。仮払い制度のように、決まった上限額はありません。
相続放棄を検討している場合の口座の取り扱い
被相続人が残した財産よりも、借金の方が多いというケースでは、相続放棄を選ぶ人も多いです。
相続放棄の手続や、相続放棄する際の故人の預金口座の取り扱いの注意点を説明します。
(1)相続放棄の手続と期限
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。 相続放棄が認められると、相続放棄をした人は、初めから相続人でないものとして、故人の財産や負債を一切引き継ぎません。
被相続人の預金口座を解約したり、引き出したりすると、相続放棄が認められない可能性がありますので、相続放棄を検討している人は注意しましょう。
相続放棄の注意点や「してはいけない行為」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)相続放棄後の口座管理の注意点
相続放棄が受理された場合、次順位の法定相続人が相続人となります。
故人の預金口座は相続人の共有となり、相続放棄した人は相続人ではありませんので、何の権限も持ちません。 通帳やカードなどは他の相続人に引き渡すようにしましょう。
【まとめ】故人の預金口座は正式な手続を経て引き出す
故人の銀行口座を、凍結前にそのまま使用して引き出すことは、法的リスクがあり相続人間のトラブルを引き起こす恐れがあります。 故人の預金を引き出すには、適切な相続手続を経ることが重要です。
相続手続は、通常、相続人の確定、相続財産の把握、相続税の概算、他の相続人との合意形成が必要になりますが、相続人同士が疎遠だったりすると話し合いもうまくできないことがあります。 早い段階で、弁護士に相談・依頼することが、相続手続きをスムーズに進めるポイントと言えるでしょう。
アディーレ法律事務所には、相続放棄、相続税、遺言書作成など、複雑な遺産相続の手続をまとめて依頼できます。 相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。