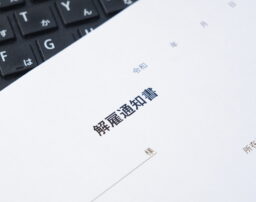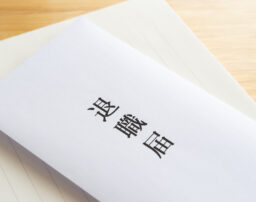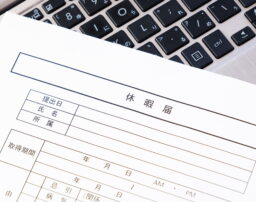「労災って何だろう?」
働いたことのある人なら一度は「労災(保険)」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
ですが、「労災とは何か」と言われると、正確なことはよく分からないという方も多いかもしれません。
労災保険とは、業務上や通勤中のケガや病気などに対して支払われる保険です。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 労災とは何か
- 労災保険の加入条件と保険料
- 労災保険の認定基準
- 労災保険の給付の種類
- 労災の申請手続き
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
労災とは
「労災」(労働災害)とは、労働者が仕事に従事したことによって起きたケガや病気、死亡のことをいいます。
また、「労災保険」(労働者災害補償保険)とは、業務や通勤を原因とするケガや病気の医療費などを補償する制度です。
労働災害のうち、業務上の事故などを「業務災害」、通勤中の事故などを「通勤災害」と呼びます。
労働災害となり得るものとして、次のようなものがあります。
- 度重なる残業でうつ病を発症した
- ベルトコンベアの修理中ローラーに体を巻き込まれ死亡した
- 宅配業務中に交通事故に巻き込まれむち打ちになった
- 通勤中自宅の最寄り駅の階段で足を踏み外して足を捻挫した
- 休憩中倒れてきた事業場の看板で頭を打った
具体的な事情によるものの、これらのケースでは労災保険が支払われる可能性があります。
(1)業務災害
「業務災害」とは、業務上の事由による労働者の死亡、負傷、疾病、または障害のことです。
具体的にどのようなケースで業務災害と認められる可能性があるのかを紹介します。
次のようなケースでは、業務災害と認められる可能性があります。
- トラックの荷台を下ろす際に誤って転倒した結果死亡した。
- 台車で荷物を運ぼうとしたところ台車が動き出したためバランスを崩し足を骨折した。
- 日射病の予防措置を採ることなく炎天下で作業をしていたところ日射病で死亡した。
- 撮影のために床面を水性塗料で塗装したところガス中毒を発症した。
- ラーメン店の圧力釜の蓋をゆるめたときに噴出した蒸気で火傷を負った。
製造業に限られず、どの業種においても業務災害は起こります。
一見リスクの低い仕事にみえても、いつ事故に巻き込まれるかわかりません。
日々の仕事において自らも事故が起きないように注意したいところです。
(2)通勤災害
「通勤災害」とは、合理的な経路・方法による通勤途中に起こった労働者の死亡、負傷、疾病、または障害をいいます。
毎日会社から直帰するわけではなく、スーパーやコンビニに立ち寄ることもあるでしょう。
最寄り駅で電車の待ち時間にジュースを買う程度ならば、何ら問題ありません。もちろんトイレに寄る程度でも「通勤」にあたります。
ただし、通勤路から外れてプライベートの用事を済ませる場合、原則として「通勤」とはいえず、通勤災害にはあたりません。
例外的に、日用品の購入のための必要最小限度の逸脱・中断などいくつかのケースでは、逸脱・中断後、再び元の通勤路に戻ると「通勤」といえます。
例えば、スーパーで日用品を購入した後、普段の通勤路に戻った後事故に巻き込まれた場合には、労災と認められる可能性があります。
労災保険の加入条件と保険料
労災保険は、社会保険制度の1つです。労災保険の加入条件と保険料について解説します。
(1)加入条件
労災保険では、勤務形態は関係ありません。
正社員に限られず、パートやアルバイト、日雇い労働者であっても、原則として、会社は従業員を雇用する限り、労災保険に加入させなければなりません。
他方、会社が従業員として雇用しているのではなく実態として請負契約の関係にあるなど、雇用関係にないといえる場合には、原則として労災保険が適用されません。
(2)保険料は会社が全額負担
労災保険の保険料は会社が全額負担します。
労災保険の認定基準
労災保険には認定基準があります。
業務災害と通勤災害の認定基準についてご説明します。
(1)業務災害の認定基準
業務災害と認定されるためには、「業務遂行性+業務起因性」が必要です。
「業務遂行性」とは、事業主の支配下にある状態を意味します。
「業務起因性」とは、業務とケガや病気などの間に一定の因果関係があるという意味です。
どのような場合に業務災害といえるかどうかは、ケースバイケースです。
もっとも、業務災害の起こる状況は、次の3つに大きくグループ分けすることができます。
- 事業主の支配下にある状態で、会社の事業場内で業務に従事している場合
- 事業主の支配下にある状態で、会社の事業場内にいるものの、業務に従事していない場合
- 事業主の支配下にある状態にあるものの、会社の事業場外にて業務に従事している場合
1のグループのように、例えば勤務時間内に会社の敷地内で会社から指示されている業務をしている中で起きた事故であれば、基本的に業務災害であると認められるでしょう(私的行為をしている場合などを除く)。
2のグループにあたるのは、例えば休憩中の事故です。このような場合、グループ1に比べれば業務災害とは認められない場合が多くなりますが、会社の施設の不備が原因で発生したケガや病気などであれば業務災害と認められます。
なお、用便等の生理行為の場合は、業務に付随する行為として、基本的には業務災害として認められます。
3のグループにあたるのは、例えば出張中の出来事です。
出張中は、基本的には、業務災害として認められます(私的行為をしている場合などを除く)。
参考:業務災害とは(業務上の負傷・疾病)|厚生労働省 福島労働局
参考:業務災害について|厚生労働省
(2)通勤災害の認定基準
一般的に通勤というと、勤務先に通うことです。
しかし、労災における通勤とは、1.就業に関し、2.次の3つのいずれかの移動を、3.合理的な経路及び方法によって行うことをいいます(業務の性質を有するものは除く)。
- A.住居と就業場所の間の移動
- B.就業場所から別の就業場所の間の移動
- C.Aの往復に先行または後続する住居間の移動
3「合理的な経路及び方法」についてご説明します。
自宅から会社に行く途中の事故でも、必要がないのにあえて遠回りをした場合には原則として「通勤」にあたりません。
たとえば、車で30分の距離にもかかわらず、気分転換のためにドライブをしようと1時間かけて会社に行った場合、通勤災害にはあたりません。
これに対して、交通渋滞のために迂回路を選んだのであれば、普段以上に通勤時間がかかる道を選んだとしても、合理的経路として通勤災害にあたります。
なお、移動の経路を逸脱・中断した場合には、逸脱・中断の間及びその後の移動は原則として「通勤」とはなりません。
労災保険の給付の種類

労災保険によって受け取れる主なお金をご紹介します。
なお、給付を受けるためにはこれからご説明するほかにも細かい要件が決まっています。
ご自身が、具体的にどのような給付の対象になるのかは、専門家に確認しましょう。
参考:労災保険給付の一覧|厚生労働省 東京労働局
参考:労災保険 請求(申請)のできる保険給付等|厚生労働省
(1)療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、簡単に言えば治療や治療費のことで、次のもののことです。
- 療養の給付(労災病院や労災指定病院での診察・処置・手術、入院や移送、薬剤の支給などの現物給付)
- 療養の費用の支給(近くに労災病院や労災指定病院がないなどの理由でそれ以外の病院にてケガや病気の治療を受けた場合に、かかった治療費などの費用を支給)
原則として、症状が治癒(※症状固定含む)するまで療養(補償)給付を受けることができます。
※症状固定とは、傷病の症状が安定し、一定の医療を行っても、改善など医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
療養(補償)給付たる療養の費用を支出した日ごとに、その翌日から2年の時効があります。
時効の期間が経過して、時効が完成すると給付を請求することができなくなるので、注意しましょう。
(2)休業(補償)給付
仕事中にケガをして働けなくなった場合、および仕事に関連する病気で働けなくなった場合その期間の給付基礎日額の8割にあたる金額が労災保険から支給されます。
給付基礎日額の6割に相当するお金を休業(補償)給付、2割に相当するお金を休業特別支給金と呼びます。
※給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当するものです。原則として、直近3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除した1日あたりの賃金額とされます。計算の基礎となる賃金の総額には、ボーナスや臨時に支払われた賃金は含まれません。
なお、休業(補償)給付、休業特別支給金の支給対象となるのは、休業第4日目からです。
休業補償は、賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年で時効になります。
(3)傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、療養(治療)開始から1年6ヶ月以上経っても労災によるケガや病気が治らず、ケガや病気の程度が障害等級第1~3級に達している場合、労働基準監督署長の職権により、かかる状況が継続している間に支給されるものです。
年金の額は、障害等級第1~3級に応じて、1年につき給付基礎日額の245~313日分です。
また、傷病特別年金として、労災が発生した日または病気になったことが診断で確定した日以前1年間のボーナス等の特別給与を算定の基礎とし、障害等級第1~3級に応じて、その算定基礎日額(ボーナス等を365で除したものです。臨時に支払われた賃金は含まれません)の245~313日分が支給されます。
支給される額は、給付基礎日額を365で乗じた金額の20%相当が上限とされますが、150万円を超えることはできないとされます。
さらに、傷病特別支給金として、障害等級第1~3級に応じ、100万~114万円が一時金として支給されます。
なお、傷病(補償)年金の支給により、休業(補償)給付は支給されなくなります(労災保険法18条2項)。
※障害等級第1~3級とは、およそ就労することが不能と評価される程の重大な障害です。
受給にあたって自分で申請しなくても良いので時効は関係ありません。
(4)障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、業務災害・通勤災害によるケガや病気が治った(症状固定した)ものの、次のような一定の障害が残ったときに給付されるお金です。
- 障害等級第1~7級に相当する障害
⇒障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金 - 障害等級第8~14級に相当する障害
⇒障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
| 障害の程度 | 労災保険の種類 | 給付額(障害の程度によって給付額は異なります) |
| 第1~7級に相当する障害 | 障害(補償)年金 | 給付基礎日額の131~313日分(年金) |
| 障害特別支給金・障害特別年金 | 【障害特別支給金】159万~342万円(一時金) 【障害特別年金】算定基礎日額の131~313日分(年金) |
|
| 第8~14級に相当する障害 | 障害(補償)一時金 | 給付基礎日額の56~503日分 (一時金) |
| 障害特別支給金、障害特別一時金 | 【障害特別支給金】8万~65万円( 一時金) 【障害特別一時金】算定基礎日額の56~503日(一時金) |
障害等級に応じて一括して一定額の前払いを受けることを可能とする障害年金の前払一時金の制度もあります。
障害(補償)給付を受ける権利は、治癒(症状固定)となった日の翌日から、5年で時効にかかります。
また、障害年金の前払一時金を受ける権利については、傷病が治癒した(症状固定)日の翌日から2年で時効にかかります。
参考:業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます|厚生労働省
参考:障害(補償)年金前払一時金|厚生労働省
(5)遺族(補償)給付
労働者が、業務災害または通勤災害により死亡したときには、一定の要件を満たす遺族に次の年金等が支給されます。
- 遺族(補償)年金
- 遺族特別年金
- 遺族特別支給金
遺族(補償)年金の支給金額は遺族の人数等に応じて、給付基礎日額153~245日分が支払われます(1回のみ給付基礎日額1000日分を限度として、年金の前払いを受けることができます)。
また、遺族特別支給金として一律300万円の一時金が支払われます。
さらに、遺族特別年金として、遺族の人数等に応じ、算定基礎日額の153~245日分の年金が支払われます。
遺族(補償)給付を受ける権利は労災にあった労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効にかかります。
また、遺族(補償)年金を一時金として前払いを受ける権利は、労災にあった労働者が亡くなった日の翌日から2年です。
(6)葬祭料(葬祭給付)
労災で死亡した方の葬祭を行う場合、一定の要件を満たすと葬祭の費用を負担した方に対して支給されるお金です。
支給金額は次の式の通りです。
葬祭料(葬祭給付)=31.5万円+(給付基礎日額×30日分)
なお、上記金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には給付基礎日額の60日分が支給されます。
労働者が死亡した日の翌日から2年を過ぎると、時効によって請求できなくなります。
(7)介護(補償)給付
介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、障害等級が第1級の方または第2級の方のうち「精神神経・胸腹部臓器の障害」が残り、かつ、現に介護を受けているときに一定の要件を満たすと給付されます。
常時介護であるのか随時介護であるのか、介護費用を支出しているのか、支出した介護費用の金額がいくらかによって、支給額が異なります。
2022年3月1日時点では、常時介護の上限額は17万1650円、最低保障額は7万3090円であり、随時介護の上限額は8万5780円、最低保障額は3万6500円とされております。
介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を過ぎると、時効によって請求できません。
(8)二次健康診断等給付
定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断されたとき、一年度内に1回、二次健康診断や特定保健指導を、自己負担なしで受けることが可能です。
一次診断を受けた日から3ヶ月以内に、一定の方法で請求する必要があります。
労災の申請手続きについて
労災保険を受け取るには、申請の手続きが必要になります。
給付内容によって労災保険の申請手続きは異なりますが、労災が起きたときにすべき主な労災保険の申請手続きは次の通りです。
- 労災が起きたことを可能な限り速やかに会社に報告する
- 指定医療機関等で診察を受ける
- 労働基準監督署に請求書等、必要書類を提出する(郵送対応も可能)
※請求する労災保険の種類によって、本人の証明のほかにも、医師、事業主の証明を請求書に記載してもらうことが必要な場合があります。 - 労働基準監督署によって調査が行われる
- 労災の審査結果が通知され、認定された場合には保険金が支払われる
認定されなかった場合には、労働者災害補償保険審査官に審査のやり直しを求める
申請手続きにあたって重要なポイントをお伝えします。
(1)労働基準監督署で労災申請する
会社が労災保険の請求を代行してくれる場合はいいのですが、そうでない場合は、労災にあった労働者等本人が手続きを行うことになります。
退職後に労災申請する場合も、自分で直接手続きします。
自分で労災申請をする場合には、厚生労働省のホームページや労働基準監督署にある請求書を労働基準監督署へ提出します。
請求する労災保険の種類によっては、請求書に、事業主の証明を書いてもらう必要があります(1回目の休業(補償)給付の請求など)。
事業主に労災であることを認められなかったとしても、事業主に労災の証明をしてもらえなかったことを記載した書面を添えて、労働基準監督署に労災を申請することができます。
労災保険の支給をするかどうかは事業主が決めるものではなく、労働基準監督署長が決めるものだからです。
会社から労災が認められない場合に備えて専門家に申請の代行を頼むこともできます。
参考:1-5 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。|厚生労働省
(2)労災の給付金を受け取る
給付金は請求書で指定した口座へ振り込まれます。
その際、基本的には「支給決定通知書・支払振込通知書」が送られてきます。
申請から支給日までの具体的な日数は、労災に関する調査の内容、保険給付の種類によっても異なるため、一概に決まりません。
例えば休業(補償)給付の場合、1ヶ月ほどはかかることが多いようです。
労災に見舞われたら、なるべく早めに申請するのが良いでしょう。
休業(補償)給付が給付されるまで時間がかかります。
このため、休業(補償)給付につき会社から立て替え払いを受け、会社はその後支給される休業(補償)給付を受け取るという「受任者払制度」を利用できる場合があります。
会社にこの制度を利用できないか相談してみましょう。
【まとめ】労災保険とは業務上・通勤中のケガや病気などに対して支払われる保険
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「労災」(労働災害)とは、労働者が仕事に従事したことによって起きたケガや病気などのこと。
労働災害のうち、業務上の事故などを「業務災害」、通勤中の事故などを「通勤災害」と呼ぶ。
- 「労災保険」(労働者災害補償保険)とは、業務や通勤を原因とするケガや病気の医療費などを補償する制度。
労災保険は、原則として正社員に限らず全ての労働者について加入義務がある。
- 「業務災害」の認定基準は、「業務遂行性(事業主の支配下にある状態)+業務起因性(業務とケガ等の間に一定の因果関係があること)」。
- 「通勤災害」における通勤とは、就業に関し、住居と就業場所の間の移動などを、合理的な経路および方法によって行うこと。
- 労災保険の給付には、次のものがある。
| 給付の種類 | もらえる条件 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 一定の病院における診察・処置・手術等をした場合 |
| 休業(補償)給付 | 仕事中のケガや病気によって働けなくなった場合 |
| 傷病(補償)年金 | 治療開始から1年6ヶ月以上経っても労災によるケガや病気が治らず、その程度が障害等級1~3級に達している場合 |
| 障害(補償)給付 | 労災によるケガや病気が治るなどしたものの、障害等級1~14級に相当する障害が残った場合 |
| 遺族(補償)給付 | 労働者が労災により死亡した場合 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 労災で亡くなった方の葬祭を行って費用を負担した場合 |
| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の障害が残り、かつ、現に介護を受けている場合 |
| 二次健康診断等給付 | 定期健康診断の結果を受けて、二次健康診断を受ける場合 |
- 労災の申請手続きは、会社が代行してくれない場合には、労働者本人が労働基準監督署に対して行う。
労働災害には遭いたくないものですが、働いている限り労働災害に遭ってしまう可能性をゼロにすることはできません。
もしも労働災害に遭ってしまうことがあったとしても、労災保険の給付があることをしっかりと知っておけば、安心して療養に専念することができます。
労災保険について分からないことがあれば、最寄りの労働基準監督署に相談するようにしましょう。
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2024年11月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。