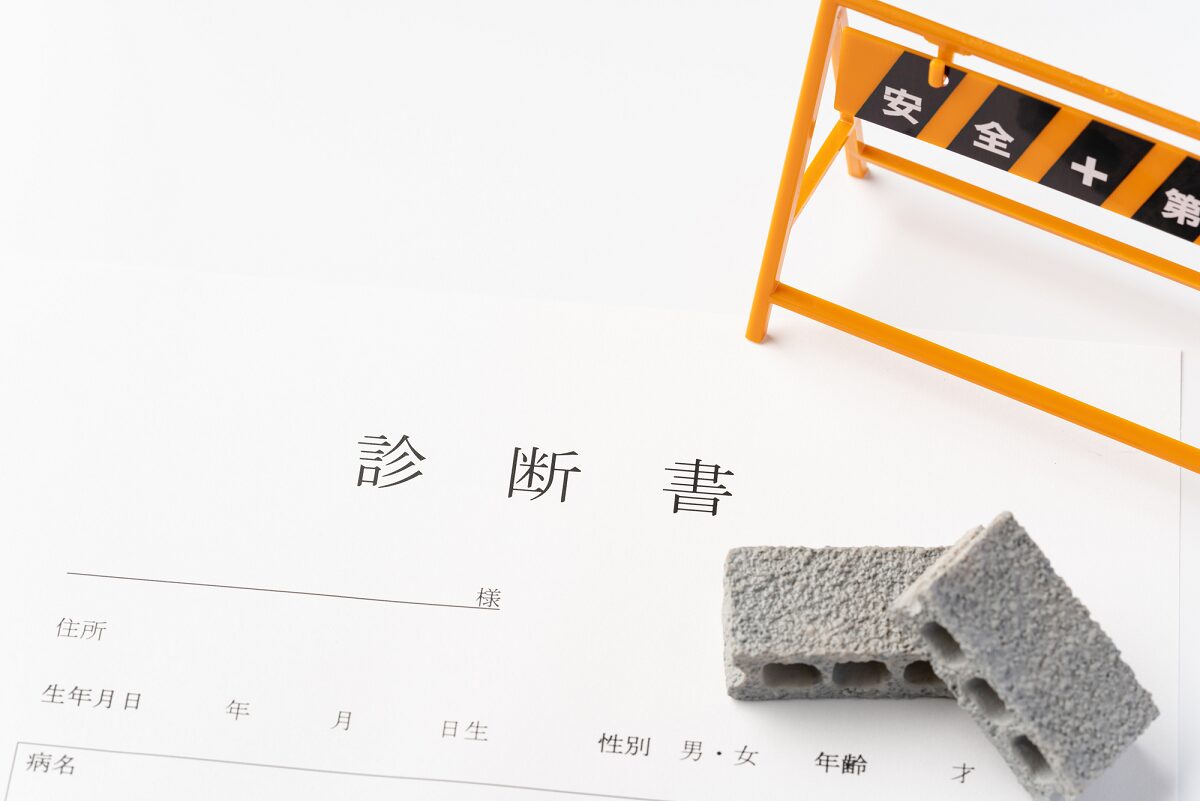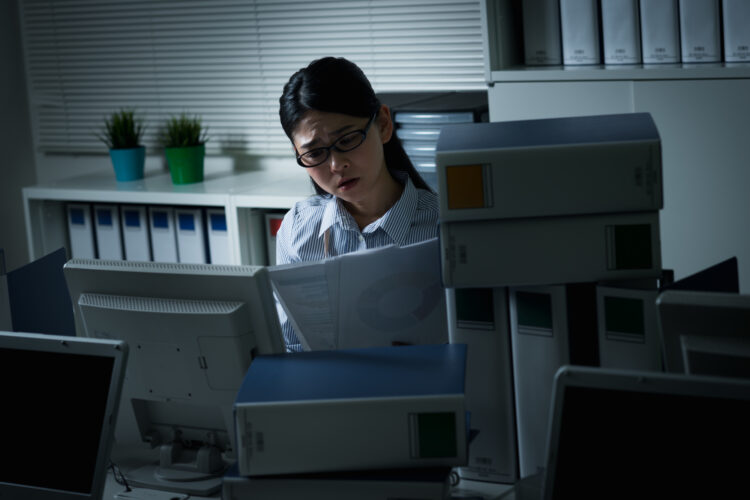労災保険の給付を受けるためには、給付の種類や治療の内容によっては、医師の作成した診断書が必要になります。
また、給付の種類や申請の内容ごとに必要となる書類や手続の流れも異なるため、申請する前にしっかりと確認しておきましょう。
この記事が、労災申請に関する疑問を解消し、スムーズに手続を進めるために役立てば幸いです。
ここを押さえればOK!
(1)療養(補償)等給付:治療行為や治療費に対する給付で、基本的に医師の診断書は不要。ただし、はり・きゅうやマッサージの施術を受けた場合には必要になります。
(2)休業(補償)等給付:仕事中のケガや病気で働けなくなった場合の給付で、医師の診断書は不要です。
(3)障害(補償)等給付:業務災害や通勤災害によるケガや病気が治った後に一定の障害が残った場合の給付で、医師の診断書が必要です。
(4)傷病(補償)等年金:治療開始から1年6ヵ月以上経っても治らない場合に支給される年金で、申請手続は不要ですが、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄の労働基準監督署長に提出します。この「傷病の状態等に関する届」は医師の診断書を添付して提出する必要があります。
(5)遺族(補償)等給付:労働者が業務災害や通勤災害で死亡した場合に遺族に支給される年金等で、死亡診断書等が必要です。
(6)葬祭料等(葬祭給付):労災で死亡した方の葬祭費用に対する給付で、死亡診断書等が必要になる場合があります。
(7)介護(補償)等給付:一定の障害状態で介護を受けている場合の給付で、原則として医師の診断書が必要ですが、一定の条件を満たす場合には不要です。
診断書の作成費用は労災指定医療機関であれば無料ですが、その他の医療機関では自己負担が発生する場合があります。
申請書類の提出先は主に医療機関と労働基準監督署で、各給付の種類ごとに異なる書類が必要です。
労災保険の申請は勤務先が行うことが一般的ですが、本人や遺族が行うことも可能です。 なお、申請には給付の種類ごとに異なる時効があり、期限内に請求する必要があります。
労災の申請でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
労災保険の申請で診断書は必要?
労災保険の申請に医師の診断書が必要かどうかは、労災保険給付の種類によって異なります。
労災保険給付の種類は、主に次の7つです。
(1)療養(補償)等給付
(2)休業(補償)等給付
(3)障害(補償)等給付
(4)傷病(補償)等年金
(5)遺族(補償)等給付
(6)葬祭料等(葬祭給付)
(7)介護(補償)等給付
では、それぞれについてご説明します。
(1)「療養(補償)等給付」を申請する場合
療養(補償)等給付とは、簡単にいえば治療行為そのものや、治療費のことです。
療養(補償)等給付の申請に、医師の診断書は基本的に必要ありません。
もっとも、はり・きゅうまたはマッサージの施術を受けた場合には、医師作成の診断書が必要になるようです。
詳しくは、管轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。
参照:療養(補償)等給付の請求手続|厚生労働省
(2)「休業(補償)等給付」を申請する場合
休業(補償)等給付とは、仕事中にケガをして働けなくなった場合、および仕事に関連する病気で働けなくなった場合に支給されるお金のことです。
休業(補償)等給付の申請に、医師作成の診断書は必要とされていません。
(3)「障害(補償)等給付」を申請する場合
障害(補償)等給付とは、業務災害・通勤災害によるケガや病気が治った(症状固定した)ものの、一定の障害が残ったときに給付されるお金です。
障害(補償)等給付の申請には、医師作成の診断書の提出が必要です。
(4)「傷病(補償)等年金」を申請する場合
傷病(補償)等年金とは、次の条件を満たす場合に、労働基準監督署長の職権により、その状況が継続している間に支給されるものです。
・療養開始から1年6ヵ月以上経っても労災によるケガや病気が治らない
・上記ケガや病気の程度が障害等級第1~3級に達している
傷病(補償)等年金が支給される場合には、療養(補償)等給付は引き続き支給されるのに対し、休業 (補償)等給付は支給されません。
傷病(補償)等年金の場合、労働者本人による申請手続は不要です。
もっとも、上記のとおり、療養開始から1年6カ月以上経過してもケガや病気が治っていない場合、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならず、その届には医師の診断書の添付が必要とされます。
なお、療養開始から1年6カ月以上経過してもケガや病気が治っていないものの、傷病(補償)等年金の受給要件を満たしていない場合、毎年1月分の休業(補償)等給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」を併せて提出するものとされます。この報告書にも医師の診断書が必要とされます。
(5)「遺族(補償)等給付」を申請する場合
遺族(補償)等給付とは、労働者が業務災害または通勤災害により死亡したときに、一定の要件を満たす遺族に支給される年金等のことです。
遺族(補償)等給付を申請する場合、労働者が死亡したことや死亡年月日を証明するために、医師作成の死亡診断書が必要です(死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書などで代替できる場合あり)。
参照:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
(6)「葬祭料等(葬祭給付)」を申請する場合
葬祭料等(葬祭給付)とは、労災で死亡した方の葬祭を行う場合に、葬祭の費用を負担した方に対して、一定の要件を満たせば支給されるお金のことです。
死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実および死亡年月日を証明できる書類が必要です。
ただし、遺族(補償)等給付の申請時に提出する場合に、重ねて提出する必要はありません。
(7)「介護(補償)等給付」を申請する場合
介護(補償)等給付とは、次の条件をすべて満たす場合に支給されるお金のことです。
- 一定の障害の状態に該当する
- 現に介護を受けている
- 病院または診療所に入院していない
- 介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどに入所していない
介護(補償)等給付の申請には、原則として医師の診断書が必要です。
ただし、次のいずれか場合には不要とされています。
- 傷病(補償)等年金の受給者
- 障害等級第1級3号・4号または第2級2号の2・2号の3に該当する方
- 継続して2回目以降の介護(補償)等給付を請求するとき
労災保険給付の種類については、こちらの記事もご覧ください。
診断書の作成費用と作成期間
労災指定医療機関(労災指定病院)であれば、診断書の作成費用はかかりません。
労災指定医療機関が診断書を労働基準監督署に直接送ってくれるからです。
また、診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、労災保険で給付される金額は最大4,000円とされており、作成費用が給付金額を超えた場合でも、差額は自己負担となります。
なお、給付を受けるためには領収書が必要ですので、保存しておきましょう。
医療機関によって異なるものの、診断書の作成期間は平均2週間程度と考えられますが、後遺障害診断書の場合にはさらに時間がかかると考えられます。
診断書の作成は、時間的な余裕を持って依頼するようにしましょう。
労災保険の申請における書類の提出先
労災保険を申請する際の書類の提出先は、基本的に医療機関と労働基準監督署の2つです。
なお、各請求書の記入方法は厚生労働省のホームページを参照し、不明点があれば管轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。
(1)医療機関に提出する書類
労災指定医療機関を受診した場合、療養(補償)等給付を申請するためには、受診した医療機関に療養の給付請求書を提出する必要があります。
なお、労災指定医療機関以外の病院を受診した場合には、受診した医療機関ではなく、療養の費用請求書を労働基準監督署に提出することが必要です。
(2)労働基準監督署に提出する書類
労働基準監督署には、労災保険給付の種類ごとに、次の書類を提出します。
- 療養(補償)等給付:(労災指定医療機関以外の病院を受診した場合)療養の費用請求書
- 休業(補償)等給付:休業給付支給請求書
- 障害(補償)等給付:障害給付支給請求書
- 遺族(補償)等給付:遺族年金支給請求書、遺族一時金支給請求書
- 葬祭料等(葬祭給付):葬祭給付請求書
- 介護(補償)等給付:介護給付・介護給付支給請求書
※給付の種類によっては、業務災害か通勤災害かで請求書の様式や名称が異なります。
なお、傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権で行われるため、申請手続は不要ですが、先述のとおり「傷病の状態等に関する届」の提出が必要とされます。
上記書類のほか、領収書や診断書などの添付書類が必要な場合も多いため、わからないことがあれば管轄の労働基準監督署に確認するようにしましょう。
労災保険申請の流れ
労災保険の申請は、受診した病院が労災指定医療機関であるかどうかで、流れが異なる場合があります。
(1)労災指定医療機関の場合
労災保険指定医療機関とは、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、都道府県労働局長が指定する病院または診療所のことです。
労災指定医療機関を受診した場合、療養(補償)等給付を申請する一般的な流れは次のとおりです。
(1)診療を受ける
(2)事業主(勤務先)から請求書に証明してもらう
(3)受診した医療機関に請求書を提出する
(4)受診した医療機関が請求書を送付し、治療費などが医療機関に直接支払われる
参照:労災保険指定医療機関になるための手続きについて|厚生労働省
参照:療養(補償)等給付の請求手続|厚生労働省
(2)それ以外の医療機関の場合
労災保険指定医療機関以外を受診した場合、療養(補償)等給付を申請する流れは次のようになります。
(1)診療を受け、治療費を支払う
(2)事業主(勤務先)から請求書に証明してもらう
(3)受診した医療機関から請求書に証明してもらう
(4)労働基準監督署に請求書を提出する
(5)労災保険の支払いを受ける(最初に支払った治療費の返金)
労災指定医療機関以外を受診すると、自分でしなければならない手続が増え、さらに治療費を立て替える必要もあります。
労災申請に関するよくある質問(Q&A)
(1)労災申請を行うのは勤務先?本人?
労災申請は勤務先の会社などが行うことが一般的です。
ただし、労働者本人が労災申請を行っても問題ありません。
また、労災によって重い障害が残ってしまった場合や、労働者本人が死亡してしまった場合には、家族や遺族が代わりに申請することになります。
(2)労災申請に期限はある?時効は?
労災申請の時効は次のとおりです。
| 労災保険給付の種類 | 請求に関する時効 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 費用の支出が確定した日の翌日から2年 |
| 休業(補償)等給付 | 労働することができないため賃金を受けない日の翌日から2年 |
| 障害(補償)等給付 | 傷病が治った日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)等給付 | 労働者本人が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 労働者本人が亡くなった日の翌日から2年 |
| 介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
なお、傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権で行われ、請求手続はないため、申請の期限や時効はありません。
(3)基準を満たす診断書を出してもらえなかった場合の対処法は?
症状があっても医師に認めてもらえなかったり、診断書の内容が不十分だったりするケースがあります。
たとえば、どのように記載すれば障害等級の何級に認定される、などといった事情については知らない医師もいるようです。
医師から労災保険の給付基準を満たす診断書を出してもらえなかった場合には、担当医師を変更してもらったり、別の医療機関を受診したりする、いわゆるセカンドオピニオンも一つの手段でしょう。
また、労災申請に精通している弁護士に相談・依頼する方法もあります。
弁護士から、診断書の記載方法などについて医師に意見したことで、診断書を再度作成してもらえることもあります。
【まとめ】労災保険給付の種類によっては診断書が必要になる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労災保険の給付は、主に次の7種類
(1)療養(補償)等給付
(2)休業(補償)等給付
(3)障害(補償)等給付
(4)傷病(補償)等年金
(5)遺族(補償)等給付
(6)葬祭料等(葬祭給付)
(7)介護(補償)等給付
- 給付の種類や内容によって、医師の作成した診断書の要否が異なる
- 診断書の作成費用として労災保険から給付される金額は最大4,000円
- 診断書の作成費用が給付金額を超えた場合でも、差額は自己負担となる
- 診断書の作成期間は平均2週間程度だが、後遺障害診断書の場合にはさらに時間がかかる
- 労災保険を申請する際の書類の提出先は、基本的に医療機関と労働基準監督署
- 労災保険の申請は、受診した病院が労災指定医療機関であるかどうかで、流れが異なる場合がある
- 労災申請には時効がある(期限内に請求しなければならない)
- 労災保険の給付基準を満たす診断書を出してもらうためには、いわゆるセカンドオピニオンだけでなく、弁護士への相談・依頼が効果的な場合がある
この記事では、労災申請における診断書の要否や費用、申請の流れについて解説しました。労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気に対する重要な補償制度です。
給付の種類や申請内容によって必要な書類や手続が異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
診断書が必要なケースやその作成費用についても理解しておくことで、スムーズに申請手続を進めることができます。
労災申請は初めての方にとっては複雑に感じるかもしれませんので、疑問がある場合には弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2025年5月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。