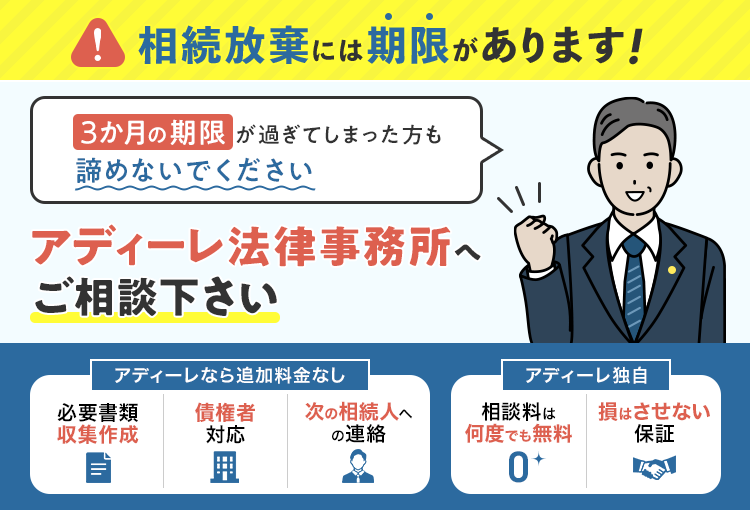相続の準備、まだ先のことだと思っていませんか?
元気に長生きできればいいですが、いつ亡くなるかわかりません。長生きできても、認知症などの病気にかかり、自分で相続の準備をすることが難しくなってしまうかもしれません。
相続の準備は、まだ余力のある今、してしまう方がよいでしょう。
前編の記事では相続の基礎知識や財産を把握する方法、生命保険などについて解説しました。
後編では、より具体的な相続準備の対策をご紹介します。遺言書の作成から生前贈与の検討まで、弁護士が「相続の準備で押さえるべき10のポイント」の後半5つを詳しく解説します。
これらの相続準備を今から始めることで、将来の漠然とした不安を解消し、大切な家族との絆を守ることができるでしょう。
ここを押さえればOK!
6.遺言書の作成を検討し、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類から適切なものを選びます。
7.エンディングノートを作成し、法的効力はないものの、自分の想いや希望を家族に伝えるツールとして活用します。
8.相続税の試算を行い、将来の経済的負担を予測し、適切な対策を講じます。
9.生前贈与を検討し、相続税の軽減と円滑な財産移転を実現します。
10.最後に、弁護士や税理士などの専門家に相談し、法律や税務の最新情報を得て、適切な対策を立てることが重要です。これらのステップを早めに実践することで、将来の不安を軽減し、家族間のトラブルを防ぐことができるでしょう。
遺言や生前対策をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
6. 遺言書の作成を検討する
遺言書は、相続に関する自身の意思を明確に示す重要な文書です。誰に、どれだけの遺産を残すのか、どの遺産を残すのか、自分の判断で決めることができます。
適切な遺言書の作成により、相続トラブルを防ぎ、円滑な財産分配が可能になります。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれに特徴があります。
遺言書の作成を検討する際は、自身の状況や希望に合わせて適切な種類を選択することが大切です。
(1)遺言書の種類と特徴
遺言書には主に次の3種類があります。
1.自筆証書遺言
特徴:自身で全文を手書きし、日付と氏名を記載、押印する。費用がかからない。
注意点:作成は簡単だが、方式に厳格な要件があり、家庭裁判所での検認が必要
2.公正証書遺言
特徴:公証人役場に出向き、公証人が作成し、証人2名以上の立会いが必要。法的に無効となるリスクや紛失するリスクが極めて低く、家庭裁判所の検認が不要
注意点:費用がかかる
3.秘密証書遺言
特徴:公証人役場で本人が作成した文書を封筒に入れて封印。公証人と証人2名以上の前で手続をするが、遺言の内容は誰にも知られない。
注意点:手続きが煩雑であまり利用されていない。
(2)遺留分侵害に注意
一定の相続人には、被相続人の相続財産から、法律上取得できることが保障されている最低限の取り分があります。それを遺留分と言います。
遺言が、遺留分を侵害するような内容だと、侵害された相続人が、「侵害された分をよこせ」という遺留分侵害額請求をすることができます。この請求により親族間のトラブルが生じるおそれがあるのです。
例えば、妻と子2人がいるAさん(仮名)が、全財産を長男にのみ相続させる遺言を残したいと思っても、妻と子は遺留分がありますので、その点を考慮して遺言を作成した方がよいでしょう。
遺言書は、遺言作成を扱っている弁護士などのアドバイスを受けながら、慎重に作成することをおすすめします。遺言書の作成時は、法的な制限を理解し、適切な内容を記載することが重要です。
(3)公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較して多くのメリットがあります。
- 確実性:公証人が関与するため、内容の適法性が確保される
- 保管の安全性:公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低い
- 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが不要で、速やかに執行できる
- 争いの防止:公証人の関与により、明確で争いの少ない内容になりやすい
- 秘密保持:相続開始まで相続人に内容を秘密にできる
公証人は遺言書を作成しますが、弁護士ではありませんので、個別に遺言者の法律相談に応じることはありません。
遺言者としては、通常、希望する内容の遺言書を弁護士などに伝えて遺言書の文案を作成してもらい、その後に公証人に遺言書を作成する流れになるでしょう。この場合、弁護士費用、公証人に支払う費用がかかりますので、費用は事前に確認するようにします。
7. エンディングノートを作成する
エンディングノートは、法的な効力はありませんが、自分の想いや希望を家族に伝える重要なツールです。
相続手続きをスムーズにし、家族間の理解を深めるのに役立ちます。エンディングノートの作成は、自身の人生を振り返り、整理する機会にもなります。また、家族との対話のきっかけとなり、より良い関係構築にも寄与します。記載内容は個人の状況に応じて柔軟に決められますが、基本的な情報から詳細な希望まで、幅広く記録することが望ましいです。定期的に内容を見直し、更新することも大切です。
(1)エンディングノートの重要性
エンディングノートの重要性は次の点にあります:。
- 意思伝達:自分の希望や想いを明確に家族に伝えられる
- 相続準備:財産情報や希望する相続方法を記録し、円滑な相続に役立つ
- 家族の負担軽減:必要な情報をまとめることで、残された家族の負担を減らせる
- トラブル防止:事前に意思を示すことで、相続や葬儀に関するトラブルを防げる
- 人生の整理:自身の人生を振り返り、整理する機会となる
- コミュニケーションツール:家族との対話のきっかけとなる
例えば、Bさん(仮名)は持病があるため、エンディングノートに治療の経過や延命治療に関する希望を記載しました。これにより、緊急時の家族の判断基準が明確になり、家族がBさんの意思を尊重した対応が可能になります。また、Bさんは趣味で集めた美術品の取り扱いについても、誰に引き継がせるかなどを詳細に記述し、相続後のトラブルを防ぐ工夫をしました。
(2)記載すべき内容
エンディングノートに記載すべき主な内容は次の通りです。
- 個人情報:氏名、生年月日、住所、連絡先など
- 家族構成:家族や親族の情報、連絡先
- 財産情報:預貯金、不動産、有価証券、保険など
- 負債情報:借入金、住宅ローンなど
- 医療・介護の希望:治療方針、延命治療の意思など
- 葬儀・埋葬の希望:葬儀の形式、埋葬方法など
- 相続に関する希望:財産分配の意向、遺言の有無など
- 大切な人へのメッセージ
- ライフヒストリー:思い出、人生の転機など
- 重要書類の保管場所:戸籍謄本、印鑑証明書、保険証書など
例えば、Cさん(仮名)は自身の趣味である園芸に関する道具や植物の取り扱いについて詳細に記載し、家族に引き継いでほしい思いを伝えています。また、長年付き合いのある友人への連絡も忘れずに記載し、人間関係にも配慮しています。このように、個人の状況に応じて柔軟に内容を追加することが大切です。
8. 相続税の試算をする
相続税の試算は、将来の経済的負担を予測し、適切な対策を講じるために重要です。基本的な計算方法を理解し、概算でも試算することで、相続税対策の必要性を判断できるでしょう。
相続税は、相続財産の価額が基礎控除額を超える場合に課税されます。試算の結果、多額の相続税が見込まれる場合は、早めに対策を検討することが大切です。
ただし、相続税の計算は複雑で、財産の評価方法や各種特例の適用など、細かな関連法律の知識が必要な部分も多いため、正確な試算は税理士に相談することをおすすめします。
(1)相続税の計算方法
相続税の基本的な計算方法は次の通りです。
- 課税遺産総額の算出:(遺産総額 – 基礎控除額) 基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 相続税の総額計算:課税遺産総額を各相続人の民法上の相続分で按分したうえで税率を適用 税率は10%〜55%の累進課税
- 実際の納付税額:相続税の総額を各相続人の実際の相続分で按分
例えば、Dさん(70歳)の相続財産が2億円、法定相続人が配偶者と子2人で、民法上の相続分どおりに相続する場合を考えます。
- 基礎控除額:3000万円 + (600万円 × 3人) = 4800万円
- 課税遺産総額:2億円 – 4800万円 = 1億5200万円
- 民法上の相続分は、妻2分の1=7600万円、子4分の1=3800万円
- 相続税の総額:妻 1580万円(7600万円×30%-700万円)
子1人あたり 560万円(3800万円×20%-200万円)
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
ただし、配偶者の税額軽減など、各種特例も考慮する必要があります。
(2)相続税対策の基本
相続税対策の基本的な方法には、次のようなものがあります。
- 生前贈与の活用
- 年間110万円までの基礎控除を利用した計画的な贈与
- 相続時精算課税制度の利用(2500万円まで非課税)
- 不動産の活用
- 小規模宅地等の特例の利用(最大80%評価減)
- 賃貸不動産による相続税評価額の調整
- 生命保険の活用
- 死亡保険金の非課税枠の利用(500万円×法定相続人の数)
- その他
- 相続財産の圧縮(生前に自己消費を増やす)
- 養子縁組による法定相続人の増加(制限あり)
例えば、Eさん(仮名)は毎年子どもたちに110万円ずつ贈与し、さらに預金で賃貸不動産を購入して評価額を下げ、かかる相続税を下げる対策を行っています。ただし、過度な節税策は税務調査のリスクがあるため、税理士と相談しながら適切な対策を選択することが重要です。
9. 生前贈与を検討する
生前贈与は、相続税の軽減と円滑な財産移転を実現する有効な方法です。贈与を受ける側も、家の購入や教育用資金など、必要な時に財産をもらった財産を利用することができ、満足度も非常に高くなります。
計画的に生前贈与を行うことで、将来の相続税負担を軽減しつつ、家族の生活基盤を整えることができます。ただし、贈与税や相続時精算課税制度など、複雑な制度があるため、税理士のアドバイスを受けながら進めることが重要です。生前贈与を検討する際は、自身の生活に必要な資金を確保した上で、家族の状況や将来の見通しを考慮し、適切な贈与計画を立てましょう。また、贈与の記録を残し、将来の相続時に備えることも大切です。
(1)生前贈与のメリット
生前贈与には次のようなメリットがあります。
- 相続財産の減少による相続税の軽減
- 計画的な贈与により、相続財産を減らし、相続税を軽減できる
- 受贈者の生活基盤の早期確立
- 子や孫の教育資金や住宅取得資金として活用できる
- 贈与税の基礎控除(年間110万円)の活用
- 毎年の基礎控除を利用することで、長期的に多額の財産移転が可能
- 相続時精算課税制度の利用
- 2500万円までの特別控除を利用できる(60歳以上の親から18歳以上の子への贈与)
- 資産の分散による相続トラブルの防止
- 事前に財産を分配することで、相続時の争いを減らせる
例えば、Fさん(仮名)は3人の孫がいるため、毎年各孫に100万円ずつ贈与しています。これにより、相続財産を減らしつつ、孫の教育資金を援助しています。また、長男夫婦には住宅取得資金として相続時精算課税制度を利用し、2500万円を贈与しました。このような計画的な贈与により、将来の相続税負担を軽減しつつ、家族の生活基盤を支援することができます。
(2)贈与税の基礎知識
贈与税に関する基礎知識は次の通りです。
- 基礎控除額
- 年間110万円まで非課税
- 110万円を超える部分に贈与税が課税される
- 税率
- 10%〜55%の累進課税
- 贈与財産の価額に応じて税率が上がる
- 申告と納付
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納付
- 特例制度
- 教育資金贈与の非課税制度(1500万円まで)
- 結婚・子育て資金贈与の非課税制度(1000万円まで)
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
- 相続時精算課税制度
- 2500万円までの特別控除
- 贈与時に贈与税を支払わず、相続時に相続財産と合算して計算
例えば、Fさん(仮名)が子どもに200万円を贈与した場合、基礎控除額110万円を超える90万円に対して贈与税が課税されます。贈与税の課税を避けるためには、1年ごとに100万円を贈与し、そのたびに贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。このように、基礎控除額を有効に活用しつつ、計画的な贈与を行うことが重要です。
10. 弁護士や税理士などに相談する
相続の準備は複雑で法律の幅広い知識が必要なため、適切な資格を有する者に相談することが重要です。資格の役割を理解し、自身の状況に合わせて適切な相談先を選ぶことで、スムーズな相続準備が可能になります。有資格者に相談することで、法律や税務の最新情報を得られ、適切な対策を立てることができます。ただし、相談には費用がかかるため、事前に料金体系を確認し、費用対効果を考慮することも大切です。様々な有資格者の意見を聞くことで、より良い選択ができる場合もあります。
(1)相続に関わる有資格者
相続に関わる主な有資格者とその役割は次の通りです。
- 弁護士
- 法的紛争の解決
- 遺言書作成のアドバイス、作成
- 相続放棄や限定承認の手続の代理
- 遺産分割協議の代理や協議書の作成
- 遺留分減殺額請求の代理
- 税理士
- 相続税の計算と申告
- 節税対策の提案
- 財産評価 など
- 司法書士
- 不動産の名義変更
- 相続登記 など
- ファイナンシャルプランナー
- 総合的な相続対策の提案
- ライフプランニング など
5.行政書士
- エンディングノート作成支援 など
例えば、Gさん(仮名)は様々な資産を持っているため、税理士に相続税の試算と対策を相談し、弁護士に遺言書の作成を依頼しました。さらに、司法書士に不動産の名義変更について相談することで、総合的な相続対策を立てることができるでしょう。
(2)実際に相談する弁護士などの選び方
弁護士などを選ぶためのポイントは次の通りです。
- 経験と実績を確認する
- 相続案件の取扱件数 など
- 得意とする分野を確認する
- 相続を積極的に扱っているか など
- 初回相談の可否や費用を確認する
- 無料相談の有無
- 料金体系の透明性 など
- コミュニケーションがスムーズにとれるか確認する
- 説明のわかりやすさ
- 質問への対応の丁寧さ など
- 複数の意見を聞く
- 異なる視点からのアドバイス
- 提案内容や費用の比較
- 所属する団体や資格を確認する
- 弁護士会、税理士会などの所属
- その他資格の有無
例えば、Hさん(仮名)は相続税対策について3名の税理士に相談し、それぞれの提案や費用、話しやすさ、コミュニケーションの取りやすさなどを比較検討しました。その結果、自身の状況に最も適した対策を見つけることができ、その提案をしてくれた税理士に依頼することにしました。実際に依頼する税理士や弁護士などの選択は慎重に行い、信頼できる相手を見つけることが重要です。
【まとめ】
この記事のまとめは、次の通りです。
- 遺言書の作成:相続トラブルを防ぎ、自身の意思を明確に伝える
- エンディングノートの準備:法的効力はないが、家族の理解を深め、手続きを円滑にする
- 相続税の試算:将来の経済的負担を予測し、適切な対策を講じる
- 生前贈与の検討:相続税の軽減と円滑な財産移転を実現する
- 相談:複雑な相続準備を適切に進めるために、弁護士や税理士などの有資格者からサポートを得る
相続の準備は早ければ早いほど効果的です。今日から、これらのステップを一つずつ実践していきましょう。あなたの状況に合った相続準備プランを立ててみてはいかがでしょうか。
アディーレ法律事務所は、生前の相続対策である遺言書作成について積極的にご相談・ご依頼を承っております。
「もしうまくいかなかったら弁護士費用無駄になってしまうんじゃない?」
ご安心ください、アディーレには、「損はさせない保証」というものがあります。
すなわち、アディーレ法律事務所では、弁護士にご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません。
なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。
※以上につき2025年5月時点
遺言書作成についてお困りの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談ください。