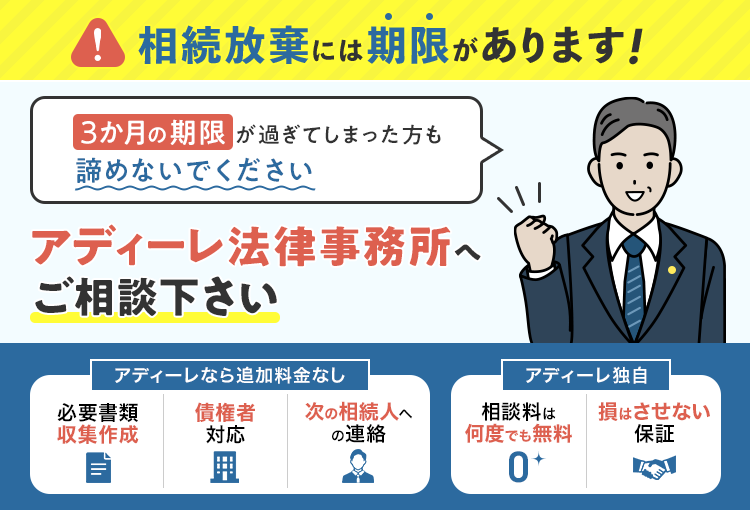2023年、生前贈与に関する税制が大きく変わりました。
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2種類の方法から選ぶことができます。
暦年課税では、相続開始前7年以内の贈与財産が相続財産に加算されるという「7年ルール」の導入により、多くの人が相続税対策の見直しを迫られています。
一方で、相続時精算課税では110万円の基礎控除が新設され、利用しやすくなりました。
資産のある方は、これらの改正が、あなたや家族の将来の資産にどのような影響を与えるのか、情報を収集して検討する必要があります。
本記事では、贈与の基本、改正の基本的な内容などを初めて生前贈与を調べる方にもわかりやすく解説します。 相続税の負担軽減や家族の経済的安定を図るために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 生前贈与と税金の関係
- 相続時精算課税が節税対策になるケース
- 2023年生前贈与改正のポイント
ここを押さえればOK!
暦年課税では「7年ルール」が導入され、相続開始前7年以内の贈与財産が相続財産に加算されることになりました(2024年1月1日以後の贈与に適用される)。
一方、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が新設され、利用しやすくなりました。60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与に適用でき、累積2500万円まで非課税となります。
これらの改正は、贈与税と相続税の関係を理解し、長期的な贈与計画を立てる上で重要です。特に、相続税の負担軽減を目的とした生前贈与を考える際には、税理士に相談し、長期的な視点で計画を立てることが推奨されます。また、遺言書の作成など生前対策をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
生前贈与とは?税金との関係
生前贈与は、将来家族が支払うことになる相続税の負担軽減や、家族の経済的支援のための有効な手段です。
しかし、税法上の規制があるため、正しい理解が必要です。
【生前贈与の基本】
- 贈与者 : 無償で財産を渡す側
- 受贈者 : 無償で財産をもらう側、原則として贈与税の納税義務を負う。
- 贈与財産 : 現金、不動産、株式など
生前贈与は、法的には、贈与契約(民法549条)に基づき行います。口頭でも有効ですが、後々税務署に「本当に贈与がされたのか」など指摘される可能性があります。問題となったときに証拠として残る書面による契約が望ましいです。
贈与者の財産が贈与で減少すると、贈与者が死亡した時の相続財産も減少し、贈与税を考慮したとしても、家族が支払うことになる相続税を軽減でき、全体としての税負担が減る可能性があるのです。
贈与税と相続税はこのように関連しており、適切な贈与計画により相続税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、税制は複雑で頻繁に改正されるため、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。
(1)生前贈与の基本:誰が、誰に、何を贈与できるのか
生前贈与は、原則として誰でも自由に行うことができます。贈与契約についての民法上のルール、税法上のルールを理解することが重要です。
【民法上のルール】
例えば、贈与契約締結の際には、贈与者及び受贈者に、「意思能力」が必要です。
意思能力とは、簡単に言うと、法律行為の結果を判断・予測できる知的能力のことをいいます。
未就学児は通常意思能力はありません。また、認知症が進んでいるような場合でも、意思能力が否定されることがあります。 意思能力のない者がした贈与契約は無効です。
また、未成年が法律行為を行う時には、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。
【税法上のルール】
生前贈与を受ける場合、2つある課税制度のうちどちらか選択できます。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
婚姻費用や養育費(扶養義務者相互間の生活費・教育費にあてるための)の贈与など例外的に非課税となるものもあります(※)。
※非課税措置は対象や期間が限定されていることがあります。利用可能な非課税措置については、最新情報について税理士などに確認するようにしましょう。
(2)贈与税と相続税の関係:なぜ贈与にも税金がかかるのか
贈与税は、相続税の補完税として機能しています。その主な目的は、生前贈与による相続税の回避を防ぐことです。
贈与税の課税方法は、暦年課税と、相続時精算課税の2つあり、どちらかを選択することができます。相続時精算課税を選ぶと、翌年以降同じ親からの生前贈与はすべて相続時精算課税の対象となります。
暦年課税を選択するときは特別な手続きは不要ですが、相続時精算課税を選択するには、原則として、贈与税の申告書提出期間内に、受贈者の納税地を所轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
(2-1)暦年課税の基本
暦年課税の基本は以下の通りです。
- 1月1日から12月31日までの1年間の贈与額(もらった額)に応じて課税される
- 親から子・孫の生前贈与に限らず、誰にでも適用される
- 贈与財産にも特に制限はない
- 基礎控除額は年110万円
- 110万円を超える贈与があった場合、受贈者は翌年の申告期間内(2月1日~3月15日)に贈与税の申告・納付をする
- 相続前7年以内の贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算する(相続前3年~7年以内に受けた贈与は総額100万円まで加算しない)=7年ルール
【暦年課税の計算方法】
(1年間に生前贈与を受けた財産の価額―基礎控除額110万円)×税率―控除額=贈与税額
※贈与されたのが一般贈与財産か特例贈与財産のいずれかにより、税率と控除額が異なります。
基礎控除額が1月1日から12月31日までの間に贈与額が110万円以下であれば、全額が基礎控除範囲内であるため、贈与税は1円もかかりません。
参考:贈与税に関する資料|財務省
(2-2)相続時精算課税の基本
相続時精算課税の基本は次の通りです。
- 基礎控除額(1年110万円)を控除した残額を相続開始まで累積し、最大2500万円まで非課税
- 非課税枠を超えた額に一律20%課税
- 相続開始後、基礎控除後の累積贈与額を相続財産の価額に足して、相続税を清算
- 支払った贈与税分は、将来支払う相続税から控除されるので、二重に課税はされない
- 贈与者が60歳以上で、受贈者が18歳以上で贈与者の子及び孫である必要あり
参考:贈与税に関する資料|財務省
このように、贈与税と相続税は関連しており、贈与する時点だけではなく、贈与者が死亡した時点での相続税の課税も踏まえて、長期的な視点での贈与計画が重要です。
税制改正で具体的にどのような影響があるのか、どのような贈与計画が妥当なのか、税理士に相談して判断するようにしましょう。
相続時精算課税が節税対策になるケース
相続時精算課税は、生前贈与では2500万円まで贈与税はかかりませんが、相続時に贈与時の価額が加算されて相続税が課税されます。
何年前の贈与であっても、加算されます。 結局、税金の先送りであって、節税対策としては使いにくいとも言われています。
しかし、次のようなケースでは節税対策になると考えられます。
(1)相続税がかからないケース
65歳の親が、子に2024年7月1日に2000万円を一括で生前贈与し、10年後に遺産1500万円を残した場合を考えます。相続人は配偶者と子1人です。その他の財産はないと仮定します。
2000万円を生前贈与する場合、暦年課税だと基礎控除110万円を控除した1890万円が贈与税の課税対象となります。
親が亡くなった場合の遺産は1500万円で、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人2人=4200万円)の範囲内なので相続税はかかりません。
一方で、相続時精算課税だと、2000万円すべてが特別控除の対象となり、贈与税は1円もかかりません。
親が亡くなった場合、2000万円から基礎控除額110万円を差し引いた1890万円が相続財産に加算され、相続財産は3390万円となりますが、結局基礎控除(4200万円)の範囲内なので、相続税はかかりません。
そのため、このようなケースでは、相続時精算課税を選択すると、贈与税も相続税も支払うことなく、親から子どもへ財産を移動することができます。
(2)資産価値上昇を見込んだ財産を生前贈与するケース
相続時精算課税も、暦年課税も、贈与時の財産の価額で相続財産に加算されます。資産価値が上がった場合、どちらの課税方式でも、相続税の軽減につながる可能性があります。
特に相続時精算課税は、特別控除が2500万円と高額です。資産価値上昇が見込まれる高額の財産を贈与すれば、価値が上がる幅も大きいことがあります。そのような場合は、価値が上がった分、相続財産として加算されるのを避けることができますので、結果として相続税対策になります。
65歳の親が、30歳の子に2024年7月1日に2000万円の株式を一括で生前贈与したケースを考えます。
10年後に親が亡くなったとときには、2000万円の株式が3000万円に価値が上がっていたとしましょう。
生前贈与せずにいたら、その株式は3000万円が相続財産となります。一方で、生前贈与したことで、相続財産に加算されるのは1890万円(贈与時の価格から基礎控除額110万円を除いた額)で済むことになります。
このような場合には、生前贈与することによって、相続税の節税が期待できる可能性があるでしょう。
2023年生前贈与改正のポイント①:暦年課税の”7年ルール”とは何か
2023年の税制改正では、暦年課税と相続時精算課税の双方に変更点があります。
特に暦年課税で改正して導入された“7年ルール”は、生前贈与と相続税の関係に大きな変更をもたらしました。まず、7年ルールの改正について説明します。
この改正により、相続税の課税対象となる相続財産に加算される贈与財産の対象期間が、相続開始日を起点に3年から7年に大幅に延長されたのです。
【主なポイント】
- 相続開始前7年以内の贈与財産が、贈与時の価格で相続財産に加算
- 加算される期間が3年から7年に対象期間が大幅に延長
- 延長された4年間の贈与は、総額100万円まで加算対象外
- 長期的な贈与計画の必要性が増加
【影響】
- 相続財産に加算される贈与財産の対象期間が増えたので、相続税の課税対象額が増加する可能性
- 改正を考慮した生前贈与の見直しが必要
7年ルールの導入により、より長期的な視点での資産管理と贈与計画が求められるようになりました。特に、相続税の負担軽減を目的とした生前贈与を考えている方は、この新ルールを十分に理解し、計画をたてる必要があります。
(1)暦年課税|7年ルール改正前後の比較
3年から7年に改正されたことで、相続税の課税対象となる相続財産の違いが分かるように、簡単な事例で簡略化して説明します。
(例)父親が2024年7月1日以降毎年1000万円を子ども1人に贈与し、7年後に相続が発生し、遺産が2000万円だった場合)
【改正前】 相続財産は5000万円= 2000万円+ 3000万円(直近3年間の贈与)
【改正後】 相続財産は8900万円= 2000万円+ 7000万円-100万円(7年間の贈与※)
7年ルールの導入により、相続税の負担軽減を目的として生前贈与を検討する場合は、7年以上の期間を見据えた計画も必要になってくると考えられます。
(2)7年ルールの適用開始時期と対象者
7年ルールは、2024年1月1日以後に贈与で取得した財産について適用されます。
この新ルールは、すべての相続に適用されるため、生前贈与を行う可能性のあるすべての人が対象となります。
【適用開始時期】
- 2024年1月1日以後に贈与で取得した財産
(その日以前の贈与で取得した財産については従来の3年ルールが適用)
【対象者】
- 暦年課税制度を選択し、被相続人から暦年贈与を受けたすべての相続人
7年ルールの具体的な適用は、次を参考にしてください。
【贈与が2023年12月31日まで】
⇒相続開始前の3年間が加算対象
【贈与が2024年1月1日以降】
〇相続開始日が2024年1月1日~2026年12月31日 ⇒相続開始前の3年間が加算対象
〇相続開始日が2027年1月1日~2030年12月31日 ⇒2024年1月1日~相続開始日までが加算対象
〇相続開始日が2031年1月1日~ ⇒相続開始前7年間が加算対象
(3)相続人でない者に生前贈与すると節税対策になる
7年ルールで生前贈与が相続財産に加算されるのは、被相続人から相続・遺贈により財産を取得したケースです。
つまり、相続人でない者が生前贈与を受けていた場合には、相続財産に加算されません。
したがって、相続人でない者(典型的には孫)に生前贈与をして相続財産を減らすことで、相続税の節税につながる可能性があります。
2023年生前贈与改正の主要ポイント②:相続時精算課税制度に基礎控除新設
2023年の税制改正で、相続時精算課税制度にも重要な変更がありました。年間110万円の基礎控除が新設されたことです。この改正により、相続時精算課税制度の利用価値が高まったと考えられます。
【主な改正ポイント】
- 年間110万円の基礎控除新設
- 基礎控除の範囲内の生前贈与は、相続財産に加算しない
- 制度選択したときは申告が必要だが、それ以降は基礎控除範囲内であれば翌年の申告義務なし
- 特別控除額2500万円は維持
この改正により、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除が適用されるうえ、110万円までは相続財産に加算もされません。
一方で、暦年課税制度は110万円の基礎控除は同じですが、相続開始前7年以内の贈与は基礎控除額も含めて相続財産に加算されます。
1年の贈与額が110万円以内であれば、受贈者の申告義務もないので、改正により非常に利用しやすい制度となりました。
改正により、納税者の制度選択の幅は広がったといえるでしょう。
ただし、この制度を選択すると、それ以降は暦年課税制度は利用できず、原則として撤回できないため、慎重な検討が必要です。
以下で、制度の基本と改正の詳細を見ていきましょう。
(1)相続時精算課税制度とは何か:基本から学ぶ
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続を一体的に捉え、基本的に贈与時には贈与税を課さず(2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかる)、相続時に相続財産と合わせて相続税を課税する制度です。
この制度を利用することで、将来の相続税負担を考慮しつつ、生前に家族間での計画的な資産移転が可能になります。
【制度の基本】
- 対象者:60歳以上の親から18歳以上の子(孫)への贈与
- 特別控除:累積2500万円まで非課税
- 基礎控除:1年110万円
- 選択後は撤回不可
- 相続時に贈与財産を年ごとに基礎控除額を除いた贈与時の時価で相続財産に加算
【メリット】
- まとまった資産の早期移転が可能
- 贈与時の時価(基礎控除額除く)で相続財産に加算される
- 基礎控除額は相続財産に加算されないので、基礎控除額も相続財産に加算される暦年課税よりも有利な面がある
- 資産価値上昇を見込んだ財産を生前贈与することで、相続財産の実質的な目減りにつながる
【デメリット】
- 相続時に贈与財産(基礎控除額除く)が全額加算される
- 資産価値が下落した場合に不利になる可能性
(2)新設された年110万円の基礎控除の意味と影響
2023年の税制改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、制度の柔軟性が高まり、より多くの人にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
【新設された基礎控除の概要】
- 年間110万円まで非課税
- 暦年課税制度の基礎控除と同額
- 特別控除2500万円に追加して適用
【影響と意義】
- 小規模な贈与がしやすくなる
- 基礎控除額までは相続財産に加算されない
- 基礎控除の有無以外で制度選択を検討できる
【まとめ】暦年課税は7年ルール導入、相続時精算課税制度は年間110万円の基礎控除新設
本記事のまとめは次の通りです。
- 生前贈与は贈与契約に基づく
- 贈与には贈与を受けた側に贈与税がかかる
- 贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税制度の2種類ある
- 2023年の税法改正で、暦年課税には7年ルールが導入される
- 相続開始前7年以内の贈与財産が相続財産に加算(従来は3年)
- 2023年の税制改正で、相続時精算課税制度には、年間110万円の基礎控除が新設される。
- 制度改正により、7年以上の長期的な贈与計画、資産の種類に応じた最適な贈与タイミングの検討が必要
2023年の生前贈与改正で導入された7年ルールにより、相続税の対象となる相続財産に加算される期間が拡大しました。
「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった気持ちをお持ちの方は、遺言書の作成など生前の相続対策のご相談を積極的に受け付けているアディーレ法律事務所へご相談ください。
「もしうまくいかなかったら弁護士費用無駄になってしまうんじゃない?」
ご安心ください、アディーレには「損はさせない保証」というものがあります。
すなわち、アディーレ法律事務所では、弁護士にご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません。
なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。
※以上につき2025年5月時点
遺言書の作成など生前の相続対策についてお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。