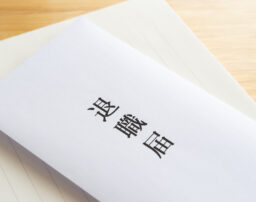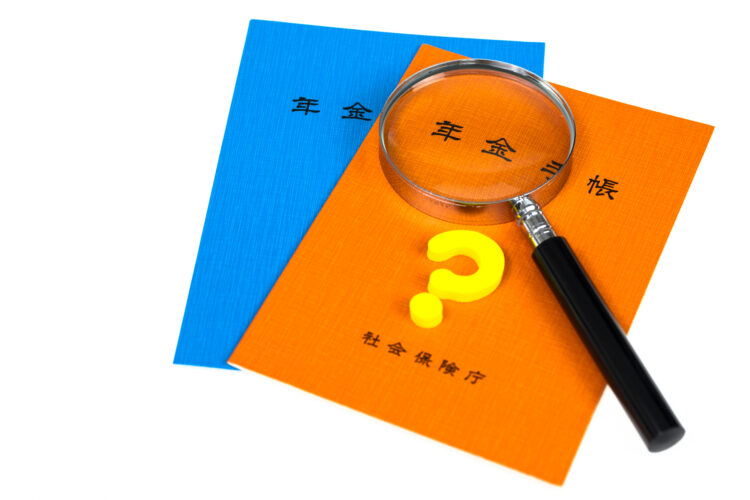「『基本給』という言葉があるけれど、『月給』や『手取り額』との違いって何なんだろう?」
「基本給」とは、給与の基本的な部分のことです。
通常、毎月の給与から残業手当や通勤手当などの諸手当を除いたもののことを言います。
基本給がいくらかによって、残業代の金額などが変わってきます。
会社によっては、基本給の金額によって、ボーナスや退職金の額までもが変わってくる場合もあります。
また、基本給は、手取り額や最低賃金とも関係してきます。
この記事では、次のことなどについて弁護士が解説します。
- 基本給とは何か
- 基本給と給与の関係
- 基本給と手取り額の関係
- 基本給と最低賃金の関係
基本給とは?
「基本給」とは、給与の基本的な部分のことです。
通常、毎月の給与から残業手当や通勤手当などの諸手当を除いたもののことを言います。
基本給の決め方は、会社によって異なります。
一般的に、基本給は次のような事情に基づいて決定されることが多いです。
- 年齢
- 勤続年数
- 個人の能力
基本給は月によって金額が変動しないという特徴があります。
基本給と給与の関係は?
給与は、基本給とさまざまな手当を合わせたものです。
給与は「基準内賃金」と「基準外賃金」で構成されています。
「基準内賃金」と「基準外賃金」について、説明いたします。
(1)基準内賃金とは?変動しない賃金のこと
「基準内賃金」とは、法律上決まった定義はありませんが、基本給や月により変動がない手当とされることがあります。
例えば、スキルに応じて支払われる職能給や役職手当などがこれにあたります。
(2)基準外賃金とは?変動する賃金のこと
「基準外賃金」とは、基準内賃金と同様に法律上決まった定義はありませんが、毎月の就業内容によって変動する賃金とされることがあります。
例えば、時間外労働手当や休日出勤手当などが、これにあたります。
基本給と一緒に支給される手当にはどんなものがある?
基本給と一緒に支給される手当は、企業によって異なります。
一般的な手当には、次のようなものがあります。
- 家族手当、扶養手当
- 時間外手当、残業手当
- 通勤手当
- 役職手当
- 資格手当
(1)家族手当や扶養手当
家族手当や扶養手当は、家族がいる社員に対して支給される手当です。
扶養人数が増えると、それに応じて家族手当や扶養手当が増えることが多いです。
(2)時間外手当や残業手当
時間外手当や残業手当とは、規定の就業時間(所定労働時間)を超えて働いたときに支給される手当のことです。
基本的には、長く働けば働くほど、時間外手当や残業手当が増えます。
時間外手当や残業手当(いわゆる残業代)は、必ずしも全ての額が支払われておらず、未払いになっていることも多い手当です。
私も、残業代を全額支払ってもらえていないなあ。
支払ってもらえていない残業代は、会社に対して請求することができますよ!
未払い残業代を取り戻す方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)通勤手当
通勤手当とは、通勤のために公共交通機関を利用する際に支給される交通費のことです。
一般的に最も安いルートの交通費が支給される場合が多いです。
(4)役職手当
役職手当は、主任や管理職など、一定以上の役職についている人に支給される手当のことです。
役職が上がれば上がるほど、役職手当が増えることが多いです。
(5)資格手当
資格手当とは、免許や仕事に関わる高度なスキル、資格などを保有している社員に支給される手当です。
基本給と給与、手取り額の関係は?
基本給にさまざまな手当を加えたものが「給与」です。
そこから保険料や税金を引かれたものが「手取り額」となります。
基本給+諸手当=給与
給与-保険料や税金=手取り額
給与から引かれる保険料や税金にはさまざまなものがあります。
たとえば、給与から引かれる保険料や税金などとして次のようなものが挙げられます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 所得税
- 住民税
- 欠勤控除
基本給が低いと損をする理由とは?3つの理由を紹介
手取り額が多くても、基本給自体が低い場合、色々と損をすることがあります。
基本給が低いと損する理由には次の3つがあります。
- 残業代が少なくなる
- ボーナスが少なくなる
- 退職金が少なくなる
(1)残業代が少なくなることも
残業代の計算は、「1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率」という式に基づいて算出できます。
このように残業代は、「基礎賃金」をもとに計算されます(基礎賃金については後でご説明します)。
基礎賃金には、基本給が含まれますが、一定の諸手当は基礎賃金に含まれないことがあります。
そのため、基本給が低いと残業代も少なくなる可能性があるのです。
ここで、残業代の金額を左右する基礎賃金について解説いたします。
基礎賃金とは
基礎賃金とは、所定労働時間に対する賃金から、次の賃金を控除した金額になります。
- 個人の事情に基づき払われている賃金
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
【控除される賃金の例】(実態で決まります)
|
|
|
|
|
|
このように、基礎賃金には、基本給が含まれることになりますが、その他の諸手当は控除されることがあるのです。
(2)ボーナスが少なくなることも
ボーナスの計算は、基本給を基にして行う会社も多いため、ボーナスが低く計算されてしまうことがあります。
例えば、ボーナスが年間3ヶ月分の会社の場合、基本給が15万円と20万円では、年間15万円の差が出ることになります。
(3)退職金が少なくなることも
基本給の金額に応じて退職金の金額が決まる会社の場合は、基本給が少ないと退職金が減ります。
会社によっては、退職金が役職や等級、ポイントで決まることもありますので、就業規則を確認しましょう。
基本給と最低賃金の関係は?月給制でも最低賃金が適用される!
「最低賃金」とは、最低限支払わなくてはならない1時間あたりの労働賃金です。
雇用形態は関係ありませんので、パートやアルバイトなどの時給制の人だけではなく、月給制の人にも最低賃金が適用されます。
最低賃金を下回る契約をしても、その契約は無効となるので、労働者は最低賃金を基準とする賃金を請求することができます。
例えば、東京都の最低賃金(地域別最低賃金)は時給1113円、大阪は1064円となっています(2023年10月現在)。
正社員や契約社員の方なども基本給が最低賃金を上回っているかを確認することが大切です。
最低賃金について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここで、最低賃金の規制の対象となる「賃金」とは何か、解説いたします。
(1)基本給と一部の諸手当は最低賃金の対象
最低賃金の算定対象となる賃金は、「1ヶ月以内の期間ごとに支払われる、通常の労働時間や労働日の労働に対してして支払われる賃金」です。
基本給と一部の諸手当は最低賃金の対象に含まれます。
最低賃金の算定対象とならない賃金は、例えば次のものです。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当、出産手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
- 時間外勤務の手当
- 休日出勤の手当
- 深夜労働(22~5時の労働)の手当の内、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)基本給や一部の諸手当が最低賃金を下回っていないか確認してみましょう
最低賃金を下回る賃金を定めた労働契約は無効です。
最低賃金の算定対象となる賃金(基本給+一部の諸手当)が、最低賃金を下回っていないか確認してみましょう。
具体的には、次の方法で、確認します。
【最低賃金を下回らない場合】
| 賃金 | 最低賃金 | |
|---|---|---|
| 時間給 | ≧ | 最低賃金 (1時間当たり) |
| (原則) 日給÷所定労働時間(日) | ||
| 月給÷平均所定労働時間(月) | ||
| (歩合給等の場合) 「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数」 | ||
| (※日額が定められている特定最低賃金が適用される場合) 日給 | ≧ | 最低賃金 (1日当たり) |
【例】
最低賃金の対象となる賃金(基本+一部の諸手当)の合計が月16万円
1日の所定労働時間が8時間
年間所定労働日数が250日
月給制
この場合、
(16万円×12ヶ月)1年間の月給総額÷(8時間×250日)1年間の所定労働時間=960円となり、
東京の最低賃金(時給1113円)を下回っていることになります。
参考:最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省
参考:特定最低賃金について|厚生労働省
【まとめ】基本給とは毎月の給与から諸手当を除いたもののこと
この記事のまとめは次のとおりです。
- 基本給とは、給与の基本的な部分のことで、毎月の給与から諸手当を除いたもののことを言う。
- 基本給と一緒に支給される手当には、時間外手当や残業手当などがある。
- 基本給にさまざまな手当を加えたものが給与。
そこから保険料や税金が引かれたものが手取り額。 - 基本給が低いと、残業代が少なくなるなどのことにより、損をすることがある。
- 月給制でも最低賃金が適用される。
自分がもらっている給与のうち基本給がいくらかということは、実は重要なことです。
自分の基本給がいくらなのかをしっかりと確認するようにしましょう。
基本給に関して疑問な点がある場合には、労働問題を扱う弁護士などの専門家に相談するようにすると良いでしょう。