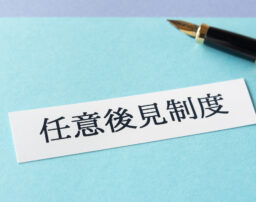「夫に先立たれたら、その先の生活が不安…」
一家の生計を支えている方が突然亡くなった場合、残された遺族は経済的な不安に直面することが多いでしょう。そんなときに頼りになるのが「遺族年金」です。
しかし、「遺族年金って具体的にいくらもらえるの?」「どんな条件で受給できるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
遺族年金の概要を知ることで、いざというときに備え、安心して生活を続けるための準備ができます。
ぜひこの記事を最後までお読みいただき、遺族年金についての理解を深めてください。
あなたの大切な家族を守るための一歩を踏み出しましょう。
この記事を読んでわかること
- 遺族年金とは
- 遺族年金の受給期間と終了条件
- 遺族年金だけでは足りない場合の対策
ここを押さえればOK!
自営業者やフリーランスが亡くなった場合は「遺族基礎年金」が支給され、会社員や公務員の場合は「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族基礎年金は、18歳未満の子どもを持つ配偶者や子どもが対象で、2024年度の基準では年間約81万円が支給されます。
遺族厚生年金は、配偶者や子ども、一定条件を満たす親や孫が対象で、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。
受給期間は、遺族基礎年金は子どもが18歳になる年度末まで、遺族厚生年金は配偶者が受給対象の場合は生涯にわたって受給可能です。
遺族年金だけでは生活費が不足する場合、生命保険の加入や貯蓄、社会福祉制度の利用が推奨されます。
申請には死亡診断書や年金手帳などの書類が必要で、早めの準備が重要です。
遺族年金とは
遺族年金とは、家族のうち主に生計を維持していた方が亡くなった際に、その遺族が経済的な支援を受けるための公的な制度です。
具体的には、国民年金や厚生年金に加入していた方が死亡した場合、その遺族が一定の条件を満たすことで受給できます。
遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。
亡くなった方が自営業者であれば「遺族基礎年金」が、会社員や公務員であれば「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族年金を受給するためには、一定の条件を満たす必要があり、その条件や受給額については後述します。
【自営業者など】遺族基礎年金
遺族基礎年金は、自営業者やフリーランスなど国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族が受給できる年金です。
受給対象となる遺族は、主に18歳未満の子どもを持つ配偶者や、18歳未満の子ども自身です。
なお、「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取っている間は、子どもに遺族基礎年金は支給されません。
受給条件としては、亡くなった方が国民年金の保険料を一定期間以上納付していたことなどが必要です。
遺族基礎年金の金額は、基本的に定額で、2025年度の基準では年間約83万円が支給されます。
さらに、子どもがいる場合は、子ども1人につき年間約24万円が加算されます。
(※3人目以降の加算額は7万9800円です。)
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
【会社員:公務員】遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族が受給できる年金です。
受給対象となる遺族は、主に配偶者や子ども、または一定の条件を満たす親や孫などです。
受給条件としては、亡くなった方が、老齢厚生年金の受給中や厚生年金の加入中に死亡した場合などが該当します。その場合、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。
基本的には、老齢厚生年金の報酬比例部分の約4分の3が支給され、遺族基礎年金を受給している場合は、その金額が加算されます。
なお、遺族年金の具体的な計算方法やシミュレーションについては、年金事務所や専門の相談窓口で確認することをおすすめします。
遺族年金の受給期間と終了条件
遺族年金の受給期間と終了条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。
まず、遺族基礎年金については、子どもが18歳の年度末を迎えると受給資格が終了します。ただし、子どもが障害等級1級または2級に該当する場合は、20歳まで受給が継続されます。
一方、遺族厚生年金については、配偶者が受給対象となる場合、基本的には生涯にわたって受給が可能です。
また、子どもや孫が受給対象となる場合は、遺族基礎年金と同様に18歳になる年の年度末まで、または障害等級1級または2級に該当する場合は20歳まで受給が継続されます。
これらの条件を満たさなくなった場合、遺族年金の受給は終了します。
具体的な受給期間や終了条件については、年金事務所や専門の相談窓口で確認することが重要です。
遺族年金の受給期間と終了条件を理解し、将来の生活設計に役立てるようにしましょう。
遺族年金だけでは足りない場合の対策
遺族年金だけでは生活費を賄いきれない場合、追加の対策が必要です。
まず考えられるのは生命保険の加入でしょう。
生命保険は、被保険者が亡くなった際に遺族に一時金や年金形式で保険金が支払われるため、遺族年金と併用することで生活費の不足を補うことができます。
特に、子どもの教育費や住宅ローンの返済など、大きな支出が見込まれる場合には有効な対策だと考えられます。
また、貯蓄や投資も重要な対策です。定期的に貯蓄を行い、緊急時に備えることで、遺族年金だけでは足りない場合の経済的な支えとなります。
もっとも、投資は資産を増やせる可能性もありますが、リスクもまた伴うため、慎重に検討してください。
さらに、社会福祉制度の利用も検討すべきです。
生活保護や児童扶養手当など、国や自治体が提供する支援制度を活用することで、経済的な負担を軽減できます。
これらの制度については、役所や専門の相談窓口で詳細を確認するようにしましょう。
このように、遺族年金だけでは生活が厳しい場合には、生命保険、貯蓄、投資、社会福祉制度の利用など、複数の対策を組み合わせることで、経済的な安定が期待できます。
遺族年金の申請手続と必要書類
遺族年金を受給するためには、適切な申請手続と必要書類の準備が不可欠です。
基本的な必要書類は、たとえば次のとおりです。
- 死亡診断書等
- 年金手帳等
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類 など
これらの書類を揃えたうえで、所定の請求書に記入し、提出します。
請求書は年金事務所や市区町村役場で入手できるほか、インターネットからダウンロードすることも可能です。
申請手続には時間がかかることがあります。スムーズに受給を開始するためにも、早めに準備を進めるようにしましょう。
また、不明点がある場合は、年金事務所や市区町村役場の窓口で相談することをおすすめします。
【まとめ】安心を得るために遺族年金のことを知っておこう
遺族年金は、家族の主要な収入源が亡くなった際に遺族が経済的支援を受けるための重要な制度です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ受給条件や金額が異なります。
遺族年金の受給条件や請求手続について詳しく知りたい方は、早めに年金事務所や市区町村役場で相談しましょう。
適切な準備をすることで、いざというときに安心して生活を続けることができます。