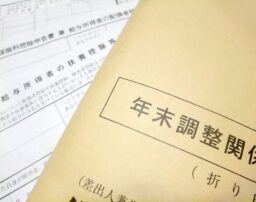働き方が多様化するなか、副業を希望する労働者が増えているようです。
しかし、多くの企業では依然として副業禁止の規定が存在し、その法的効力や理由について疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
副業を始める前に知っておくべき重要なポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して副業に取り組むことができます。
副業を考えている方や、既に副業を始めている方が、この記事を通じて、副業に関する疑問や不安を解消し、より良い働き方を実現するためのヒントを得ることができれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 副業禁止の法的効力
- 企業が副業を禁止する理由
- 労働者が確認すべきポイント
ここを押さえればOK!
これにより、副業と合算した総労働時間がその上限を超えないようにする必要があります。
企業の就業規則には副業禁止条項が含まれることが多いですが、職業選択の自由を不当に制限する内容であれば、その効力は否定される可能性があります。企業が副業禁止を正当化するためには、合理的な理由が必要です。
企業が副業を禁止する理由としては、労働時間の管理が大変なことや企業秘密の保護があります。
副業が本業に与える影響としては、労働者の集中力やパフォーマンスの低下、職場環境への悪影響が挙げられます。
一方で、副業を通じて新しいスキルや知識を習得し、本業に活かすことができる場合もあります。
副業解禁の背景には、働き方改革や経済環境の変化があり、副業は収入の増加やスキルの向上、新たなキャリアの開拓に寄与します。
副業を希望する労働者は、本業の勤務先の就業規則を確認し、副業禁止条項や申告義務の有無を確認することが重要です。また、健康管理にも注意しましょう。
労働基準法における副業の位置づけ
労働基準法は、労働者の権利を保護し、適正な労働条件を確保するための基本的な法律です。しかし、副業に関しては明確な規定が存在しません。
労働基準法第32条では、労働時間の上限を定めており、1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。この規定は副業にも適用されるため、労働者が複数の雇用主の下で働く場合でも、総労働時間がこの上限を超えないようにする必要があります。
したがって、労働基準法は直接的に副業を禁止しているわけではありませんが、労働時間や健康管理の観点から、間接的に副業に対する制約を設けているといえるでしょう。
就業規則における副業禁止の法的効力
企業が定める就業規則には、副業禁止条項が含まれることが多く、労働者が副業を行うことを制限する内容が記載されています。
基本的に、労働者は就業規則に従う義務があります。
しかし、就業規則の副業禁止条項が無条件に有効であるわけではありません。
労働者には職業選択の自由があるため、掛け持ちで仕事をすることも本人の自由のはずです。
したがって、労働者の職業選択の自由を不当に制限する内容であれば、その効力は否定される可能性があります。
具体的には、企業が副業禁止を正当化するためには、合理的な理由が必要です。
たとえば、労務提供上の支障がある場合や、競業により企業の利益が害される場合などです。
また、就業規則は労働者に対して事前に周知されていなければなりません(労働基準法第106条1項)。
この周知義務に違反した場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります(同第120条1号)。
就業規則における副業禁止条項の法的効力は、副業禁止の合理的必要と労働者の権利とのバランスなどを考慮して判断されるといえるでしょう。
副業禁止の理由
企業が副業を禁止する理由は多岐にわたりますが、主に次の観点から説明されます。
(1)労働時間の管理が大変
企業が副業を禁止するもっとも一般的な理由の一つは、労働時間の管理です。
労働基準法は、労働者の労働時間の上限を原則1日8時間、週40時間と定めていますが、副業を行うことでこれを超過することになる可能性が高いでしょう。
法定労働時間を超えているかどうかは、本業と副業の労働時間を合算した総労働時間を基準に判断されます。
そのため、労働者が副業をすると、企業などの使用者にとっては労働時間の管理がやりにくくなるのです。
また、法定労働時間を超える時間外労働には、割増賃金(いわゆる残業代)を支払わねばなりませんが、その金額の計算にも手間がかかるようになります。
(2)企業秘密の保護
もう一つの重要な理由は、企業秘密の保護です。
労働者が副業で競合他社でも働く場合、企業の機密情報が漏洩するリスクが高まります。
これにより、企業の競争力が損なわれる可能性があるため、企業は副業を禁止することでこのリスクを回避しようとしているのです。
こういった場合における副業禁止は、特に技術職や営業職など、企業の機密情報にアクセスする機会が多い職種で多いようです。
副業が本業に与える影響
副業が本業に与える影響は多岐にわたりますが、主に労働者の集中力、パフォーマンス、そして職場環境に影響します。
まず、副業により労働者の集中力が散漫になることが挙げられます。
複数の仕事を掛け持ちすることで、労働者は本業に対する集中力を維持することが難しくなり、結果として業務の質が低下する可能性があるでしょう。
また、副業による疲労やストレスも本業に悪影響を及ぼす要因です。
長時間労働や過重労働は、労働者の健康に悪影響を及ぼし、病気や過労死のリスクを高めることがあります。
これにより、労働者の欠勤や遅刻が増え、本業での業務に支障をきたすことがあるかもしれません。
また、疲労やストレスが蓄積すると、労働者のモチベーションや生産性が低下し、企業全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性もあります。
さらに、職場環境にも影響が及ぶ可能性があります。
副業を行う労働者が増えると、ほかの従業員との間で不公平感が生じることがあります。
たとえば、副業を行っている労働者が本業の業務を疎かにする一方で、副業を行っていない労働者がその分の負担を背負うことになると、職場の士気やチームワークが損なわれる可能性があります。
一方、副業が本業にプラスの影響を与える場合もあります。
たとえば、副業を通じて新しいスキルや知識を習得することで、本業においてもそのスキルを活かすことができる場合があります。また、副業によって得られる収入が労働者の生活の安定に寄与し、結果として本業に対するモチベーションが向上することも考えられます。
このように、副業が本業に与える影響は一概に悪いものばかりではありません。
ただし、労働者も自身の状況をよく見極め、副業が本業に悪影響を及ぼさないよう注意することが必要になるでしょう。
副業解禁の背景とその影響
副業解禁の背景には、働き方改革や経済環境の変化が大きく影響しています。
政府は労働者の多様な働き方を推進するため、いわゆる「働き方改革」により、副業・兼業の促進を打ち出しました。
これにより、多くの企業が副業禁止規定を見直し、労働者に副業の機会を提供する動きが広がっています。
副業解禁の影響は多岐にわたります。労働者にとっては、収入の増加やスキルの向上、新たなキャリアの開拓といったメリットがあります。
特に、経済的不安が高まる中で、副業は生活の安定に寄与する重要な手段となっていくと考えられます。
一方で、企業にとっては、労働者の健康管理や労働時間の管理が難しくなるリスクがあります。
また、前述のとおり、副業による疲労やストレスが本業に悪影響を及ぼす可能性や、企業秘密の漏洩リスクの問題も懸念されます。
このように、副業解禁は労働者と企業の双方にとってメリットとデメリットが存在します。企業が適切なルールを設けることで、双方が利益を享受できる環境を整えることが求められているといえるでしょう。
副業を希望する労働者が確認すべきポイント
副業を希望する労働者は、まず本業の勤務先の就業規則を確認することが必要です。
多くの企業では、副業に関する規定が就業規則に明記されており、これに違反すると懲戒処分の対象となる可能性があります。
特に、副業禁止条項や副業の申告義務の有無について確認しましょう。
違反すると、場合によっては懲戒処分や損害賠償義務などの法的リスクが生じる可能性があります。
また、仮に副業禁止条項や申告義務についての規定がなかったとしても、副業を始める際には、本業での勤務先に相談しておいたほうがよい場合もあります。
企業によっては、副業に対する柔軟な対応を行っている場合もあるため、事前に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して副業を行うことができるでしょう。
さらに、副業による労働時間や自身の健康管理も重要です。
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間の労働時間の上限が定められているため、これを超える労働には割増賃金(いわゆる残業代)が発生するためです。
(ただし、副業が個人事業として行われる場合や、管理監督者に該当するなどの場合には、企業に割増賃金の支払義務はありません。)
なお、副業による過労で健康リスクが生じやすくなる点にも注意しましょう。
【まとめ】副業を禁止するには合理的理由が必要|最近は副業解禁が広がりつつある
今回の記事では、副業禁止の法的効力やその影響について解説しました。
労働基準法に副業に関する明確な規定はありませんが、労働時間の管理や過労などの健康リスクを考慮する必要があります。
また、企業が副業を禁止する理由には、企業秘密の保護という目的もあります。
労働者が副業で競合他社でも働く場合、企業の機密情報が漏洩するリスクが高まるからです。
昨今の副業解禁の背景には働き方改革があり、労働者にとって収入増やスキル向上のメリットがありますが、リスクも存在します。
副業を希望する労働者は、就業規則や労働契約を確認し、法的トラブルを避けるための注意点を守ることが重要です。
これらのポイントを押さえ、安全かつ効果的に副業を行うようにしましょう。