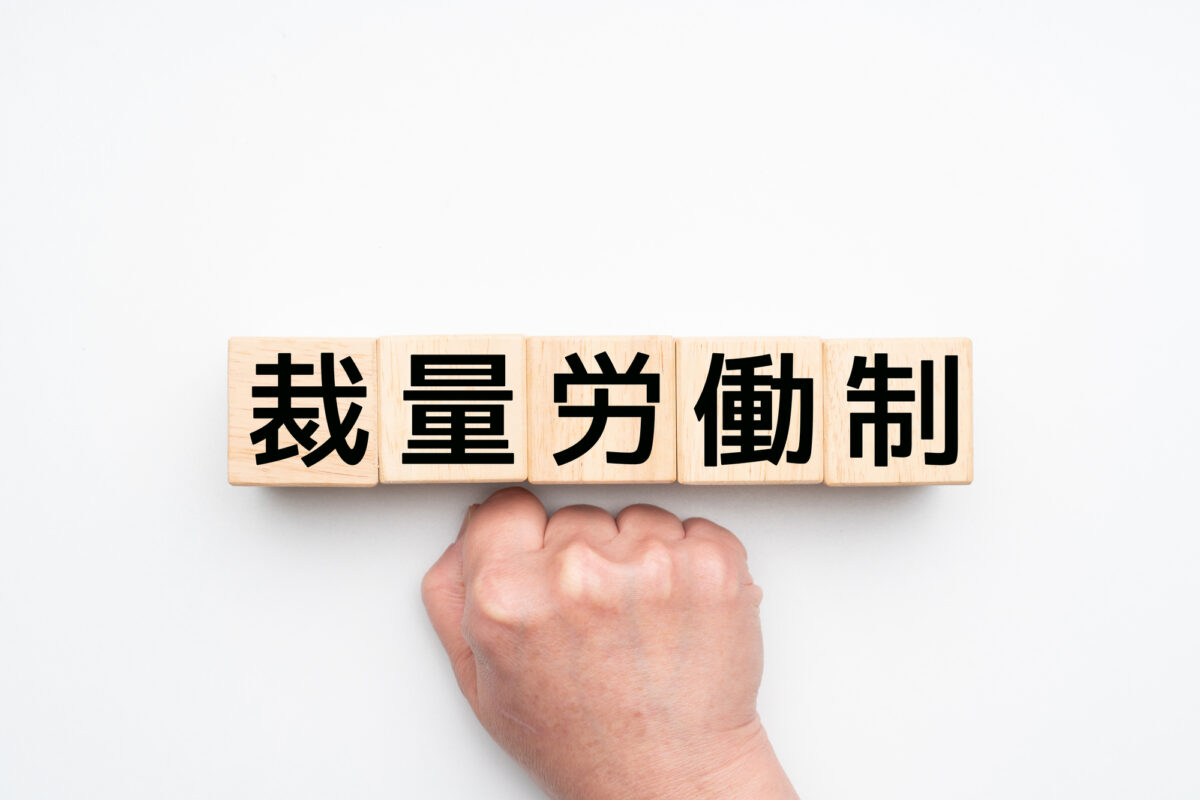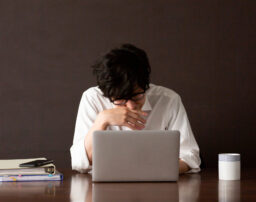働き方改革の一環として注目される裁量労働制。
しかし、その運用には細かな注意が必要です。
本記事では、裁量労働制の基本から36協定が必要なケース、運用時の注意点までをくわしく解説します。知識を深めることで、柔軟な働き方を実現しましょう。
この記事を読んでわかること
- 裁量労働制と36協定とは
- 裁量労働制で36協定の締結が必要なケース
- 裁量労働制を運用する上での注意点
ここを押さえればOK!
裁量労働制の導入には労働基準監督署への届出が必要で、次の場合には36協定の締結が必要になります。
・みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
・休日労働を行う場合
36協定は時間外労働や休日労働を可能にする協定ですが、無制限というわけではありません。
36協定を締結した場合でも時間外労働は原則月45時間、年間360時間との上限があります。
裁量労働制とは
裁量労働制は、業務の性質からその遂行方法を労働者に大幅な裁量を認めるべきものについて、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ定められた時間(みなし労働時間)働いたとみなして、労働者に賃金が支払われる制度です。
この制度の導入には、労働基準監督署への届出が必要です。
ただし、労働基準法の枠組み内で適正に運用しなければなりません。例えば、みなし労働時間が1日8時間の法定労働時間を超える場合には、36協定を結ぶ必要があります。
36協定とは
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働を可能にするために労使間で締結される協定です。この協定がなければ、法定労働時間を超える労働や休日労働は原則禁止されています。
ただ、36協定を結べば長時間労働が上限なくできるわけではありません。36協定を結んでも時間外労働は原則月45時間・年間360時間までと上限があります(※)。
(※)「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合」においても、月100時間未満、年720時間以内、複数月平均80時間以内の制限があるため、注意しましょう。
裁量労働制で36協定が必要なケースとは
裁量労働制の場合は、実際の労働時間とは関係なく一定の時間を働いたものと「みなされる」ため、時間外労働や割増賃金は発生しないかのようにも思えます。
しかし、次に掲げる2つの場合には、会社は36協定を締結するとともに、割増賃金を支払わなければなりません。
- みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
- 休日労働を行う場合
それぞれ見ていきましょう。
(1)みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
裁量労働制であってもみなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、36協定が必要です。
労働基準法第では労働時間の上限を「1日8時間以内・1週40時間以内」とすることと定められており、この上限のことを法定労働時間といいます。つまり、みなし労働時間が1日8時間・1週間40時間を超える場合、36協定が必要となります。
そして、1日8時間・1週間40時間を超える労働時間には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金が支払われる必要があります(時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときは基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金が支払われる必要があります)。
(2)休日労働を行う場合
裁量労働制であっても休日労働を行う場合にも36協定が必要です。
休日労働とは、法定休日(1週間当たり1日又は4週間当たり4日以上の休日)に行う労働のことをいいます。
例えば、土日が休みの会社であれば土曜が法定外休日、日曜が法定休日とさていることが多いです。この場合日曜に働くと「休日労働」ということになります。
休日労働を行った場合、基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金が支払われる必要があります。
裁量労働制運用の注意点
裁量労働制を適切に運用するためには、次の点に注意が必要です。
- 裁量労働制ができる職種には制限がある
- みなし労働時間と実際の労働時間はかけ離れたものにしてはいけない
それぞれ見ていきましょう。
(1)裁量労働制ができる職種には制限がある
裁量労働制の目的は、専門性のある業務などその遂行方法を労働者の大幅な裁量に委ねる必要のあるものについては、労働者が画一的な労働時間の規制にとらわれず働くことができるようにすることにあります。
業務の遂行方法について労働者の大幅な委ねる必要のないものにまで、裁量労働制を採用することができるとなると、法定労働時間の規制が潜脱される可能性があります。そのため、裁量労働制の対象とされる業務は制限されます。
(1-1)専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、弁護士やシステムエンジニアなどの厚生労働省が定める20の専門性の高い職種に適用されます。これにより、専門業務の特性に合わせた柔軟な労働時間管理が可能となります。
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析又は設計の業務
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組若しくは有線ラジオ放送の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 大学における教授研究の業務
- M&Aアドバイザーの業務(※)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
専門型業務型裁量労働制の導入には、本人の同意(※)と事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
(※)2024年4月1日より適用
(1-2)企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析などを行う労働者に適用されます。
企画業務型裁量労働制の導入には、本人の同意と労使委員会の決議を経た上で、労働基準監督署への届出が必要です。
(2)みなし労働時間と実際の労働時間はかけ離れたものにしてはいけない
みなし労働時間は、実際の労働時間とかけ離れたものにならないようにする必要があります。
なぜなら、みなし労働時間と実際の労働時間がかけ離れており、そのような状態で裁量労働制が運用され続けると、長時間労働が恒常化して労働者の健康面に悪影響をもたらすからです。
さらに、残業代の支払いを抑えるためだけに裁量労働制が利用されることにもなりかねず、労働者はその業務遂行に見合った適正な賃金の支払いを受けることができなくなるともいえます。
裁量労働制を採用した場合でも、健康福祉確保措置を講じることが義務付けられており、又使用者は労働安全衛生法上労働者の健康管理義務を負っているため、会社側は実際の労働時間を把握・管理する必要があります。そうした労働時間の把握・管理を通して、みなし労働時間と実際の労働時間がかけ離れたものにならないようにするべきです。
【まとめ】裁量労働制でも36協定は必要!働かせ放題の制度ではない
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 裁量労働制:業務の性質からその遂行方法を労働者に大幅な裁量を認めるべきものについて、実際の労働時間数とは関係なく、一定の労働時間(みなし労働時間)分を働いたとみなして、労働者に賃金が支払われる制度のこと
- 36協定:労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働を可能にするために労使間で締結される協定のこと
- 裁量労働制で36協定が必要なケース :みなし労働時間が法定労働時間を超える場合、休日労働を行う場合。
- 裁量労働制の注意点:裁量労働制の適用は特定職種に限られる、みなし労働時間と実際の労働時間は乖離させない。
休日労働や深夜労働をしても割増賃金が支払われなかったりするなど、いわゆる「残業代の未払い」がある方は、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません(※以上につき2024年12月時点)。
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。