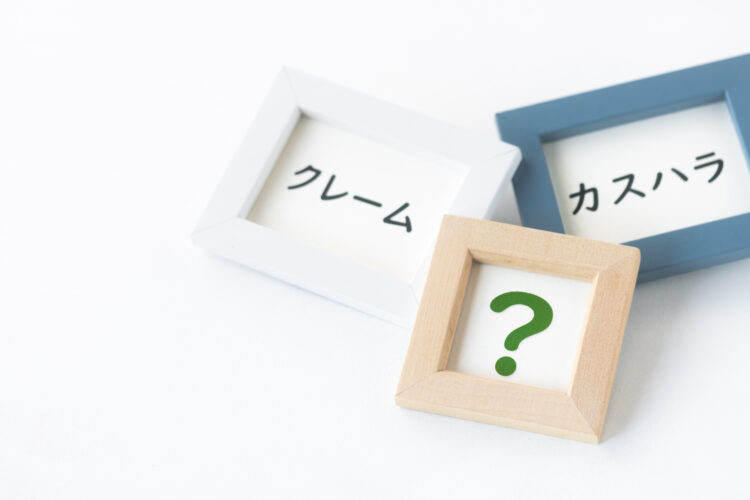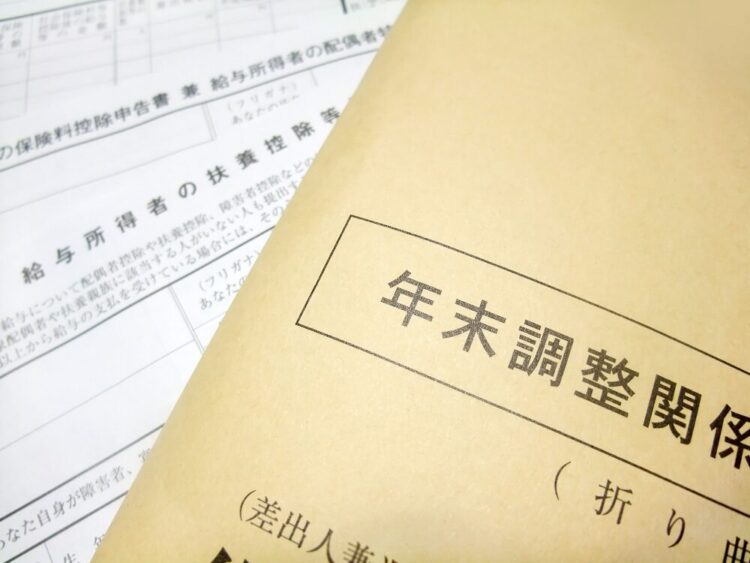この記事を読んでわかること
- 高年齢者雇用安定法は、事業主に対して60歳未満の定年を禁止し、65歳までの雇用を確保する義務を課している
- 具体的には、65歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、または継続雇用制度のいずれかの導入が必要で、70歳までの就業機会を確保する努力義務もある
- 2025年4月からは経過措置が終了し、65歳までの雇用確保が完全に義務化され、それに伴い、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給率が縮小されている
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高齢者が活躍できる環境を整備することを目的とした法律です。
この法律により、事業主に対して60歳未満の定年を設けることは禁止されています。
また、65歳までの雇用を確保する義務も定められており、65歳未満を定年としている場合は、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度の導入
加えて、65歳以上の労働者についても、事業主には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課されています。具体的には、70歳までの定年引上げや、70歳までの継続雇用制度を設けるなどの措置です。
2025年4月からの変更点のポイント
主なポイントは以下の通りです。
(1)65歳までの雇用確保が「完全」義務化
法律上、事業主には、65歳未満で定年した後の継続雇用を希望する者に対し、継続雇用制度を導入する義務があります。
この継続雇用制度は、希望する従業員すべてを対象とする必要があります。
しかし、2013年3月31日(平成24年度)までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、一定の年齢について継続雇用制度の利用を限定できる、という経過措置が認められていました。
ただ、この経過措置は2025年3月31日をもって終了しますので、4月1日からは65歳までの雇用確保が「完全」義務化されることになったのです。
したがって、経過措置を利用していた事業主は、2025年4月1日から、65歳までの雇用確保措置として、以下のいずれか措置を講じる必要があります。
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年引き上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
この点誤解されることがあるのですが、経過措置の終了により「65歳までの定年引上げ」が義務付けられるわけではありません。定年を65歳に引き上げなくても、継続雇用制度の導入により65歳までの雇用を確保する方法もあります。
厚生労働省の調査によれば、雇用確保措置を実施済みの企業の措置の内訳は次の通りです。
- 定年制の廃止:3.9%
- 定年の引き上げ:26.9%
- 継続雇用制度:69.2%
参考:高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~|厚生労働省
参考:令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省
(1-1)定年廃止
定年廃止は、事業主が定年(一定の年齢になったら労働契約を終了する)を廃止することです。
これにより、従業員は60歳を超えても年齢に関係なく、働く意欲があれば働き続けることができます。
(1-2)定年引上げ
定年引上げは、今まで60歳未満とされていた定年の年齢について、65歳に引き上げることです。
これにより、従業員は65歳まで働くことができます。
(1-3)希望者全員に対する雇用継続制度の導入
雇用継続制度は、本人の希望があった場合(期間の定めのない雇用契約のみ)、定年を迎えた後も引き続き雇用する制度です。
具体的には、再雇用制度又は勤務延長制度が考えられます。
再雇用は、一度定年を迎えて退職した従業員を再度雇用する方法です。いったん退職しますので、雇用形態が変わります。例えば、契約期間を定めない雇用契約(正社員など)であった人も、定年退職後の再雇用により、嘱託や契約社員、パートアルバイトなどに変わることになるでしょう。雇用形態が変わることにより、給料などの諸条件が変わることがほとんどです。
勤務延長は、定年後も希望する従業員をそのまま雇用し続ける方法です。定年後も正社員として働き続けることができます。
(2)高年齢雇用継続給付の縮小
雇用保険には、高年齢雇用継続給付という制度が設けられています。
これは、5年以上の被保険者期間がある、60歳以上65歳未満の一定の労働者で、60歳到達等時点に比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける方に対して、減少した分の賃金の補助として給付金が支給される制度です。
雇用保険法の改正により、2025年4月から給付金の支給率が減少します。
具体的には、60歳に達した日が2025年3月31日以前の人は、各月の賃金の最大15%が支給されますが、4月1日以降の方は、最大10%まで縮小されます。
実際の支給額は賃金がどれだけ減ったかによって異なりますので、詳しくは下記厚生労働省のサイトをご確認ください。
参考:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省
65歳までの雇用確保「完全」義務化により企業がすべき対応
厚生労働省の調査によれば、2023年6月1日時点で、報告した企業の99.9%が高年齢者の雇用確保措置を実施済みでした。
また、継続雇用制度により雇用確保措置を実施している企業のうち、経過措置により対象者を限定していた企業は15.4%に過ぎません。
したがって、ほとんどの企業が65歳までの雇用確保義務化に伴う対応は既に取っているものと考えられます。
継続雇用制度の経過措置により対象者を限定していた企業については、主に次のような対応が求められます。
(1)就業規則の見直し
2025年4月以降、どのような方法(定年年齢引き上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入のいずれか)で65歳までの雇用確保を実践するのか明確にしたうえで、就業規則を見直して変更し、労働基準監督署へ提出する必要があります。
そのうえで、変更した就業規則を従業員へ周知します。
(2)賃金制度や労働条件の見直し
高年齢者雇用確保措置を導入するにあたり、賃金を含む労働条件の見直しが必要な場合があります。
労働条件は、基本的には事業主と労働者の間の話し合いで決定されますが、厚労省の指針で、主に下記について留意することが求められています。
・年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度を採用している場合、能力や職務等の要素を重視した制度への見直しに努める。そのとき、高年齢者の雇用と生活の安定にも配慮した、計画的かつ段階的なものとなるように努める。
・継続雇用後の賃金は、高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮して適切なものとなるよう努める。
・短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努める。
・継続雇用の希望者の割合が低い場合、労働者のニーズや意識を分析し、制度の見直しを検討する。 など
参考:高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針|厚生労働省
(3)助成金を活用できないか検討する
高年齢者の雇用確保のため、厚生労働省は「65歳超雇用推進助成金」という制度を設け、該当する申請者に対して助成金を給付しています。
助成金は、次の3種類あります。
- 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成
- 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成
支給額や受給手続きはそれぞれ異なりますので、詳しくは厚生労働省のサイトで確認してください。
【まとめ】高年齢者も働いて活躍できる社会へ
日本は、働く意欲のある高年齢者が、働き続けることができる社会を目指しています。
企業は、今後はより、高年齢者の経験や知識を活用し、組織全体の成長を促進することが求められるでしょう。