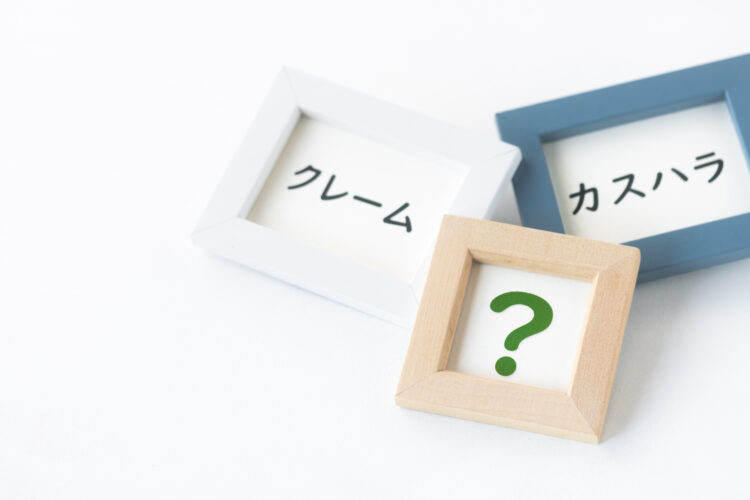「男性が育児休業を取るなんてありえない」
「育休を取ったら昇進は諦めろ」
「男のくせに育児なんかに時間を使うな」
こんな言葉を職場で聞いたことはありませんか? または、言ってしまったことはありませんか?
これらは、近年注目されている「パタハラ(パタニティハラスメント)」の典型例です。
男性の育児参加が推奨される現代社会において、パタハラは深刻な問題となっています。
では、パタハラとは具体的にどのようなものなのでしょうか? そして、企業はパタハラにどのように対応すべきなのでしょうか?
本記事では、弁護士の視点から、パタハラの定義、具体例、法的問題点、そして企業が取るべき対策について詳しく解説します。育児に積極的に参加したい男性社員の方、人事担当者の方、そして働きやすい職場環境づくりに関心のある全ての方にとって、必読の内容となっています。
この記事を読んでわかること
- パタハラの定義
- パタハラの事例・裁判例
- パタハラが発生する主な原因
- パタハラに対して企業がとるべき防止策・とるべき対処法
ここを押さえればOK!
パタハラの事例には、育児休業や時短勤務を理由とする解雇や降格、ためらわせる言動、利用後の嫌がらせが含まれます。
具体的には、育児休業の相談した際の「辞めてもいい」といった発言や、育児休業を取得した後に昇進を見送るなどの事例が挙げられます。
企業はパタハラ防止策として、明確な方針の周知・啓発や、相談体制の整備を行うことが求められます。
また、パタハラ発生時には迅速かつ適切な対応が必要であり、事実関係の確認や被害者への配慮、行為者への措置、再発防止策を講じることが重要です。
企業は男性の育児休業取得を促進し、パタハラ防止に向けた取り組みを強化する必要があります。
パタハラの定義とは?マタハラとの違いとは
パタハラ(パタニティハラスメント)とは、育児休業や育児時短などを利用しようとする男性に対して行われる嫌がらせを指します。パタニティとは「父性」を意味します。
厚生労働省の調査によれば、育児に関わる制度を利用しようとした男性社員の中で、「過去5年間に育児休業等ハラスメントを受けた」と回答した人の割合は24.1%で、ほぼ4人に1人の男性がハラスメントを受けているとのことです。
参照:令和5年度調査 職場のハラスメントに関する実態調査について|厚生労働省
マタハラとの違いとは
パタハラと同じくよく聞く言葉として「マタハラ(マタニティハラスメント)」があります。
マタハラ(マタニティハラスメント)とは、妊娠・出産・育児休業などを理由とする女性労働者への不利益取扱いや嫌がらせを指します。
パタハラとマタハラは育児に積極的に取り組む労働者に対して行われる嫌がらせという点で共通していますが、対象者が男性か女性かで使い分けられます。
法律上は男性・女性に区別なく、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益な取り扱いは禁じられています。
育児介護休業法第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
パタハラの事例とは
パタハラでよくある事例としては、育児のための休業や時短勤務などを申請した男性労働者に対し不利益な扱いをする、上司が嫌味を言うなどの嫌がらせが挙げられます。
もっと具体的に見ていきましょう。
(1)パタハラの典型的な事例
パタハラのパターンを分けると、次の3つが挙げられます。
- 育児休業の取得や育児のための時短勤務を理由とした解雇や減給・降格
- 育児休業の取得や育児のための時短勤務をためらわせるような言動
- 育児休業や育児のための時短勤務を利用したことに対する嫌がらせ
詳しく見ていきましょう。
(1-1)育児休業の取得や育児のための時短勤務を理由とした解雇や減給・降格
育児休業の取得や育児のための時短勤務などを理由に次のような取り扱いをするのは、典型的な「パタハラ」となります。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 減給や降格をすること
- 不利益な自宅待機を命じること
- 不当な評価を行うこと
- 不利益な配置転換を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと など
厚労省の通達によると、育児休業の取得や時短勤務を「契機として」降格や配置転換などの不利益な取り扱いがなされたときは、原則育児介護休業法第10条に違反するものとされます。
「契機として」いるかどうかは、厚労省による行政解釈において原則制度利用の終了から1年以内に不利益な取り扱いがなされた場合は、「契機として」いると判断されます。
つまり、この行政解釈によれば、育児休業や時短勤務を終えてから1年以内に降格や配置転換がなされたときは、原則として育児休業や時短勤務の取得を理由として降格や配置転換がなされたものと判断され、違法ということになるのです。
ただし、業務上の必要性などの特段の事情がある場合には、上記の通達や行政解釈においても、例外的に不利益な取り扱いが育児休業や時短勤務の取得を理由とするものではないとされます。
ただし、業務上の必要性があるとの特段の事情は、簡単に認められるものではありません。
【業務上の必要性があるとの特段の事情】
- 円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障が あるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、
- その業務上の必要性の内容や程度が、育児介護休業法第10条の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められるもの
つまり、育児休業や時短勤務を終えた後で降格や配置転換がなされ、会社から業務上の必要があると説明されたとしても、会社に対し、上記のような特段の事情があるのか厳しく問題とするべきです。
参照:職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント対策やセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です!!|厚生労働省
(1-2)育児休業の取得や育児のための時短勤務をためらわせるような言動
上司や同僚による育児休業の取得や育児のための時短勤務などをためらわせるような言動も典型的な「パタハラ」に当たります。
<典型的な事例>
- 育児休業の取得を上司に相談したら「休みをとるなら辞めてもいい」と言われた
- 育児休業の取得を上司に相談したら「次の査定では昇進しない」と言われた
- 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言われて、育児休業の取得を諦めた
- 育児休業の取得を同僚に相談したところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたもそうすべき。」と繰り返し言われた。
(1-3)育児休業や育児のための時短勤務を利用したことに対する嫌がらせ
育児休業や育児のための時短勤務を利用したことによる解雇や降格など目に見える形での不利益を受けなくても上司や同僚から嫌がらせ的な言動を受けていれば、典型的な「パタハラ」に当たるといえるでしょう。
<典型的な事例>
- 上司・同僚から「時短勤務をしている人にはたいした仕事はさせられない」と繰り返し言われ、簡単な仕事しかやらせてもらえない
- 上司・同僚から「この忙しい時期に育休を取得するなんて迷惑だ。」と繰り返し言われている
(2)パタハラに関する裁判例
パタハラについて「違法」と判断した裁判例もあります。簡単に紹介します。
<大阪高裁平成26年7月18日判決(医療法人稲門会事件)>
病院に勤務する男性が3か月間の育児休業を取得したところ、育児休業を取得したことを理由に昇給や昇格試験を受験させなかったことが問題となりました。
判決では、育児休業を取得したことを理由に昇給や昇格試験を受験させなかったことどちらも「違法」と判断し、昇給させなかった分の差額8万9040年と慰謝料15万円の支払いを命じました。
パタハラが発生する主な原因
パタハラが発生する主な原因は、「根強い性別役意識」と「企業の制度や意識改革の遅れ」にあります。
昨今女性の社会進出が進み、夫婦の共働きが当たり前となっていますが、個人や企業の感覚がそこまで追いついておらず、パタハラが発生する要因となっているのです。
(1)根強い性別役割意識
過去には「男は仕事、女は家庭」が当たり前の時代もありましたが、2000年代頃から男性雇用者と無業の妻からなる世帯(いわゆるサラリーマンと専業主婦の世帯)が減少しています。
2021年のデータでみると、妻が64歳以下の世帯で専業主婦世帯は夫婦の世帯全体の23.1%です。現在子育て中の20代30代の世帯に限定すればもっと割合は低くなるでしょう。
このように現在、子育てに取り組む夫婦の多くが「共働きをして育児も夫婦で協力するのが当たり前」となっているにもかかわらず、個人の感覚が「男は仕事、女は家庭」という思い込みから脱却できない人も少なからずいるのです。
参照:2-15図 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移|内閣府 男女共同参画(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-15.html)
(2)企業の制度や意識改革の遅れ
企業の制度や意識改革の遅れもパタハラを生む要因の1つです。
企業の制度として男性の育児休業制度が整えられていなかったり、会社の経営陣の意識が進んでいなかったりすることがあります。こういった会社では、育児休業などに関する制度を利用することがしにくい雰囲気があり、実際育児休業など申請しようとしても「男性なのに」「そんな制度はないから利用できない」と利用を拒まれてしまうことがあるのです。
そもそも男性の育休取得は法律上権利として定められています。「男性が取得した前例がない」「就業規則に男性が取得できると書いていない」などの事情があっても、男性社員が育休取得を望めば会社側は拒否することはできないのです。
男性の育休取得の制度については、こちらの記事もご覧ください。
パタハラに対して企業がとるべき防止策
育児介護休業法によれば、企業は職場におけるパタハラを防ぐための防止策を講じなければならないとされています。
育児介護休業法第25条
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
厚生労働省が定めた指針によれば、パタハラに対して企業がとるべき防止策として次のようなポイントが挙げられています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
それぞれの具体例を見ていきましょう。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
企業はパタハラ防止のために、企業として妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを許さないという方針を明確化し、その方針を労働者に周知・啓発する必要があります。
<取り組み例>
- 就業規則などに会社の方針を規定し、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景などを労働者に周知・啓発すること。
- 社内報、パンフレットなど資料にハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を記載し配付などすること。
- 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
- 事業主の方針と併せて育児休業制度などが利用できる旨を周知 ・ 啓発すること。
このように企業全体でパタハラに対する理解を深め、「根強い性別役意識」と「企業の制度や意識改革の遅れ」をなくしていくことが、パタハラを防ぐのにつながっていきます。
(2)相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることが必要です。そのためには、相談窓口の設置だけではなく、相談を受けた場合にどのように対応するのかについての制度づくりや相談担当者研修制度などの体制づくりをする必要があります。
事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討するのでは対応を遅らせることになります。迅速かつ適切に対応するために、問題が生じた場合の担当部署や対応の手順などをあらかじめ明確に定めておきましょう。
パタハラが発生した場合に企業がとるべき対応
パタハラが発生した場合、企業として適切に対応が求められます。被害が続いたり、拡大したりすることを防ぐため、相談があったら迅速に開始しましょう。
(1)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
相談者とパタハラを行ったとされる者双方から事実関係を確認する必要があります。双方で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を確認するようにしましょう。
(2)事実確認ができた場合には、被害者に対する配慮を適正に行うこと
被害者の職場環境の改善や被害者とパタハラを行った者の間の関係改善に向けての援助、メンタルヘルス不調への相談対応等の措置などを講ずる必要があります。場合によっては被害者とパタハラを行った者を引き離すための配置転換が必要なケースもあるでしょう。
被害者の希望や事案の内容に応じて企業として適正な配慮を行わなければなりません。
(3)パタハラを行った者に対する措置を適正に行うこと
就業規則など(職場におけるハラスメントに関する規定など)に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずる必要があります。
企業の体裁などを理由に秘密裏に処理しようとしたり、個人間の問題として当事者の解決に委ねたりするケースもありますが、こうした対応は、のちのち問題をこじらせ企業としてより大きな問題になりうる可能性があります。
(4)再発防止に向けた措置を講ずること
パタハラの再発を防ぐため、パタハラに関する企業の方針や制度などを改めて労働者に周知・啓発する必要があります。これまでの防止対策に問題がなかったかどうか再点検するようにしましょう。
2023年4月1日から、従業員1000人超の企業は、年1回、男性の育児休業などの取得率を公表する義務があります。インターネットなど一般の方が確認できる方法で公表する必要があり、厚生労働省のウェブサイトで公表する企業が多いようです。
さらに、2025年4月1日からは、この義務が従業員が300人超の企業に拡大されます。企業としても男性の育児休業などの取得を促進する機運が高まっています。
【まとめ】パタハラとは育休などを利用する男性に対する嫌がらせ|企業は適切な対処を
企業は、パタハラの定義や事例を理解し、防止策を講じなければなりません。パタハラのない職場づくりは、全ての従業員の働きやすさにつながります。
あなたの職場でパタハラが起きていないか、今一度確認してみましょう。そして、パタハラのない職場環境づくりに向けて、できることから始めてみませんか?男性の育児参加を応援する第一歩を、今日から踏み出しましょう。