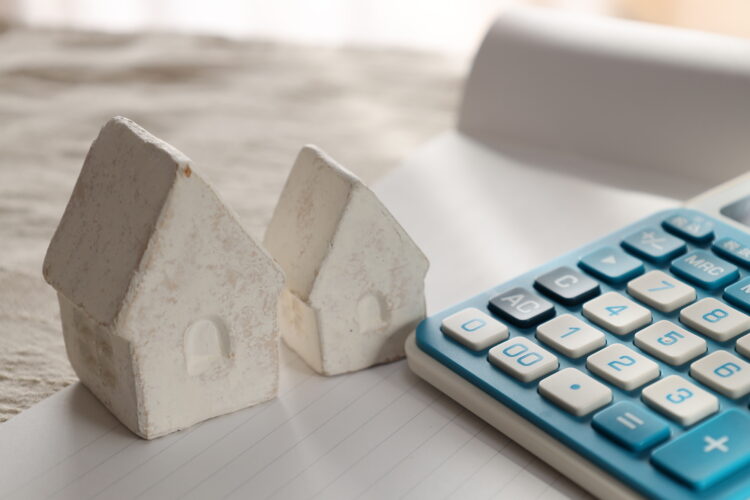「相続できると思っていたら、遺言で相続分ゼロにされた!何も相続できないの?」
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続財産に対して、法律で定められた一定割合の「遺留分(いりゅうぶん)」があり、遺留分を侵害されたら支払いを求めることができます。
この記事では、遺留分の基本概念から、算定方法、遺留分侵害額請求の具体的な手続き、制度変更の簡単な説明などについて弁護士が解説します。
ここを押さえればOK!
遺留分とは、法律で定められた一定の割合の相続財産を指し、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)が対象となります。遺留分の総額は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、配偶者や子がいる場合は遺産の2分の1です。個別の遺留分は、遺留分の総額に法定相続分を乗じて算定します。
遺留分侵害額請求の手続きは、請求期限の確認、遺産や相続人・請求相手の調査、当事者同士の話し合い、調停や訴訟の流れで進められます。請求期限は、相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年間、または相続開始から10年間です。
遺留分侵害額請求をする際は、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが重要です。
弁護士に依頼すると、弁護士が複雑な遺留分侵害額の算定や請求相手の特定をしたうえで、あなたの代わりに交渉します。
遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
遺留分の基本概念
まず、遺留分について説明します。
(1)遺留分とは
自分の財産については、遺言書で相続人にどのように分けるかを指定することができます。
しかし、遺言によっても、一定の近親者に留保された一定割合の相続財産については、奪うことができません。
近しい家族であれば、相続で一定割合の遺産がもらえると期待するのが通常ですし、また相続できなければ生活に困ることがあるかもしれません。
そこで、相続財産の一定割合を、一定の近親者に留保するとしたのが遺留分の制度です。
(2)遺留分を有するのはだれ
遺留分を有するのは、「兄弟姉妹を除く法定相続人」です。
具体的には、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)が該当します。
子がすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続しますが、孫にも遺留分が認められます。
通常、兄弟の遺産を期待して生活するということは考えられないので、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
例えば、配偶者がいて、両親と子どもがいない方が亡くなった場合、その相続人は配偶者と兄弟姉妹です。
このような場合、「全財産を妻(夫)に相続させる」という内容の遺言を残せば、全財産を妻(夫)に残すことができます。兄弟姉妹には遺留分が存在しないためです。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権は、兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺留分が侵害された場合に、他の相続人などにその侵害額を支払うよう請求できる権利です。
どのように遺留分を計算するのか、侵害されるといえる額はどれくらいなのか説明します。
遺留分侵害額の算定方法
まず、遺留分を確定します。
遺留分の総額を算定し、その後、複数の相続人がいる場合には法定相続分の割合によって各相続人の遺留分を算定します。
遺留分の総額は、次のとおりです(民法1042条)。
- 相続人が、直系尊属(父母や祖父母など)のみの場合:遺産の3分の1
- 相続人に、配偶者や子などがいる場合:遺産の2分の1
ここから、各相続人の個別の遺留分を計算します。
相続人が1人であれば、上記の遺留分の総額がそのまま個人の遺留分になります。
相続人が複数いる場合、遺留分の総額に、各自の法定相続分を乗じた割合が個別の遺留分になります。
下記のケースで、具体的に計算してみます。
(1)相続人が子ども2人のケース
父親Aと子ども2人B・C(すべて仮名)がいて、母親は既に亡くなっているケースで考えます。
Bは音信不通である一方、CはAの近くに住み、Aの自宅を訪ねて掃除を行うなど高齢のAの生活を手助けしていました。
Aは亡くなりましたが、生前Aは「全財産をCに相続させる」という内容の自筆証書遺言を残していました。遺産は2000万円相当の不動産と、1000万円の預金です。
この場合、相続人はBCの子ども2人です。
Bが遺留分を主張した場合、Bの遺留分はいくらになるかを計算してみます。
遺留分の総額は、遺産3000万円の2分の1の1500万円です。
Bの法定相続分は2分の1なので、1500万円に2分の1を乗じた750万円が遺留分になります。
BはCに対して、遺留分侵害額請求権として、750万円の支払いを請求することができます。
(2)相続人が、両親2人のケース
亡くなったXは、結婚はしていませんが、生前、長年事実婚をしてきた相手Y(すべて仮名)に対して「全財産を遺贈する」という内容の自筆証書遺言を残していました。Xには兄弟として兄がおり、また両親は健在です。
遺産は、3000万円相当の不動産、預金3000万円です。
この場合、法定相続人はXの両親2人です。
Xの両親がそれぞれ遺留分を主張した場合、遺留分がいくらになるか計算してみましょう。
遺留分の総額は、遺産6000万円の3分の1の2000万円です。
両親それぞれの法定相続分は2分の1なので、2000万円に2分の1を乗じた1000万円が遺留分になります。
Xの両親はYに対して、遺留分侵害額請求権として、それぞれ1000万円の支払いを請求することができます。
(3)請求できるのはお金?不動産?
2019年7月1日に改正民法が施行され、遺留分侵害額請求の制度が導入されました。
この制度では、遺留分を侵害された場合、相当する額の金銭での支払いのみ請求することができます。したがって、「不動産を返せ」と請求できる権利はありません。
それ以前の遺留分減殺請求という制度では、原則として「現物を返還する」という遺留分減殺請求権が定められていましたので、不動産を返せと請求することができました。
しかしこの場合、返還された不動産は共有財産となり、共有する相続人同士でその処分について話し合う必要があります。遺産の権利関係が複雑になったり、話し合いがうまく進まないという問題がありました。
この法改正により、名称は「遺留分侵害請求権」と変更され、手段も現物返還から金銭精算へと手続きが簡素化されました。
(2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合には、改正前の遺留分減殺制度による請求をすることになります)
(4)具体的な遺留分侵害額は、弁護士に相談を
遺留分算定の基礎になる財産は、被相続人が亡くなったときの遺産に、贈与した金額(相続人以外に対する贈与は原則相続開始前1年間、相続人に対する贈与(生計の資本など特定の贈与のみ)は相続開始前10年)を加算し、負債を控除した額となります。
また、遺留分を主張する者が、被相続人から遺贈や特別受益を受けていた場合には、それらを控除した額が具体的な請求額になります。
個別具体的な遺留分侵害額の計算は難しいこともありますので、相続を扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求の手続きは、次の流れで行います。
- 請求期限を確認
- 遺産や相続人の調査などの準備
- 他の相続人などと話し合う
- 調停や訴訟をする
順に説明します。
(1)請求期限の確認
遺留分侵害額請求ができる期間は、次のように制限があります(民法1048条)。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間
- 相続開始の時から10年
の、いずれか早い方
この期限を過ぎると、請求権は時効で消滅してしまいますので、早めの対応が求められます。
(2)遺留分侵害額の算定など請求の準備
遺留分侵害額請求を行うためには、まず自分の遺留分を算定し、侵害されている額を明らかにする必要があります。
そのために、被相続人の遺産(借金含む)と相続人、遺留分の総額に加算すべき贈与の有無も調査します。自身の法定相続分も確認します。
相続財産の調査について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
法定相続人と相続分について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
さらに、遺留分侵害額請求をすべき相手方を特定する必要があります。遺留分侵害額を負担するのは、受贈者(贈与によって財産を得た者)又は受遺者(遺言によって財産を得た者)です。具体的に誰に請求すべきかは、民法で定められていますが、その相手を特定するのは複雑な計算が必要です(民法1047条)。
請求には時間制限がありますので、迅速に行いましょう。
自分一人では不安な時は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
(3)相続人間での話し合い
次に、実際に遺留分侵害額の支払いを請求します。
まずは、当事者で話し合いを行うことが推奨されます。
遺留分は法的に認められた権利です。遺留分が侵害されていれば、相手も支払いに応じざるをえません。調停などの法的手続を経ることなく、当事者間の話し合いで支払ってもらうことができれば、問題の早期解決に繋がります。
話し合いが不調の場合は、次のステップに進むことになります。
(4)内容証明郵便の送付
話し合いがなかなか進まない、請求期限が迫っている、というような場合には、遺留分侵害額請求権を行使する意思を相手に示したことを証拠に残すために、内容証明郵便を送付します。
後々調停などの法的手続に移った際にも、内容証明郵便は証拠となります。
送付する際は、文書に遺留分侵害額請求を行うことを明確に記載することが重要です。
弁護士に対応を依頼すれば、適切な文書を作成し送付してくれるでしょう。
(5)調停と訴訟の流れ
当事者間の話し合いでまとまらない場合や、そもそも話し合いが困難な場合には、家庭裁判所での遺留分侵害額の請求調停手続を利用します。
調停では、調停委員が当事者双方から個別に話を聞き、資料を確認し、必要に応じて資料の提出を促したりして、和解案や助言をしたりして、解決を目指します。
調停でも合意できない場合には、訴訟を提起して請求します。
円満な解決に向けてできること
遺留分侵害請求権を行使するかどうかは、各遺留分権利者が自由に決められます。
被相続人の意思を尊重して、行使しない人も少なくありません。
一方、法律上認められた権利ですので、遺留分を行使することに罪悪感を持ったり躊躇したりする必要はありません。遺留分侵害額の負担者は、請求されたら相当額を支払う必要があります。
できれば感情的な対立をさけ、冷静に話し合いましょう。
当事者同士での話し合いが難しいときは、弁護士に依頼して代わりに話し合ってもらうこともできます。
【まとめ】
遺留分とは、一定の近親者に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。この遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額請求権を行使して、贈与又は遺贈を受けた者に対し、侵害額相当額の支払いを請求することができます。
アディーレ法律事務所では、遺留分侵害額請求についてご相談・ご依頼をお受けしています。遺留分侵害額請求に関してお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。