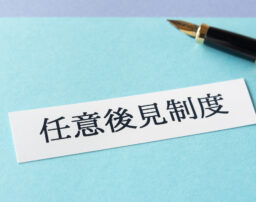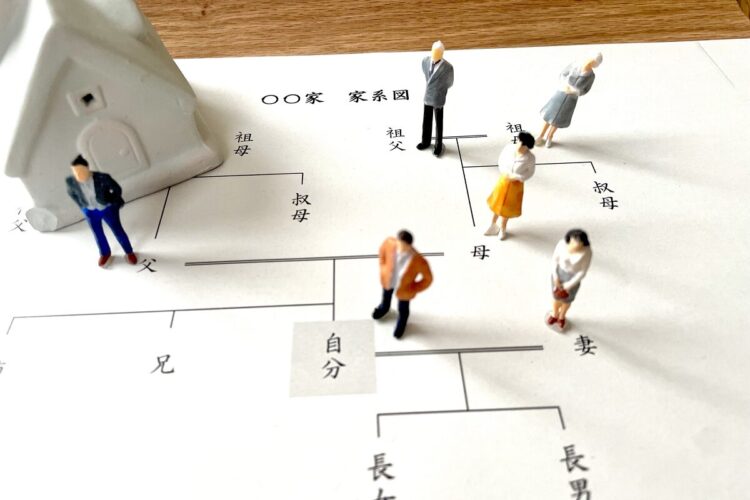成年後見制度は、認知症などで判断能力に問題がある人を法的に支援する制度の一つです。
そして、成年後見人は、法律で定められた欠格事由に該当しない限り、基本的に誰でもなることができます。
専門知識が必要なこともあるため、家族や親族だけでなく、弁護士といった第三者の専門家が選任されることも多いです。
ここを押さえればOK!
なお、法人も成年後見人になることが可能です。
法定後見人は家庭裁判所の審判で選任され、任意後見人は本人が事前に選任します。
成年後見人、保佐人、補助人は本人の判断能力の程度に応じて選任され、権限の範囲が異なります。
成年後見人の主な職務は、財産管理と身上監護です。
財産管理には預貯金や不動産の管理、資産運用などが含まれ、身上監護には医療や介護サービスの契約、生活環境の整備などが含まれます。
成年後見制度の概要
まずは、成年後見制度の内容とその目的について説明します。
(1)成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力に問題がある成年者を法律的に保護し、支援するための制度です。
この制度では、本人の権利を守りつつ、財産管理や身上監護を行う成年後見人等が選任されます。
なお、後述のとおり成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
(2)成年後見制度の目的
成年後見制度の主な目的は、判断能力に問題がある人の権利と利益を守ることです。
認知症などで判断能力に問題がある場合、契約内容が自分にとって不利益であることがわからず、悪質商法の被害にあってしまいかねません。
そこで、選任された成年後見人は、本人の財産を適切に管理し、必要な契約を締結するなど、本人に代わって法律行為を行います。
また、本人の意思を尊重しながら、生活の質を維持・向上させるための支援を提供します。
参考:ご本人・家族・地域のみなさまへ 成年後見制度とは|厚生労働省
成年後見人になれる人の条件
成年後見人になれる人・なれない人について説明します。
(1)成年後見人になるために資格は必要?
成年後見人になるために、特別な資格は必要ありません。
ただし、民法第847条で定められている欠格事由に該当する人は、成年後見人になれません。
欠格事由は、次のとおりです。
- 未成年者
- 過去に家庭裁判所から成年後見人等を解任されたことがある者
- 破産者
- 被後見人(後見されている人)に対して訴訟をした者や、その配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
上記のいずれにも該当していなければ、成年後見人になることができます。
また、法人が成年後見人となることも可能です。
ただし、家庭裁判所が成年後見人を選任する法定後見の場合、被後見人の子など親族のほか、弁護士や司法書士などの法律の専門家が選任されるケースが多いです。
(2)家族や親族がなれるケース
成年後見人には、本人の家族や親族がなることも可能です。
その場合は、本人と同居している配偶者や子、兄弟姉妹などが候補として考えられます。
ただし、本人と利害関係が対立している場合や、財産管理能力に不安がある場合は、弁護士などの第三者が選任されるでしょう。
成年後見人は、本人の利益を最優先に考え、公平に職務を遂行することが求められるからです。
法定後見人と任意後見人の違い
法定後見人は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所の審判によって選任されます。選任されるのは家族や親族、弁護士などの専門職であることが多いです。
一方、任意後見人は、本人が判断能力を有する間に、将来の判断能力低下に備えて自ら選任し、任意後見契約を締結する後見人です。
法定後見人が事後的な対応であるのに対し、任意後見人は事前の備えという点で異なります。
また、自分で後見人を選任するため、任意後見人の方が本人の意思をより反映しやすいという特徴があるといえるでしょう。
成年後見人と保佐人・補助人の違い
成年後見人、保佐人、補助人は、本人の判断能力の程度に応じて選任される支援者です。
主な違いは、次の表のとおりです。
| 種類 | 本人の判断能力 | 代理権の範囲 |
|---|---|---|
| 成年後見人 | 常に欠く状態 | 全般的に広範 |
| 保佐人 | 著しく不十分 | 特定の法律行為(代理権付与の審判が必要) |
| 補助人 | 不十分 | 特定の法律行為(代理権付与の審判が必要) |
成年後見人が最も広い権限を持ち、保佐人、補助人の順に権限が限定されます。
成年後見人の主な職務内容
次に、成年後見人の基本的な職務内容について説明します。
(1)財産管理に関する職務
成年後見人の主要な職務の一つが財産管理です。これには次のような業務が含まれます。
- 預貯金の管理
- 不動産の管理や処分
- 株式や債券などの資産運用
- 年金や保険金の受け取り
- 債務の返済 など
成年後見人は、本人の財産を適切に管理し、その利益を最大限に守る義務があります。
また、定期的に家庭裁判所に財産状況を報告することが必要です。
(2)身上監護に関する職務
身上監護は、本人の生活や健康、福祉に関する職務を指します。
主な職務内容は次の通りです。
- 医療に関する契約
- 介護サービスの契約や手配
- 施設入所の契約
- 住居の確保や生活環境の整備 など
成年後見人は、これらの職務を通じて本人の生活の質を維持・向上させる役割を担います。ただし、身上監護は本人の意思を最大限尊重しながら行うべきで、過度の干渉は避けるべきとされています。
成年後見制度に関するよくある質問(FAQ)
(1)成年後見人になるために特別な資格は必要ですか?
成年後見人になるための特別な資格は必要ありません。
成年被後見人の利益を適切に代弁できる成年者であれば、民法に定める欠格事由に該当しない限り誰でもなることができます。
ただし、弁護士、司法書士などの専門職が選任されることも多く、複雑な案件では専門知識が求められる場合があります。
重要なのは、本人の福祉を第一に考え、誠実に職務を遂行できることです。
(2)成年後見人の変更や解任は可能ですか?
本人、親族、検察官などが家庭裁判所に申立てを行うことで、審判によって変更や解任をすることができる場合があります。
変更や解任の理由として、成年後見人が不正行為をしたことや、著しい不行跡その他後見の任務に適しないといえる事由が必要です。
単なる意見の相違だけでは変更や解任の理由とはなりません。
家庭裁判所は慎重に審査を行い、本人の利益を最優先に判断します。
(3)成年後見制度を利用すると、選挙権はどうなりますか?
2013年の公職選挙法改正により、現在は成年被後見人(後見されている人)であっても選挙権を行使できるようになりました。
ただし、本当に成年被後見人本人の意思が反映された投票なのかについて、大いに配慮する必要があると考えられています。
【まとめ】
成年後見制度は、認知症などで判断能力に問題がある人を支援する重要な制度です。
成年後見人になるための特別な資格は不要ですが、本人の利益を第一に考え、誠実に職務を遂行できることが求められます。
判断能力に問題が生じている程度によって、成年後見だけでなく、保佐・補助といった制度も設けられているため、適切な支援を選択することが大切です。
成年後見・保佐・補助の申立てを検討している方は、にアディーレ法律事務所にご相談ください。