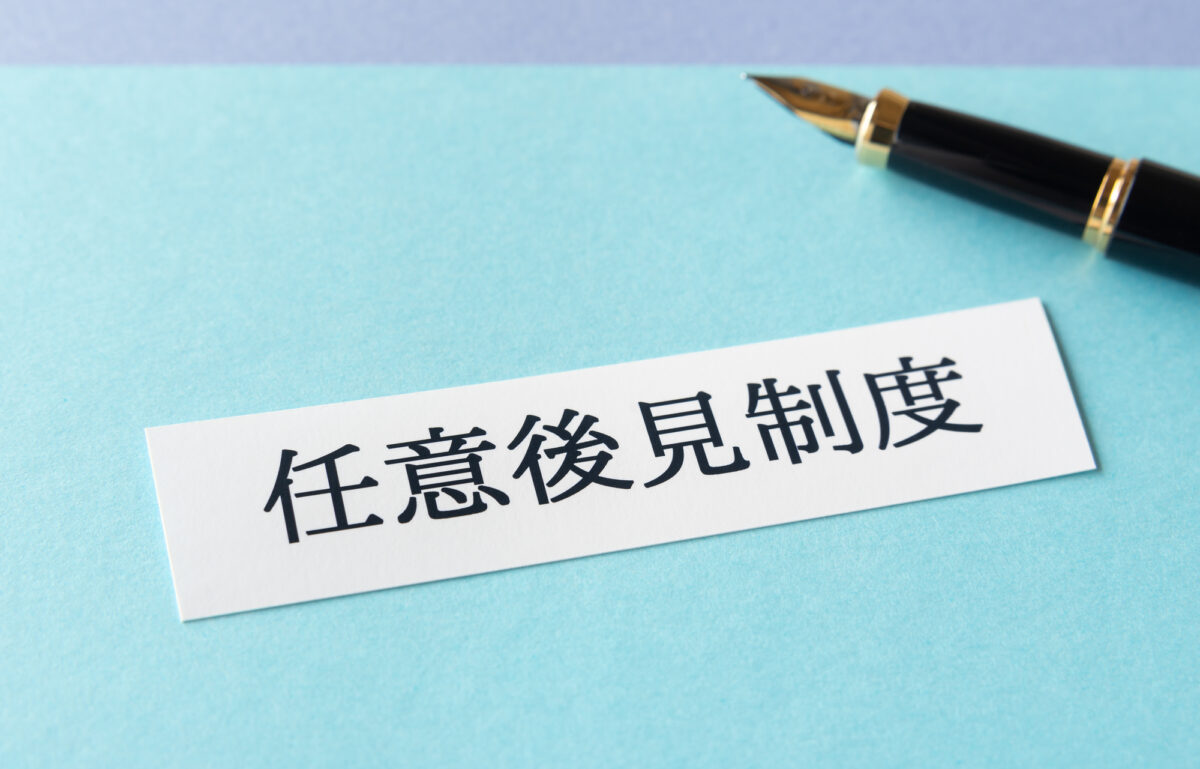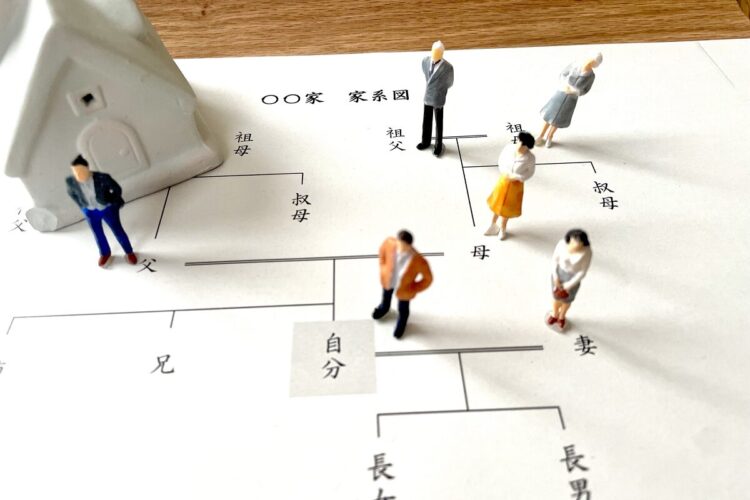「将来、親や自分の判断能力が衰えたらどうしよう…」
認知症など判断能力が衰えたときのために活用できる法的な制度を知ることは、安心への第一歩です。その選択肢の一つが「任意後見制度」です。
この記事では、任意後見人とは何かという基本から、よく似た法定後見との違い、メリット・デメリット、費用、手続きまで、弁護士が解説します。
ここを押さえればOK!
判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」とは異なり、任意後見では、本人が信頼する家族や専門家を後見人に指名し、支援内容もライフプランに合わせて自由に設計できるのが最大のメリットです。これにより、本人の意思を最大限尊重した将来への備えが可能になります。
手続きは、まず後見人となる人との間で契約内容を決め、公証役場で公正証書を作成します。その後、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。監督人が選任されると契約の効力が生じ、任意後見人の仕事が始まります。
ただし、任意後見人には本人に不利益な契約を取り消す「取消権」がない点や、後見人を監督する任意後見監督人への報酬が別途発生するなどの注意点も理解しておく必要があります。
任意後見人とは?あなたの“もしも”に備え、意思を未来につなぐパートナー
厚生労働省の資料によれば、2022年で認知症患者は443万人、軽度認知障害の方は559万人で、合計1002万人にも上ります。65歳以上の、およそ8人に1人が認知症です。また認知症予備軍を加えると、3.6人に1人が判断能力に問題を抱えていることになります。
現在判断能力に問題がなくても、高齢になるにつれ、問題が生じる可能性は十分にあります。
任意後見は、契約により、そのような“もしも”に備えることのできる制度です。
参考: 認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計|厚生労働省
(1)任意後見の仕組み|元気なうちに将来の財産管理・生活を託す契約
任意後見制度とは、将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備え、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、判断能力に問題がないうちに自らの意思で決めておく契約制度です。
民法上委任契約の一種と考えられており、具体的なルールは任意後見契約に関する法律に規定されています。
具体的には、あらかじめ内容について本人と任意後見受任者(将来任意後見人としてサポートをしてくれる人)とで話し合った上で合意し、公証役場で「任意後見契約」という契約書を公正証書で作成します。
例えば、「将来もし認知症になったら、長男に預貯金の管理と介護施設との契約をお願いしたい」というように、任意後見人を選び、具体的にやってほしいことについて代理権を与え、報酬などの定めを書面に残します。
任意後見制度は、自分の未来を、自分の意向を踏まえてオーダーメイドでデザインできるため、将来のための有効な備えと言えるでしょう。
(2)任意後見人の重要な役割|「身上監護」と「財産管理」
任意後見人は、契約に基づき、委任された事項について、ご本人の代わりに活動を行います。
任意後見人の主な役割は、「身上監護」と「財産管理」の2つです。
(2-1)身上監護の例
身上監護は、わかりやすく言うと、日々の生活を手伝ったり、介護に必要な様々な事務手続きを手配することです。
具体的には、以下のような事項を任意後見人に委任できます。
- 介護サービスの利用契約、要介護認定の申請、認定に関する承認又は異議申立て
- 医療機関での入院手続き、医療契約、医療費の支払い
- 老人ホームなどの施設や住居の確保・契約
- 日々の生活に必要な買い物、生活関連の取引
- 訴訟行為 など
任意後見の仕事は、本人の代理として様々な事項を行う事です。したがって、食事の世話や掃除、入浴介助といった直接的な「介護行為」そのものを、契約により任意後見人に依頼するものではありません。
(2-2)財産管理の例
財産管理の例として、以下のような事項を任意後見人に委任できます。
- 不動産の保存、管理、処分
- 有価証券の管理、処分
- 預貯金の管理、処分
- 年金の受領、税金や公共料金など日常生活に必要な費用の支払い など
任意後見と法定後見の違いは?
任意後見とよく似た制度に「法定後見」がありますが、両者は根本的に異なります。あなたの希望に合うのはどちらか、4つの違いを理解しましょう。
| 比較ポイント | 任意後見制度(事前の備え) | 法定後見制度(事後の対応) |
|---|---|---|
| ①タイミング | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下した後に申立て |
| ②後見人の選び方 | 自分で信頼できる人を選べる | 家庭裁判所が選任する |
| ③権限の範囲 | 契約内容により自由に設計できる | 法律で定められた代理権 |
| ④取消権 | ない | ある |
(1)違い① タイミング|本人の意思で「事前に」備える任意後見
任意後見は「判断能力があるうち」に自ら備える制度であり、将来への「予防」と位置づけられます。
一方、法定後見は「判断能力が低下した後」に家族などが家庭裁判所へ申し立てる制度で、問題が発生した後の「対応」です。
ご自身の意思を確実に反映させたいのであれば、事前に備える任意後見が適しています。
(2)違い② 後見人の選び方|「自分で選べる」任意後見
任意後見では、法律でなれないと定められている人を除けば、「自分で信頼できる人」や「家族」を後見人に選べます。一方、法定後見では、家庭裁判所が、弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選任するのが一般的です。
法定後見では、ご家族を後見人候補として希望しても、必ずしも希望通りになるとは限りません。
後見人を「自分で選びたい」という強い希望があるなら、任意後見が適しています。
なお、任意後見人として選べない人物は次のとおりです(民法847条、任意後見契約に関する法律4条1項)。
- 未成年者
- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人又は補助人を解任された者
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 行方不明者
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
誰が成年後見人になれるのかについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)違い③ 権限の範囲|「自由に設計できる」任意後見
任意後見は、契約によって「支援してほしい内容を自由に設計」できます。
例えば、「介護施設に入居するにあたって、費用が必要であれば自宅を売却して欲しい」「毎年孫に一定額を贈与して欲しい」など、ご自身がサポートを受けたい範囲について、財産管理や身上監護の内容を具体的に契約に盛り込めるのが大きな強みです。
一方、法定後見には、ご本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3種類があります。一番広い権限を有するのは、ご本人の判断能力が全くないときに選任される成年後見人です。
成年後見人は、財産に関する全ての法律行為についての代理権を付与され、ご本人の日常生活や介護の方針を決定し、必要な財産を処分します。
(4)違い④ 取消権の有無|任意後見には「取消権」がない
成年後見人は、ご本人が必要のない高価な商品を買ってしまったなどのトラブルがあった際、日用品の購入その他日常生活に関する行為でなければ、ご本人の法律行為を取り消すことができます(民法9条)。
しかし、任意後見人には、任意後見人固有の取消権がありません。ご本人が自分に不利益な契約をしても、任意後見人が取り消すことはできないのです。これは任意後見の重要な注意点です。
ただし、任意後見人も、もともとご本人が有している詐欺による取消権や、消費者契約法上の取消権などを、本人の代理として行使することはできると考えられています。
したがって、心配な方は、任意後見人の契約において、「各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項」や「各事項に関連する一切の事項」などについても委任することを検討するとよいでしょう。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度には、法定後見と比べて、メリットもデメリットもあります。両者を理解したうえで、制度の利用を検討するとよいでしょう。
(1)【メリット】本人の意思を最大限に尊重できる
任意後見の最大のメリットは、ご自身の将来を自分の意思で決定できる「自己決定権の尊重」にあります。
(1-1)信頼できる人を後見人に選べる
最も信頼するご家族や、専門知識を持つ弁護士など、ご自身の将来を託すにふさわしいパートナーを自分の意思で選べます。
(1-2)支援内容をオーダーメイドで決められる
ご自身のライフプランや価値観に合わせて、支援してほしい内容を具体的に、そして柔軟に設計できます。
(1-3)任意後見監督人によるチェック機能で安心
後で説明しますが、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」が後見人の仕事をチェックするため、不正や権限の濫用を防ぎ、安心して財産を託せます。
(2)【デメリット】契約前に必ず理解すべき注意点
任意後見には、メリットだけでなくデメリットも存在します。契約を結ぶ前に必ず理解しておく必要があります。
(2-1)本人がした不利益な契約の「取消権」がない
前述の通り、法定後見と違い、ご本人が必要のない高価な商品を購入したとしても、取消権がありません。ただし、騙されて結んだ契約など、本人に取消権がある場合には、代理で行使できると考えられています。
(2-2)任意後見監督人への報酬が別途発生する
任意後見人への報酬とは別に、任意後見監督人に対しても月々数万円の報酬が継続的に発生します。
(2-3)亡くなった後の手続き(死後事務)は原則として依頼できない
葬儀の手配や遺品整理、行政手続き、残されたペットの世話等といった亡くなった後の手続きは、任意後見契約の範囲外です。ご希望の場合は、別途「死後事務委任契約」などで依頼する必要があります。
任意後見契約の手続
任意後見契約の手続の流れと、かかる費用について説明します。
任意後見は、ご本人の判断能力に問題がないうちの「契約」と、判断能力が低下した後の「契約の発効」という2段階があることが、ポイントです。契約しただけでは、任意後見契約の効力は生じません。ご本人の判断能力が低下した後に「発効」されることで、契約の効力が生じるのです。
手続の流れを簡単に説明します。
(1)任意後見契約の内容の決定
「誰に(任意後見人候補者)」「何を(支援内容)」「いくらで(報酬)」頼むかを、任意後見受任者とよく話し合って合意します。
代理してもらう事項については、公証役場で標準的な代理権目録について案内を受けることができますので、相談するとイメージしやすいかもしれません。
(2)公正証書の作成
任意後見契約は、公正証書を作成する必要があります。
公証役場に連絡して日時を予約したうえで、作成当日、当事者が必要書類を持参して公証役場に出向いて、公証人が公正証書を作成します。
病気などで出向けない場合には、公証人が出張して作成してくれますが、その分費用が加算されます。
作成された契約は法務局で登記されます。
(3)家庭裁判所への申立て
ご本人の判断能力が低下したら、申立てできる人(本人、配偶者又は4親等内の親族、任意後見受任者)が、必要書類を準備し、本人の現住所を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てます。
本人の申立てによらずに任意後見人を選任する場合、本人が意思を表示できないときを除いて、あらかじめ本人の同意が必要です。
任意後見監督人を選任するという審判が出されると、その旨の登記がなされます。
ここで初めて、任意後見契約の効力が生じます。これを、「任意後見契約の発効」といいます。
選任の申立てには、様々な書類の準備が必要です。仕事や家事をしながらの準備は大変ですので、任意後見を扱っている弁護士への相談・依頼をお勧めします。
参考:申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任) 東京家庭裁判所後見センター|裁判所
(4)後見開始
任意後見契約の発効後、任意後見人の仕事が正式にスタートします。任意後見人は、ご本人の代理として、委任された事項についてすべきことを進めていきます。
家庭裁判所で選任された任意後見監督人は、任意後見人の仕事を指導・監督します。
任意後見にかかる費用の内訳
費用は、大きく契約時の「初期費用」と、任意後見監督人選任にかかる「裁判費用」、後見開始後に継続してかかる「ランニングコスト」の3種類に分けられます。
(1)初期費用|数万円
任意後見契約をする際にかかる初期費用は、次のとおりです。具体的なケースによって異なりますが、合計で1万5000円~数万円で済むことが多いでしょう。
- 公証役場に支払う公正証書作成の基本手数料(1万1000円)、枚数が4枚を超えるときは1枚につき250円加算
- 収入印紙代 2600円
- 登記嘱託手数料 1400円
- ご本人らに交付する正本謄本の作成手数料 枚数×250円
- 登記申請のための書留郵送料 実費
- 出張を依頼した時の病床執務加算 5000円と交通費代 など
参考:4任意後見契約|公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04)
(2)後見監督人選任にかかる裁判費用|1万円~
後見監督人選任を家庭裁判所に申し立てるのに必要な費用は、主に次のとおりです。
- 申立手数料 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
- 登記手数料の収入印紙 1400円
以上の他、ご本人の診断書、ご本人が不動産を有する場合には不動産登記事項証明書などを提出する必要がありますので、書類収集にかかる費用もあります。
ケースによりますが、全体の費用は1万~数万円かかることが多いといえるでしょう。
(3)ランニングコスト| 月数万円~
任意後見人と任意後見監督人への報酬です。
報酬額は、ご本人の財産状況や支援内容の難易度が考慮されます。
身内の方が任意後見人となる場合、任意後見人の報酬は無報酬とされることも多いようです。
任意後見監督人の報酬は、任意後見人の事務内容や管理財産などを考慮して家庭裁判所の判断で決まります。管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万~2万円、5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円です。これらの報酬は、ご本人の財産から支払われます。
2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化
公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。
参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省
参考:公正証書の作成の手続がデジタル化されます!|公証人連合(https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf)
(1)具体的に何が変わる?
この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。
また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。
同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。ウェブ会議システムを利用すれば、自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。
さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。
公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。
(2)デジタル化のメリットとデメリット
デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。
(2-1)メリット
メリットとしては、次の3点があげられます。
- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。
- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。
- スケジュール調整が容易になる。
(2-2)デメリット
デメリットとしては、次の3点があげられます。
- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある。
- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。
- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。
(3)手数料の見直し
手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。
また、養育費や死後事務委任契約の手数料はこれまでより軽減されます。
弁護士が回答!任意後見人に関するよくある質問(Q&A)
(1) 任意後見人は、息子や娘など家族にお願いできますか?
はい、できます。
任意後見のメリットは、ご自身の意思で自由に、依頼する人と依頼することを選べる点にあります。
法律上の欠格事由(未成年者、破産者、行方不明者など)に該当しなければ、ご家族やご友人など、信頼できる方であれば誰でも任意後見人となることができます。
ただし、財産管理や法的な手続きは専門的な知識が求められる場面も多く、ご家族や友人の負担が大きくなる可能性もあります。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家を選ぶという選択肢もあります。
(2)認知症が少し始まったようです。もう任意後見契約は結べませんか?
諦めるのは早いです。契約という法律行為の結果受ける利益・不利益を判断する能力(法律上「事理弁識能力」といいます)があれば、契約は可能です。
このような事理弁識能力がない者がした契約は、無効です。
医師の診断書や、契約を作成する公証人との面談を通じて、公証人において契約を締結する能力があるかを検討することになります。
軽度の認知症と診断されていても、意思能力が認められて契約できるケースはあるようです。
「もう遅いかも」と自己判断せず、早めに弁護士や公証役場に相談することが重要です。
(3)任意後見契約した後に、やめることはできますか?
はい、できます。
ただし、変更や解除の方法は、任意後見監督人が選任される「前」か「後」かで異なります。 監督人が選任される前であれば、契約者双方の合意の場合は、合意解除公正証書を作成するか、解除の合意書に公証人の認証を受ければ、解除の効力が生じます。
任意後見監督人が選任された後(=後見がスタートした後)は、「正当な理由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
任意後見契約を解除した際には、その旨の登記申請も必要です。
一度効力が発生すると簡単にはやめられないため、契約は慎重に行う必要があります。
(4)任意後見監督人とは何ですか?必ず選ばなければいけませんか?
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに仕事をしているか、財産を不当に利用していないかなどをチェックする人で、任意後見を開始するためには必ず選ばなければなりません。
任意後見監督人は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの中から、ご本人との利害関係がない中立的な第三者を選任します。これは、任意後見人による財産の使い込みや権限の濫用を防ぎ、ご本人の利益を保護するための重要な仕組みです。監督人がいるからこそ、安心して大切な財産を託すことができるのです。
【まとめ】任意後見は、あなたの未来と家族を守る“元気なうちのお守り”です
「自分に何かあったら、身の回りの世話や財産の管理をどうしよう」
このような将来への漠然とした不安は、誰にでもあるものです。しかし、その不安を「もしもへの備え」に変えることで、漠然とした不安は「未来への安心」に変わるのではないでしょうか。