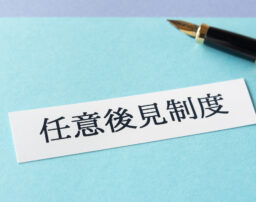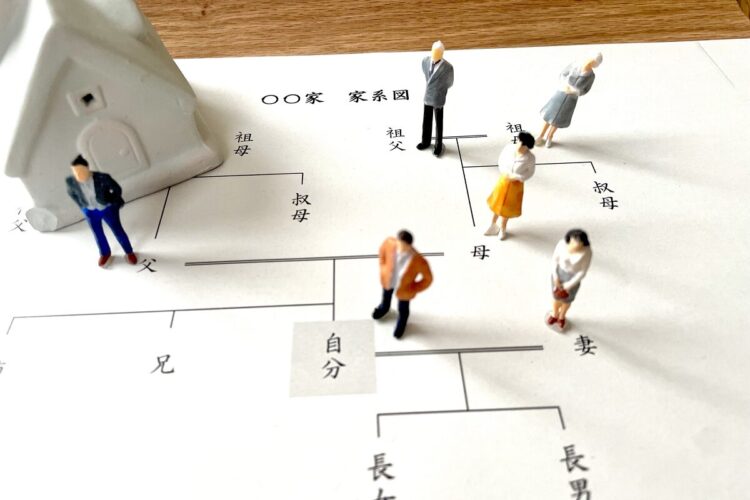突然発覚した亡くなった方の借金。「相続放棄の期限である3ヵ月はとうに過ぎてしまった…」と、諦めかけてはいませんか?
諦めるのはまだ早いかもしれません。特定の条件を満たせば、期限を過ぎたと思ったあとでも相続放棄が認められる可能性があります。
この記事では、期間経過後の相続放棄が認められる条件や具体的な手続の4ステップ、知らずに行うと後戻りできなくなるNG行為について、弁護士が網羅的に解説します。
あなたの不安を解消し、ご自身の財産を守るための道筋が見つかる一助となるでしょう。
知らなかった借金と相続放棄の期限
相続放棄には期限が定められていますが、相続人が知らなかった借金については、その存在を知ったあとに相続放棄が認められる可能性があります。
まずは、相続放棄の原則的なルールと、その例外について正しく理解するところから始めましょう。
相続放棄の原則的な期限(3ヵ月)
相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と法律で定められています(民法第915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
注意すべきは、起算点が「被相続人が亡くなった日」ではなく、ご自身が相続人であることを「知った時」である点です。
この期間内に相続財産を調査し、単純承認(すべて相続する)、限定承認、相続放棄のいずれかを選択し、家庭裁判所で手続を行う必要があります。
期限後でも認められる例外
ご自身が相続人であることを知った時から3ヵ月の期間を過ぎてしまったあとでも、相続放棄が認められるケースがあります。
最高裁判所の判例では、被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合、熟慮期間は「相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常これを認識するべき時」から起算される、と示されています。
つまり、借金の存在をあとから知った場合、その時点から3ヵ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があるのです。
期間経過後の相続放棄が認められる3つの条件
3ヵ月の期間が過ぎたあとに相続放棄が認められるためには、先ほど述べた「相当な理由」が必要であり、その場合に相続放棄の申述を受理してもらうには、家庭裁判所を納得させるだけの特別な事情を適切に説明することが必要です。
ここでは、その代表的な3つの条件を具体的に見ていきましょう。
被相続人と疎遠だった
被相続人と長年にわたり音信不通であったり、生前の交流がほとんどなかったりした事実は、相続放棄が認められる有力な事情となり得ます。生活状況や経済状態をまったく知らず、借金の存在を予見できなかった、と主張できるからです。
裁判所に対して、生前の関わりが希薄であったことを客観的な事実として示すことで、「相続財産がないと信じたこと」に相当な理由があったと判断されやすくなります。
相続財産がないと信じていた
被相続人の生前の言動や生活状況から、相続財産はプラスもマイナスもないと信じ込んでいた場合も、期間経過後の相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、被相続人から「借金はない」と明確に伝えられていた、あるいは質素な生活ぶりから多額の借金を抱えているとは到底考えられなかった、といった事情です。
単に知らなかったというだけでなく、財産がないと信じたことに客観的に見て無理からぬ事情があったと説明できることが重要となります。
財産調査が困難だった
相続開始後、被相続人の財産調査を行ったものの、借金の存在を発見することが著しく困難だったという事情も考慮されます。
例えば、被相続人が財産に関する資料を一切残しておらず、債権者から督促状が届くまで借金の存在を知る術がなかったケースです。
自ら財産調査を試みたにもかかわらず借金を発見できなかったという事実は、「相続財産がないと信じたこと」の相当な理由を補強する要素として、家庭裁判所に評価される可能性があります。
相続放棄が無効になるNG行為(法定単純承認)
相続放棄を検討している場合に、特定の行為をすると相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
これを「法定単純承認」と呼び、ここでは特に注意すべき3つのNG行為を解説します。
遺産を処分・使用する
相続財産の一部または全部を処分する行為は、法定単純承認にあたります。具体的には、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使ったり、不動産や自動車を売却・名義変更したりする行為が該当します。
亡くなった方の財産を使ってしまうと相続の意思があるとみなされ、あとで借金が発覚しても相続放棄は原則として認められません。
ただし、社会通念上相当な範囲の形見分けや、葬儀費用を遺産から支払う行為については、例外的にその後相続放棄が認められる場合もありますが、判断が難しいため避けるのが無難でしょう。
借金を一部でも返済する
債権者から督促を受けた際に、預貯金などの相続財産を用いて、亡くなった方の借金の一部でも返済してしまうと、相続を承認したとみなされます(民法第921条1号)。
たとえ少額であっても、相続財産の中から返済することは、自分が相続人として債務を引き継いだと認める行為と解釈されるのです。
道義的な責任を感じて支払いに応じたくなるかもしれませんが、相続放棄の権利を失うきわめてリスクの高い行為であるため、慎重に判断するようにしましょう。
遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行い、その内容を記した遺産分割協議書に署名・押印した場合も、単純承認したものとみなされます。
プラスの財産を分ける話し合いに参加した時点で、相続する意思があると判断されるからです。後に多額の借金が発覚しても、遺産分割協議を成立させていると、原則として相続放棄はできません。
借金の有無が不明な段階で、安易に遺産分割協議に応じるべきではありません。
期限後の相続放棄・手続の4ステップ
3ヵ月の期間を過ぎてしまった場合の相続放棄は、通常のケースよりも慎重な手続が求められます。
ここでは、家庭裁判所に申述を受理してもらうための具体的な4つのステップを解説します。
STEP1:証拠を集める
期限後の相続放棄を認めてもらうためには、「相続財産がないと信じたことに相当な理由があった」ことや、「借金の存在を知った経緯」を客観的に証明する証拠がきわめて重要です。
有効な証拠の例は以下のとおりです。
- 手紙やメールの履歴
- 債権者からの督促状(日付が重要)
- 財産調査を依頼した弁護士などの専門家とのやり取り
これらの証拠を揃えることで、家庭裁判所に対する主張の説得力が増すでしょう。
STEP2:必要書類を準備する
家庭裁判所に相続放棄を申立てる(申述する)には、定められた書類を正確に準備する必要があります。
基本的な書類は以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(ご自身)の戸籍謄本
これらの書類は、被相続人の最後の住所地や本籍地の役所で取得します。
期間経過後の申述では、これらに加えて次のステップで説明する事情説明書が事実上、不可欠です。
STEP3:事情説明書を作成する
期間経過後の相続放棄手続において、最も重要なのが「事情説明書(上申書)」の作成です。
この書類には、なぜ3ヵ月の期間内に相続放棄ができなかったのか、その具体的な理由を詳細に記載します。
記載すべき主な内容は以下のとおりです。
- 相続人であることを知った時から3ヵ月以内に放棄できなかった理由
- 被相続人との関係性
- 相続財産がないと信じた理由・経緯
- 借金の存在を知った経緯と時期
これらの事実を時系列に沿って、矛盾なく具体的に記述する必要があります。この事情説明書の内容が、申述が受理されるか否かを左右するといっても過言ではないでしょう。
STEP4:裁判所からの照会書に回答する
相続放棄の申述書と事情説明書を家庭裁判所に提出すると、後日、裁判所から「照会書(回答書)」という書類が送られてくることがあります。
これは、申述が本人の真意に基づくものか、法定単純承認にあたる行為をしていないかなどを確認するための質問状です。
照会書への回答内容は、申述を受理するかどうかの重要な判断材料となります。先に提出した事情説明書の内容と食い違いがないよう、慎重かつ誠実に回答を作成し、期限内に返送しましょう。
亡くなった方の借金を正確に調べる方法
相続放棄を判断する前に、亡くなった方の財産、特に借金の全体像を正確に把握することが不可欠です。ここでは、借金を調べるための具体的な方法を3つ紹介します。
信用情報機関へ照会する
亡くなった方がクレジットカード会社や消費者金融、銀行などから借り入れをしていた場合、その契約内容や残高は信用情報機関に登録されています。
相続人であれば、必要な書類を揃えることで、以下の信用情報機関に情報開示請求を行えます。
- CIC
- JICC
- KSC
これにより、把握していなかった借金が見つかる可能性があります。手続は郵送でも可能です。
郵便物や遺品を確認する
最も基本的かつ重要な調査方法が、亡くなった方の自宅に届いた郵便物や遺品の確認です。
以下のような書類が残されていないか、隅々まで探しましょう。
- 金融機関からの通知
- カード会社の利用明細書
- 消費者金融からの督促状
- ローン契約書
また、亡くなったあとしばらくして相続人宛てに届く郵便物は、債権者が死亡の事実を知って請求を始めている可能性があり、重要な手がかりとなります。見慣れない会社からの封書は安易に捨てずに必ず中身を確認してください。
預金口座の履歴を確認する
亡くなった方名義の預金通帳を確認したり、金融機関から取引履歴明細書を取り寄せたりすることで、借金の存在が判明することがあります。
特定の会社名での定期的な引き落としがあれば、それはローンの返済である可能性が高いでしょう。
また、キャッシュカードの利用履歴から、キャッシングを利用していた形跡が見つかることもあります。入出金の流れを丹念に追うことで、借入先や返済状況を把握する一助となります。
相続放棄以外の選択肢「限定承認」
相続財産に借金があるものの、プラスの財産も存在し、放棄すべきか迷う場合があります。そのような状況で有効なのが「限定承認」という手続です。ここでは、限定承認の概要と活用できるケースを解説します。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を返済する責任を負う相続方法です。
この手続を行えば、あとから想定外の多額の借金が判明した場合でも、相続した財産を超えて自分の財産から返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てる必要があり、手続も複雑で時間がかかるというデメリットがあります。
限定承認が有効なケース
限定承認は、借金の総額が不明確なものの、どうしても手放したくないプラスの財産(自宅や事業用資産など)がある場合に特に有効な選択肢となります。
また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断がつかない場合にも、リスクを限定しつつ財産を引き継げる可能性があります。
ただし、手続が煩雑であるため、利用を検討する際は弁護士などの専門家への相談が不可欠です。
弁護士などの専門家への相談
期限後の相続放棄や限定承認は、法的な知識と専門的な手続が不可欠です。ご自身で進めるのは困難なため、弁護士などの専門家への相談が賢明といえるでしょう。
なぜ弁護士などの専門家に相談すべきか、そして誰に相談すればよいかを解説します。
弁護士などの専門家への相談を推奨する理由
期限後の相続放棄が受理されるかは、最終的に家庭裁判所の判断に委ねられます。
弁護士などの専門家、特に弁護士に依頼すれば、法的な観点から受理される可能性を高めるための的確なアドバイスを受けられます。
説得力のある事情説明書の作成や、裁判所とのやり取りなど、専門的な知識が要求される場面で全面的にサポートしてもらえる点も大きなメリットです。
手続の負担と精神的な不安を軽減し、ご自身の財産を守るためにも、弁護士などの専門家の力を借りることが賢明な策といえるでしょう。
弁護士と司法書士の違い
相続放棄の手続は、弁護士と司法書士のどちらにも相談できます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 司法書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|
| 主な業務 | 家庭裁判所に提出する申述書の作成代行 | 書類作成に加え、代理人として裁判所とのやり取りや債権者との交渉が可能 |
| 適したケース | 書類作成のサポートを主として希望する場合 | 3ヵ月の期間を過ぎた複雑なケース、ほかの相続人と意見が対立している場合など、広範な対応を望む場合 |
特に、3ヵ月の期間を過ぎてしまった複雑なケースや、他の相続人と意見が対立している場合には、より広範な代理権を持つ弁護士への相談が適しているといえるでしょう。
まとめ
本記事では、3ヵ月の期間後に亡くなった方の借金が発覚した場合の対処法を解説しました。
借金の存在を知ってから3ヵ月以内であれば、「財産がないと信じた相当な理由」などを家庭裁判所に説明することで相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、遺産を処分・使用してしまうと放棄できなくなるおそれがあるため、避けるようにしましょう。
期間経過後の相続放棄は手続が複雑で、専門的な判断が不可欠です。
アディーレ法律事務所では、相続問題に関するご相談を承っております。予期せぬ借金が発覚してお困りの方は、手遅れになる前に、まずはお気軽にご連絡ください。