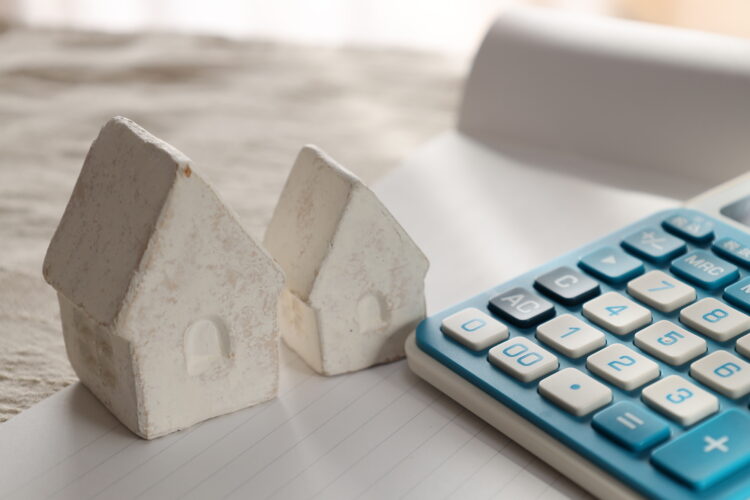「遺言により、他の相続人がすべての財産を相続することになった。」
もしあなたがそのような状況に直面したら、どうすればよいのでしょうか。
実は、法律上、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」が保証されています。
この記事では、この遺留分を侵害された場合に請求できる「遺留分侵害額請求」について、その仕組みや手続き、新旧制度の違いまで、弁護士がわかりやすく解説します(法改正前は、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました)。
この記事を読めば、あなたが直面している問題の解決策が見つかるかもしれません。
※従来の遺留分減殺請求は、2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分侵害額請求権へと権利の内容や名称が変更されました。この記事では、主に遺留分侵害額請求権について説明します。
ここを押さえればOK!
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月の法改正により、金銭での解決を原則とする「遺留分侵害額請求」に変わりました。これにより、不動産などが共有状態となることで生じていたトラブルが減り、より円滑な解決が可能になりました。
請求できるのは、配偶者や子ども、父母などの兄弟姉妹以外の相続人で、期限は、相続の開始と遺留分侵害があったことを知った時から1年、または相続開始から10年以内です。
請求手続きは、まず話し合いでの解決を目指し、合意できない場合は内容証明郵便を送付します。それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、最終的に裁判で決着をつけることもあります。
遺留分の計算や手続きは複雑なため、弁護士に相談・依頼することで、手続きを任せて適切な解決を目指すことができるでしょう。
遺留分侵害額請求でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは?基本的な仕組み
「遺言で、他の相続人がすべての財産を相続することになった。」
そんなときでも、一定の相続人には、最低限の遺産を受け取る権利があります。それが「遺留分」です。
遺留分侵害額請求は、この遺留分を侵害された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する手続きを指します。
(1)遺留分とは「最低限保証された相続財産」のこと
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)について、法律上保証されている、遺産の最低限の取り分のことです(民法1042条1項)。
亡くなった人(被相続人)が遺言を残した場合、その意思が尊重されるのが相続の原則です。
しかし、近しい家族であれば、相続で一定割合の遺産がもらえると期待するのが通常ですし、また相続できなければ生活に困ることがあるかもしれません。
そこで、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という権利が定められています。
(2)遺留分侵害額請求は「遺留分を侵害された人」が行う請求
遺言によっても「遺留分」を奪うことはできません。
したがって、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分侵害額請求を行う条件と注意点
遺留分侵害額請求を行うには、いくつかの条件を満たす必要があります。
具体的に誰が、いつまでに請求できるのか、また、どのような財産が対象になるのかを見ていきましょう。
(1)誰が遺留分を請求できる?
遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者、子ども、父母や祖父母(直系尊属)等が該当します。
一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
例えば、亡くなった人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもです。仮に、遺言書に「すべての財産を慈善団体に寄付する」と書かれていた場合、配偶者と子どもは遺留分がありますので、両者とも遺留分相当額を請求することができます。
一方、亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合(父母(祖父母)・子(孫)はいない)、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹です。仮に、「全ての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言がある場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、請求することはできません。
(2)遺留分を請求できる期限
遺留分侵害額請求ができる期間には制限があり、下記いずれかの早い方が期限となります(民法1048条)。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間
- 相続開始の時から10年間
この期間を過ぎてしまうと、遺留分を請求する権利は時効で消滅します。
例えば、遺言書に自分の遺留分が侵害されていると知ったのが相続開始から半年後だった場合、その時から1年以内に請求しなければなりません。
そのため、遺留分を侵害する遺言書の内容を知ったら、早めに行動を起こすことが重要です。
(3)遺留分侵害額請求の対象となる財産・人
請求の対象となる財産は、被相続人が亡くなる前に贈与した財産や、遺言によって他人に遺贈された財産です。
また、請求すべき人は、受贈者(贈与によって財産を得た者)又は受遺者(遺言によって財産を得た者)です。
遺留分侵害額について、具体的に誰が負担するのか、その対象や順序は、民法で定められています(民法1047条1項)。
次のように決められた遺贈・贈与の順位のとおりに、上位の遺贈・贈与を受けた人から順番に、遺留分侵害額請求に相当する金銭を支払う義務を負うことになります。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
参考:民法1047条|e-gov
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
相続人への生前贈与は、婚姻・養子縁組・生計のためにした贈与に限り、基本的に相続開始前の10年間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。また、相続人以外への贈与は、基本的に相続開始前の1年間に限られます(民法1044条1項、3項)。
遺言による遺贈は、遺留分を侵害するものであれば、そのすべてが対象です。
遺留分を誰に、いくら請求するかは、過去の生前贈与を含めた複雑な計算が必要になりますので、1人で計算して請求するのは困難なケースもあります。
「侵害された遺留分を請求したい」と考えている方は、一度遺留分侵害額請求を扱っている弁護士に相談する事をお勧めします。
遺留分減殺請求の具体的な手続きの流れ
遺留分を侵害されていることがわかったら、時効消滅する前に、早急に手続きを進めることが大切です。
ここでは、遺留分を請求する際の一般的な流れを解説します。
(1)話し合いでの解決を目指す
遺留分侵害額の請求は、相手方に対して、遺留分の権利を行使する意思表示をする必要があります。
そこで、遺留分を計算できたら、請求すべき相手に対して、実際に遺留分侵害額相当額の支払いを請求します。
遺留分は法的に認められた権利ですので、遺留分が侵害されている以上、相手方も支払いに応じざるをえません。
相手と話し合いが可能であれば、話し合いでの解決を目指すのが、早期解決に繋がります。
(2)内容証明郵便を送付する
話し合いが進まない、請求期限が迫っている、という場合には、内容証明郵便を利用して遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額を請求する意思表示は口頭でも可能ですが、「言った言わない」というトラブルを避けて証拠を残すために、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
送付する際には、遺留分侵害額請求を行うことを明確に記載するようにします。
後々調停や訴訟の手続をとらざるをえなくなった際にも、内容証明郵便は証拠になります。
弁護士に対応を依頼すれば、あなたの代わりに適切な文書を作成し送付してくれるでしょう。
(3)話し合いで解決しない場合は調停を申し立てる
話し合っても合意できない場合や、そもそも話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停の申立てだけでは、相手方に遺留分の権利を行使する意思表示をしたことにはなりませんので、別途内容証明郵便等を送って意思表示する必要があることに注意してください。
調停は、調停委員が間に入り、当事者間の合意を目指し、話し合いを円滑に進める手続きです。具体的には、調停委員が当事者双方から個別に話を聞き、資料を確認したり、資料の提出を促したりします。また、双方が合意できるよう、助言や和解案を提示したりして、解決を目指すのです。
それでも調停で合意に至らない場合は、地方裁判所に訴訟を提起し、証拠を提出したうえで、裁判によって決着をつけることになります。
これらの手続きは、法律や実務の知識が必要となるため、弁護士に依頼してサポートを受けることをお勧めします。
旧制度「遺留分減殺請求」との違いとは?
2019年7月1日の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」という制度に変わりました。ここでは、旧制度と新制度の主な違いを解説します。
(1)「金銭」での解決が原則になった
旧制度の「遺留分減殺請求」では、遺留分を侵害している相手から、侵害された分の現物(不動産など)を取り戻すことが原則でした。
しかし、新制度の「遺留分侵害額請求」では、侵害された遺留分を金銭で支払うことが原則となりました。
これにより、財産を共有することなく、金銭で清算できるため、より円滑な解決が期待できるようになりました。
(2)なぜ制度が変わったのか?
旧制度では、遺留分減殺請求で現物(不動産)が返還されることによって、不動産が遺留分権利者と受遺者又は受贈者で共有されることになり、その共有関係を解消するために新たな紛争になるケースが多く見られました。
そこで、相続を巡る紛争をより簡潔に解決するため、遺留分を金銭で請求する「遺留分侵害額請求」へと改正されたのです。この改正により、金銭請求で解決することが原則となったので、複雑な共有関係が生じることなくなりました。
遺留分侵害額請求は弁護士に相談すべき?
遺留分に関する手続きは、遺留分侵害額の計算から請求相手の確定、請求手続きなど法律の条文の理解と、実務の知識が必要となります。
そのため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(1)弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは、請求手続きをすべて任せられることです。
遺留分の正確な計算や、必要書類の準備、相手方との交渉、調停や訴訟の手続きなど、法律や実務の知識がなければ難しい作業を一任できます。
また、弁護士が代理人となることで、相手方と直接やり取りをする精神的な負担も軽減されます。
さらに、法的な観点から適切な道筋を提案してくれるため、ご自身の権利を守るサポートを受けることができるでしょう。
(2)弁護士費用はどのくらいかかる?
弁護士費用は、事務所や事案の内容によって異なります。
一般的には、相談料、着手金、成功報酬、実費、出張費などがかかります。着手金は、依頼した時点で支払う費用で、成功報酬は、遺留分を無事獲得できた場合にその経済的利益に応じて支払う費用です。
ホームページで費用体系を明確にしている法律事務所も多いので、一度気になる法律事務所のホームページを確認してみるとよいでしょう。
相談料を初回無料で対応している事務所もあります。まずは相談してみて、費用について分からない点も確認するとよいでしょう。
【まとめ】
遺留分侵害額請求は、遺言書などによって遺留分を侵害された一定の相続人が、その侵害額相当額を請求するための法的な手続きです。請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人で、遺留分侵害を知ってから1年、または相続開始から10年以内という期限があります。
旧制度では現物での請求が原則でしたが、現在は金銭での解決が基本となり、より円滑な解決が可能になりました。しかし、遺留分の計算や手続きは複雑なため、ご自身で進めるには多くの時間と労力がかかるでしょう。
遺留分を請求したいが何から始めればよいかわからない、相手との交渉がうまくいかない、といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。