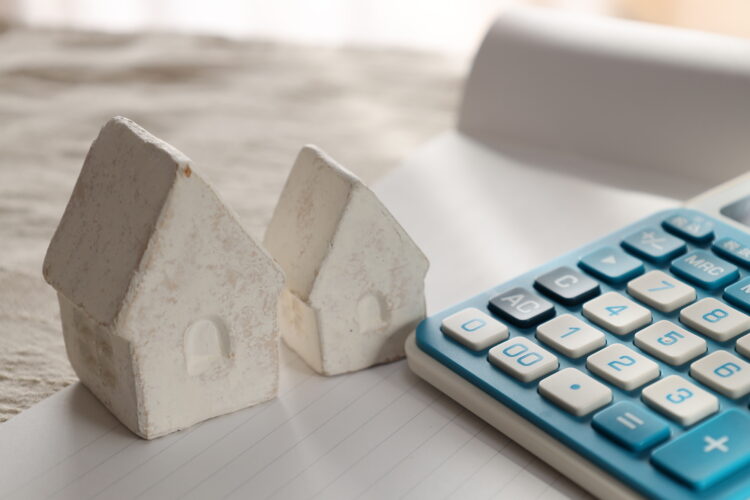「遺言書の内容に納得がいかない。故人の財産が、特定の相続人に偏っている。」
そのような状況に直面し、ご自身の正当な取り分である「遺留分」が侵害されているのではないかと不安を感じていませんか?
特に、「遺留分を請求するのには時効がある」と聞き、もう手遅れかもしれないと焦っている方もいるかもしれません。
遺留分を請求する権利には、法的に定められた期限があり、これを過ぎると大切な権利を失ってしまうことになります。
本記事では、「遺留分侵害額請求」(法改正前は、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました)の時効について、その正しい知識と具体的な対処法をわかりやすく解説します。
※従来の遺留分減殺請求は、2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分侵害額請求権へと権利の内容や名称が変更されました。2019年6月30日までに亡くなった方の相続については、遺留分減殺請求となります。この記事では、主に遺留分侵害額請求権について説明します。
ここを押さえればOK!
1つは、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間の時効です。この時効は、相手が主張した場合に権利が消滅します。
もう1つは、相続開始から10年間の除斥期間です。この期間は、10年が経過すると自動的に権利が消滅します。
1年間の時効の起算点である「知った時」は争いになることがあるため、被相続人の死亡日から1年以内に内容証明郵便で意思表示をしておくのが賢明です。 また、内容証明郵便を送って請求意思を示した後も、金銭債権として別途5年の時効が適用されるため、速やかに訴訟などの手続きを進める必要があります。
遺留分侵害額請求には法的な判断や手続きが伴うため、権利を失わないようにするためにも、弁護士に相談することが推奨されます。
遺留分の請求をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求のご相談は何度でも無料!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
遺留分侵害額請求の時効は2種類|1年と10年の違いを解説
遺留分を請求する権利には、期限が2つ存在します。どちらの期限も非常に重要ですので、ご自身のケースに当てはめて確認しましょう。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
引用:e-Gov法令検索
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(1)相続開始と遺留分侵害を「知った時」から1年(時効)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。
この「時効」は、期限を過ぎても権利が自動的に消滅するわけではなく、相手方が時効を主張した場合に権利が失われるという特徴を持ちます。
(2)相続開始の時から10年(除斥期間)
もう一つの期限は、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始した時から10年です。
この10年の期限は「除斥期間」と呼ばれ、1年間の時効とは法的性質が異なります。
除斥期間は、相続人の事情に関わらず自動的に進行し、10年が経過すると遺留分を請求する権利は消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求の時効消滅を防ぐ方法
では、1年間の時効が迫っている場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
内容証明郵便で意思表示の証拠を残す
遺留分の時効を止めるには、相手に対して「遺留分を請求します」という意思表示をすることが必要です。
口頭でも有効とされていますが、後々のトラブルを防ぐためには書面で行うことが重要です。遺留分侵害額請求の意思表示をしたこと、した日など明確にするために、配達証明付きの内容証明郵便で行うとよいでしょう。
【内容証明の例】
〇〇殿 〇年〇月〇日
被相続人〇〇の令和〇年〇月〇日付自筆証書遺言の遺言内容は、私〇〇の遺留分を侵害しています。
したがって、私は、貴殿〇〇に対し、遺留分侵害額請求を行います。
「知った時」がいつか争いになるケースもある
遺留分侵害の1年間の時効は相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を「知った時」から始まります。
しかし、この「知った時」=時効の起算点がいつなのか、争いになることがあります。
例えば、被相続人の死亡日から1年を過ぎてから遺留分侵害額請求権を行使した場合、相手方から「もっと前に知っていたはずだ」と主張され、時効を理由に請求を拒否される可能性があるのです。
いつ知ったかについて争いになると、訴訟を提起したうえで、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈を「知った時期」について、裁判で立証しなければなりません。その結果、時間も費用もかかってしまいます。
そのため、遺留分侵害額請求権の行使は、起算点の争いの余地がないように、被相続人の死亡日から1年以内に行うとよいでしょう。
例えば、被相続人の死亡と、遺留分を侵害するような遺言の存在を知ったら、その両方を知った時が時効の起算点とされる可能性が高いでしょう。遺留分侵害額請求を行使する側としては、その時から1年以内に意思表示を行う必要があります。
1年以内に請求しても、放置していれば5年の時効にかかる可能性
遺留分侵害額請求権は、「侵害された遺留分に相当する金銭を支払うよう求める権利」です。一度行使した後は一般の金銭債権として、別途5年の時効が適用されます(民法166条1項号)。
(債権等の消滅時効)
引用:民法|e-gov
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
したがって、知った時から1年以内に内容証明郵便を送って意思表示をしたとしても、その後放置していると、別途5年の時効で消滅してしまいます。
そのため、1年間以内に内容証明郵便を送った後も、実際に遺留分を取り戻すために、速やかに話し合いを進めたり、訴訟提起するなどの手続きを進める必要があります。
遺留分侵害額請求はなぜ弁護士へ相談した方がいいのか
ここまで見てきた通り、遺留分を請求する際には複数の期間制限が存在し、「知った時」が争いになるケースや、請求後に新たな時効が発生するなど、法的な判断が必要な面があります。
また、遺留分侵害額請求は、正しい相手に意思表示をしなければ、行使したことになりません。行使すべき相手は、民法に規定されていますが(民法1047条1項)、法的な知識がなければ正確に特定することが難しいケースもあります。
さらに、遺留分侵害額請求権は法律で決められた権利なので、遺留分侵害の事実があり、時効期間内に請求された以上、相手方は応じざるを得ないのですが、「お金を渡したくない」という動機から交渉がスムーズに進まないケースもあるでしょう。
これらの問題を自力で解決するのは難しく、解決できたとしても労力がかかり、精神的なストレスもかかります。遺留分に関する問題は、放置すると権利を失ってしまうリスクがあるため、早い段階で相続問題を扱っている弁護士に相談・依頼し、確実な方法で遺留分侵害額請求権を行使し、回収してもらうことをお勧めします。
【まとめ】
本コラムでは、遺留分を請求する権利には、相続開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈を「知った時」から1年間の時効と、相続開始から10年間の除斥期間という2つの重要な期限があることを解説しました。
特に、1年間の時効は「知った時」について争いになるケースがあるため、被相続人の死亡日から1年以内に意思表示をして行使することをお勧めします。行使後も、金銭債権として別途5年の時効にかかるリスクがありますので、速やかに手続きを進めましょう。
遺留分の侵害を知った後、放置してしまうと取り返しのつかない事態になりかねません。 法的知識が求められる面もあるため、不安を感じた際には一人で悩まず、アディーレ法律事務所にご相談ください。