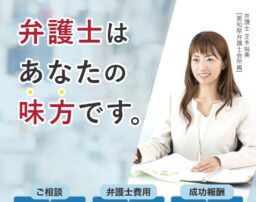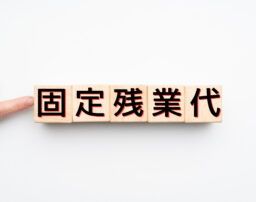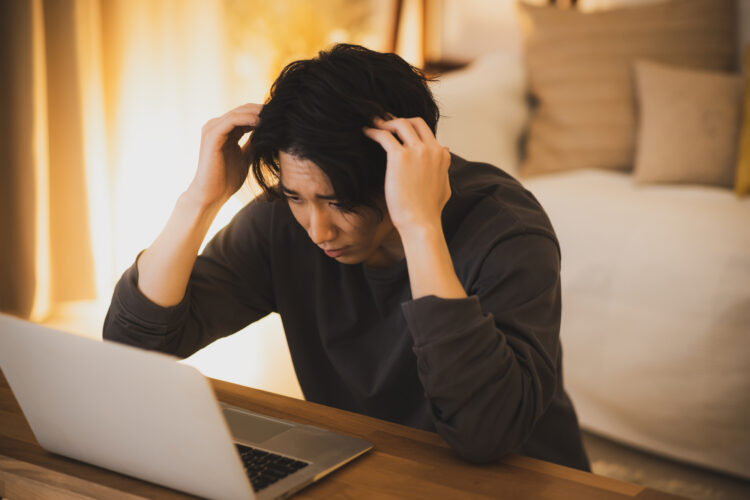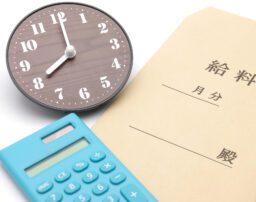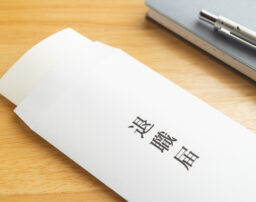「長時間労働を強いられているのに、裁量労働制で働いているから残業代が支払われない……」
実は、裁量労働制で働いているからといって残業代が出ないということはありません。
裁量労働制で働いていても、時間外労働や休日労働、深夜労働をすると残業代などの割増賃金が発生することがあります。
このことを知っておくと、裁量労働制で働いていても残業代が出る場合には適切に残業代を請求することができます。
この記事では、
- 裁量労働制の内容
- 裁量労働制でも残業代が出る場合
- 裁量労働制における残業代の計算方法
について弁護士が解説します。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
裁量労働制とはどのような制度なのか
「裁量労働制」とは、業務遂行に労働者の大幅な裁量を認める必要がある一定の業務について、実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間だけ働いたとみなす制度です(労働基準法38条の3第1項、労働基準法38条の4第1項)。
裁量労働制は、仕事に対する成果さえきちんと上げていれば労働時間が短くても問題ではないという考え方に基づいています。
そもそも「裁量」にはその人の考えによって判断し、処理するという意味があります。
裁量の対義語は、「決裁」「裁断」であり、誰かに決めてもらうことをいいます。
次で解説する通り、裁量労働制はどのような業務にでも適用できるわけではなく、適用の対象となる業務が限定されています。
裁量労働制のタイプ
裁量労働制には次の2つのタイプがあります。
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
どちらのタイプでも、残業代の計算方法は同じですが、どのような業務が裁量労働制の対象になるのかによって名称が異なります。
これらの2つのタイプの裁量労働制について、解説いたします。
(1)専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の対象となる業務とは、業務の性質上、業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、使用者が、業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関し、労働者に具体的な指示をすることが困難な一定の業務をいいます(労働基準法38条の3第1項1号)。
専門業務型裁量労働制の対象となる業務は限定されており、次の業務が該当します(労働基準法施行規則24条の2の2第2項)。
◆対象業務
- 新商品または新技術の研究開発
- 人文・自然科学の研究
- 情報処理システムの分析・設計
- 新聞・出版の取材・編集
- 放送番組制作のための取材・編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等のデザイナー
- 放送番組、映画等の制作のプロデューサー・ディレクター
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェア開発
- 証券アナリスト
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
- 学校教育法に規定する大学における教授研究
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
(2)企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制の対象となる業務とは、「業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し、使用者が労働者に具体的な指示をしない業務」のことをいいます(労働基準法38条の4第1項第1号)。
この対象業務を適切に遂行するための知識・経験等を有する労働者(例:3~5年程度の職務経験のある労働者)にのみ、企画業務型裁量労働制が適用されます(同項2号)。
裁量労働制における出退勤時間
裁量労働制の下では、基本的には出退勤時間の指定はなく、労働者が出退勤時間を自由に決めることができます。
また、実際の労働時間が何時間であっても(4時間でも10時間であっても)賃金は変わりません。
裁量労働制における割増賃金
裁量労働制では、一定の労働時間働いたと「みなされる」ことから、割増賃金が発生しないと誤解している方も多いです。
しかし、次の通り、裁量労働制でも割増賃金は発生します。
計算してみましょう。
裁量労働制の割増賃金の計算方法
法律上、時間外労働、休日労働、深夜労働をすると割増賃金が発生します。
それぞれの割増賃金の計算方法について、ご説明します。
時間外労働
裁量労働制であっても通常の勤務体系の場合と時間外労働の計算方法は同じです。
すなわち、時間外労働の割増賃金は次の通り計算することができます。
割増賃金=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金
ア 残業時間
労働したとみなされる時間数が、法定労働時間(原則として、1日8時間または週40時間)を超えている場合には、法定労働時間を超えた分が、残業時間(「時間外労働の時間」)となります。
また、所定休日(※)に労働させられた場合、「所定休日の実際の労働時間+その週の本来の労働日に労働したとみなされる時間」が原則として週40時間を超える部分が、時間外労働の残業時間となります。
※休日は法定休日(原則週1回)とそれ以外の休日である所定休日の2種類があります。例えば、週休2日制の会社であれば、原則1日が法定休日で、残り1日が所定休日となります。
【例】
例えば、裁量労働制が採用されている会社(週の法定労働時間40時間が適用される会社)において、労働したとみなされる時間数が、9時間と決められているとします。
この場合、法定労働時間である1日8時間を1時間超えていますので、この1時間が時間外労働となります。
週5日勤務の場合、毎日1時間時間外労働が発生しますので、1週間に5時間の時間外労働が発生します。
さらに、同じ週の所定休日に、6時間出勤した場合は次のようになります。
↓
まず、平日の労働時間は9時間×5=45時間です。そして、所定休日に6時間出勤することでその週の労働時間は計51時間となります。
すると、この週の労働時間は、法定労働時間である週40時間を11時間超えたことになります。そのため、この週の時間外労働時間の合計11時間となります。
イ 割増率
裁量労働制であっても通常の勤務体系の場合と割増率は同じです。
すなわち、時間外労働の場合の割増率は以下の通りです。
| 時間外労働が月60時間までの部分 | 1.25倍以上 |
| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 1.5倍以上(※) |
ウ 基礎賃金
次に、基礎賃金の計算方法について、解説いたします。
裁量労働制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。
1.1時間当たりの基礎賃金の計算方法
【月給制の場合】
月給の基礎賃金÷(※)1年間における1ヶ月平均所定労働時間
※1年間における1ヶ月の平均所定労働時間
=1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12
【年俸制の場合】
1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間
【歩合給の場合】
1ヶ月の歩合給÷その月の総労働時間
ここでいう基礎賃金とは、次の2で解説の通り、一定の賃金を控除したものとなります。
2.基礎賃金の算定にあたり、給料から控除される賃金
基礎賃金は、定時の労働時間に対する賃金から、以下の賃金を控除した金額となります。
- 個人の事情に基づき払われている賃金(家族手当など)
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
【休日労働の場合】
休日労働の割増賃金は次の式で計算できます。
休日労働の割増賃金=残業時間×割増率1.35以上×1時間当たりの基礎賃金
法定休日の労働のみ、休日労働の残業時間となり、法定休日の労働時間全てが残業時間になります。
基礎賃金は前述の通りの計算方法です。
【深夜労働の場合】
深夜労働の割増賃金は次の式で計算できます。
深夜労働の割増賃金=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金
ア 残業時間
22~9時までの労働時間全てが深夜労働となります。
イ 割増率
0.25以上
| 22~5時の間の労働(他の種類の残業と重複がない場合) | 0.25倍以上 |
| 時間外労働が0時間を超えて月60時間までの時期に、深夜労働した部分 | 1.5倍以上 |
| 時間外労働が月60時間を超えた時期以降に、深夜労働した部分 | 1.75倍以上(※) |
| 法定休日に深夜労働した部分 | 1.6倍以上 |
ウ 基礎賃金
基礎賃金は前述の通りの計算方法です。
裁量労働制と混同されがちな「フレックスタイム制」とは
裁量労働制と混同されがちな制度として、「フレックスタイム制」があります。
「フレックスタイム制」とは、一定の期間のなかで、一定時間労働することを条件として、自由な時間に出勤・退勤できる制度です。
裁量労働制の場合は、実際に働いたかどうかに関係なく、一定時間働いたとみなされますが、フレックスタイム制の場合は、実際に働いた時間が労働時間となる点で異なります。
裁量労働制における弁護士への相談事例
裁量労働制に関する弁護士への相談事例を次のとおり解説いたします。
(1)裁量労働制だからと長時間労働を強いられる
裁量労働制だからといって、長時間労働を強いてよいわけではありません。
長時間労働により過労死に至ることもあります。
長時間労働を強いられている場合には、労働基準監督署に申告し、指導してもらうことが可能です。
(2)裁量労働制だからと残業代を支払わない
裁量労働制でも、残業代を支給する義務があります。
それにもかかわらず、裁量労働制であるからといって残業代を違法にも支給しない企業があります。
この場合、労働基準監督署へ申告したり、残業代を請求したりしましょう。
なお、労働基準監督署に申告しても必ずしも動いてくれるわけではありません。
他方、弁護士に依頼すればあなたの味方となって、残業代請求をしてくれます。
【まとめ】裁量労働制でも残業代は出る
今回の記事のまとめは次の通りです。
- 裁量労働制では実際の労働時間に関係なく一定の労働時間だけ働いたとみなされる。
- 裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があり、業務の種類によって名称が異なる。
- 裁量労働制では出退勤時間は労働者が任意に決めることができる。
- 裁量労働制でも割増賃金は発生する。
- フレックスタイム制は自由な時間に出勤・退勤できるが、実際に働いた時間が労働時間となる点で裁量労働制と異なる。
- 裁量労働制だからと長時間労働を強いられたり残業代を支払われなかったりするという相談事例がある。
裁量労働制の制度によって何か不利になるような事態に遭遇していると感じたなら、自分だけで抱え込まないことが大切です。裁量労働制に限らず労働問題は法律が細かい上に、解決のためには会社とのハードな交渉が要求されるので弁護士に相談するとよいです。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年10月時点
裁量労働制の残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。