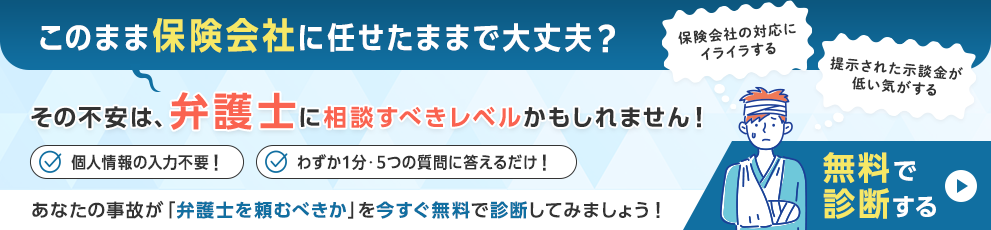「交通事故に遭ったが、加害者が任意保険に未加入だった。自賠責保険だけでは十分な補償を受けられない場合、加害者に請求するしかない?」
実は、ご自身が加入している任意保険に人身傷害保険を付帯させている場合、人身傷害保険に慰謝料や治療費を請求できる可能性があります。
人身傷害保険は、保険契約者本人やその家族、契約車両に乗っている人が交通事故の補償を受けられる保険のため、加害者の自賠責保険の補償が十分でなかった場合、人身傷害保険から補償を受けられることがあるからです。
このことを知っていれば、交通事故の補償を十分に受けられずに泣き寝入りするリスクを減らせるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 人身傷害保険とは
- 人身傷害保険の補償内容
- 人身傷害保険が役に立つケース
人身傷害保険とは
人身傷害保険は、一般的に自動車保険などの任意保険に特約として付帯しているものです。
保険会社によっては、「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」という名称になっていることもあります。
人身傷害保険を利用するための前提として、交通事故発生時点で、任意保険に人身傷害保険を付帯しておく必要があります。
(1)人身傷害保険の補償範囲
人身傷害保険は、補償範囲によって大きく次の2つに分かれています。
(ただし、詳細は加入している保険の約款を確認してください)
| 1.契約車限定タイプ | 契約している車に搭乗中の交通事故について補償を受けられる |
| 2.一般タイプ | 上記以外の交通事故についても補償を受けられる (例:契約車以外の車に搭乗中の事故、自転車搭乗中の事故、歩行中の事故、など) |
通常、契約車限定タイプは、一般タイプに比べて保険料が割安になっています。
(2)人身傷害保険の補償対象
人身傷害保険の補償対象は、保険契約者本人だけとはかぎりません。
契約車限定タイプの場合、契約車の搭乗中に交通事故に遭った人(同乗者など)も補償対象となり、一般タイプの場合、同乗者などのほか、契約者本人の家族も補償対象に含まれることがあります。
(3)人身傷害保険の補償項目と保険金額
人身傷害保険で補償される損害項目は、大きく次の3種類に分けられます。
- 精神的損害(入通院慰謝料、後遺症慰謝料など)
交通事故でケガをしたことによって受けた精神的苦痛に対する補償です。
- 積極損害(治療費など)
交通事故によって実際に生じた支出に対する補償です。
- 消極損害(休業損害、逸失利益など)
その交通事故がなければ得られたはずの利益を得られなくなったことに対する補償です。
人身傷害保険の保険金額は、保険会社が約款で定められた基準に基づいて算出します。
そのため、事故当事者の過失割合に関係なく、契約時の上限金額の範囲内で、実際の損害額が支払われることになります。
ただし、加害者側から賠償金等を受け取った場合には、その金額が相殺され、不足分があればその分のみ支払われることになります。
(4)人身傷害保険を請求しても、保険料や等級には影響しない
人身傷害保険のみの利用であれば、「ノーカウント事故」として扱われ、翌年の保険料が上がったり、保険の等級が下がったりすることはありません。
ただし、自身が加害者となってしまい、その賠償のために保険金を請求した場合や、物損や盗難が原因で保険金を請求した場合は、「ノーカウント事故」にはならないためご注意ください。
人身傷害保険が役に立つ5つの典型ケース
次に、人身傷害保険が交通事故で役に立つ典型的なケースを5つご紹介します。
(1)相手方が任意保険に加入していない場合
自賠責保険によるケガの補償額は、上限が120万円と決まっています。
そのため、120万円を超える損害が生じたにもかかわらず、事故の相手方が任意保険に加入していない場合、相手方の資力が少なければ120万円を超える部分の損害賠償を受け取れないリスクがあります。
このように、相手方から適切な賠償を受けられない場合、不足分を人身傷害保険から受け取れることがあります。
交通事故の相手方が任意保険未加入だった場合について詳しくはこちらをご覧ください。
保険未加入による3つの影響について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)自身の過失割合が大きい場合
交通事故の賠償金は、事故の当事者双方の過失割合によって金額が大きく左右されます。
自身の過失割合に応じて賠償金が減額されるため、自身の過失割合が大きいと判断されてしまった場合、受け取れる金額は損害額から大きく減額されてしまうことになります(このことを「過失相殺」といいます)。
この点、人身傷害保険は過失割合に関係なく保険金が支払われます。
そのため、契約時の上限金額や損害額にもよりますが、人身傷害保険は自身の過失割合が高い場合に役立つ保険であるといえるでしょう。
そもそも相手方の主張する過失割合に納得できません。
そのような場合はどうすれば良いですか?
過失割合は、交通事故の示談交渉の中でも揉めやすい項目のひとつです。
示談交渉において相手方の主張する過失割合に納得できないのであれば、弁護士にまず相談してみると良いでしょう。
また、弁護士であれば、法的な観点から的確な反論ができますので、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうと、相手方にこちらの主張を認めさせられる可能性が高まります。
(3)示談交渉が長引く場合
交通事故によるケガで後遺障害が残ってしまったケースでは、賠償金が高額になる傾向があります。
そのため、過失割合の設定や、逸失利益の算出などで互いの主張が対立しがちであり、示談交渉が難航しやすいでしょう。
示談交渉が長引けば、その分、賠償金を受け取れるのが先になってしまいます。
人身傷害保険を使えば、示談成立を待たずに、人身傷害保険で認定された保険金を受け取ることができます。
もっとも、人身傷害保険の上限金額や自身の過失割合などの条件によっては、人身傷害保険を請求するのが示談成立の前か後かによって、結果的に受け取ることができる金額の総額が変化する可能性があります。
そのため、人身傷害保険の請求を検討しているのであれば、示談成立のタイミングには慎重になった方が良いでしょう。
(4)自損事故の場合
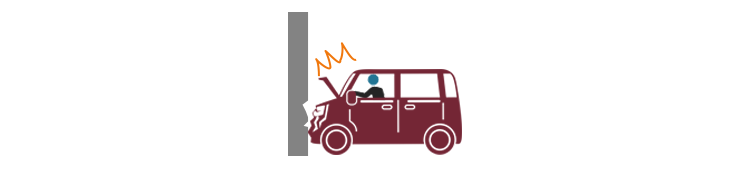
自身の過失によりガードレールや電柱にぶつかってしまった場合など、自損事故によって生じた損害は、自賠責保険で補償されることはありません。
損害賠償の請求相手である事故の相手方が存在しないためです。
しかし、自損事故の場合であっても、ケガをした場合であれば人身傷害保険を使って保険金を受け取れる可能性があります。
したがって、自損事故の場合には、人身傷害保険が役に立つといえるでしょう。
(5)ひき逃げに遭った場合

ひき逃げに遭って損害賠償の相手方が見付からない場合にも、人身傷害保険を使えば損害を補填できる可能性があります。
また、ひき逃げなど加害者不明の場合や、加害者が自賠責保険にすら加入していなかった場合には、政府の保障事業に治療費や慰謝料などの補償を求めることもできます。
なお、政府保障事業での賠償金の支払限度額は、自賠責保険と同額です。
ひき逃げに遭った場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【コラム~交通事故の賠償金請求のポイントは「弁護士に相談・依頼すること」~】
先ほども述べたように、人身傷害保険の請求には、適切なタイミングがあります。
弁護士に相談すれば、自身の場合の適切な請求のタイミング(示談成立前か後かなど)についてのアドバイスが受けられるでしょう。
そして、弁護士を利用するメリットは、人身傷害保険を請求する場合にとどまりません。
例えば、後遺障害に認定され得る症状の見落としを防ぐことが期待できるうえ、適切な後遺障害等級が認定されやすいポイントについて熟知しているため、適切な金額の賠償金が受け取れる可能性が高まります。
さらに、弁護士に示談交渉を依頼すれば、相手方の任意保険会社から受け取れる慰謝料の増額が期待できます。
また、自身が加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は基本的に保険で賄われることになります(金額の上限は存在します)。
そのため、自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているのか、付いていればその補償範囲について確認しておくことをおすすめします。
(加入者本人だけでなく、一定範囲の親族も補償対象になることがあります)
なお、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。
※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。
【まとめ】交通事故の加害者から十分な補償を受けられない場合は人身傷害保険の確認を!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 人身傷害保険は、一般的に自動車保険などの任意保険に特約として付帯しており、大きく分けて1.契約車限定タイプ、2.一般タイプの2つがある
- 人身傷害保険の補償対象は、保険契約者本人だけとはかぎらない
- 人身傷害保険を請求しても保険料や等級には影響しない
- 人身傷害保険が役に立つ典型的なケースは次の5つ
- 相手方が任意保険に加入していない場合
- 自身の過失割合が大きい場合
- 示談交渉が長引く場合
- 自損事故の場合
- ひき逃げに遭った場合
交通事故でケガをした場合であっても、必ず十分な補償を受けられるとはかぎりません。
人身傷害保険を請求したいと検討中の方は、自身が加入している任意保険の契約内容を確認したうえ、弁護士に相談してみることをおすすめします。