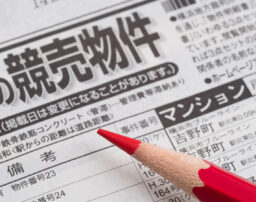「名誉毀損って、侮辱罪と何が違うの?ネットやSNSに悪口を書かれたらどうすればいい?」
現代社会では、インターネットやSNSの普及により、名誉毀損の問題がますます身近なものとなっています。
この記事では、名誉毀損罪の概要から、成立要件、侮辱罪との違いなどについて解説します。
名誉毀損に関する知識を深め、いざというときに適切な対応を取るための参考になれば幸いです。
ここを押さえればOK!
名誉毀損罪の成立要件は、(1)事実の摘示、(2)公然性、(3)名誉の毀損、(4)故意の存在です。侮辱罪との違いは事実の摘示の有無にあります。
名誉毀損罪の時効は犯罪行為終了から3年ですが、告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月です。
民事上の請求は、次のうち早く訪れた時点で時効となります。
・損害および加害者を知った時から3年間
・不法行為の時から20年間
なお、名誉毀損罪には公共の利害に関する場合の特例があり、一定の条件下では名誉毀損罪は成立しません。
被害者には、告訴や民事上の請求(削除請求、発信者情報開示請求など)といった対処法があります。複雑な手続きのため、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。
名誉毀損とは
名誉毀損とは、簡単に言うと他人の社会的評価を低下させるような事実を公然と示す行為のことをいいます。
具体的には、個人や法人(組織)の名誉を傷つけるような事実を第三者に伝えることで、その人や法人の社会的評価を損なう行為です。
犯罪としての名誉毀損罪は、刑法第230条に規定されていますが、名誉毀損に当たる行為に及んだ場合、刑事罰の対象となるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得ます。
刑法第230条
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名誉毀損は、インターネットやSNSの普及により、ますます身近な問題となっています。匿名性が高いインターネット上では、特に誹謗中傷やデマが拡散しやすく、被害者は増加傾向にあるといえるでしょう。
そのため、名誉毀損に関する法的知識を持つことは、現代社会において非常に重要といえます。
名誉毀損罪の成立要件
では、名誉毀損罪が成立するための要件を見てみましょう。
(1)事実の摘示
まずは、具体的な事実の摘示が必要です。
たとえば、「○○は前科者だ」「△△は職場の同僚と不倫している」などの具体的事実が挙げられます。
なお、対象は特定の個人や法人などである必要があります。
そのため、「○○県人」などを対象に悪口を言ったとしても、名誉毀損罪は成立しません。
そして、名誉毀損罪の成立に、示した具体的事実が真実かどうかは基本的に関係ありません。
ただし、対象が故人の場合、ウソの事実を摘示した場合でなければ、名誉毀損罪は成立しないとされています(刑法第230条2項)。
死者に関する事実については、歴史的批判を可能にする必要があるからです。
(2)公然性
次に、公然性が必要です。
つまり、不特定または多数の人が認識できる状態でなければなりません。
そのため、不倫している事実を、その両親に宛てた手紙で暴露したとしても、特定かつ少数と判断されれば、名誉毀損罪は成立しないと考えられます。
一方、インターネットの掲示板やSNS上に、誰かの名誉を毀損する事実を書き込んだ場合、実際にはほとんど誰にも見られていなかったとしても、名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。 多くの人が認識できる状態にあることには違いないからです。
(3)名誉の毀損
また、摘示された事実が、対象の社会的評価を害する事実であることが必要です。
もっとも、対象の社会的評価を害する危険性がある事実を摘示すれば足り、実際に社会的評価が下がったことまでは必要ありません。
(4)故意の存在
故意とは、簡単に言うと罪を犯す意思のことです(刑法第38条1項本文)。 つまり、自分の行為が他人の名誉を毀損することを認識していることが必要です。
ただし、名誉を毀損する目的で行ったことまでは必要ありません。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは?
名誉毀損罪と侮辱罪は、どちらも他人の名誉を傷つける行為についての犯罪ですが、その内容には違いがあります。両者の違いを一言で表すと、事実の摘示の有無です。
名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させる事実を公然と示す行為に成立し得る犯罪です。
一方、侮辱罪は、事実の摘示を伴わず、公然と他人を侮辱する言動に成立し得る犯罪です。
侮辱罪について定めた刑法第231条には、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とあります。
【名誉毀損罪と侮辱罪の違い】
| 名誉毀損罪 | 侮辱罪 | |
| 定義 | 公然と他人の社会的評価を低下させるような事実等を指摘する行為に成立し得る犯罪 | 事実等は指摘せず、公然と他人を侮辱する行為に成立し得る犯罪 |
| 具体例 | 「○○は前科者だ」と公然と発言する | 「○○はバカだ」と公然と発言する |
| 条文 | 刑法第230条 | 刑法第231条 |
このように、名誉毀損罪は具体的な事実を示す必要があるのに対し、侮辱罪は事実の摘示を必要としません。
名誉毀損罪の時効について
名誉毀損罪の時効は、犯罪行為が終わったときから3年とされています。
たとえばインターネット上の書き込みの場合、書き込まれた時から3年です。
ただし、名誉毀損罪の場合、被害者の告訴(犯人の処罰を求めて捜査機関に申告すること)がなければ刑事裁判を開くことができません。
そのため、自分の名誉を毀損した人物を罰して欲しいのであれば、告訴期間にも注意する 必要があります。 告訴期間は原則、犯人を知った日から6ヵ月とされています。
つまり、時効期間の3年は経過していなくても、犯人を知った日から6ヵ月が過ぎると、告訴することはできず、犯人に刑事上の責任を負わせることができなくなります。
民事上の時効
なお、損害賠償請求など民事上の請求の場合は、次のうち早く訪れた時点で時効となります。
- 損害および加害者を知った時から3年間
- 不法行為の時から20年間
つまり、犯人がわかっていれば、犯人が判明したときから3年間ですが、犯人がわからないままでも、名誉毀損行為(インターネットへの書き込みなど)があったときから20年経つと、 損害賠償請求など民事上の請求もできなくなります。
名誉毀損罪が成立しない場合
名誉毀損罪には、公共の利害に関する場合の特例があり、次の3つの要件を満たす場合には、名誉毀損罪は成立しないとされています(刑法第230条の2)。
- 公共の利害に関する事実であること
- 専ら公益を図る目的であったこと
- 真実性の証明があったこと
典型的なケースとして、報道機関による政治家の汚職についての報道をイメージすればわかりやすいでしょう。
もっとも、真実性の証明については、次のように考えられています。
⇒摘示された事実は真実ではなかったものの、行為者は真実であると思い込んでおり、そう思い込んでしまったことにつき相当の理由があったといえる場合には、名誉毀損罪は成立しない。
名誉毀損された場合に取り得る法的措置
名誉毀損の被害にあったと感じた場合に考えられる法的な対処法についてご説明します。
(1)告訴
前述したとおり、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判ができません。
そのため、自分の名誉を毀損した犯人に刑事責任を負わせたい場合には、捜査機関への告訴が必要です。
告訴は法律上、口頭でもできることになっていますが、一般的には告訴状を提出します。
(2)民事上の請求
名誉毀損の被害にあった場合、告訴することで犯人の処罰を求めるだけでなく、不法行為に基づく損害賠償請求など、民事上の請求をすることもできます。
また、名誉毀損がインターネットの書き込みによって行われた場合、サイト管理者に対し、書き込みの削除を請求することもあります。(削除請求が必ず認められるとは限りません。)
また、インターネット上の匿名の書き込みの場合、誰が書き込んだのかわからないことが一般的ですから、サイト管理者や接続プロバイダなどに対し、発信者情報開示請求を行うこともあります。
発信者情報開示について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
もっとも、削除請求を先に行い、書き込みが削除されてしまうと、書き込んだ者の特定に必要な発信者情報も削除されてしまいます。
書き込みをした人に対する告訴や損害賠償請求などを検討しているのであれば、先に削除請求をしてしまわないようにご注意ください。
名誉毀損では?と感じたら弁護士に相談を
今回の記事でご説明してきたように、犯罪が成立するかどうかの判断は難しいものです。
告訴をするにしても、一般の方がすんなりと受理される告訴状を自分で作成することは難しいでしょう。
また、民事上の請求にしても、発信者情報開示請求などの手続はとても複雑で手間がかかることが一般的です。
そのため、名誉毀損の被害にあい、法的措置を取ることを検討しているのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】名誉毀損とは、公然と他人の社会的評価を低下させるような事実を告げること
名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる事実を公然と示す行為を指し、刑事罰や、不法行為に基づく損害賠償請求など、民事上の請求の対象となり得る行為です。
刑事告訴や民事上の請求を行うには、専門的な知識が必要となるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、1人で悩まず、 アディーレ法律事務所にご相談ください。 フリーコール「0120-554-212」にてご予約の電話を承っています。