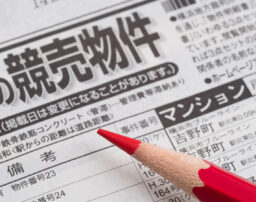育児休業(育休)は、子どもが生まれた後に育児をするために、一定期間仕事を休む制度です。
特に男性の育休取得は、近年制度の変更もあり注目を集めていますが、まだまだ低い取得率が課題です。
この記事では、男性の育休期間や取得方法、法改正、給付金など、最新の情報を詳しく解説します。育休を取得したいと考えている方や、育休取得後のキャリアや経済的な不安を抱えている方はぜひお読みください。
この記事を読んでわかること
- 育休とは
- 男性の育休取得率
- 男性の育休期間
- 企業の育休取得率の公表義務
ここを押さえればOK!
令和5年度の調査によれば、男性の育休取得率は30.1%で増加傾向にあるものの、女性の84.1%に比べて低いです。
育休を取る条件は雇用形態によって異なり、無期雇用の場合は育児休業を取得できますが、労使協定により一定の労働者は除外されることがあります。有期雇用の場合も特定の条件を満たせば取得可能です。
男性の育休期間は原則1年間で、分割して2回まで取得でき、条件を満たせば最長2歳まで延長可能です。産後パパ育休という出産直後に休業できる特別な制度もあり、こちらも2回まで分割して取得可能です。育休取得の手続きは会社に書面で申し出る必要がありますので、計画的に申請しましょう。
育休中は給与が支払われませんが、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金が支給され、社会保険料もかかりません。
育休取得後のキャリアや職場復帰の不安はありますが、国や社会全体が男性の育休取得を後押しする方向に変わってきています。育休を取得して育児を行い、家族との時間を過ごすことで、あなたと家族の人生がより豊かになるでしょう。
育休とは
育児休業(育休)は、子どもが生まれた後に一定期間、仕事を休んで育児をするための制度です。法律的には、育児・介護休業法に基づいており、男女問わず取得が可能です。
育休は、原則子どもが1歳になるまで取得でき、特定の条件を満たせば最長で2歳まで延長することができます。
育休を取得することで、母親も父親も育児に専念でき、子どもの成長を一番そばで感じながら、子どもや家族との絆を深めることができます。
(1)就業規則に育児休業の定めがないケースでも育休は取得可
「男性が取得するなんて前例がない」「就業規則に男性が取得できると書いていない」などという理由で、もしかしたら育休取得を断られた人もいるかもしれません。
しかし、労働者は法律に基づき育休を取得できる権利がありますので、就業規則に定めがなくても、会社側は拒否することはできません。
(2)男性の育休取得はすすんでる?
男性の育休取得率は、まだまだ低いのが現状です。
厚生労働省の令和5年度の雇用均等基本調査によると、男性の育休取得率は30.1%です。育休を取得しやすくする法改正や社会の理解などから、年々男性の育休取得率は上がっており、令和4年度の調査結果の17.13%からは13%も上昇しています。
しかし一方で、女性の育児休業取得率84.1%に比べると、格段に低い数値となっています。依然として、子どもが1歳に満たない時期の子育ては女性が担っていることがほとんどであることが分かります。
男性の育休取得が進まない理由として、職場の理解不足やキャリアへの影響を懸念する声が多く挙げられます。しかし、男性が育休を取得したいのに取得できず、女性が育児を一手に担うという状況は変えていかなければなりません。
この課題を解決するために、企業や社会全体でのさらなる意識改革が求められています。
育休を取れる男性の条件とは
育休を取る条件は、雇用形態などによって異なります。無期雇用と有期雇用のケース別に育休を取れる男性の条件について説明します。
参考:育児休業制度|厚生労働省
(1)無期雇用のケース
期間の定めのない労働契約のことを、無期雇用と言います。通常の正社員は無期雇用のケースがほとんどです。
無期雇用の場合、育児休業を取得することができます。また、1日の労働時間が通常より短い時短で働いていたり、パートやバイトの名称で働いていても、無期雇用であれば、育児休業を取得することができます。
ただし、労使協定により一定の労働者の育児取得を拒否できると定められることがあります。例えば、入社1年未満のケースで育休の対象から除外すると定められている場合には、育休を申し入れても会社は拒否することができます。
(2)有期雇用のケース
期間の定めのある雇用契約のことを、有期雇用といいます。
有期雇用の場合、次のケースで育児休業を取得することができます。
- 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合
具体的には、次の場合には要件を満たさず育児休業は取得できない可能性が高いです。
- 労働契約の更新回数の上限が明示されていて、その上限まで契約が更新された場合の労働契約の期間の末日が、子が1歳6ヶ月に達する日までの間である。
- 労働契約の更新をしない旨が明示されていて、申出時点で締結している労働契約の期間の末日が、子が1歳6ヶ月に達するまでの日である。
また、労使協定により一定の労働者の育休取得が拒否されることもあります。具体的には、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について労使協定で育休取得できないと定めた場合、会社は育休取得の申し出を拒否することができます。
男性の育休期間とは
男性の育休期間の基本について説明します。
(1)原則1年間(最長2歳まで)
男性の育児休業制度は、原則として子どもが1歳になるまでの間で、労働者が申し出た期間に取得できます。ただし、保育所に入所できない場合など特定の条件を満たせば、最長で1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長することが可能です。
また、父母が一緒に育休を取り、一定の要件を満たす場合、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月まで延長されます(パパママ育休プラス)。
女性は産休が認められているため、ママの育児休業は、通常産休(産後8週間)終了後に取得することになります。 出産予定日から育休を取得できるのは、主にパパとなります。
育児休業は育児・介護休業法に基づいて認められている制度であり、労働者が仕事を休業して育児に専念するための重要な制度です。出産後は子育てで忙しくなりますので、事前に取得時期や取得期間などについて調べて理解しておくようにしましょう。
(2)分割して2回取得可能
育休は分割して2回まで取得することができます。例えば、子どもが生まれた直後に1回目の育休を取得し、数ヶ月後に2回目の育休を取得することが可能です。
これにより、仕事の忙しい時期に育休取得を避けたり、ママが大変な時期にパパが育休を取得したり、育休取得を推進することに繋がることが期待されています。
(3)産後パパ育休も取得可
育休が制度化されて長い時間がたちますが、パパの育休取得率はまだまだ低い状況です。そこで、パパが育休を取得しやすいよう、「産後パパ育休」という新しい制度が導入されました。
産後パパ育休は、子どもが生まれてから8週間以内に取得できる特別な育休です。この期間中に最大4週間の育休を取得することができます。申出期間は、原則休業希望日の2週間前までで、分割して2回取得可能です。
育休中は働くことはできませんが、産後パパ育休については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に働くことが可能です。
産後パパ育休を利用することで、出産直後の母親のサポートや新生児との時間を確保することができます。
育休取得の手続きとは|申し出の方法と期限
育休を取得するためには、会社に、書面で育休を申し出る必要があります。通常は所定の書式がありますので、そちらに必要事項を記載したうえで申し出ます。
育休取得の申請は、子が1歳に達するまでは、原則として育休を開始しようとする日の1ヶ月前までに行う必要があります。出産予定日より早く子が出生したなど、特別の事情がある場合には、1週間前の日までに申し出ます。
また、1歳以降の育休は、要件を満たす場合のみ取ることが可能ですが、決められた時期までの育休取得の申し出が必要ですので注意しましょう。
ママが育休を先にとり、ママが仕事に復帰するタイミングでパパが育休を取得する、というケースもあるかもしれません。希望日に育休取得を開始するためには、いつまでに会社に申し出ればよいのか、人事窓口などで事前に確認し、しっかりと理解しておくようにしましょう。
育休期間の繰り上げや繰り下げも可能
一度育休取得を申請したけれども、家庭の事情により育休開始を繰り上げたい、逆に繰り下げたい、ということもあるはずです。そういった場合にも慌てずに、会社に対して繰り上げ、又は繰り下げの変更を申し出ましょう。
法律上は、一定の場合に限り、1歳までの育児休業1回につき、1回だけ繰り上げ変更が可能です。例えば、出産予定日よりも早く子が出生した場合などがあります。
希望通りに繰り上げ変更するためには、変更後の育休を開始しようとする日の1週間前までに変更を申し出る必要があります。
また、繰り下げの変更は、理由を問わず、1歳までの育児休業1回につき、1回だけ行うことができます。例えば「当初は6ヶ月くらいで仕事に復帰する予定だったけれども、もう少し育休を取得して子どものそばにいたい」などというケースで、繰り下げ変更が可能です。
1歳に達するまでの繰り下げ変更の場合、当初育休を終了しようとしていた日の1ケ月前までに、変更の申し出をする必要があります。
※法律上は、育休1回につき、繰り上げ・繰り下げ変更は1回だけですが、労使間の合意でこれ以上認めることは問題ありません。
【2023年4月1日~】育児休業の取得状況の公表義務とは
2023年4月1日から、従業員1000人超の企業は、年1回、男性の育児休業等の取得率を公表する義務があります。インターネットなど一般の方が確認できる方法で公表する必要があり、厚生労働省のウェブサイトで公表する企業が多いようです。
これは、育児休業の取得を促進し、企業の透明性を高めるための措置です。企業だけでなく社会全体が男性の育休取得に寛容なものとなり、男性社員が育休を取得しやすくなることが期待されます。
2025年4月1日からは、この義務が従業員が300人超の企業に拡大されます。
育休中の給付金と経済的サポートとは
育休中は、仕事は休業しますので給与が支払われません。しかし、育休中は、一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給されますので、取得前にどれくらいもらえるか計算しておきましょう。
育休開始から180日間は、賃金の67%、それ以降は50%相当額が支給されます。
産後パパ育休を取得した場合、一定の条件を満たすと、出生時育児休業給付金が支給されます。最大28日間、賃金の67%が支給されます。ただし、産後パパ育休では休業中に就業できるため、就業日数が多くなると出生時育児休業給付金が不支給となることがあることに注意が必要です。
なお、育休中は社会保険料の支払いが免除されます。
育休中、どれくらいの給付金を得られるのかシミュレーションできるサイトも数多くあります。そちらも参考にしながら育休中の生活費についても事前に把握しておくとよいでしょう。
【2025年4月1日から】あたらしい給付金制度が創設
2025年4月1日から、共働きと共子育てを推進するため、子どもの出生直後の一定期間に、パパママともに14日以上の育休を取得した場合、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金にあわせて、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されることになりました。
支給額は、休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)×13%です。
別途支給される育児休業給付金又は出生時育児休業給付金と併せて考えると、育休取得前とくらべてもほぼ同額の収入が得られることになります。
また、同日から、2歳未満の子どもを養育するために所定の労働時間を短縮して、時短で就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと、「育児時短就業給付金」が支給されます。
子育てによる収入減のダメージを減らすために、あたらしい給付金制度の受給も視野に入れて、計画的に育休を取得したいところですね。
よくあるQ&A
男性が育休を取得するにあたり、よくある質問に回答します。
(1)会社に育休取得を拒否されたら?
育休の取得は、法律上労働者に認められた権利です。法律上育休の取得が認められている労働者に対して、会社が育休の取得を拒否することはできません。
厚生労働大臣や都道府県労働局長は、違反をした会社に行政指導を行うことができます。また、勧告したにもかかわらず従わない場合には、その旨公表されることもあります。さらに、報告を求められたのに報告をしない、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。
(2)育休を取るなら降格すると言われたら?
労働者が育休(産後パパ育休含む)取得を申し出たことや、実際に育休を取得したことを理由として、会社が解雇その他不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
原則として、育休の終了から1年以内に不利益取り扱いがなされた場合には、育休を契機として不利益取り扱いがなされたと解され、原則として法違反と考えられます。
参考:妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A|厚生労働省
【まとめ】
男性も女性と同じく、一定の条件を満たせば育休を取得することができ、原則として子供が1歳になるまでの間で、労働者が申し出た期間に取得できます。育休を取得するためには、事前に会社に申請する必要があります。
また、育休中は育児休業給付金など、経済的なサポートも充実しています。育休取得後のキャリアや職場復帰の不安はあるかもしれませんが、国も社会全体も男性の育休取得を後押しする方向へ変わってきています。
育休は子どもが0~2歳の限られた時期しか取得できません。取得して育児を行い、家族との時間を過ごすことで、きっとあなたと家族の人生がより豊かになるでしょう。