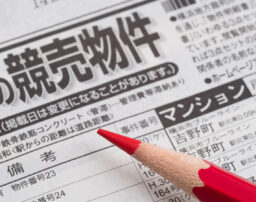いじめは、深刻な社会問題となっています。
わが子がいじめにあわないか不安な方、いじめにあっているようだがどうすればわからない方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、いじめの定義から具体的な種類、原因、そして対応策までを詳しく解説します。
いじめについて知識があれば、早期発見と適切な対応が可能になるかもしれません。
子どものいじめについて少しでも知りたいという方は、是非この記事を読んでみてください。
この記事を読んでわかること
- いじめの定義
- いじめの種類
- いじめの発生件数
- いじめのおこる原因
- いじめへの対処法
ここを押さえればOK!
行為者と対象者が児童であること、一定の人間関係があること、心理的または物理的な影響を与える行為が行われたこと、対象者が心身の苦痛を感じていることの4つの要素が含まれます。
いじめには、言葉のいじめ、無視をするいじめ、暴力によるいじめ、お金のいじめ、強要によるいじめ、ネットによるいじめの6種類があります。
2023年度には全国で73万2568件のいじめが認知され、過去最多となっています。
いじめの原因として、劣等感や嫉妬心、集団心理や同調圧力、家庭環境や教育の影響が挙げられます。
いじめを認知したら、証拠を集める、学校に通報する、相談窓口に相談する、警察や弁護士に相談するなどの対応策を講じることが重要です。
これにより、いじめ被害の拡大を防ぎ、被害者を守ることにつながります。
いじめの定義
いじめは、法律上次のように定義されています。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
逆に言えば、この要素が満たされれば、それはいじめです。
いじめの定義は、過去何度か変遷しています。
昭和61年の定義では、いじめというためには「学校がいじめの事実を把握している」「攻撃を継続的に加えている」「相手が深刻な苦痛を感じている」ことなどの厳格な要件が必要とされていました。
いじめとされるための要件が厳格であると、問題があっても「いじめ」として把握されないために対処が遅れて、被害者が受ける被害が拡大するおそれがあります。
とくにこの要件だと「学校がいじめを確認していない」というだけで、いじめと認められないことになってしまいます。
このような厳格な要件が問題視され、平成6年に定義が変更され、学校の確認が必要という要件が削除されました。
さらに平成18年にも定義が変更され、「継続的」「深刻な苦痛」などの要件がなくなりました。
平成25年にはいじめ防止対策推進法が施行され、現在の定義となりました。
いじめの判断基準
いじめの判断基準は、被害者が心身の苦痛を感じているかどうかが重要です。
文部科学省も、「個々の行為がいじめに当たる否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行う」とし、被害者がどう感じるのかという点を重視しています。
「それくらいでもいじめなの?」というような行為でも、法律上の定義に当てはめればいじめとなることもあります。
文部科学省はごく初期段階のいじめとして、次のような具体例をあげています。
・授業中に先生に刺されたが答えられないBさんに、Aさんが「こんな問題もわからないの」と言った。Aさんはショックを受けて下を向いてしまった。
・BさんはAさんから滑り台の順番を抜かされて悲しい顔をしていることが度々ある
些細な行為であっても、被害者が心身の苦痛を感じてれば、予期せぬ事態が起こって重大な結果が生じる可能性はゼロではありません。
初期段階のいじめも「いじめ」として認識して、学校や大人が指導・解決に向けて動くことが重要です。
いじめの種類
いじめには様々な種類があります。
文部科学省が公表しているいじめの態様別状況から、6種類にまとめて紹介します。
(1)言葉のいじめ
言葉のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言って相手の心を傷つける行為です。
いじめの態様としても、言葉のいじめは一番多くなっています。
例えば、「バカ」「死ね」などの言葉を伝えることが挙げられます。
言葉のいじめは、被害者の自尊心を傷つけ、深刻な精神的ダメージを与えることがあります。
(2)無視をするいじめ
無視をするいじめは、被害者を集団から排除して仲間外れにし、孤立させる行為です。
例えば、一定のグループが一人の生徒を仲間外れにしたり、無視したりすることが挙げられます。
この行為は、被害者に孤独感と疎外感を与え、心を傷つけます。
被害者は自分が存在しないかのように扱われるため、学校に行きたくなくなり、不登校になってしまうこともあります。
(3)暴力によるいじめ
暴力によるいじめは、身体的な攻撃を伴う行為です。
暴力によるいじめは、被害者がケガをする恐れがあるだけでなく、精神的苦痛も与えます。
軽くぶつかったり、遊ぶふりをして軽く叩かれたり、蹴られたりすることは、小さい子どもならめずらしくないことかもしれません。
実際に、小学校でみられるいじめの態様として多いようです。
しかし、被害者が心身の苦痛を感じていれば、それもいじめです。
(4)お金のいじめ
お金のいじめは、金銭をたかったり、盗んだり、隠したりする行為です。
例えば、お金を持ってくるように強要したり、おごるように強要したりする行為があげられます。
お金のいじめは、被害者の家庭に経済的な負担をかけるだけでなく、被害者自身の精神的なストレスも増大させます。お金を持っていかなければならないというプレッシャーにさらされる被害者は、学校生活が苦痛になるでしょう。
(5)強要によるいじめ
強要によるいじめは、嫌なことや恥ずかしいことなどを無理やりする・させる行為です。
例えば、宿題を代わりにやらせたり、ランドセルを代わりに持たせたりする行為があげられます。
被害者は自分の意思に反して嫌な行動をさせられることで、精神的な負担を感じます。
(6)ネットによるいじめ
ネットによるいじめは、インターネットを通じて行われる嫌がらせや誹謗・中傷行為です。
中学生や高校生でスマホを保有する子どもは、もはや珍しくありません。
例えば、SNSで被害者を誹謗中傷したり、個人情報を拡散したりする行為があげられます。
ネットいじめは、匿名性が高く安易に行為に加担するおそれがあり、簡単に加害者・被害者が生まれる、情報が拡散すると被害が甚大になる、などという特徴があります。
文部科学省は、2008年(平成20年)に「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集(学校・教員向け)」を作成・公表しており、対策に力を入れています。
参考:「ネット上のいじめ」から子どもを守るために|文部科学省
いじめの認知件数
いじめの認知件数は年々増加傾向にあります。
文部科学省の調査によると、2023年度(令和5年度)、いじめは全国で73万2568件認知されています。前年度から7.4%増加しており、過去最多です。
これは、あくまで学校が認知している件数ですので、実際に発生しているいじめは、これよりも多くなるでしょう。
いじめの件数自体が増えている、とも考えられますが、以前は「いじめ」として認知されていなかったような行為がいじめとして認知されるようになって、件数が増えたと考えることもできるでしょう。
参考:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要|文部科学省
いじめが起こる原因
いじめが起こる原因は多岐にわたります。以下で、主な原因3つを説明します。
(1)劣等感や嫉妬心
他人に対する劣等感や嫉妬心がいじめの動機となることがあります。また、好意を持っていて良かれと思ってしたことでも、相手が精神的苦痛を受けることもあります。
(2)集団心理や同調圧力
集団の中での同調圧力や集団心理がいじめを助長することがあります。
例えば、特定の子がいじめをしていたが、それに同調する子どもが増え、「抜けたら次は自分がいじめられる」などという心理からいじめが助長されるケースがあります。
(3)家庭環境や教育
家庭環境や教育の影響もいじめの原因となることがあります。
例えば、家庭内で日常的に暴力や虐待が行われていると、その子も他の子に暴力を振るったりすることがあります。
いじめの対応策
いじめを認知したら、適切な対応策を講じることが重要です。
以下に具体的な対応策を示します。
(1)証拠を集める
いじめの証拠を集めることは、学校や警察に被害を伝えるときに、非常に役立ちます。
「やっていない」という言い逃れを封じ、いじめが事実だと証明するためにも、できるだけいじめの証拠を確保しましょう。
例えば、いじめの現場を録音・録画する、いじめの内容を日記に記録する、見聞きした子がいれば聞き取りをする、ケガをしたらケガの写真や診断書を取る、壊されたものがあれば状態を写真にとる、などの方法があります。
(2)学校に連絡する
いじめが発生した場合、学校に通報連絡することが重要です。
「これくらいで連絡するなんて迷惑では?」と思うかもしれません。
そういうときは、次のいじめの定義の4要素を思い出してください。
- 行為者(A)とその対象者(B)が児童であること
- AとBの間に一定の人間関係があること
- AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
- Bが心身の苦痛を感じていること
この4要素が満たされていればそれはもういじめですので、エスカレートしないうちにすぐに連絡するようにしましょう。
電話ではうまく伝えられないと思う方は、書面にするとよいでしょう。 特に小学校では、連絡帳を活用して担任と連絡をとる方法もあります。
学校は、いじめの相談を受けた時には、すみやかに学校のいじめ対策組織に対して情報を伝え、組織的な対応を行わなければなりません。
学校は、被害児童を守り、加害児童に対しては教育的配慮の下で、毅然と指導する必要があります。
(3)いじめの相談窓口に相談する
「これっていじめなの?」「どう対応したらいいのだろう?」と対応に悩んだときは、国や各自治体が運営する、次のようないじめ相談窓口に相談することも有効です。
- 子どもの人権110番|法務省
- URL:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
電話番号:0120-007-110
受付時間:月~金曜、8時半~17時15分
※メールやLINEでも相談可能
- URL:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
- 24時間子供SOSダイヤル|文部科学省
- URL:https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
電話番号:0120-0-78310
受付時間:365日、24時間
- URL:https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
- 教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン|東京都教育相談センター
- 電話番号:0120-53-8288
- 受付時間:365日、24時間 (※都内在住・在籍の高校生相当年齢の方と保護者・親類・教職員 )
- 「ネット・スマホの悩みを解決こたエール」|都民安全推進部
- URL:https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/
電話番号:0120-1-78302
受付時間:月~土曜、15~21時(祝日を除く)
※メール、LINEでも相談可能
- URL:https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/
(4)警察に相談する
いじめが下記の犯罪行為にあたるようなひどい態様の場合、学校は所轄警察署と連携し、援助を求めることになっています(いじめ防止対策推進法23条6項)。
- 繰り返し殴ったり蹴ったりする(刑法208条暴行罪)
- 骨折するようなケガをさせる(刑法204条傷害罪)
- 断れば危害を加えると脅して汚物を口に入れさせたり、性器を触ったり、金品をたかったりする(刑法223条強要罪、刑法176条強制わいせつ、刑法249条恐喝罪)
- 教科書等の所持品を盗む(刑法235条窃盗罪)
- 誹謗中傷するためインターネットで実名をあげて悪口を書く(刑法230条231条名誉棄損罪、侮辱罪)
もしこのようなひどいいじめがあるのに、学校がすぐに警察に相談しない場合には、直接警察へ相談することを検討しましょう。
刑法で罰されるのは14歳以上の人間に限られます(刑法41条)。つまり、13歳以下の者は、犯罪行為を行ったとしても刑法で罰されることはありません。ただし、「触法少年」(少年法3条1項2号)として警察が補導し、調査を行います。
警察に相談することで、いじめの加害者に対して法的な措置が取られ、強い抑止力となることが期待されます。
参考:平成25年5月16日 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知)|文部科学省 (mext.go.jp)
(5)弁護士に相談する
自分で学校と話したり交渉したりすることが、時間的・精神的に難しいと感じる方は、いじめ問題を取り扱っている弁護士に相談して対応を依頼する方法もあります。
弁護士に相談・依頼することで、いじめに対する具体的な対応策を提案してくれるでしょう。
各都道府県の弁護士会では、子どもの法律相談なども行っていますので、1人で悩まずに相談してみることをお勧めします。
【まとめ】いじめは速やかな対応が重要|まずは学校など窓口への連絡を
いじめは多くの学校で認知されており、わが子も被害者となる可能性があります。
いじめには多様な態様がありますので、早期の段階でいじめに気付き、学校に連絡して対処することが大切です。
1人での対応が不安なときは、様々な相談窓口がありますので、一度相談してみることをお勧めします。
いじめを防ぐための知識と行動が、子どもを守る盾となるでしょう。