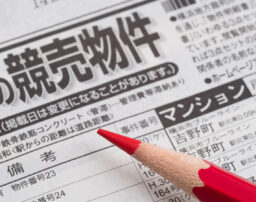離婚をする場合には、いろいろな方法があります。
それぞれの方法に必要な手続きも、いろいろなものがあります。
そうした手続きや、調停、裁判などによる方式について、解説していきます。
離婚の方法
協議、調停、審判、裁判の4種類の離婚方法の概要と、各方法で離婚するケースについて解説していきます。
(1)協議離婚
夫婦間の話し合いで合意することによって離婚を決める、もっとも一般的な方法です。
厚生労働省の統計によると、2020年度の日本の離婚総数は19万3253件で、うち17万603件が協議離婚の方法で離婚していますので、日本での離婚のうち、約88.3%が協議離婚の形式をとっています。
協議離婚では、双方で合意ができたら、離婚届を役所に提出し、受理されると離婚が成立します。
離婚原因も特別な手続きや費用も必要なく、離婚届が市役所で受理さえすれば、離婚成立です。
この方式は、離婚届以外の手続きは不要のため、早く離婚することができます。
(2)調停離婚
協議離婚で双方の合意がまとまらない場合には、調停離婚を目指すことになります。
これは、家庭裁判所に離婚調停を申立てて、話し合いを行う方法になります。
離婚調停を申し立てると、家庭裁判所が選任した調停委員二名が夫婦の間に介在し、離婚すること、各離婚条件について調整を進めながら、夫婦での離婚に関する話し合いをすすめます。
2020年度の日本の離婚総数は19万3253件で、うち1万6134件が調停離婚の方法で離婚していますので、日本の離婚のうち、約8.3%が調停離婚の形式をとっています。
調停離婚は、夫婦双方に離婚することの合意が成立し、家庭裁判所で調書が作成されることで離婚が成立します。その後、戸籍に離婚の事実を反映させるため、離婚届を提出します。
もし、夫婦で離婚についての合意が得られなければ、調停をしても離婚は成立しません。
(3)審判離婚
調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚を命ずる方法になります。
双方でほとんど合意できているが、わずかな意見の食い違いや、入院、入獄などで完全な合意ができない場合に該当します。
些細な理由で合意できないケースは少ないため、審判離婚で離婚するケースは非常にまれです。
(4)裁判離婚
離婚調停が成立しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして離婚を求める方法です。
家庭裁判所で離婚判決の言い渡しがあって、その判決が確定すると離婚が成立します。この方法による離婚を一般に裁判離婚といいます。
日本の法律制度では、はじめから離婚裁判を起こすことは認められず(一部の例外はありますが)、先に離婚調停を行なう手続ルールになっています。つまり、家庭裁判所で調停をしても、夫婦で離婚(条件)することに合意ができなかったときに、はじめて次のステップとして裁判をすることになるのです。
そのため、裁判をして離婚する夫婦は少なく、2020年度の日本の離婚総数は19万3253件で、裁判離婚はうち1740件にすぎませんので、全体の1%よりも少ない数になっています。
なお、協議離婚及び調停離婚では離婚理由は問わず何であってもかまいませんが、裁判離婚が認められるには、法定の離婚事由が必要になり、訴訟を提起したからと言って離婚できるとは限りません。
法定の離婚事由は、民法770条1項に規定があり、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」とされています。
- 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3号 配偶者の生死が3年に状明らかでないとき。
- 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
以上のいずれかの離婚事由が認められ、離婚の判決が確定すると離婚が成立します。
調停離婚の手続きと離婚成立までの流れ
離婚調停の申立てから調停終了までの流れ、終了までの期間について解説します。
(1)家庭裁判所に離婚調停を申立てる
冷静に離婚の話し合いができない、条件に折り合いがつかないなど、協議離婚が難しいときに利用する制度です。子どもの親権者を誰にするか、親権者にならない親と子の面会交流をどうするか、などに関する問題も話し合うことができます。
離婚の条件が合わないなど、調停申立てをするタイミングについて紹介します。
また、離婚調停に必要な書類や、費用、家庭裁判所への提出方法を解説していきます。
(2)離婚調停当日までの準備
申立書を提出し、受理されたら2週間程度で申立人と相手方に調停期日通知書が郵送されてきます。
調停期日通知書以外に提出する必要がある書類については、以下のようなものがあります。
これらは、必ず申立人用の控えをとった上で、調停期日に持参する必要があります。
- 申立書及びその写し1通
- 標準的な申立添付書類
事情説明書(未成年の子がいる場合には子についての事情説明書も必要となります)
連絡先等の届出書
進行に関する照会回答書
夫婦の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
年金分割のための情報通知書
調停が開かれるのは、裁判所が開廷している平日の10~17時までの間になります。
所要時間としては、概ね2~2時間半程度が予定されています。
ただし、1回目期日の日程は双方の都合を考慮していないため、都合が合わない場合は日程変更が可能です。
調停で主張をするにあたっては、言いたいことを事前にまとめておくとよいでしょう。
参考:夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所- Courts in Japan
(3)離婚調停の当日の流れ
調停期日通知書を持参し、通知書に記載の日程で家庭裁判所に行くことになります。
相手も来ていたら、調停委員を介して離婚の話し合いを行います。
離婚調停では、調停委員が中立の立場で、それぞれの主張を聞きながら話し合いを進めていくことになります。これは非公開の手続きです。
調停委員と話すときは、言葉遣いや表情、声のトーンに注意しましょう。
(4)離婚調停の終了と離婚成立
話し合いで合意し、調停が成立すると離婚成立となります。
この場合、裁判所に調停調書を申請し、調停調書と離婚届を10日以内に提出する必要があります。
10日を過ぎると、過料が科される場合もあります。
こうしたときには、離婚成立から2、3日後に家庭裁判所から調停調書が届きます。
(5)離婚成立までの期間と期日回数
期日回数は2~4回、期間は3~6ヶ月のケースが多いです。
ただし、親権や面会交流など、子供に関する話し合いは、家庭裁判所調査官の調査があるので、次回の期日までの間隔が開きやすい傾向にあります。
裁判離婚の裁判手続きと離婚成立までの流れ
裁判離婚ができる条件と必要な準備、裁判離婚で訴状提出から判決までの流れを解説します。
(1)裁判離婚に必要なこと
裁判離婚は、離婚調停をしていること、法定離婚事由に該当することが前提です。
裁判離婚においては、法定離婚事由があると証明する証拠が必要になります。
この場合は、裁判の前に証拠を集めておく、必要に応じて調査会社などを利用しておくとよいでしょう。
(2)裁判離婚の基本的な流れ
裁判離婚の、訴状提出から判決・和解までの流れを以下で説明します。
(2-1)家庭裁判所に訴状を提出
まず、原告または被告の住所を管轄する家庭裁判所に、訴状を提出します。
訴状を作成するにあたっては、法律の専門知識が必要になりますので、弁護士に依頼するとよいでしょう。
(2-2)第1回口頭弁論の通知・答弁書の提出
訴状が受理されると、原告には訴状の副本、被告方には口頭弁論呼出状が届きます。
被告が作成した答弁書と、訴状の問題点を裁判所が整理して、双方が反論を準備書面にまとめるということになります。
(2-3)第1回口頭弁論期日
原告は訴状の請求をし、被告は答弁書通りの主張、認否をします。
(2-4)第2回目位階の口頭弁論
双方が主張、主張に対する反論を答弁し、裏付ける証拠を提出するなどのことを繰り返します。
食い違いのある点は、書類や本人尋問、証人尋問をもとに調べます。
本人尋問の前に、離婚に至る経緯などをまとめた陳述書を作成したりします。
(2-5)判決・和解による裁判終了
判決は、原告の請求を認めるか、または棄却のどちらかになります。
判決書の送達から2週間以内なら、控訴ができます。
控訴せずに判決が確定した場合は、判決が確定した10日以内に、判決書謄本、判決確定証明書と、離婚届を市役所に提出します。
和解は、判決前に話し合いで解決するに至る、または裁判官の判断で話し合いを進めて合意を求めるという場合になります。
和解調書が作成されると、それと同時に、離婚が成立します。
和解成立から10日以内に、和解調書謄本と離婚届を市役所に提出することになります。
【まとめ】離婚方法の種類は協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つ
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- まずは話し合いの協議離婚を目指し、話し合いでまとまらなければ調停で話し合う調停離婚、さらに調停で解決しない場合には審判離婚、裁判離婚になります。
- 調停離婚や審判離婚、裁判離婚になる場合には、双方の言い分を主張するため、事前に証拠などの準備しておくとよいでしょう。
今回の記事では、離婚方法の種類や離婚手続の流れについて説明しました。しかし、今回の記事を読んでも「離婚について順調に進められるか不安がある」「相手が話し合いに応じてくれるのか不安…調停や裁判になるのでは?」などお悩みを抱えていませんか。
これらの悩みをお持ちの場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。弁護士に相談いただくことで、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたします。費用倒れになることは原則ありませんので、安心してご依頼いただけます(2024年8月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。