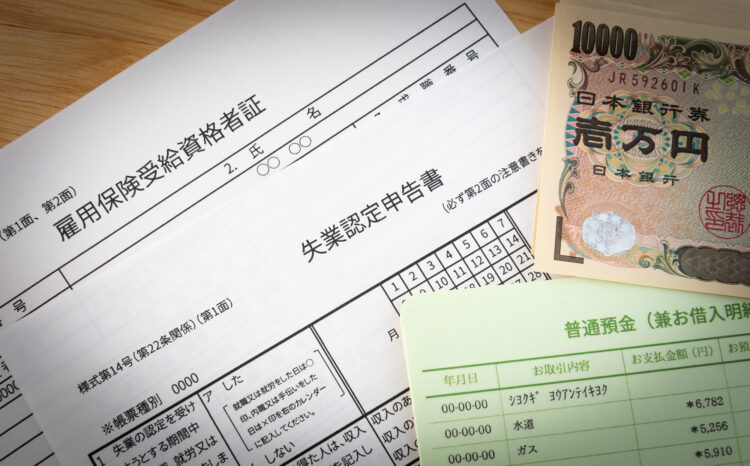労災遺族年金という言葉を聞いたことはありますか?
ニュースで、労災で会社員が亡くなった、などのニュースを聞いて、「遺族はどのような補償が受けられるのだろう」などと考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社員が亡くなると、残された家族などは家族を失った悲しみだけでなく、経済的に困窮してしまいます。このような時のために、労災の制度があります。
業務災害や通勤災害で労働者が亡くなった場合、労働者災害補償保険(労災保険)によって、その労働者の遺族に対して労災遺族(補償)年金などの給付が行われます。
今回は、この労災遺族年金等の遺族給付について解説します。
万が一の労災死亡事故に備え、少しでもお役に立てば幸いです。

この記事では、
- 労災遺族給付の内容
- 労災遺族給付の種類(遺族補償年金、遺族特別年金、遺族補償一時金)
- 労災遺族給付を受給するための要件(生計、続柄)
- 労災遺族給付の請求方法
- 労災遺族給付の請求には時効制度
などについて弁護士が解説します。
労災遺族給付とは
労災遺族給付とは、労働者が業務や通勤途中で亡くなった場合、一定の範囲の遺族に対して支給される年金や一時金です。
業務災害の場合に支払われる給付金を遺族補償給付、通勤災害の場合に支払われる給付金を遺族給付といます。
労災遺族年金には、遺族(補償)年金と遺族特別年金があります。
年金を受け取ることのできる資格のある遺族がいない場合には、特定の範囲の遺族に一時金が支給されます。
労災遺族給付の受給には、被災労働者の死亡当時、その労働者と特定の範囲の関係にある必要があるなどの受給要件があります。
この支給対象となる遺族の範囲はかなり複雑であり、後述しますが、はじめに給付を受けていた遺族に再婚・死亡などの事情が発生すると、次の順位の遺族がもらうことができるという仕組みになっています。
労災遺族給付の種類
労災遺族給付には、
- 遺族(補償)年金
- 遺族特別年金
- 遺族補償一時金
- 遺族特別年金一時金
- 遺族特別支給金
があります。それぞれについて説明します。
(1)遺族(補償)年金
遺族(補償)年金には、遺族(補償)年金と、遺族(補償)年金前払一時金があります。
遺族(補償)年金とは、死亡した労働者と、特定の関係にある遺族に支給される年金です。
遺族(補償)年金は、労災保険による保険給付であり、給付基礎日額の一定日数分が支給されます。年金ですので、受給権者である間は継続的に受給できます。
給付基礎日額とは、事故発生日または医師の診断により疾病発生が確定した日の直前3ヶ月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
年金額は、遺族の人数により異なります。遺族がお1人のときは、原則として給付基礎日額の153日分となります。
| 遺族数 | |||
| 1.遺族(補償)年金 | 2.遺族特別支給金(一時金) | 3.遺族特別年金 | |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
| 3人 | 同223日分 | 同223日分 | |
| 4人以上 | 同245日分 | 同245日分 | |
参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続│厚生労働省
ボーナスや臨時に支払われる賃金は除外されます。
ボーナスや臨時に支払われる賃金部分は、次に説明する遺族特別年金部分で受給できます。
遺族(補償)年金前払一時金とは、遺族補償年金の支給を受ける際に、まとまったお金が必要な場合は、遺族補償年金前払一時金として、給付基礎日額の1000日分を上限に一時金の支給を受けることが可能になる給付金です。
被災した労働者が死亡した日の翌日から2年以内で、かつ年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、遺族(補償)年金を受け取った後でも前払い一時金を請求することができます。
(2)遺族特別年金
遺族特別年金とは、労災保険法の社会復帰促進等事業により給付される年金です。
算定基礎日額の一定日数分が支給されます。
年金ですので、受給権者である間は継続的に受給できます。
この算定基礎日額とは、事故発生日または医師の診断により疾病発生が確定した日以前1年間に被災労働者に対して支払われた特別給与(給付基礎日額から除外されるボーナスなど、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額を、算定基礎年額として365で割った金額です。
年金額は、遺族の人数により異なります。遺族がお1人のときは、原則として算定基礎日額の153日分となります。
遺族の数による年金額は、遺族(補償)年金のところに添付した表を参照してください。
(3)遺族(補償)一時金
遺族(補償)一時金は、被災労働者の死亡当時、遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合に、特定の関係にある遺族に支給される給付金です。
労災保険法の社会復帰促進等事業により給付されます。
遺族補償一時金は、給付基礎日額の1000日分が支給されます。
遺族(補償)一時金は、1.上記の遺族(補償)等年金の受給資格のある遺族がいないときのみならず、2.遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まで失権し、受給権者であった遺族全員がそれまで受給した年金及び遺族(補償)年金前払一時金の総額が、給付基礎日額の1000日分に満たないときにも支給されます。
そして、2の場合の支給額は、上記1000日分との差額となります。
受給権者の優先順位は、
| 第1順位 | 配偶者 |
| 第2順位 | 被災労働者の収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 |
| 第3順位 | その他の子・父母・孫・祖父母 |
| 第4順位 | 兄弟姉妹 |
となっています。
(4)遺族特別一時金
遺族特別一時金は、被災労働者の死亡当時、1.遺族特別年金の受給資格のある遺族がいないときのみならず、2.遺族特別年金の受給権者が最後順位者まで失権し、受給権者であった遺族全員がそれまで受給した遺族特別年金の総額が、算定基礎日額の1000日分に満たないときにも支給されます。
遺族特別一時金は、1の場合、算定基礎日額の1000日分が支給されます。そして、2の場合の支給額は、上記1000日分との差額となります。
受給権者の優先順位は、遺族(補償)一時金と同じです。
(5)遺族特別支給金
遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金の受給権者に対して、遺族特別支給金として、300万円の一時金が支給されます。
なお、上記のとおり、遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まで失権し、受給権者であった遺族全員がそれまで受給した年金及び遺族(補償)年金前払一時金の総額が、給付基礎日額の1000日分未満のときにも、その差額分が遺族(補償)一時金として支給されますが、この場合には遺族特別支給金は支給されません。
労災遺族給付を受給するための要件
労災遺族給付を受給するためには2つの要件を満たす必要があります。
ここでは、労災遺族給付を受給するための要件について解説します。
(1)被災労働者の収入で生計を維持していたこと
労災遺族給付を受給するためには2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、被災労働者の死亡当時に、その収入によって生計を維持していたという要件です。
この要件は、生計の大部分を被災労働者の収入に依存していた場合のほか、生計の一部を被災労働者の収入で維持している場合も要件を満たすものとされています。
たとえば、夫婦共働き(共稼ぎ)で、被災労働者の妻も働いていた場合もこの要件を満たします。
(2)被災労働者との続柄
2つ目の要件は、被災労働者との続柄です。
受給資格を有する遺族のうち、一番優先順位が高い人が受給権者になります。
受給権者が死亡・再婚した場合、資格要件となる年齢を超過した場合は受給権を失い、次の順位の者に受給権が移ります。これを「転給」といいます。
受給権者の順位は次のとおりです。
| 第1順位 | 妻又は60歳以上若しくは一定障害の夫 |
| 第2順位 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子 |
| 第3順位 | 60歳以上又は一定障害の父母 |
| 第4順位 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫 |
| 第5順位 | 60歳以上又は一定障害の祖父母 |
| 第6順位 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹 |
| 第7順位 | 55歳以上60歳未満の夫 |
| 第8順位 | 55歳以上60歳未満の父母 |
| 第9順位 | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
| 第10順位 | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 P.2│厚生労働省
労災遺族年金の請求手続きについて
労災遺族年金の請求手続きについて説明します。
労災遺族年金を請求するためには、受給権者が、会社の事業所等を管轄する労働基準監督署長に対し、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」という書類を提出します。
この書類は、労働基準監督署に置いてあります。
また、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。
参考:遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書│厚生労働省
なお、同順位の受給権者が2人以上いる場合は、そのうちの1人を労災遺族年金の請求・受領の代表者とすることになります。受領の代表者は、受給権者の協議により決めることになります。
そして、遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書には、必要に応じて、書類を添付することになります。
遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書に必ず添付する書類は以下のとおりです。
- 被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など)
- 請求人およびほかの受給資格者と、被災労働者の身分関係を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本など)
- 請求人およびほかの受給資格者が、被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
上記にあげた書類1~3以外にも、受給権者が事実婚の配偶者の場合には、事実婚の事実を証明する書類や、受給権者に障害がある場合には、その障害の状況を証明する書類などの提出が必要となることもあります。
このような場合には、労働基準監督署から、指示がありますので、この指示に従って提出することが必要になります。
参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 P.4│厚生労働省
労災遺族給付の請求に関する時効
労災遺族給付の請求権については、時効があります。
労災遺族年金・一時金は、いずれも、被災労働者が亡くなった日の翌日から、5年を経過すると、時効により請求権が消滅してしまいます。
労災遺族給付を請求する場合は、5年の時効が成立する前に請求することが必要です。
労災遺族給付は、不幸にも労働災害で亡くなった方のご遺族に対する大切な補償です。時効により権利を失効しないように、早めに対応することが必要です。
参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 P.4│厚生労働省
【まとめ】労災遺族年金は時効が成立する前に請求する必要がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労災遺族給付とは、労働者が業務や通勤途中で亡くなった場合、遺族に対して支給される年金や一時金のこと
- 労災遺族給付には、遺族補償年金、遺族特別年金、遺族補償一時金の3種類がある
- 労災遺族給付を受給するためには、被災労働者の収入で生計を維持していたこと、被災労働者と特定の続柄にあることの、2つの要件を満たす必要がある
- 労災遺族給付は、所轄の労働基準監督署長に必要書類を提出することで請求できる
- 労災遺族給付の請求には時効があり、時効が成立すると請求できなくなる
労災を認定するのは労働基準監督署です。会社が認定するのではありません。
労災遺族(補償)給付は、不運にも被災されて亡くなった労働者のご遺族を守るために構築された仕組みです。
会社が労災手続きに応じないのであれば、ご遺族側で労働基準監督署に労災の申請をすることもできます。
また、労災遺族給付の請求権は、被災された労働者が亡くなってから5年の時効で消滅してしまいます。時効になる前に必ず請求の手続きをとるようになさってください。
ご不明な点がある場合は、躊躇せず、労災遺族給付の請求に関するお悩みは、労働基準監督署にご相談ください。
この記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧│厚生労働省
アディーレ法律事務所では、労災に関するご相談は、何度でも無料です(2024年11月時点)。
労災に関するお悩みは、労災問題を扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。