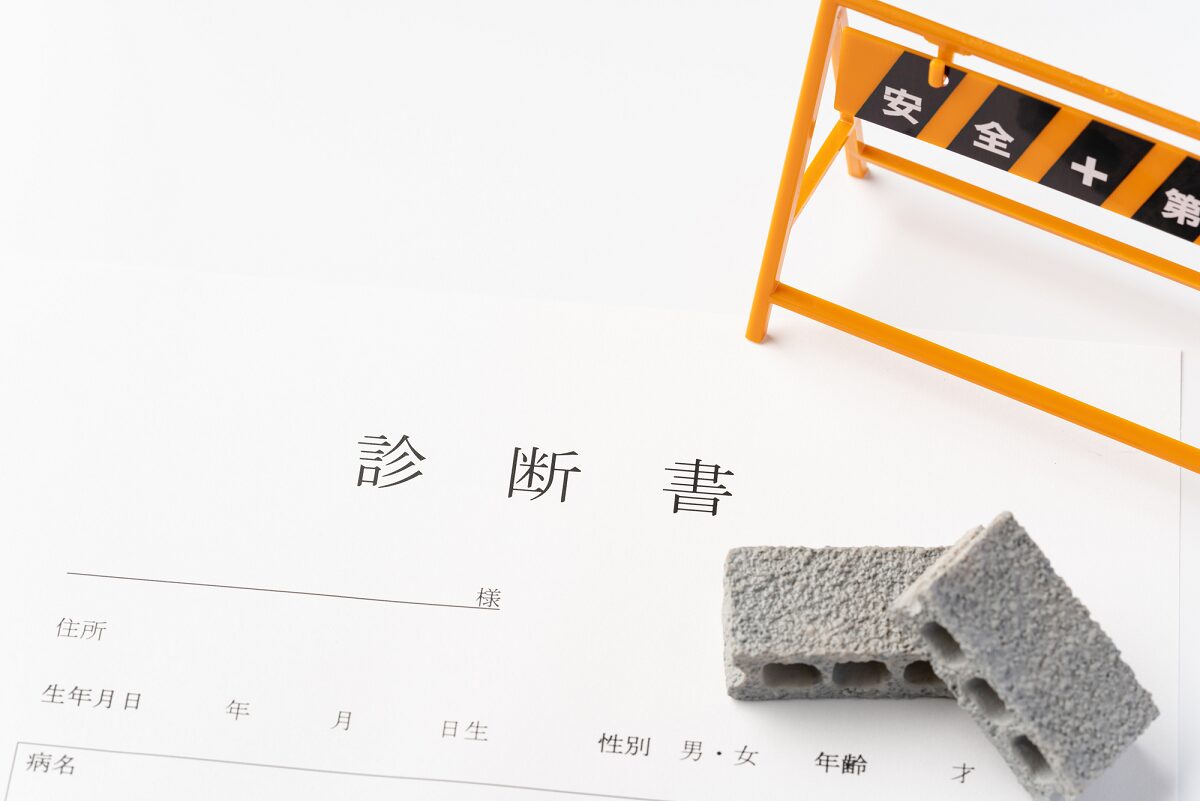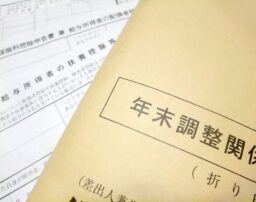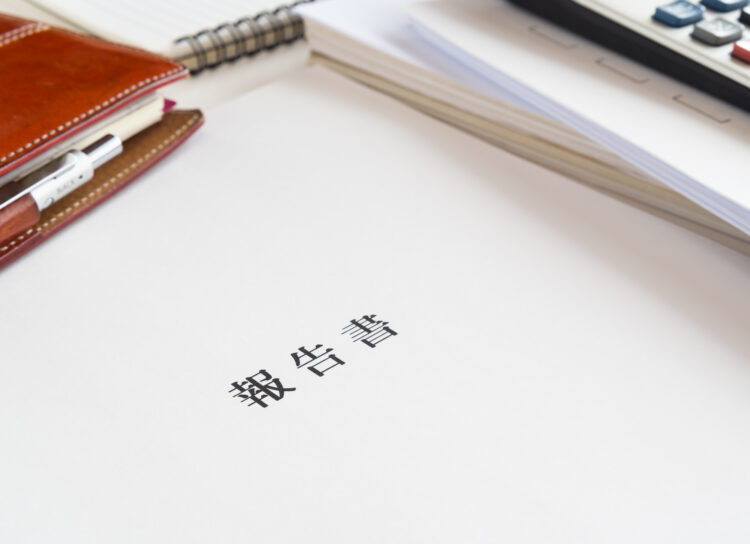この記事を読んでわかること
- 労災保険申請における診断書の要否は給付の種類によって異なる
- 労災申請用の診断書費用は、4,000円を上限に労災保険から支給され、指定医療機関なら自己負担なし、そうでない場合は立て替え後に請求できる
- 診断書作成にはおよそ数週間かかり、後遺障害診断書など複雑な診断書の場合には、さらに時間がかかる場合もある
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
労災給付の種類別「診断書」の要否
労災保険にはさまざまな給付があり、それぞれで診断書の必要性や目的が異なります。
給付ごとに診断書の要否と、その役割を解説しましょう。
(1) 療養(補償)等給付
療養(補償)等給付とは、簡単にいえば必要な治療を受けるための費用を補償する給付のことです。
療養(補償)等給付の申請に、医師の診断書は基本的に必要ありません。
もっとも、はり・きゅうまたはマッサージの施術を受けた場合には、医師作成の診断書が必要になります。
詳しくは、管轄の労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。
(2)休業(補償)等給付
休業(補償)等給付とは、仕事中にケガをして働けなくなった場合、および仕事に関連する病気で働けなくなった場合に支給されるお金のことです。
休業(補償)等給付の申請に、医師作成の診断書は必要とされていません。
(3)障害(補償)等給付
病気やケガが治っても(労災保険において「治った」とは医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を含んで使います)、身体に一定の障害(後遺障害)が残ってしまった場合に給付されます。この給付の申請には、障害の状態を記載した診断書が必要です。
(4)傷病(補償)等年金(療養開始後1年6ヵ月経過後の長期療養者)
傷病(補償)等年金とは、次の条件を満たす場合に、労働基準監督署長の職権により、その状況が継続している間に支給されるものです。
- 療養開始から1年6ヵ月以上経っても労災によるケガや病気が治らない
- 上記ケガや病気の程度が障害等級第1~3級に達している
傷病(補償)等年金が支給される場合には、療養(補償)等給付は引き続き支給されるのに対し、休業 (補償)等給付は支給されません。
傷病(補償)等年金の場合、労働者本人による申請手続は不要です。
もっとも、上記のとおり、療養開始から1年6ヵ月以上経過してもケガや病気が治っていない場合、その後1ヵ月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならず、その届には医師の診断書の添付が必要とされます。
なお、療養開始から1年6ヵ月以上経過してもケガや病気が治っていないものの、傷病(補償)等年金の受給要件を満たしていない場合、毎年1月分の休業(補償)等給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」を併せて提出するものとされます。
この報告書にも医師の診断書が必要です。
参照:休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省
(5)介護(補償)等給付
介護(補償)等給付とは、次の条件をすべて満たす場合に支給されるお金のことです。
- 一定の障害の状態に該当する
- 現に介護を受けている
- 病院または診療所に入院していない
- 介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどに入所していない
介護(補償)等給付の申請には、原則として医師の診断書が必要です。
ただし、次のいずれか場合には不要とされています。
- 傷病(補償)等年金の受給者
- 障害等級第1級3号・4号または第2級2号の2・2号の3に該当する方
- 継続して2回目以降の介護(補償)等給付を請求するとき
(6)遺族(補償)等給付(労災死亡者の遺族へ)
遺族(補償)等給付とは、労働者が業務災害または通勤災害により死亡したときに、一定の要件を満たす遺族に支給される年金等のことです。
遺族(補償)等給付を申請する場合、労働者が死亡したことや死亡年月日を証明するために、医師作成の死亡診断書が必要です(死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書などで代替できる場合あり)。
参照:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
【ポイント】 労災申請で必要となる診断書や証明書は、厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできるものもあります。ご自身の申請する給付に応じた様式を確認しましょう。
労災保険給付の種類については、こちらの記事もご覧ください。
労災の診断書作成にかかる費用と支払い方法
診断書の作成には費用がかかる場合がありますが、労災保険の適用状況によって誰が負担するかが変わってきます。
(1)労災保険でカバーされる費用(上限4,000円)
労災申請のために医療機関が作成する診断書については、労災保険から費用が支払われます。
- 労災指定医療機関の場合: 原則として、診断書作成費用は労災保険から医療機関へ直接支払われるため、労働者の自己負担はありません。あなたは費用を支払う必要がないのが一般的です。
- 労災指定医療機関以外の場合: 一度あなたが診断書作成費用を立て替えて支払う必要があります。しかし、その後、労災保険に請求することで、4,000円を上限として支給されます。立て替えた際の領収書を忘れずにもらい、申請時に添付しましょう。
(2)労災保険の対象外となる費用(自己負担となるケース)
労災保険が適用される診断書は、あくまで「労災申請のために必要と認められたもの」に限られます。以下のようなケースでは、費用が自己負担となる場合があります。
- 会社からの提出を求められた診断書:会社があなたに診断書の提出を求めた場合、就業規則の定め等により、診断書作成費用をあなたが負担するか会社が負担するかが決まります。自己負担となる可能性もゼロではありませんので、事前に会社に誰が費用を負担するのか確認しましょう。
- 個人的な保険(生命保険・医療保険など)に提出する診断書:あなたが個人的に加入している生命保険や医療保険の給付金請求のために診断書が必要な場合、その費用は労災保険の対象外であり、自己負担となります。労災申請用の診断書のコピーで代用できるケースもあるため、加入している保険会社に確認してみると良いでしょう。
診断書の作成期間と医師への依頼時の注意点
診断書は、医師があなたの診察記録や検査結果などを確認し、慎重に作成するものです。依頼すればすぐに発行されるわけではありません。
(1)一般的な作成期間
- 通常の診断書:数週間程度が目安です。
- 後遺障害診断書などの複雑な診断書:症状の評価や検査結果の確認に時間を要するため、さらに時間がかかる場合もあります。
後述しますが、労災の各給付には申請期限(時効)があるため、診断書の作成期間を考慮し、余裕を持って早めに医師に依頼することが重要です。
(2)医師への依頼時の注意点
- 診断書作成の目的を明確に伝える:「労災申請のため」であることを伝え、具体的に「どの労災給付(例:障害補償など)の申請で必要か」を明確に伝えましょう。
- 正確な情報を提供する:症状や治療経過、業務との関連性など、医師が診断書を作成するうえで必要な情報を正確に伝えましょう。質問には正直に答え、伝え漏れがないようにメモを用意していくのも有効です。
- 後遺障害診断書の場合の注意:後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定に直結するため、非常に重要です。
- 症状(自覚症状、他覚症状)や可動域の制限などを具体的に、かつ客観的に記載してもらうよう依頼しましょう。
- もし可能であれば、労災認定や後遺障害等級に関する知識を持つ医師、または専門分野の医師(整形外科、神経内科など)に相談することも検討してください。
労災保険の申請における書類の提出先
労災保険を申請する際の書類の提出先は、基本的に医療機関と労働基準監督署の2つです。
なお、各請求書の記入方法は厚生労働省のホームページを参照し、不明点があれば管轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。
(1)医療機関に提出する書類
労災指定医療機関を受診した場合、療養(補償)等給付を申請するためには、受診した医療機関に療養の給付請求書を提出する必要があります。
なお、労災指定医療機関以外の病院を受診した場合には、受診した医療機関ではなく、療養の費用請求書を労働基準監督署に提出することが必要です。
(2)労働基準監督署に提出する書類
労働基準監督署には、労災保険給付の種類ごとに、次の書類を提出します。
- 療養(補償)等給付:(労災指定医療機関以外の病院を受診した場合)療養の費用請求書
- 休業(補償)等給付:休業給付支給請求書
- 障害(補償)等給付:障害給付支給請求書
- 遺族(補償)等給付:遺族年金支給請求書、遺族一時金支給請求書
- 介護(補償)等給付:介護給付・介護給付支給請求書
※給付の種類によっては、業務災害か通勤災害かで請求書の様式や名称が異なります。
なお、傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権で行われるため、申請手続は不要ですが、先述のとおり「傷病の状態等に関する届」の提出が必要とされます。
上記書類のほか、領収書や診断書などの添付書類が必要な場合も多いため、わからないことがあれば管轄の労働基準監督署に確認するようにしましょう。
労災の診断書はいつ、誰が、どうやって用意する?具体的な手続き
診断書を受け取ってから、労災申請を進めるまでの基本的な流れを解説します。
(1)申請の基本的な流れ
- 労災発生・負傷:業務中または通勤中に災害が発生し、負傷や疾病が発生します。
- 医療機関での受診・治療:すぐに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。労災である旨を医療機関に伝えてください。
- 医師への診断書作成依頼:治療が進み、診断書が必要な段階になったら、医師に労災申請用の診断書の作成を依頼します。
- 診断書受領:医師から診断書を受け取ります。内容に不備がないか確認しましょう。
- 必要書類の準備:診断書以外にも、各給付に応じた請求書事業主の証明など、必要な書類を準備します。
- 労働基準監督署への提出:準備した書類一式を、事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(2)申請者と時効
- 申請者:労災の給付は、原則として労働者本人が申請します。労働者が死亡した場合は遺族が申請します。事業主(会社)が書類作成や提出を代行することも可能ですが、最終的な申請者は労働者(または遺族)です。
- 時効:各給付には申請期限(時効)があります。
- 療養(補償)等給付:治療費を支払った日の翌日から2年。
- 休業(補償)等給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年。
- 障害(補償)等給付:症状固定日の翌日から5年。
- 遺族(補償)等給付:労働者の死亡日の翌日から5年。
- 介護(補償)等給付:介護を受けた月の翌月の1日から2年
- 傷病(補償)等年金:傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権で行われ、請求手続はないため、申請の期限や時効はありません。
時効を過ぎると給付を受けられなくなるため、早めに手続きを進めましょう。
労災申請に関するよくある質問(FAQ)
(1)会社に診断書を提出する場合、費用は会社が負担してくれるの?
誰が診断書作成費用を負担するかは就業規則などの定めによります。あなたが負担する必要があるかもしれませんので、事前に会社にご確認いただくのがよろしいと思います。
(2)個人的な保険(生命保険・医療保険)に提出する診断書は労災申請でも使える?
個人的な保険会社に提出する診断書は、労災申請でそのまま使えるとは限りません。労災申請には専用の様式があるため、労災用の診断書を改めて取得する必要があります。
ただし、保険会社に提出する診断書は、場合によっては労災用の診断書のコピーで代用できることもあるので、加入している保険会社に確認すると良いでしょう。
(3)診断書を書いてくれない医師がいる場合はどうすればいい?
医師には基本的に診断書作成の義務がありますが、労災の専門知識が不足している、または症状の判断が難しいといった理由で作成を渋るケースも稀にあります。
その場合は、労災に詳しい医師のセカンドオピニオンを検討するのも一つの方法です。
(4)診断書の内容が労災認定に不利になりそうだが、どうすればいい?
診断書の内容は労災認定に非常に大きな影響を与えます。
もし、内容に事実と異なる点がある、または業務との関連性について十分に記載されていないと感じる場合は、まずは医師に相談し、修正や追記をお願いできるか確認しましょう。
それでも解決しない場合や不安が残る場合は、労働基準監督署や労災問題にくわしい弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
【まとめ】
この記事で解説したように、労災給付の種類によって診断書の要否や費用負担、必要な様式は異なります。
スムーズな申請のために、医師との連携を密にし、正確な情報が記載された診断書を適切なタイミングで取得することが大切です。
もし、診断書の取得や労災申請に関して不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。