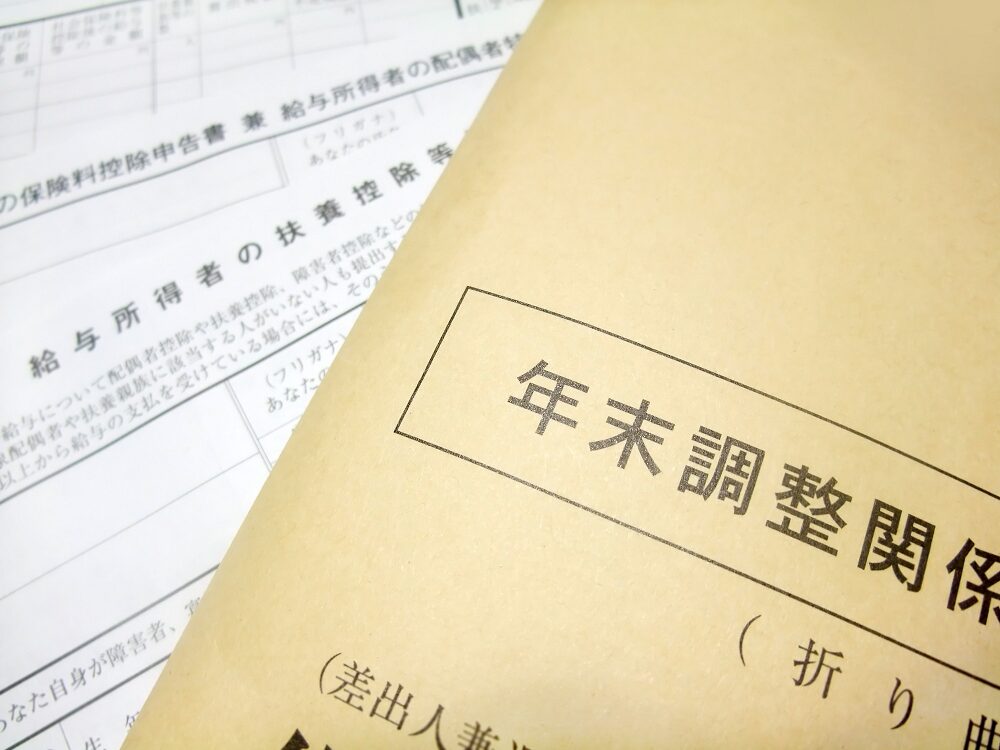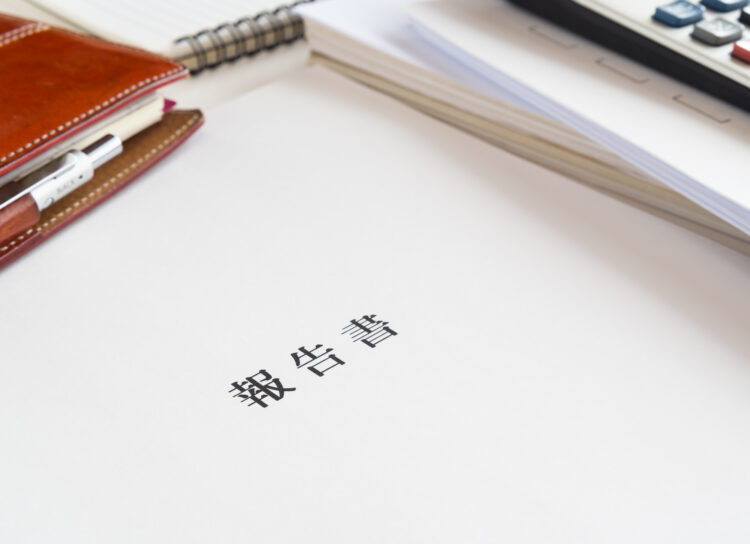育児休業中でも、年末調整は欠かせない手続きの1つです。
特に、育休中の収入や控除についての知識がないと、不必要な税負担を背負ってしまうことがあります。しかし、年末調整をしっかり行うことで、払いすぎた税金が還付され、家計の助けとなる可能性が高いのです。
このコラムでは、育休中の年末調整についてわかりやすく解説し、あなたが経済的な安心感を得られるようサポートします。具体的な手続き方法や控除などをしっかり押さえ、適切な準備をしていきましょう。
ここを押さえればOK!
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除・配偶者特別控除
・保険料控除
・住宅ローン控除
手当金の年末調整での取り扱い
・出産手当金:産前産後休業中の所得補償として支給される非課税
・出産育児一時金:出産にかかる費用の補助として支給される非課税
・育児休業給付金:育児休業中の所得補償として支給される非課税
いずれも非課税とされるため、年末調整の対象とはされません
年末調整を忘れた場合の対応
・会社に相談:年末調整の申請が間に合わなかった場合、総務部門や人事部門に相談
・確定申告:年末調整ができなかった場合、確定申告を行うことで税額の調整が可能
育休中でも年末調整を忘れずに行うことが重要です。控除を適用することで税金還付が期待でき、経済的負担を軽減できます。必要な書類を準備し、会社の総務部門や税務署に確認してスムーズに手続きを行いましょう。
育休中の年末調整とは?
年末調整は、年間の所得税を正確に計算し、税金の過不足を精算する手続きです。
そして、産休中や育休中の方でも1月から育休取得まで仕事をして収入がある場合には、年末調整が必要となります(合計所得金額が2000万円以下の場合)。
年末調整で受けられる控除とは?
産休中や育休中で収入が少なくなっている場合でも、年末調整をして控除を受けることで税金が還付される可能性があります。
年末調整で受けられる主な控除には、基礎控除、扶養控除、配偶者控除・配偶者特別控除、保険料控除、住宅ローン控除などがあります。ここでは、年末調整で受けられる主な控除について簡単に説明します。
(1)基礎控除
基礎控除は令和7年度の税制改正により、合計所得金額が2350万円以下の控除額が10万円引き上げられ、58万円となります。
また、合計所得金額が655万円以下の場合、58万円に一定額が加算されます(令和9年度までの特例)。
合計所得金額2500万円までの場合、下記のように一定額の基礎控除が受けられます。
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円を超えて336万円以下 | 88万円(令和9年分以降は58万円) |
| 336万円を超えて489万円以下 | 68万円(令和9年分以降は58万円) |
| 489万円を超えて655万円以下 | 63万円(令和9年分以降は58万円) |
| 655万円を超えて2350万円以下 | 58万円 |
| 2350万円を超えて2400万円以下 | 48万円 |
| 2400万円を超えて2450万円以下 | 32万円 |
| 2450万円を超えて2500万円以下 | 16万円 |
(2)給与所得控除
給与所得控除とは、年間の給与所得から一定額の範囲で受けられる控除です。
令和7年度税制改正により、最低保証額55万円が、65万円に引き上げられました。
| 給与などの収入金額 (源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額 |
| 190万円円以下 | 65万円 |
| 190万円を超えて360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円を超えて660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円を超えて850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円を超えて | 195万円(上限) |
(3)扶養控除
基礎控除の金額が増えるのに伴い、扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のように引き上げられました。
| 扶養親族 | 所得要件額 |
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 58万円以下(改正前48万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 | 58万円以下(改正前48万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 85万円以下(改正前75万円以下) |
生計を同一とする年齢16歳以上の親族(居住者)のうち、合計所得金額58万円以下の人がいる場合に一定額の扶養控除を受けられます(給与所得だけの場合は、給与の収入額123万円以下)。 控除金額は被扶養者の年齢によって異なり、38万円~58万円です。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2)
参考:No.1180 扶養控除|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
(4)特定親族特別控除
令和7年度税制改正により、創設された控除です。人材不足解消を目的とした制度で、所得要件を引き上げることで、大学生がアルバイトでより収入を得やすくなりました。
特定親族(※)を有する場合、総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円が控除されます。
※特定親族とは、生計を一つにする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除く)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈のこと。いわゆる里子も含まれます。
年末調整で特定親族特別控除の適用を受けたい場合、勤め先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円を超えて85万円以下(123万円を超えて150万円以下) | 63万円 |
| 85万円を超えて90万円以下(150万円を超えて155万円以下) | 61万円 |
| 90万円を超えて95万円以下(155万円を超えて160万円以下) | 51万円 |
| 95万円を超えて100万円以下(160万円を超えて165万円以下) | 41万円 |
| 100万円を超えて105万円以下(165万円を超えて170万円以下) | 31万円 |
| 105万円を超えて110万円以下(170万円を超えて175万円以下) | 21万円 |
| 110万円を超えて115万円以下(175万円を超えて180万円以下) | 11万円 |
| 115万円を超えて120万円以下(180万円を超えて185万円以下) | 6万円 |
| 120万を超えて123万円以下(185万円を超えて188万円以下) | 3万円 |
| 123万円超(188万円超) | 0円 |
※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
参考:特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等(令和7年度改正)|財務省
(5)配偶者控除・配偶者特別控除
所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる、一定の金額の所得控除を配偶者控除と言います。
| 本人の合計所得金額 | 控除額 | |
| 一般の控除対象配偶者(配偶者が70歳未満) | 老人控除対象配偶者(配偶者が70歳以上) | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円を超えて950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円を超えて1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1000万円超え | 0円 | 0円 |
本人の所得が1000万円以下で、配偶者の年間所得が58万円以下(給与収入123万円以下)であれば配偶者控除が適用され、給料所得者の合計所得金額に応じて最高38万円が控除されます。
また、本人の所得が1000万円以下で、配偶者の年間所得が58万円を超え、133万円以下(給与収入123万円超 201万6000円未満)であれば配偶者特別控除が適用され、給与所得者と配偶者の合計所得金額に応じて最高48万円が控除されます。
参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)
(6)保険料控除
保険料控除とは、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っている場合に受けられる控除です。
| 控除の種類 | 控除額 | ||
| 社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | ||
| 生命保険料控除(一般の生命保険料の場合) | 旧契約 | 新契約 | 両方 |
| 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
| 地震保険料控除 | 地震保険料のみ | 旧長期損害保険料のみ | 両方 |
| 最高5万円 | 最高1万5000円 | 最高5万円 | |
(7)住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を購入し、返済をしている場合に適用される控除です。
住宅ローン控除を受けるための要件は複数ありますので、事前によく確認するようにしましょう。
控除を受けるための手続きとしては、初年度は確定申告で住宅ローン控除適用の申請を行います。そして、2年目以降は年末調整で特例控除の適用を受けることができますので、必要書類を勤務先に提出します。
年末調整の手続き方法とは?
会社は産休中や育休中の社員も含めて、年末調整を行います。
従業員は会社の総務部門や人事部門に提出します。
通常は12月末までですが、会社によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
必要な書類
まず、年末調整に必要な書類を準備することが重要です。主な書類は次の通りです。
- 扶養控除等(異動)申告書(扶養親族がいない人でも提出が必要)
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書 など
これらの書類は、会社から配布されるか、税務署のウェブサイトからダウンロードできます。必要な控除を受けるために、各種証明書も忘れずに準備しましょう。具体的には、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書などがあります。
手当金や給付金の年末調整での取り扱いとは?
次に、出産手当金、出産育児一時金などの給付金の取り扱いについて説明します。
(1)出産手当金
出産手当金は、産前産後休業中の所得補償として健康保険から支給されるお金です。
基本的に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以降56日までの間で休んだ期間を対象に支払われます。
出産手当金は非課税であり、年末調整の対象にはなりません。
(2)出産育児一時金
出産育児一時金も、出産にかかる費用の補助として健康保険から支給されるお金です。
妊娠85日以上(4カ月)の妊婦が出産した場合、出産児1人につき50万円が支払われます。
出産育児一時金も非課税であり、年末調整の対象にはなりません。
(3)出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
一定の条件を満たすと、出生時育児休業給付金が支給されます。最大28日間、賃金の67%が支給されます。ただし、産後パパ育休は休業中に就業できるため、就業日数が多くなると出生時育児休業給付金が不支給となることがあることに注意が必要です。
出生時育児休業給付金も非課税であり、休業期間中は社会保険料の支払いが免除されます。
(4)出生後休業支援給付金
2025年4月1日から、男性育休取得を促進するため、子どもの出生直後の一定期間に、父母ともに14日以上の育休を取得した場合に支給される給付金です。
特に母親の出産直後は、心身ともにサポートが必要な時期です。この時期に父親が育休を取得した場合に、特に金銭的に給付を行うこととしたものです。
基本的に、父親が子の出生後8週間以内に、母親は産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、それぞれに育児休業給付金(休業前賃金67%相当)に上乗せして、最大28日支払われます。こちらの給付も非課税です。
支給額は、休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)×13%です。
別途支給される育児休業給付金又は出生時育児休業給付金と併せて考えると、育休取得前とくらべてもほぼ同額の収入が得られることになります。
(5)育児時短就業給付金
2025年4月1日から、2歳未満の子どもを養育するために所定の労働時間を短縮して、時短で就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと、「育児時短就業給付金」が支給されることになりました。支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です(それ以前の賃金水準を超えないように調整されます)。
こちらの給付金も非課税です。
参考:2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設しました|厚生労働省
(6)育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業中の所得補償として雇用保険から支給されるお金です。
育児休業給付金も非課税であり、年末調整の対象にはなりません。
以上の手当金や給付金は年末調整の対象とはなりませんが、育休中に出勤して給与の支払いを受けた場合、育休に入る前に出勤して給与の支払いを受けた場合には、年末調整によって還付金を受ける可能性があります。
育休中及び育休前のいずれも会社に出勤をすることがなく、上記の手当金や給付金の支払いしか受けていなかったとしても、年末調整時に扶養控除等申告書を提出することで、翌年の源泉徴収時にその扶養控除が前提とされることになります。
育休中に年末調整を忘れた場合の対処法
年末調整の申請を忘れてしまった場合でも、会社に相談したり、確定申告を行ったりすることで対応可能です。
- 会社に相談:まずは勤務先の総務部門や人事部門に相談し、年末調整の申請が間に合わなかったことを伝えましょう。場合によっては、遅れても申請を受け付けてもらえることがあります。
- 確定申告を行う:年末調整ができなかった場合、確定申告を行うことで税額の調整が可能です。これにより、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
給与所得者でも医療費控除を受ける場合や最初の住宅ローン控除を受ける場合などには、確定申告を行わなければなりません。
育休期間中だけ配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性
育休期間中でも、妻が出産手当金や育児休業給付金などの手当金を除いて育休中の年間所得が133万円以下(給与収入約201万円6000円未満)であれば、夫の配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
夫の配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、夫が年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除の申告をする必要がありますので、夫と相談するようにしましょう。
【まとめ】育休中でも年末調整を忘れずに行おう!
育休中でも年末調整は重要な手続きです。
特に控除の適用を受けることで、税金の還付が期待でき、経済的な負担を軽減することができます。
この記事では、育休中の年末調整の具体的な手続きや控除の種類、さらに年末調整を忘れた場合の対処法について解説しました。この記事を読んで疑問が解消された方は、今すぐ手続きを始めましょう。分からないことは会社の担当部署や税務署に確認し、必要な書類を揃えることで、スムーズに年末調整を行えます。